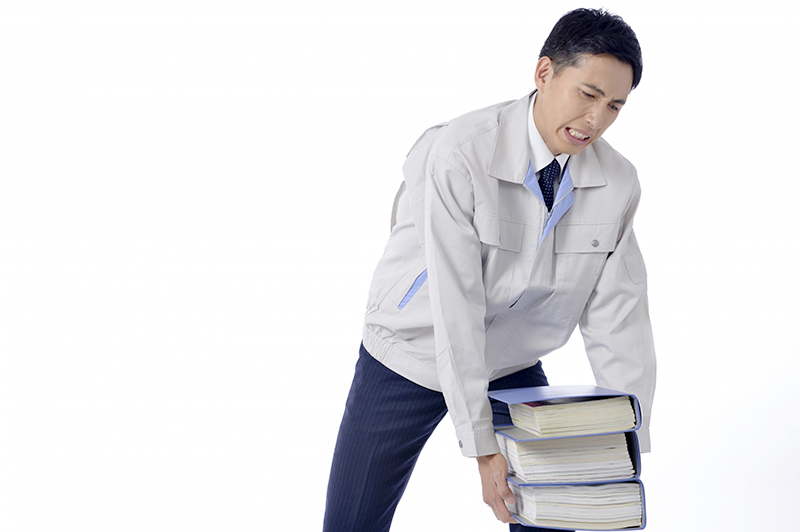フリーランスの施工管理技士は、茨の道?
近年、多様化してきている施工管理技士の働き方。様々な働き方があるが、フリーランスは「稼ぐことが厳しい」と言われることが多い。実際、厳しいこともあるのは事実だが、「人脈さえあれば、思った以上に簡単に稼げてしまう」というのが私の正直な感想である。
もちろん、それは私に施工管理技士という国家資格と、それなりの実務経験があるからなのだが、私のような人間がフリーランスになって、給料が2〜3倍になったという人もいると聞いたことがある。
何より、今はフリーランスになれる環境が整っている。施工管理技士の求人サイトを見ても、ここ数年で伸びてきている印象だ。この背景には、施工管理技士の人材不足が挙げられるが、需要に対して供給が足りていないこの業界が、シンプルに稼げないはずがないのである。
ではなぜ、私がフリーランスとして働く施工管理技士は残酷なのか。その内容を詳しく解説していこう。
「知っていて当然」という目で見られる
フリーランスの場合、工事で問題が発生しても助けてくれる体制があまり整っていないことが多い。
施工管理技士は、会社に雇われていなければ主任技術者として工事に携わることができないため、会社の使用するソフトや管理道具、測量機器などは貸し出してもらえることがほとんどなのだが、問題は、その使い方や操作がわからない時、基本自分で解決しなければならないということだ。
周りの会社員の方に聞けば良いという意見があるかもしれないが、ここがフリーランスとして働く上で最も過酷なところで、フリーランス=スキルの高い人間という認識が強く、基本知っていて当然という考え方をされる。
さらには、先程も述べた通り、施工管理技士が非常に足りていない状況で雇う会社が多いため、そういったことを聞ける人材がそもそも現場にいなかったりする。
私の場合は、最初に従来使っていた測量機器と違う種類の機械を用意されたため、操作をインターベットで調べながら、半日かけてやっと使えるようになった経験がある。こういった状況下では、フリーランスは本当に面倒であると感じてしまう。
責任ある仕事は任せてもらえない
フリーランスで成長したいと考えている人は、自分から積極的に学ぼうという姿勢がなければ成長することは難しい。当たり前のことだが、施工管理技士は本当に足りておらず、管理業務の助手として、人材をフリーランスで雇い入れるケースが多い。
基本的に、管理業務の中でも本当に雑務(簡単な書類の作成や押印)を任されるケースが多く、施工計画書や図面の作成、写真管理など、責任ある仕事は基本的に回ってこないと考えたほうが良い。
会社の立場で考えれば、正社員として雇い入れている人材は、積極的に教育を行えば今後会社のためになるが、フリーランスに時間を費やして教育をすることにはメリットを感じない。極端な話をしてしまえば、雇い入れて使えそうならばヘッドハンティングをしてしまうほうが、会社のコスパが良いのである。
このような理由から、フリーランスとして働く環境の中でスキルアップをすることは、非常に厳しいということを頭に入れておいて欲しい。
土木など新しい分野への挑戦が難しくなる
工事の中でも、土木工事は、法面、河川、ダム、橋、トンネルなど様々な分野の工事が存在する。全てに従事できる人材になることは少ないが、基本的な道路や河川などの仕事は管理できるようにしておきたいもの。工事の管理工程自体に大きな差異はないのだが、やはり現場によって使う材料や、その決まり、施工方法などが異なるため、高い専門性が要求される。
例えば、法面工事に使用する法枠の材料であるフレーム材は、基本的には法面だけにしか使用しない。法面分野に携わったことのない人間は、当然戸惑う。フリーランスで法面工事の経験がない人間は、基本的には任せてもらえない。その点、正社員は今後法面工事に携わる可能性があるとなれば、積極的に研修にいかせてもらえるだろう。
今後コロナショックの影響で、工事の件数は減少していくと考えられる。そうなった時に、ある程度の工事現場をこなすだけのスキルは身につけておきたいところだが、新しい分野へ挑戦すること自体がフリーランスでは過酷といえる。
これから、まだまだ公共工事が加速していく中で、もちろんフリーランスの需要もうなぎ上りで上昇していくことは間違いない。しかし、それにはやはり、常に自ら成長しようとする意識を持っていないと、建設業界の変化に対応することは難しくなってくる。
逆に言えば、そういった意識さえあれば、フリーランスの環境は会社員として働くよりも、遥かに稼ぎやすい環境であることも知っておいていただきたい。