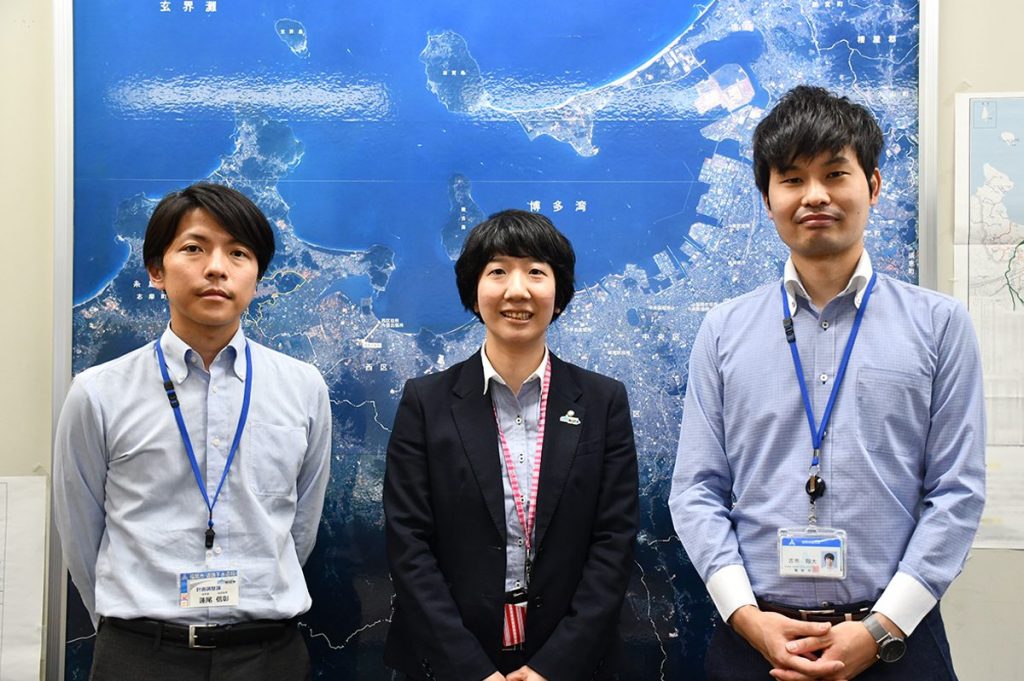福岡市役所がつくった「FUKUOKAモデル」を紐解く
国土交通省をはじめ、全国の自治体では、ずいぶん前から「無電柱化」に取り組んでいる。
無電柱化とは、道路沿いに設置されている電柱や電線などを地中に埋設することを指す。なぜ地中化するのかと言えば、まちの景観を損なうということほか、地震や台風などで倒壊すると危ないとか、倒れた電柱が道路をふさぐと通行できなくなることがある。
筆者としては、「非常にもっともなことだし、早く電柱がなくなれば良い」と以前から思っていたわけだが、その進捗となると、全国的に見ても芳しくないところがある。この点、「やっぱりちゃんと予算がつかないからだろうな」と漠然と考えていた。
そんなとき、福岡市役所が無電柱化を推進するために「FUKUOKAモデル」をつくったという情報を耳にした。FUKUOKAモデルとは、どのようなものなのか。これによって何がどう変わるのか、興味が湧いた。ということで、福岡市役所の無電柱化推進プロジェクトチーム(PT)のメンバーの方々に話を聞いてきた。
「コスト」、「スピード」、「住民理解」という課題
――無電柱化を進めるうえで、どのような課題があるのですか?
蓮尾さん 無電柱化を進めるうえで、3つの大きな課題があります。1つ目が「コスト」、2つ目が「スピード」、3つ目が「住民理解」です。これらのため、無電柱化は、福岡市をはじめ、全国でもあまり進んでいません。
福岡市内の道路延長は約3,900kmありますが、無電柱化率はわずか3%(市内の国道、県道、市道、平成29年度末)にとどまっています。日本で一番進んでいる東京23区でも8%です。一方、海外では、ニューヨークが83%、ロンドンやパリに至っては100%に達しています。
――緊急輸送道路の無電柱化率はどの程度ですか?
蓮尾さん 20%程度です。市が管理する緊急輸送路の延長は233kmほどありますが、無電柱化されているのは、そのうちの45kmほどです。緊急輸送路の無電柱化率を100%にすることが、われわれがまず目指すべきところだと考えています。
――そもそもなぜ無電柱化が必要なのですか?
蓮尾さん まず、地震などの災害が発生した場合、電柱が倒壊し、周辺の建物などを損壊するリスクがあります。道路上に倒壊すると、緊急車両をはじめとする車両交通の妨げになります。あと、電柱、電線によって、周辺の景観が損なわれるケースもあります。
近年は、地震や水害などの自然災害のリスクが高まっています。福岡市役所としても、「無電柱化をなんとか前に進めなければならない」という思いがありました。そこで、福岡市役所として、無電柱化推進PTを立ち上げたわけです。
柔軟な発想を期待し、若手中心PTが発足
――無電柱化推進PTを立ち上げた理由はなんでしょうか?
安河内さん 無電柱化がなかなか進まない中、柔軟な発想のもと、抜本的な対応が必要だということで、若手主体で考えてもらおうということで、道路下水道局として、PTを設置した経緯があります。PT設置には若手職員の育成というねらいもあります。
――無電柱化推進PTのメンバーはどういった方々ですか?
蓮尾さん 無電柱化推進PTは、福岡市役所の20才代、30才代の職員を中心として、電気・通信事業者の社員を加えた15名のメンバーから成る組織です。平均年齢は33才(2021年4月時点)です。道路下水道局だけでなく、観光や景観の視点から経済観光文化局、住宅都市局の職員も入っています。職種も、土木だけでなく、事務職や建築職などの職員がいます。
キックオフ時の集合写真
――いつPTを設置したのですか?
古市さん 国では11月10日を「無電柱化の日」と定めています。福岡市では2020年11月10日にキックオフ宣言を行いました。PTでは、ビジョンに「無電柱化リーダー都市の実現」、コンセプトに「空を感じる道づくり」を掲げ、無電柱化を推進するための手法について、様々な検討を行ってきました。そして今年5月、これまでの検討成果をとりまとめ、高島宗一郎市長に対し、令和2年度の活動報告を行いました。
道路縦方向のみ地中化する「ファスト地中化」
――無電柱化推進の手法とはどのようなものですか?
古市さん PTでは、無電柱化の「FUKUOKAモデル」として、7つの柱を提唱しています。その中でも、特に効果が高いと考えている取り組みが、「ファスト地中化」、「工事ヤードの常設化」です。
現状の地中化は、道路縦方向、民地引き込み線も含め、すべてを地中化するのがスタンダードになっています。これが無電柱化に時間とコストがかかる大きな要因の一つになっています。
われわれが考えるファスト地中化は、道路縦方向の高圧線などを地中化し、各戸への民地引き込み線はとりあえずそのまま上空に残すという手法です。民地引き込み線の地中化は、各戸ごとに交渉調整を行う必要があり、時間もコストもかかります。上空に残った引込線は、地中化する代わりに、照明柱などを活用し、固定します。これによって、地中化に伴う時間とコストをカットし、コストと効果を最適化することができます。景観的にもかなりスッキリします。
ファスト地中化の整備前
ファスト地中化の整備後
なぜ道路の縦方向だけを地中化するのかと言うと、過去の自然災害を見ると、電柱、電線の被害は、大半が縦方向に設置された電線に倒木や飛来物が引っかかり、電柱をなぎ倒してしまうことが原因のほとんどです。この縦方向の電線を無くすことで、大規模停電や電柱倒壊の被害がほぼ解消すると考えています。民地引き込み線と固定する柱は残るわけですが、仮に倒木や飛来物があった場合、引き込み柱は倒れないと考えています。電線が外れ、断線するリスクはありますが、断線した引き込み線の復旧は、外れた電線をもとに戻すだけなので、復旧時間はかなり早いと考えています。
民地引き込み線はとりあえず上空に残しますが、われわれとしては、最終的には地中化する点では現行の手法と変わりはありません。ファスト地中化はあくまで暫定整備と言うか、縦方向の地中化を先行させる段階的手法として位置づけています。道路整備や民地の建て替えのタイミングで地中化することなどを想定しています。
ただ、課題もあります。現行の無電柱化法では、「道路の新設、改築及び修繕時に、電柱又は電線を道路上において新たに設置しないものとする、既存の電柱又は電線を撤去するものとする」と定めています。FUKUOKAモデルを実現するには、この部分の法解釈を整理する必要があります。この点、われわれとしても、国としっかり協議する必要があります。
――コストは予算との見合いだと思われますが。
古市さん 必要な予算はそれなりに確保してきたものと認識していますが、コストがネックだと考えています。PTとしては、無電柱化には、1km当たり約5億円のコストがかかるので、これを抜本的に見直すべきだと考えているところです。やはりコストカットは避けて通れないところです。縦方向の地中化自体のコストを下げていくことも必要になってきます。
通行止めをかけ、短期集中工事する「工事ヤードの常設化」
――「工事ヤードの常設化」とはどのようなものですか?
古市さん 無電柱化工事では、管路や電線、ボックスなどを埋設するため、広い工事ヤードが必要になります。福岡市でも実際、一定の交通規制をかけ、一車線まるまる工事ヤードとして確保して工事を行っているわけですが、交通に与える影響が大きいので、交通量が多い時間帯はヤードを撤去し、再びヤードを設置するという作業を毎日繰り返しているのが現状です。
工事ヤードの常設化は、工事中は通行止めをかけ、工事の効率化を図る手法です。ヤードの撤去、設置にかかる時間をなくすことにより、1日当たりの作業効率は倍程度に向上すると試算しています。
常設化の導入にあたっては、交通になるべく影響を与えず、車や歩行者が安全かつスムーズに通行できるよう、交通誘導員の配置を強化したり、従来は作業ヤードをカラーコーンなどで囲いますが、常設化する際にはバリケードのようなしっかりしたもので囲うなどの安全対策を強化します。
工事ヤードの常設化のイメージ(片側1車線の場合)。工事着工前のイメージ(左)、工事中のイメージ(右)
片側1車線の場合は、交通量の多い道路での導入は難しいですが、交通状況を見ながら、導入を検討していくことにしています。1車線の場合は、完全通行止めになるので、交通にまったく影響が出ないことを確認したうえで、導入を検討していくことにしています。
課題としては、住民生活、交通への影響が大きいことが挙げられます。この点、交通管理者である福岡県警と連携しながら、導入路線の選定、交通誘導員などの安全対策の強化、迂回ルートの事前情報提供など広報体制強化による理解向上を図っていくことにしています。
コスト最大3割カット、スピード1.5倍へ
――FUKUOKAモデルによって、どれだけの効果が期待できるのでしょうか?
古市さん コストは最大約3割カット、スピードは約1.5倍の効果が期待できます。これらによって、住民理解も向上すると考えています。
――今後のスケジュールはどうなりますか?
古市さん 国や県警との協議は2021年度からスタートしています。できれば、2021年度中に実証実験に入りたいと考えているところで、2023年度からの本格導入を目指しています。また、FUKUOKAモデルの残り5つの柱には、中長期計画の策定、3Dレーダー探査などによる地下埋設物の見える化、占用料の見直しなどによるインセンティブスキームなどがあり、引き続き検討を進めていきたいと考えているところです。
――通行止めは県警がかなりイヤがりそうですが。
古市さん 私もそう思います(笑)。これからしっかり協議していきたいと考えています。
――PTで議論した内容を市の組織としてどう共有していくか、難しいところがあると思いますが。
古市さん PTのメンバー同士はざっくばらんに前向きに話し合えるようになっていますが、それぞれが所属する組織同士となると、いろいろなカベが出てくることが予想されます。ただ、この点については、市長から「全面的にバックアップしていきたい」というお言葉をいただいています。道路下水道局長からも「自由にやって良い」と言っていただいています。これから先はわかりませんが、少なくとも、これまではスムーズに活動できていると感じています。