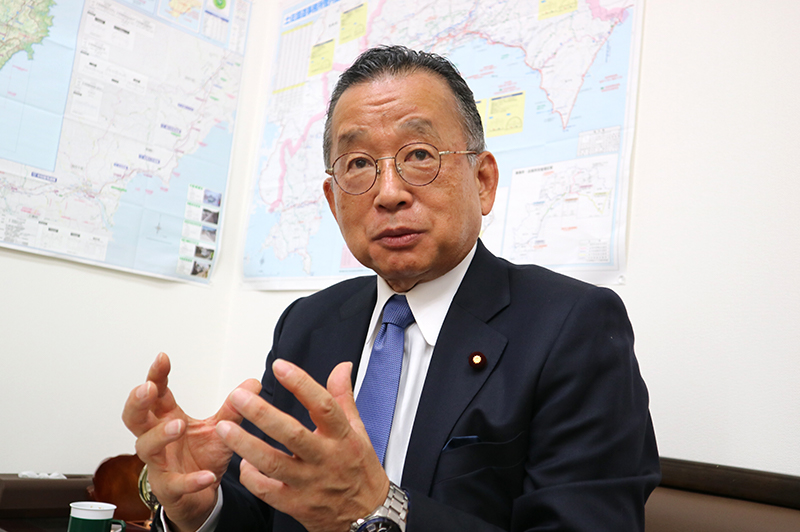事業費1.5兆円の四国新幹線は実現するか?
ここ数年、四国新幹線実現に向けた動きが盛り上がりを見せている。四国新幹線の基本計画は1973年からあるが、未だ実現のメドは立っていない。その理由には、ルート設定、事業の膨大さ、財源問題、事業採算性などいろいろあるが、そもそも地元四国4県が熱心でなかったことが大きく左右したようだ。
四国新幹線を巡る議論が再活性化したのは2010年ごろ。同年には「四国における鉄道ネットワークのあり方に関する懇談会」が発足し、新幹線導入に関する要望書を国に提出した。その後、様々な組織活動を経て、2017年には、「四国新幹線整備促進期成会」が発足。以降、国への要望活動や県民へのPRイベントなどを展開している。
ただ、その整備には1.5兆円規模の事業費が必要になるが、「緊縮財政」路線を爆走中の現政権がGOサインを出すか不透明だ。
果たして四国新幹線はアリなのか。自由民主党の四国新幹線プロジェクトチーム(PT)座長を務める山本有二衆議院議員に話を聞いてみた。
新幹線が開通していないのは四国だけ
――山本議員が四国新幹線に関わるようになったきっかけは?
山本有二 10年ほど前、四国電力の社長、会長を歴任した千葉昭さんという方が「四国に新幹線をつくりたい」ということで、私のところに相談に来られました。その際、四国経済連合会の「四国の鉄道高速化検討準備会」がB/Cの基礎調査を行ったところ、「1.03」という結果が出たとおっしゃいました。この情報は、私だけでなく、すべての国会議員に共有されたと思います。
四国新幹線はすでに基本計画が存在しますが、「夢の計画」だと考えられていました。というのも、この基本計画には、紀淡海峡トンネル、豊予海峡大橋がビルトインされており、新幹線が和歌山から鳴門に来て、四国を横断し、佐田岬から大分に抜ける計画だったからです。第2国土軸を形成すると言える計画ですが、高知は通らない計画でした。
ところが、千葉さんが考える新幹線ルートは、岡山から本四連絡橋を通って、四国中央市を経由して高松、徳島に至るルート、四国中央市から松山に至るルート、四国中央市から高知に抜けるルートと、3本の枝分かれルートでした。四国中央市から高知に抜けるルートは、95%がトンネルのほぼ直線で、延長は43kmというもので、所要時間は10分少々ということでした。
千葉さんは「(このルートを元に)与党でウォーミングアップしていただき、国会議員のみなさんと一緒に成案づくりを進めたい」とおっしゃいました。私は「一緒に成案づくりをするなら、お付き合いしましょう」と申し上げました。
四国新幹線整備のイメージ(四国新幹線整備促進期成会資料より抜粋)
地域経済の低迷、地域の人口減少、都会での就学就労には、当時から与党としてわれわれは頭を痛めていました。新幹線ができれば、地域経済の活性化につながるし、地元に残る若者が増え、人口増加や就学就労者の増加につながるのではないだろうか。私は「これはやってみようじゃないか」と考えました。自民党四国ブロック両院議員のブロック会議も行われ、「やろう」ということで一致しました。
山本議員の高知市内にある事務所に掲げられた看板
――山本議員は、自民党の四国新幹線のPT座長に就いていますね。
山本有二 自民党として、このプロジェクトを誰がこれをまとめるかという話になり、当時道路調査会長をやっていた私に「同じ公共事業だから」と白羽の矢が立ち、自民党の新幹線プロジェクトチームの座長をお引き受けしました。
イギリスに鉄道博物館という施設があります。こちらに日本の新幹線を紹介するパネルが展示されていたのですが、日本列島の地図の中に四国が入っていなかったんです。四国に新幹線が走っていないからです。海外から見ると、日本はそう映っているわけです。これがきっかけになって、国内の「四国新幹線は必要だ」という機運が高まった経緯があります。
瀬戸大橋にはすでに新幹線がビルトインされている
――45年以上前から基本計画はあるのに、未だ実現していないのはナゾです。
山本有二 瀬戸大橋には、建設当初から高速鉄道、つまり新幹線のための鉄道専用部がビルトインされています。このことがわれわれが新幹線整備に動かす大きな理由になっています。瀬戸大橋ができたのは30年前ですが、設計段階の50年前の時点で、当時の関係者が「四国に新幹線を走らせる」と考えていた証だからです。
先人たちは、四国のあり方、日本のあり方について、しっかり考えていたわけです。逆に言えば、その後のわれわれの世代は、それをちゃんと考えることを怠ってきたと言えます。
――四国新幹線整備による効果をどう整理していますか?
山本有二 現在、4県の県庁所在地にある駅から鉄道で新大阪駅に移動する場合、新幹線への乗換のため岡山駅まで在来線(特急)で移動する必要があります。
それと4県から新大阪まで新幹線で直通する場合の時間を比較すると、徳島が1時間35分(現状2時間53分)、高松が1時間15分(現状1時間44分)、松山が1時間38分(現状3時間30分)、高知が1時間31分(現状3時間15分)になります。いずれも時間短縮効果は明らかです。
四国新幹線による時短効果試算(同)
鉄道局には「四国新幹線を整備したい」親心がある
ーーJR四国の経営も良くなるのでしょうか?
山本有二 そうですね。JR四国の資料によれば、2018年度決算は、収入は262億円、経費が397億円で、135億円の赤字でした。これをベースに新幹線が開業した場合、収入は640億円(380億円増)、経費は540億円(140億円増)で、一転して100億円の黒字となり、収支改善効果は240億円以上になるという試算が出ています。
――国土交通省鉄道局の動きは?
山本有二 国土交通省鉄道局は今、九州新幹線(西九州ルート)を巡る問題への対応に追われています。このルートは、博多〜長崎を結ぶルートとしてスタートしましたが、現在、佐賀県内の区間新鳥栖〜武雄温泉間の新幹線建設が着手できないまま止まっているんです。プロジェクトの優先順位があるので、佐賀県内の新幹線整備がストップしたままだと、四国新幹線になかなか手を付けられません。
でも、鉄道局は「四国新幹線を実現したい」という親心を持っています。四国新幹線の事業費は1.5兆円と試算されていますが、なんとかコストカットできないかということで、いろいろと調査を行いました。
その中で、複線ではなく単線で整備すれば、事業費を約5000億円削減できる調査結果が出ました。岡山から四国中央市までは複線ですが、ほかの路線は単線にするというわけです。5000億円削減すれば、B/Cは1.03より高くなります。
2037年の新大阪駅リニア開業には間に合わせたい
――新幹線開業に向け、どのようなスケジュール感をお持ちですか?
山本有二 われわれとしては、着工を前提とした法定調査を早くやってほしいという思いがあります。もし今年4月に着工した場合、設計や用地買収も始まります。北陸新幹線や九州新幹線の実績を見ると、設計や用地買収にかかってから、だいたい20年後に開業していますので、四国新幹線の開業は2040年頃になります。
ただ、私には、2037年のリニア中央新幹線 新大阪駅開業に間に合わせたいという思いがあります。
三大都市圏では、リニアなど新しい鉄道インフラがドンドコ整備されていますが、四国には新幹線すらありません。三大都市圏では、リニア開業によりスーパーメガリージョンが誕生し、さらに大きく飛躍しようとしているのに、四国ではなにもしていないわけです。このままでは格差が開く一方です。都会に出ていく若者に歯止めがかかりません。
リニア開業までに四国新幹線を開業させること。これは四国にとって、最後のチャンスだと考えて、われわれ関係者は頑張っているところなんです。
四国4県の足並みは揃っている
――岡山県の協力も必要です。
山本有二 果たして、県が四国4県のために、建設に必要な費用を負担してくれるのかは大きな問題です。だいたい1000億円負担する必要があります。岡山県知事は「採算が合うなら、やっても良い」というスタンスですが、県会議員の中には「四国のために支出する県費はない」と言う方もいます。
ただ、岡山県の経済界は「ぜひやってほしい」と言ってくれています。われわれとしては、このパンドラの箱を開けたいけれども、九州新幹線整備に対し、佐賀県が負担を拒否しているのを目の当たりにすると、なかなか開けられないところがあります。
――そもそも四国4県の足並みは揃っているのですか?
山本有二 徳島県はもともと、岡山ルートではなく和歌山ルートを主張していました。そこで私は「(岡山ルートに)徳島県がついて来ないなら、PTの座長を辞める」と豪語したんです。岡山県知事と面談する機会を得たのですが、「その場に徳島県知事が来なかったら、座長を辞める」と言ったわけです。
面談の日、徳島県知事はその場に来られました。そして、私の手を握って「来ましたからね」とおっしゃいました。私は、徳島県を含め、4県すべて岡山ルートに合意していると承知しています。和歌山ルートは、岡山ルートが開業した後、四国新幹線の枝線として整備を要望していくことになっています。
今年2月、高知市内で開催された四国新幹線に関するシンポジウム。山本議員も冒頭挨拶に立った。
――県民の機運の盛り上がりはいかがでしょうか?
山本有二 昔、高知県民の有志が吉田茂さんに「鉄道をつくってほしい」と要望に行ったとき、吉田さんから「今の時代は鉄道じゃない。道路をつくったほうが良い」と言われたそうです。今私が、高知県民に「新幹線をつくろう」と呼びかけると、「それより高速道路をつくってくれ」と言われます。
ただ、高速道路と新幹線は両方必要なインフラであって、どちらかを捨てるという話ではありません。200kmまでは車、600kmまでは新幹線が優位なので、それをわかっている人間が先頭に立って、その理屈を県民にちゃんと理解させる必要があります。それぞれの県民性だけに任せたら、さらに遅れると思っています。
JR四国では、大人だけではなく、子どもにも新幹線をアピールしています。小学生に「私のまち、ぼくのまちの新幹線」をテーマに絵を描いてもらうコンテストを開催する予定です。優秀作品受賞者には、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに招待する予定です。
その際の移動は、もちろん新幹線です。今は小学生ですが、10年後に大人になったときに、新幹線について前向きに考えてくれることを期待してやっているわけです。
「普通の考えのウラ」をかかないと、事は成就しない
――まずは「岡山〜高松」を通して、次に「高松〜松山」、徳島と来て、最後に「高知」と段階的に整備するのが妥当だという意見がありますが。
山本有二 経済合理性を考えれば、当然そうなります。ところが、九州新幹線を見ると、博多から順番に整備してきたかと言うと、そうじゃないんです。博多駅で工事に着工したのとほぼ同時に、鹿児島駅の方でも工事を始めたんです。鹿児島〜新八代の利用客数はそれほど多くないと目されていましたが、だからこそ、そこを工区設定したわけです。
なぜそんなことをしたかと言うと、博多駅から順番にやっていくと、熊本駅どまりになると考えたからです。先に鹿児島駅の工事を始めれば、途中で止まることはないだろう。それが九州全体の合意だったんです。「普通の考えのウラ」をかくようなことをしないと、事は成就しません。
私は、四国新幹線の工事に着手するのは、各県それぞれで同時に着手するべきだと考えています。場合によっては、県費で始めても良いとすら考えています。上り新幹線で魚や農産物などを貨物を運ぶのも良いかもしれません。
新幹線は夢のある乗り物です。そんな新幹線について考えると、いろいろなアイデアが浮かんできて、楽しいんですよ(笑)。