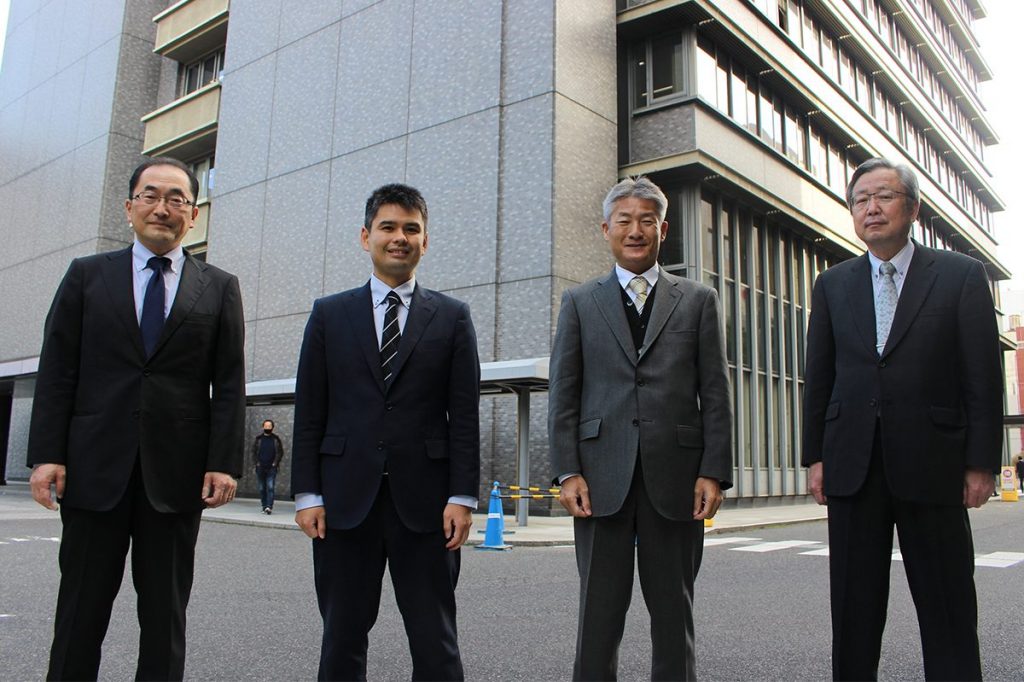プロフェッショナル人材事業とは
プロフェッショナル人材事業とは、各道府県にプロフェッショナル人材戦略拠点を設置し、地域の関係機関等と連携しながら、地域企業の「攻めの経営」への転身を後押しするとともに、それを実践していくプロフェッショナル人材の活用について、経営者の意欲を喚起し、民間人材ビジネス事業者等を通じてマッチングの実現をサポートするもので、東京都と沖縄県を除く、45道府県が参画している。
企業は各地域のプロフェッショナル人材戦略拠点に相談することで、プロフェッショナル人材戦略マネージャーをはじめとした拠点のスタッフが金融機関等と連携しつつ、企業の経営者と丁寧な対話を重ね、新規事業の立ち上げ、販路開拓など、「攻めの経営」に向けた自社の課題と、それを解決するための人材像を明確にした上で、その人材ニーズを同拠点に登録している人材ビジネス事業者に取り繋ぎ、事業者が把握している人材を紹介していく。
さらに、人材のマッチング後にも、関係機関と協力し、企業の経営課題の解決や、成長戦略の実現などに向けて、フォローアップを行っていくものだ。
プロフェッショナル人材戦略事業のイメージ / 内閣府
広島県における人材動向
このプロフェッショナル人材事業制度を活用し、建設人材の獲得に奔走しているのが広島県だ。
広島県では、平成30年7月豪雨の被害からの復旧・復興が急がれる中、広島駅周辺では大型事業・再開発の動きも活発化している。玄関口であるJR広島駅でも、今年3月から新駅ビルの建設工事も始まった。事業費は約600億円で、2025年春に開業予定となっている。広島県の建設投資額は、2017~2018 年度の2年は1兆円を超え、建設企業の生み出す付加価値額も過去10年の中で高い水準に達している。
しかし、一方で建設業の就業者数は減少を続けており、県内の一部地域においては、今後の建設業の持続可能性に懸念が生じている状況で、建設産業の担い手不足が課題となっている。
広島県プロフェッショナル人材戦略拠点の村岡健太氏は「豪雨被害により、未だ道路も復旧されてないところがあり、川の浚渫も5年ぐらい続く見込みだ。今後2~3年は復旧・防災工事の需要が続くだろう。慢性的な人材不足により拍車をかけている」と話す。
広島県の建設業界の現状とは?
広島県における建設投資額は 2012 年度に7,400億円程度に減少したが、近年は増加傾向にあり、2018年度は平成30年7月豪雨への対応もあり、約1兆 1,000億円となり、過去 10 年で最も高い水準となっている。このうち、民間・建築についても2018年度は約5,200 億円と底堅い動きを見せている。このような建設投資の伸びを背景に、県内建設企業の完成工事高も高い水準で推移しており、企業経営についても、過去に比べ高い営業利益を生み出している。
だが一方で、人手不足は顕著に進んでおり、広島県の建設業就業者は、1995年から2015年の20年間で3割以上が減少し、2015年には 10.1 万人となっている。就業者総数は同期間で約 1 割の減少にとどまっていることから、建設業からの人材流出は特に顕著だ。
また、広島県の建設業の有効求人倍率は、全国的にも高い水準にあり、人手不足も深刻な状況にある。建設技術者に限って見ても、県内の土木・測量技術者については、1995年の1.3万人から2015年の約6,000人まで半数以下にまで減少。建築技術者も 1995 年の約 9,800 人をピークに、2015 年は約 4,900人に半減している。とくに、広島県は 20 代~50 代の若手・中堅クラスの技術者の割合が、全国に比べ少ない状況にある。
平成 30 年 7 月豪雨を始め、近時では自然災害が多発・大規模化しており、地域の建設業の衰退は、地域の持続可能性を危うくしてしまう。建設技術者のニーズが極めて高い地域だ。今年10月には、30年後の「あるべき姿」を構想し、10年後の「目指す姿」とその実現に向けた取組の方向性を描いた『安心▷誇り▷挑戦 ひろしまビジョン』を策定している。
産業間競争が激化する広島県
広島県は製造業が最大の産業分野であり、総生産の約3割弱を占めている。今後、人口減少とともに就業者数も減少していくことが想定され、すべての産業で人手不足感が高まっていくことから、産業間での人材獲得がより激化することが予想される。
このような状況下で、建設業については製造業、卸売・小売業と比べ給与水準には優位性があるが、労働時間の長さなどの就労環境から、製造業や卸売・小売業に向く可能性もある。
ただ、広島県における建設業への入職者数は、近年 20~40 代の若手・中堅層で増加しつつあり、2000年代前半の建設投資の減少が続いた時期からは好転している。また、高校卒業者の進路でも建設業は製造業、卸売・小売業に次いで 3番目に位置しており、かつ県内就職率は全国的にも高い状況にある。
これら雇用条件・労働条件については、他産業との人材獲得競争という観点からも、建設業が対応していくべき課題となっている。