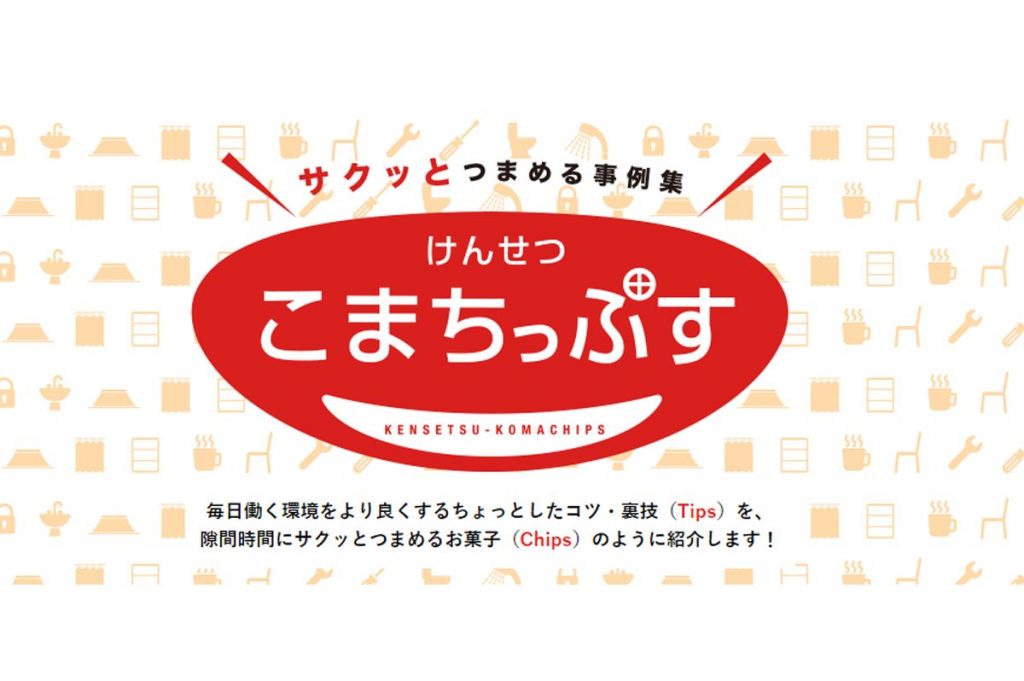「けんせつ小町」誕生の経緯や活動内容
建設業界の女性活躍が叫ばれて久しいが、国土交通省の「建設業活動実態調査」によると、事務職の女性の割合は約4割とまずまずの結果を残した。
一方、女性技術者の割合は、2000年(1.7%)から2020年(7.9%)にかけて約4.6倍の増加を見せているも、未だに1割にも届かない現状がある。やはり現場業務を担う技術者は「3K(きつい・汚い・危険)」であるため、女性に敬遠されやすく、入社してもなかなか定着しにくいようだ。
とは言え、建設業界としても手をこまねいているわけではない。正会員142社を有し、建設業界全体における会員の完成工事高比率は約25%を占める”日本建設業連合会”は、女性の入職を促進し、活躍を推進するべく、2014年に「けんせつ小町」のネーミングを制定し、2015年に「けんせつ小町委員会」を立ち上げた。
それ以降、様々な企画を展開するなど、女性活躍推進に尽力してきたが、正直けんせつ小町がどのような活動をしているのか私自身あまりピンと来ていなかった。そこで、日本建設業連合会 企画調整部の本田一幸氏と市村要介氏に話を聞いた。
愛称誕生のキッカケ
――「けんせつ小町」誕生のキッカケを教えてください。
本田氏 安倍首相は2014年に所信表明演説にて、「女性が輝く社会」を掲げましたが、この流れを受けて建設業界でも女性活躍に本格的に舵を切りました。そこで弊会では 2014年10月、建設業で活躍する女性の愛称として「けんせつ小町」が公募によって決定したのが最初です。
――プロジェクトというよりは名称なのですね。
本田氏 そうです。ちなみに、けんせつ小町は現場技術者・技能者だけでなく、事務職や営業職も含めたすべての女性の愛称になります。ですので、建設業界に従事する女性が働きやすい、働き続けられる環境を整備するためのプロジェクトと言って差し支えないです。
――けんせつ小町は、2014年から具体的にどのような活動を行ってきたのですか?
本田氏 最初に取り組んだことは、女性が働きやすい環境を整備しているかどうかを確認する”現場環境整備チェックリスト”の作成です。男性用トイレしかない現場も多かったので、まずはトイレ・更衣室などから確認する必要があると考えました。
「女性用トイレは男性が無断で使用できないよう外側から施錠管理している」「現場において、鏡付きの洗面所を設置している」などのチェック項目があります。当時リストは紙でしたが、最近では手軽に利用できるWeb版も公開しております。
現場環境整備チェックリストWeb版
また、もう一歩踏み込み、毎日働く環境をより良くするちょっとしたコツ・裏技(Tips)をまとめた「こまちっぷす」も最近公開しました。
トイレに化粧品や小物の収納ができる小物入れの設置、後付け設置可能な女性用トイレなど、女性が安心して働ける環境を整備する事例を写真付きでまとめています。現場立ち上げや、はじめて現場環境整備を担当した方にぜひ活用していただきたいです。
「こまちっぷす」で公開されている事例集
多種多様なテーマでセミナーを定期開催
――現場改善以外に何をされていますか?
本田氏 “けんせつ小町セミナー”という定期的なセミナーを開催しています。当初は、女性活躍に関する知識インプット型のテーマが中心でしたが、最近は性別に関係なく、誰もがいきいきと働ける現場作り・建設業界にすることを目的とした内容となっています。
具体的には、「アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)」や「自己肯定感の高め方」といった、他業界でも好評でかつ、多種多様なテーマで行われています。手法も、対話型を取り入れ、普段接することのない同業他社の参加者同士の交流の機会にもしています。
また、2015年から5回ほど、けんせつ小町の活躍推進に資する活動やけんせつ小町自身の活躍を顕彰する”けんせつ小町活躍推進表彰”も開催しました。
週に一度、従業員が集まってお互いの良いところを褒め合う”褒めパトロール”を実施した大成建設さん、女子大生が作成した仮囲いデザインを実際の現場仮囲いで実現した熊谷組さんなど、バラエティに富んだ活動が受賞されています。
――こういった企業がロールモデルとして、他社の参考になると良いですね。
本田氏 はい。また、最近力を入れているのが、建設現場で施工に携わっている女性がリーダーとなって、現場の環境改善に取り組んでいるチーム”けんせつ小町工事チーム”です。
けんせつ小町工事チームに登録することで、「女性も現場で働いている」という求職者に向けたPRになりますし、実際の活動内容をけんせつ小町HPに載せ、FacebookやInstagramなどで発信しています。現場で女性が働いていることを自然なかたちでアピールし、ボトムアップ式に業界の空気感を変えていきたいと思っています。
――現場を意識した活動が盛んなのですね。
本田氏 はい。そのほか、小中学生を対象に、毎年夏休みシーズンには”けんせつ小町活躍現場見学会”といって、実際に女性が働く建設現場を子供たちと保護者に見学してもらい、現場の仕事に触れてもらうというイベントも開催しています。
2020年、2021年は新型コロナウイルスの影響で中止しましたが、これまでは予約がすぐに埋まってしまうほど好評でした。「建設業・施工業=男性の仕事」というイメージを払しょくし、業界に親しみをもってもらう狙いがあり、建設業界に従事していない人に向けたアピールも展開しています。
量だけでなく質においても平等に近づいている
――建設業界の男性中心主義は根強そうですが、この空気感は変えられそうですか?
本田氏 それが、けんせつ小町活動において最大の課題です。女性のため、女性のみが集まった活動というイメージを変えていくことに現在は取り組んでいます。
――実際に現場を見て「変わったな」と感じるシーンはありますか?
本田氏 感覚的な印象ですが、女性の現場監督の割合が圧倒的に増えたと思います。また、女性若手社員が増えたこともあります。同期の男性社員と同じ負荷の業務量を任されていることも当たり前になり、量だけでなく質においても平等に近づいている印象を受けました。また彼女たちも、それを望んでこの業界に入っている覚悟もありますね。
市村氏 私も感覚的ではありますが、現場の雰囲気が変わったように感じます。以前よりも整理整頓されるようになり、花を飾る事業所もあって驚きました。ただこれは、”女性=花が好き”という話ではなく、画一的ではなく現場ごとの個性が可視化されるようになり、働きやすい空間作りに関する声を挙げられやすくなったからだと思います。
現場風土や文化を変えていくためのキッカケ作りが重要
――徐々にではありますが、女性活躍は着実に進んでいるのですね。
本田氏 とは言え、弊会は元請の業界団体ですので、直接的に会員企業やその現場に介入する強制力はありません。会員企業の管理職の方や、現場の最高責任者である所長やその候補者に向けたセミナーを実施することはできます。ただ、実際に得た知識や情報を現場に反映させるかどうかは、その会社やそこに所属している方々次第です。
また、会員企業の役職員だけでも約15~20万人はおります。これだけの規模の母体だからこそ、一方的かつ直接的な単純なアプローチは難しいです。ある施策を展開し、それで問題が解決できるならとっくに解決しているはずです。
だからこそ、セミナーなどのイベントやWEBを活用したオープンな情報発信などを粘り強く継続的に展開し、少しずつ現場の風土・文化を変えていくためのキッカケ作りが大事だと思います。
――思っていたよりも前途多難ですね…。
本田氏 はい。アンケートを取っても「男女別のトイレ・更衣室を設置して!」という不満の声も少なくありません。ただ、仮にそれらの問題を100%クリアしても、真の意味のダイバーシティの実現、男女ともに働き続けられる業界になるかは別次元の問題だと思います。もちろん、トイレや更衣室といったハード面の問題改善は当然のことですが。
ハード面は非常にわかりやすく、そこばかりに注目されやすい。本来はハード面だけでなく、男性社会の根強い空気感を変える、ソフト面に対するアプローチも同時に進めなければいけません。
表彰で受賞した活動は、ハード面だけでなくソフト面も優れており、「結婚や出産を経験しても現場で働き続けたい」という声に上司が真摯に耳を傾けながら実行に移しています。逆に、ハード面ばかりに気をとられていると、いつまで経っても現場の本質的な課題の改善は進まない。わかりやすい部分(ハード面)に囚われない運営を、今後はより一層意識しなければいけません。
――男性中心の空気感、つまりソフト面を改善する際に何がネックになっていますか?
市村氏 やはり”女性技術者=レア”という先入観が根強いことが影響しています。けんせつ小町を展開することで、多少は空気を換えることはできているかもしれません。それでも、現場仕事は身体が資本になるため、他の業界よりも”男らしさ”をイメージしやすいことが影響していると思います。
本田氏 トイレや更衣室といった現場改善だけでなく、”育休取得の向上”といった制度におけるハード面も着手しています。ただ、現在の男性上司、役員層は育休を取得せずに仕事中心のキャリアを歩んできました。
そうした価値観の方が経営層に大半を占める場合、そもそも男性が育休を取得する、それ以前に男性が家事育児に携わることさえ理解を示してもらえないことも珍しくありません。”マッチョに働いてきた男性”が決定権を持っていることは大きいです。
誰もが「働きやすい、働き続けたい」と思える業界に
――ソフト面改善のためにどのような対策が必要ですか?
本田氏 いかに男性を巻き込めるかが重要だと思います。「更衣室を設置してほしい」「育休を数ヶ月間取得したい」と考える男性も少なくなく、”女性活躍を推進することが、まわりまわって自分たちにも良い影響をもたらす”ということ知ってもらうことが今後の課題になると思います。
ただ、「けんせつ小町・女性活躍=女性優遇・男性にデメリットがある」という認識が強く、余計に反発されやすい。男性側の心理を酌みつつ、男性に応援されることが希望につながるのではないでしょうか。
――男性も、女性活躍を自分事として考えられれば良くなりそうですね。
本田氏 はい。また、「もっと女性が活躍できる建設業を目指す」というキャッチコピーを掲げたのですが、「女性のやる気が足りない!」「なんで女子だけ活躍?」などを連想させ、実は女性の評判があまり良くなかったんです。けんせつ小町は、女性活躍のためだけではなく、誰もが不自由を感じることなく自分が働きたいように働ける取り組みとしてPRしていきたいです。
――けんせつ小町として、今後はどのように活動されるのでしょうか?
本田氏 2019年にこれまでの活動方針を見直しました。正直、いろいろな企画を講じてはいましたが、これまでの活動は「建設業界は人手不足だから」という前提の下、女性活躍が進められていた節があります。それでは、一般社会に共感されませんし、仮に入職者が増えたところで定着はしません。
4年間活動をし、けんせつ小町の委員さんたちともじっくり対話した上で、2019年に今後5年間の活動方針を定めた「けんせつ小町活躍推進計画」(2020~2024年度)を発表し、けんせつ小町の新しい柱として「定着」「活躍」「入職」の3つを掲げました。
女性のみならず、男性であっても離職する人は多いです。先述した通り、特定の枠を設けずに、誰もが「働きやすい」「働き続けたい」と思える業界に整備するために活動していく方針を固めました。
今後はこの方針を羅針盤に実行に移していきます。現在、けんせつ小町のリ・ブランディングを”ちゃく、ちゃく”と進めているところです。2022年4月に公表予定ですので、その際にはまた施工の神様でもぜひ取り上げてください(笑)。
市村氏 将来的には、けんせつ小町という言葉を無くせるよう、建設業界で働く人が壁を感じなくなるように頑張りたいです。