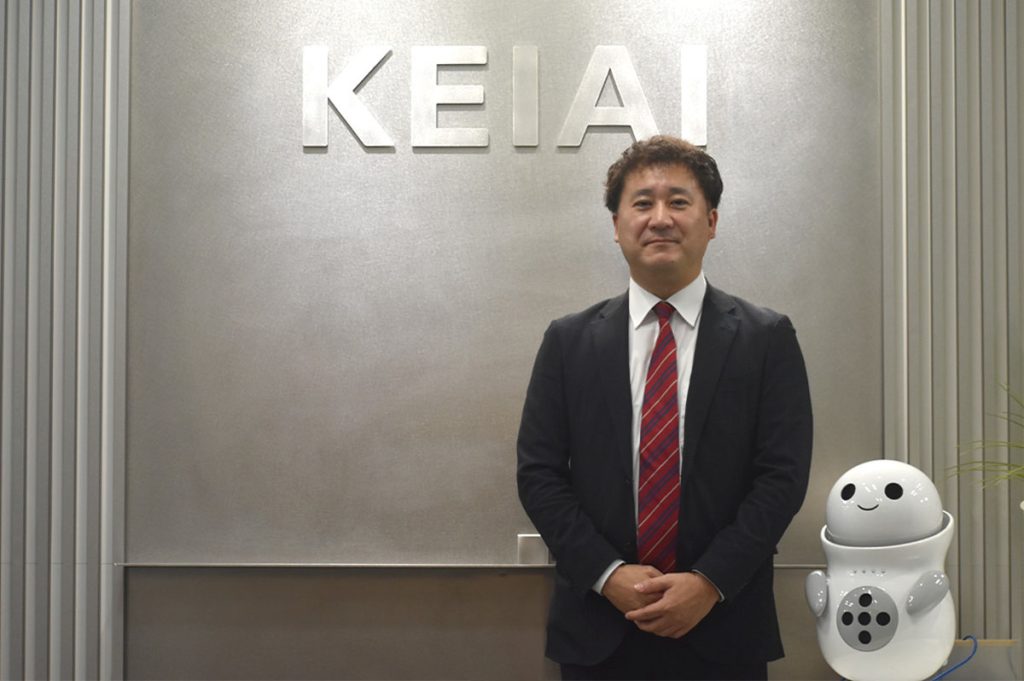戸建て新築着工戸数は年々減少傾向にある。国土交通省の2023年建築着工統計調査報告によると、新設住宅着工戸数は前年比4.6%減の81万9,623戸まで減少。人口減により、今後も大きな回復を見込めないが、落ち込みつつある住宅市場にあって、急成長中の分野が「平屋住宅」だ。国土交通省の同調査によれば、全国の新築の木造平屋住宅の着工棟数は2012年度の約27,000棟に対し、2022年度には約52,000棟へと倍増している。
拡大を続ける平屋市場において、ケイアイスター不動産(埼玉県本庄市)のグループ会社・ケイアイネットクラウド株式会社(東京都中央区)では、規格型平屋注文住宅「IKI(イキ)」シリーズを展開。IKIは規格型のプラン、工法、資材の大量一括購入で安価に仕入れる優位性をもとに、ローコストの注文住宅として幅広い世代からの支持を集め、平屋市場でのブランドを確立しつつある。昨年にはIKIシリーズを軸としたフランチャイズ(FC)事業「IKI.net」(イキドットネット)も開始し、さらに展開を加速中だ。
今や、“平屋住宅戦国時代”とも言われ、各ハウスメーカー、工務店やビルダーがしのぎを削る中、ケイアイネットクラウドはどのような戦略で平屋住宅市場に望んでいくのか。同社のネットワーク事業推進部次長 安田秀一郎氏に話を聞いた。
規格化で800万円台から平屋を提供
――ケイアイネットクラウドの事業内容を教えてください。
安田秀一郎氏(以下、安田氏) 母体のケイアイスター不動産は、土地を仕入れて住宅を建築し販売する戸建分譲事業がメインですが、ケイアイネットクラウドは非戸建分譲事業になります。具体的には、顧客が購入・所有している土地に建物の商品を提供する注文住宅事業です。
また、不動産事業のノウハウを活用し、全国で不動産事業の立上げを希望される事業者に向けて「KEIAI FC」(ケイアイエフシー)という不動産仲介業のフランチャイズ(FC)事業も展開しており、現在は北海道と沖縄を除く、北から南まで100社弱の企業が参加する全国ネットワークを構築しています。そして、FC事業の第2弾として、ケイアイネットクラウドが設計・施工し、すでに3年間の販売実績がある規格型平屋注文住宅「IKI(イキ)」シリーズを軸とした建築事業「IKI.net」(イキドットネット)を2023年10月1日から開始しました。私の役割は両FCのネットワークの拡大や、加盟いただいた企業を支援するスーパーバイザー(SV)の責任者になります。
IKI (株)の群馬県太田市下浜田 平屋展示場(モデルハウス)
――IKIの強みはどこにあるのでしょうか。
安田氏 “ローコスト” と“集客力”です。IKIは規格型の注文住宅ですので、広さは17坪、19坪、24坪、27坪と決まっており、お客様にはこの中からプランを選んでいただくかたちになります。通常の注文住宅ではゼロからのスタートで時間もかかりますが、IKIでは6帖ユニットでパターン化し、おさまりも決まっていますし、建材も同一製品を扱うため施工性も高く、施工費用を抑えられます。加えて、ケイアイスター不動産では、年間7,000棟以上(土地含む)の分譲住宅を提供しており、このスケールメリットを活かした材料調達もあわせることで、1LDKの17坪台のサイズで材料調達もあわせることで、坪単価40万円台からご用意しています。
敷地面積としては50坪ほどの土地が必要になるため、現在は埼玉県北部、群馬県、栃木県や茨城県といった地域からの受注をメインとしながら、年間約100棟を手掛けています。
【経験者歓迎】リゾートホテル新築工事の建築施工管理求人 [PR]
リモート接客で成約率が4倍に
――集客力のポイントは?
安田氏 家を建てたい方が住宅会社をお探しになる際は、まずは大手ポータルサイトへアクセスし、地域にどのような住宅会社があるかを調べて、その中から気に入った住宅会社のホームページにアクセスするのが一般的なフローです。しかし、当社はSEOに注力し、集客経路を最適化しています。例えば、「平屋 ローコスト」と検索するとIKIのサイトが上位に表示されますが、これによりお客様がダイレクトに当社のサイトへとアクセスしていただけるため、集客率も成約率も高くなっています。また、表示回数が増えることで「ローコスト平屋といえばIKI」という認知も高まり、ブランディングにも繋がっています。
また、コロナ禍により住宅業界全体でモデルハウスでの集客がほとんどできなくなった中で、リモート接客を専門に行うロボット部を立ち上げて、他社に先駆けて無人内覧(リモート接客)を推進してきました。リモート接客では、まずはモデルハウス内の案内ロボットを通してロボット部の社員が来場されたお客様の対応をし、お客様が前向きに購入をご検討されてから、初めて営業スタッフが有人で対応するように接客フローを変えました。
モデルハウス案内ロボット「ミレルン」による説明
これにより、従来の体面による接客と比較して、成約率は約4倍に跳ね上がりました。初回内覧時の営業スタッフとのコミュニケーションに負担を感じる方は多いですが、リモートでの接客によりお客様はゆっくりと内覧することができますから、とくに若い世代の方に好評でした。
住宅購入は、営業スタッフとお客様の関わり方が非常に重要です。良い住宅会社であっても、営業スタッフとの折り合いが悪いと、そこで関係が終わってしまいますから。リモート接客により、いわゆる“営業ガチャ”がなくなったことは、IKIの営業戦略としてもうまくはまりました。
平屋市場が10年間で2倍に増加した理由
――平屋というとシニア層のイメージがありましたが、いまのお話にもあったように若い方の購入者も増えているのでしょうか。
安田氏 そうですね。昨年、「SUUMOリサーチセンター」は“平屋回帰”を住まいのトレンドキーワードとして発表していますが、人口減少社会の日本の住宅市場において、平屋は数少ない成長セグメントの一つです。新築住宅の全体着工戸数は100万戸数時代から下落を続け、今後もさらに減る一方でしょう。しかし、平屋住宅に限定すると、この10年で約2倍の伸びを示しています。国土交通省の建築着工統計調査によると、全国の新築の木造平屋住宅の着工棟数は2012年度の約27,000棟に対し、2022年度には約52,000棟へと倍増しています。
平屋の新築着工棟数は10年で約2倍に / 国交省の調査をもとにケイアイネットクラウドが作成
――なぜ、“平屋に回帰”しているのでしょうか。またその中でIKIが選ばれる特徴はなんですか?
安田氏 まず、ご年配の方のケースですと、お子さんが独立したあとにご夫婦で住まわれるケースが増えています。お子さんがいるときは2~3階のスペースが必要になりますが、お子さんが独立されたあとに使わない部屋が増えたり、同じ規模で建て替えるとなると、費用面でも老後の大きな負担となります。また、高齢になられてからは階段の上り下りも負担になるため、利便性が悪くなります。そのため、必要な広さで快適な生活を送る事のできる平屋はご年配の方から高い人気があります。
一方、若い世代ですが、コロナ禍でリモートワークが定着し、郊外に広い土地を購入される方が増えてきました。そこにマンションと似たワンフロアで家事導線など利便性が高い平屋のニーズがマッチしました。また、今の世相では離婚される方も少なくなく、シングルマザーも増えていますが、これらの理由で平屋はちょうどいいサイズで若い世代にも人気があります。
あとは趣味を大切にされている方からの人気も高まっていて、当社としてもこうした方々に向けてはガレージプランをご用意しています。時代の変化もあり、本当に幅広い層の方々から支持されているように感じています。その中でもIKIは規格型プランで分かりやすく価格が抑えられる点が選んでいただける特徴と考えています。
FC展開でIKIの全国展開へ
――FC事業の「IKI.net」の進捗はいかがでしょうか。
安田氏 主に工務店、または不動産仲介FC「KEIAI FC」の加盟店で建築分野に参入されたいとの意向を持つ事業者を対象にPRしているところで、現在参画している企業はすでに10社を超え、毎月加盟店が増加しています。当面は100社の加盟獲得を目指しています。
規格型平屋注文住宅「IKI」シリーズを軸としたFC事業「IKI.net」(イキドットネット)がスタート
――地域の小規模の工務店は生き残っていくのが難しい時代ですが、FC加盟のメリットは?
安田氏 中小工務店には、「商品力」「集客力」「資材の調達力」「人材力」の4つの課題があります。自社で独自の商品を開発することは難しいですし、インターネットを活用した集客手法が確立している企業も多くありません。仕入れについても年間数棟ほどの施工では資材を高く仕入れざるを得ませんし、営業手法を凝らしてスムーズに受注していくことも簡単なことではありません。
IKI.netでは、こうした悩みを抱える工務店に向けて、IKIで培った次世代の注文住宅事業経営手法を基にDXサポート・IKIブランド使用権の提供・マーケティング・送客・部資材提供・建築サポートという総合的なバックアップを行っています。
――工務店からの反響はいかがですか?
安田氏 平屋も含めた他社の住宅建築のFCと比較されることもありますが、先ほど申し上げたバックアップ体制をお伝えすると、非常に前向きに検討いただけています。また、当社では事前に市場調査を行うのですが、地域によっては年間10棟以上の反響が予測されることもあり、驚かれる方も多いです。
発足当初は関東、東海を中心としていましたが現在は中部、近畿からの反響も増えてきており、九州も平屋住宅の需要が高い地域のため、今後は全国展開を積極的に進めていく考えです。