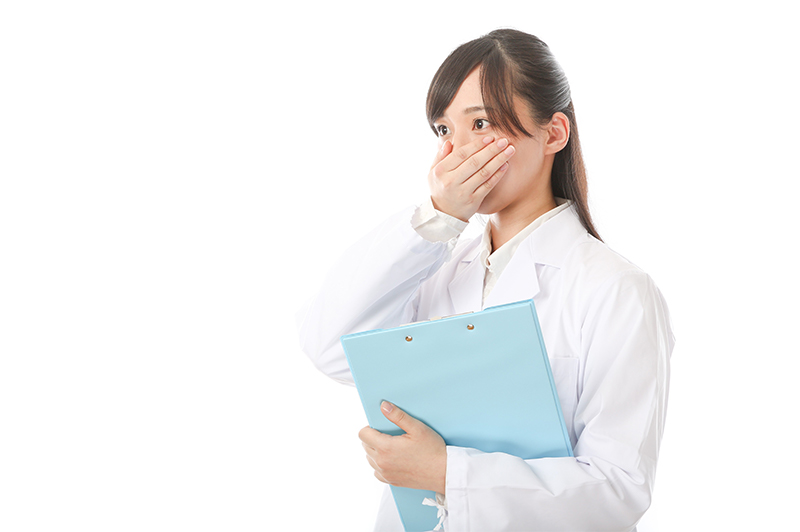振動、騒音、薬品…繊細な生物研究施設の改修工事
改修工事の施工管理では、個々の物件について臨機応変の工事が必要となる。私自身、特殊な条件下での改修工事にいくつも携わってきたが、その中で最も特殊だった事例を紹介したい。
その改修工事とは、生物研究施設の内外の改修工事である。建物の構造はRC造で、外壁はレンガタイル、屋上はシート防水。単純な矩形の形でなく、いくつかの建物が繋がった複雑な形だ。
工事概要は建物全体の調査、必要個所の内部改修と補修、外壁タイルの剥離調査と補修、防水やり替え、各階研究室の改修。工期は1年だった。
昆虫や爬虫類への影響も配慮した改修工事
私は当時、この生物研究施設の建築物全般の施工監理と同時に工事管理を担当していた。
研究所の構造は、本館に管理棟と展示棟が増築され、それぞれが渡り廊下で繋がった、かなり複雑な建物だった。さらに各階の研究室から排出される有害ガスを含んだ多数の配管が、バルコニーを貫通して外壁沿いに立ち上がり、屋上にはそれらのガスを浄化する多数のスクラバーが設置されていた。
各階は中央に廊下を配し、研究室の個室が左右に並ぶ。各部屋は研究者が自由に改造していて、研究者が入れ替わるたびに細かな壁や設備が付けられたり撤去されたりと、私は工事以前に各階の状況把握の図面作成から始めなければならなかった。
工事は研究者がいる昼間だけ
研究所の建物内には、昆虫や爬虫類などの小動物から、麦や米の生育を研究する研究者まで、様々な生物の研究者が集まっていた。多くの人たちが使用中の建物の内外改修は、一番面倒な工事である。
せめてもの救いは、夜は無人になることであった。そこで私は、面倒な工事は夜間工事で対応しようと思ったのだが、そうはいかないのが、この現場泣かせの研究施設であった。
多くの研究室では、夜間も様々なデータを取っているので、過剰な騒音や振動を伴う工事は、研究者がいる昼間に限定されたのである。特に小さな生物を扱っている研究者が多いため、有害なガスを発生する可能性のある塗料や防水材などは詳細な成分説明が要求された。
工事以外の多くの調査が不可欠な改修工事
調査や図面作成が多い場合は、そのための時間と費用をハッキリさせておくのも、施工管理者の大事な仕事である。
この研究施設の改修工事では、まず着手できる場所から工事を始め、それと並行して調査や図面作成を行う平凡な手順で工事を始めた。
まず、それぞれの研究室の現状を図面にして、その図面を元に各研究者の希望改修案を聞いていくわけだが、総予算や工事期間が決まってるので、こちらとしても個別に勝手な返事は出来ない。全員の話を聞き終わってから、全部を総合的に判断しなければならない。
かつ、正確な返事をするためには、壁を解体したり、配管を調べたり、工期時間と費用を推定しなければならず、その調整は研究者同士の上下関係も絡み、決定されるまで予想外に時間が掛かってしまった。
そうした調整を重ねながら、同時に各研究室の工事期間の希望時期を聞いてまわる。なにしろ全部で200以上の研究室が集まってるのだから厄介だ。一応希望を聞いた上で、あくまでこちらの予定に組み込んでいく方向で進めていった。
改修工事における「無理な注文」への対応方法
本館の他に別棟にも実験室や飼育室を持っている研究者たちは、それほど問題なく調整できたが、研究室の中や外のバルコニーで生物を飼育したり生育させたりしている研究者からは、相当細かい指示があった。
研究者いわく、生き物は環境の変化に敏感で、すぐ新たな環境に適応しようとする。工事の騒音・振動、薬品の臭いなどは、本来の変化とは別に、一種の突然変異として表れてしまうので、絶対避けなければならない、と念を押された。
「じゃ止めましょうか?」と言いたい気持ちをグッと堪えて、ここは冷静に話を聞く場面だ。 建設工事、特に改修工事ではしょっちゅう出てくる場面である。
ここでしっかり相手の言い分を記録し、どんな無理なことでも全部記録しておくことが、のちのち役に立つ。相手だって自分の言ってることに無理があるのは分かっていながら言ってくる場合がほとんどだ。
要するに、改修工事の施工管理業務では、相手が想っていることを全部言わせてあげる、空っぽになるまで話を聞いてあげる、という仕事が重要である。ここに費やした時間は決して無駄にはならない。急がば廻れである。
「どうせ納得しないんだから」とか「結果駄目でした」という気持ちで応対していては、相手だって納得しない。見せかけだけの誠意は逆効果と思ったほうがいい。どんな小さな要求でも、実現可能なことは協力する気持ちを決して忘れてはいけない。
利害関係者の感情をこっちのペースに引き込む方法
どんな工事でも、人間を相手にしてる以上、理屈を超えた「感情」が最後の決め手になる。建築工事といえども、理屈だけで相手を説得するのは難しい。そして強引で一方的な決定は、後々の問題の火種になる事が多い。
しかし、様々な立場の人間が関わってる以上、特定の意見だけを聞き入れることは不可能であり、実際はどこかで線引きをしなければいけないのが現実だ。
そうした説明をする時に、関係者からヒアリングした詳細な記録が役に立つ。相手が忘れているような事柄まで、細かい話を持ち出せば、相手は徐々に心を開く。ほとんどの場合、相手の要望は聞き入れられないが、こちらから小さな提案を用意することも忘れてはいけない。
この研究施設の改修工事でも、ほとんどの研究者達に「NO!」の結論を伝えなければならなかった。せいぜい工事の時間帯や日程の希望ぐらいしか希望は叶えられなかった。激昂した研究者もいたが、それはそれでしょうがない。
私に怒ってもどうしようもないが、不満の持って行き場が無いのも良く分かる。「どうせ怒られるなら、手間暇をかけた時間がムダじゃないか!」と言う技術者もいるかも知れないが、それは違う!
狂った躯体壁の「直角」を、仕上げで調整していた!
研究施設の改修工事で実際に一番手間取ったのは、外壁タイル工事だった。調査の段階でタイルの浮きを調べたところ、ほとんどのタイルが浮いていた。剥離、剥落してる箇所も多い。酷い箇所では、総重量にして100kgもの塊が落下していた。
調査の結果、元のコンクリートの躯体壁の直角が狂っていることが判明。それをタイル壁面の仕上げで調整したのだろう。幾層にも下地を塗った痕跡も見つかり、タイル貼代は最大120になっていた。
そこで私は、工事中のタイル落下を考え、建物への出入口を最小限に集約し、仮設屋根を設けることにした。そして落下寸前の危険なタイルを全部除去したのだが、その量が予想をはるかに上回る面積になった。
しかし、全部のタイルを貼替える予算は組まれていないという問題が出てきた。一応、公共工事であるため、予備調査が行われた上で、予算は組まれている。そこで総工事費の仕事の内訳を変更し、総工費はそのままで工事を続けることになった。
工事の中身を変えられない以上、どこかで金額の調整をしなければならないので、金額の大きい順に同等の代価品を考え、節約案を練った。が、タイルに掛けられる金額の上限が決まっただけで、必要数のタイルを全数貼替えるまでは届かなかった。
結局、浮き部分はエポキシ樹脂注入後ピン固定として、剥落部分はアンカー打設にステンレス網を絡ませ、樹脂モルタルを塗ってから新たにタイルを貼った。
タイルの色も当然焼き色が違い、自然なまだら模様になるように配置するのは相当苦労した。
改修工事は「変更」への心構えが必須
他にも、屋上の防水、各階のバルコニーの工事の時間と時期調整など、職人には随分と苦労をかけた。
フタを開けてみるまで分からないのが改修工事だが、本工事もまさしくその通りだった。どんなに事前調査をしても、いざ工事を開始すれば、予想外の事態に見舞われる。
だからこそ、住んでる人や使用している人がいる建物の改修工事では、工事の説明や時期、打ち合わせ内容が変更になることも珍しくないと肝に命じておくべきだろう。