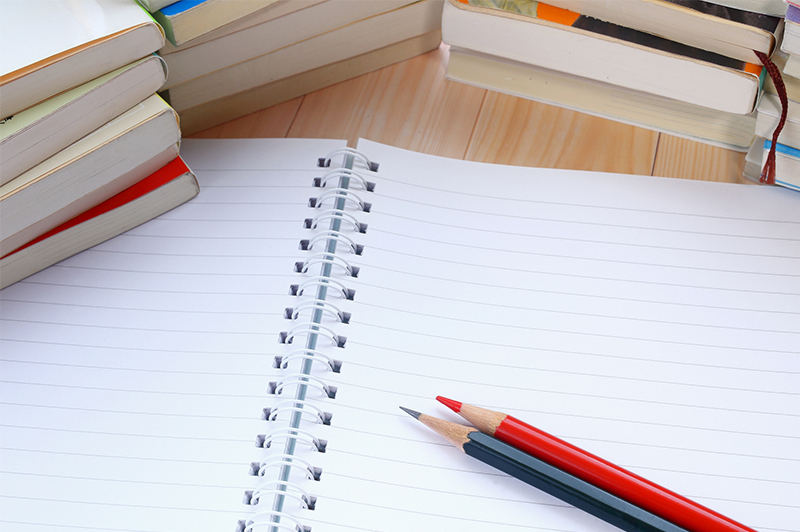「技術士第二次試験」受験記
9月22日に技術士二次試験(建設部門の施工計画、施工設備及び積算)の筆記試験を受験した。
受験した直後の感想としては、「準備不足があった。合格か不合格か、微妙なところ…」である。とはいえ、問題自体はこれまでと比べて大きく変わったりイレギュラーな内容ではなかったので、しっかり準備して臨めば十分合格できるといえる内容でもあった。
私は今回の技術士受験は初めてであり、何をどう準備すればよいか手探りしながら勉強を進めてきたのだが、受験したこと自体は貴重だったと思っている。そこで、実際に受験をしてみて分かったこと、押さえておいたほうが良いポイントなどをまとめてみた。
受験にあたり必ず取り組むべきもの
受験にあたり、必ず取り組むべきものがある。それは、「解答文骨子の作成」だ。なぜ必ず取り組むべきかというと、受験の準備だけでなく受験後にも必要になるからだ。
骨子を作成しておくことで、出題内容に合わせたキーワード抽出と論文構成が容易になる。こういう問いが出たらこう答える、こういう構成で論文を書く、ということをあらかじめ頭に入れておくことができる。つまり、論文執筆がとても簡単になるのだ。さらに書き始めてから大きな手直しの発生を回避できる。
そして、骨子は受験後にも役立つ。骨子を手元に残しておくことで、受験後の論文復元が可能になる。なぜ論文復元が必要かというと、筆記試験合格後に行われる口頭試験に必要だからだ。
口頭試験では筆記試験での解答を踏まえて質問がされると聞いている。論文を細かく復元できなくても、キーワードをあげて論文要旨を書いておくだけでもいい。また、仮に筆記試験が不合格であったとしても、次回の受験への振り返りができる。
骨子は問題用紙の裏面にでも記載しておけばいい。問題用紙は持ち帰りができるので、問題用紙を活用して骨子を書いておき、受験後なるべく早いうちに論文復元もしくは要旨作成をしておくことが望ましい。
必須科目への対策
今回の試験は、中小建設企業の担い手確保に関する内容と、老朽化するインフラ施設をどう戦略的にメンテナンスするか、を問う内容であった。どちらも、何かしら自分なりに問題点と解決法を整理できていれば、回答可能な内容であったと思う。
昨年と少し変わった点として、設問が一つ増え、少し踏み込んだ問いかけがあった。自分が責任者としてこれらの問題に向かうにあたって、どう取り組むかを考えておいたほうがいいかもしれない。
必修科目は、建設産業全体に関する内容が問われる。国土交通省が公表する建設白書に目を通しておくことをお勧めする。また、最近は新型コロナウィルス感染拡大に伴い、いくつかのリリースが国交省から発出されており、それらのチェックも可能な限り行う。
さらに、新・担い手三法(品確法、建設業法、入契法)も最近改正が行われており、チェックしておきたいところだ。
その他、建設産業ではよく出てくる話題として、人口減少に伴う人材不足や災害対応、老朽化していくインフラ施設の維持修繕に対して、自分なりの問題点とそれに対する解決法などをまとめておくといいだろう。
選択科目の問題構成
選択科目は、昨年と同じ問題構成であった。
Ⅱ-1では、基本的な知識が問われる問題が出される。例年と同じく、土やコンクリートについての基本知識を問う問題、安全管理に関する問題、契約に関する問題であった。Ⅱ-1は、基本を勉強しておけば対応できる問題である。それぞれの得意分野があると思われるので、得意分野に絞って勉強しておけばいいだろう。
Ⅱ-2についても例年と同じく、具体的な条件が提示されたうえで、施工計画を立てる際に調査・検討すべき事項や業務の手順、関係者との調整方策を問う問題である。こちらはある程度の経験が必要になると思われる。ある程度の経験があれば、十分対応できる内容であったと考える。
Ⅲについては、過疎地域におけるインフラの維持・更新についてと、元請けと下請け間の適正な契約について問われる内容であった。設問も昨年と大きく変わってはいないが、少し踏み込んだ問いかけがあった。専門技術を踏まえた回答を求められる内容が含まれているので、それぞれの専門技術をどう盛り込むか、専門分野とどう関連付けられるかを整理しておくといいだろう。
受験申込書も手を抜くな!
ここまで受験記を述べてきたが、もう一つ重要な項目がある。それは、受験申込書だ。申込書作成には、実務経験証明書の作成が含まれている。この証明書作成をしっかり作り込むことが重要だ。
必要な実務経験の記載はもちろんだが、業務内容の詳細の取りまとめがかなり重要視されるとのことだ。業務での立場や役割、成果、問題をどう解決したか等をうまくつなげてまとめておく。
これは口頭試験でも問われる可能性があるとのことだ。技術士試験において、申込書作成から手を抜いてはいけない。試験はここから始まっているのだ。