必須科目への対策
今回の試験は、中小建設企業の担い手確保に関する内容と、老朽化するインフラ施設をどう戦略的にメンテナンスするか、を問う内容であった。どちらも、何かしら自分なりに問題点と解決法を整理できていれば、回答可能な内容であったと思う。
昨年と少し変わった点として、設問が一つ増え、少し踏み込んだ問いかけがあった。自分が責任者としてこれらの問題に向かうにあたって、どう取り組むかを考えておいたほうがいいかもしれない。
必修科目は、建設産業全体に関する内容が問われる。国土交通省が公表する建設白書に目を通しておくことをお勧めする。また、最近は新型コロナウィルス感染拡大に伴い、いくつかのリリースが国交省から発出されており、それらのチェックも可能な限り行う。
さらに、新・担い手三法(品確法、建設業法、入契法)も最近改正が行われており、チェックしておきたいところだ。
その他、建設産業ではよく出てくる話題として、人口減少に伴う人材不足や災害対応、老朽化していくインフラ施設の維持修繕に対して、自分なりの問題点とそれに対する解決法などをまとめておくといいだろう。





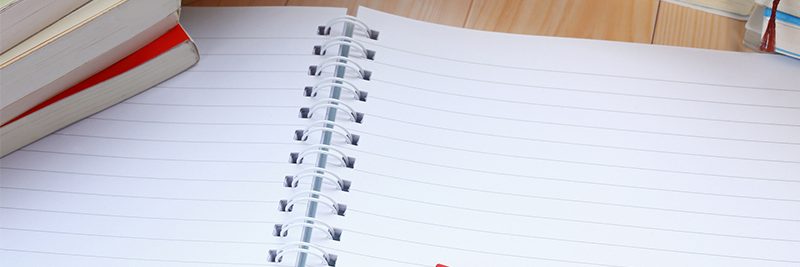

頑張ってください。
1/8の筆記試験の結果と、今後のご予定を教えて頂きたいです。
勉強方法の参考にさせて頂きたいと考えております。
宜しくお願い致します
筆者(セキサンシロート)です。返事が遅くなりました。
結果は不合格でした・・・。
また改めてチャレンジを考えてます。
大丈夫です。
某スーパーゼネコンの奴らも全然受かりません。
それでも工事長になるので大したもんです。
某マリコン最大手でも技術士持ってなくても土木部長になれるので大したもんです
私も建設コンサルタントで設計業務(道路設計・道路構造物設計)に従事する技術者です。
設計と施工の乖離をなくし、速やかに施工に取り掛かれるような設計計画を立案したく、セキサンシロートさんと同じく、設計屋ですが技術士二次試験は「施工計画,施工設備及び積算」で受験しており、今年、やっと合格に至りました。
著者さんも大変苦労するかと思いますが、コツコツと知識を積み上げ、合格を勝ち取ってください。
ゼネコンマンだと持ってても特に役に立たない資格。
技術者同士でマウントとるのにはいいかな。
よっぽどアーク溶接のほうがコスパがたかい。