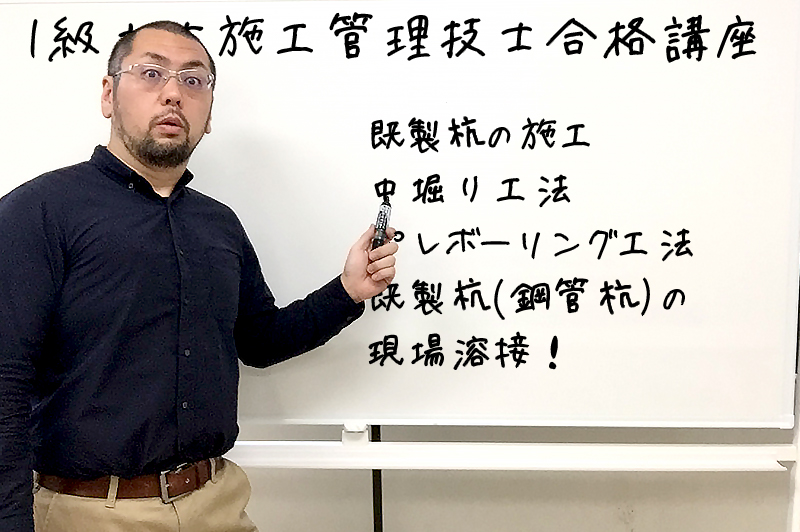1級土木施工管理技士 過去問分析に基づく試験合格対策 基礎工「既製杭の施工・中堀り工法・プレボーリング工法」の勉強ポイント
1級土木施工管理技士 過去問分析に基づく試験合格対策の第9回目は、基礎工「既製杭の施工・中堀り工法・プレボーリング工法」についての勉強ポイントをまとめます!
「既製杭の施工(杭の建込・打ち込み)」の出題傾向
既製杭の施工に関する問題では、杭を建て込む施工上の留意点に関する正誤を問う問題が多く出題されます。
- 杭を建て込むときの鉛直性は、杭に対して直行する2方向から確認を行う(上杭・下杭とも)
※「どちらか一方は1方向から確認を行う」のような記載があると×。 - 複数の杭を打ち込む場合は、「一方から順に杭を打っていく」もしくは「中央から外側にむかって杭を打っていく」のいずれかが正解。
※両端から中央にむかっていくように打ち込むと力の逃げ場がなくなりひずみや下がりなど先に打ち込んだ杭に影響を与える恐れがある。
※構造物の近くで杭を打つ場合は、構造物の近くから杭を打ちはじめ、遠ざかるように順次杭を打つ。
「中堀り工法」の出題傾向
中堀り工法に関する出題は、ボイリングの対策がポイント!
ボイリングとは、地下水位が高い砂質土で起こる、掘削底面の破壊。破壊時にお湯が沸き立つように砂が掘削面に流出してくる現象。
- 杭の中空部に注水しながら掘削する。孔内水位を常に地下水位より低下させないように注意!
- 最終を打撃にて根固めを行う場合は、所定の深さまで貫入させる。
※この場合、「杭中空部の土砂を残さないようにする」との記載があると×。固定させるために貫入している底部を掘削して土砂を排出するとゆるみが生じ、ボイリングを助長する恐れがある。 - セメントミルクを噴出撹拌して根固めを行う場合は、所定の形状になるように先掘り・拡大掘りを行う。
※セメントミルク噴出撹拌方式で、「先掘り・拡大掘りをしてはいけない(根固め球根の径は杭径以内)」という記載があれば×。
※セメントミルク噴出撹拌方式では、杭径よりも大きな根固め球根を構築すると覚えておく!チューリップの球根などをイメージ→茎よりも根の方が大きい形状! - オーガ引き上げ時は、吸引による掘削面の破壊防止のため、掘削水もしくは貧配合の安定液を注入しながらゆっくりと引き上げる。
「プレボーリング工法」の出題傾向
根固め液・杭周固定液の注入に関する箇所が×の選択肢として多く出題される。
- プレボーリング工法では、まず掘削を行う。掘削・泥土状の地盤に「根固め液」「杭周固定液」を注入し、撹拌し、ソイルセメント状にした後に、既製のコンクリート杭を沈設する。強い強度が必要な杭先端周辺は「根固め液」、中間部から杭頭部には「杭周固定液」が注入される。
- 杭の沈設時は、杭周固定液が杭頭部からあふれることを確認する。
※「あふれないように施工する」と記載されていると×。 - 杭周固定液の硬化に伴い、掘削した孔壁と杭体との間にすき間が生じる場合には、杭周固定液を充填する。
「既製杭(鋼管杭)の現場溶接」の出題傾向
溶接作業時の留意点・検査・溶接の不良箇所についてなどが出題ポイント!
- 気温5度以下の場合は、溶接作業は中止。
※ただし、気温が-10~+5℃の場合で溶接部から100mm以内の部分が36℃以上に余熱されている場合は作業してもOK! - 風速10m/sec以上の場合・降雨・降雪のある場合は、溶接作業は中止。
※ただし、シートで覆うなど溶接部が天候の影響をうけないような措置を行っている場合は除く。 - 溶接箇所はすべて目視によって外観検査を行う。
- 表面の傷(ピット・アンダーカット等)の検査 → 外観検査・浸透探傷試験。
- 有害な内部きず(ブローホール等)の検査 → 超音波探傷試験・放射線透過試験。
- アンダーカットは、溶接電流が高すぎるときなどに発生する欠陥である。
【練習問題】次の記述は正しいでしょうか、誤っているでしょうか?
| 杭の建込み作業時、上杭の鉛直性は下杭の鉛直性に左右されないため、下杭の鉛直性は一方向で確認する。 |
→解答×…杭の鉛直性の確認は、上杭であろうと、下杭であろうと、2方向から確認しながら打ち込む必要がある。
| プレボーリング杭工法にて、杭を沈設する場合、注入した杭周固定液が杭頭部からあふれないように施工する。 |
→解答×…杭周囲固定液は、「あふれないように」ではなく「杭頭部からあふれることを確認」
| 溶接時、溶接部が風の影響を受けないような措置を行う場合を除いて、風速20 m/sec以上では溶接作業を行わない。 |
→解答×…溶接作業を行ってはならない風速は10m/sec以上。