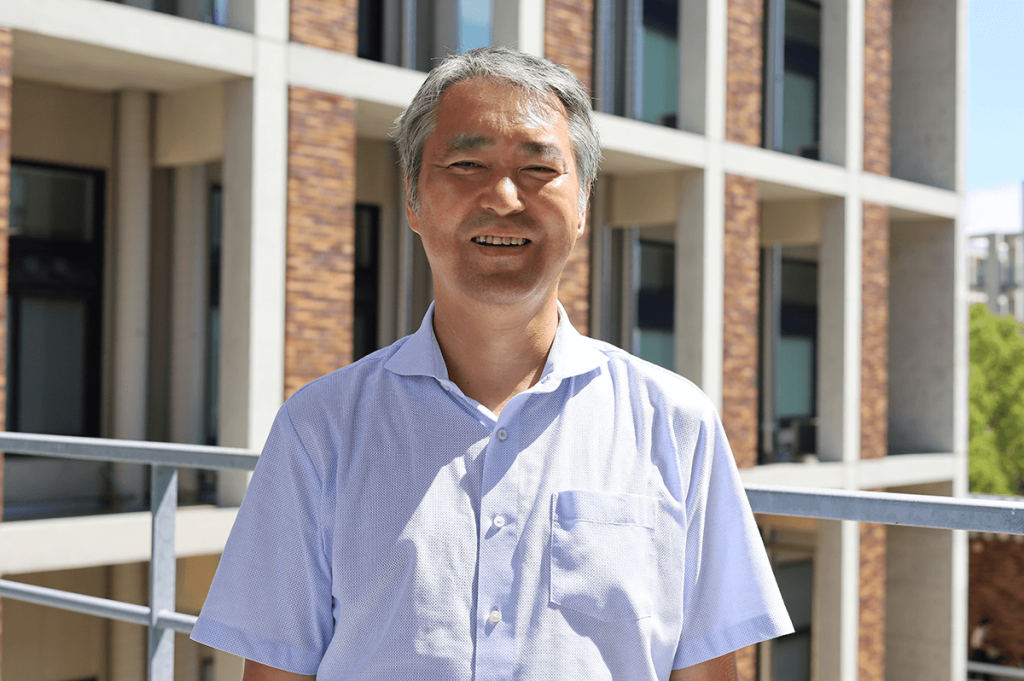板前志望だった青年が、土木の大学教授になった理由
とあるスジから、「京大の教授にはおもろい人間が多い」という話を聞いた。じゃあということで、「おもろい先生」を何人かピックアップしてもらった。その中の一人が、今回紹介する京都大学で構造工学を研究している北根安雄さんだ。
北根先生は、京都大学で鋼構造物の耐震性能を研究した後、アメリカの大学でコンクリートとFRPのハイブリッド構造の橋梁利用に関する研究で学位を取得。アメリカのコンサルタント会社でフォレンジックエンジニアリング(法工学)の仕事に従事した経験を持つ。帰国後は、名古屋大学、京都大学で研究を続け、今年5月、奇しくも自身が学んだ研究室の教授に就任した。
そんな華麗なるキャリアを持つ北根先生だが、もともとは板前志望。しかも、板前になるため、大学進学はおろか、高校も中退する気でいたというのだから、人生わからないものだ。ガチで板前を目指していた人間がなぜ、土木の大学教授になったのか。お話を聞いてきた。
「板前になるために高校を辞める」
北根 安雄さん 京都大学大学院工学研究科社会基盤工学専攻構造工学講座 教授
――土木に興味を持ったきっかけはなんでしたか?
北根さん 私はもともと、板前になりたかったんです。板前になるためには、中学校を出たら、どこかの料理店で弟子として修行するものだと本気で思っていました。それで、高校1年生のときに、親に「板前になるために高校を辞める」と言いました。しかし、「高校は行っとけ」ということで、親は許してくれませんでした。
それで仕方なく、高校に通っていたのですが、高校2年生のときに高校の先生と親とで進路相談をしました。その場では「大学には行きません」と言いました。ところが、家に戻ってから、親が「大学には行っとけ」と言い出して、だいぶモメました。最後は私が折れて、大学に行くことにしました。
その後、再び先生に相談をしたところ、先生から「板前になりたいということは、なにかをつくりたいということだろう。建築や土木なら、大きなものをつくれるよ」と言われました。そこで初めて、土木というものが自分の中に入りました。それから大学で土木を学ぶということを目指すようになりました。それで京都大学の土木に入りました。
――高校の先生のアドバイスで、土木にしたということですか。
北根さん そうです。先生の一言がなかったら、全然違う道に進んでいたかもしれません。
――板前と土木をつなげるその先生の発想力がスゴいですね(笑)。
北根さん そうですね(笑)。
阪神淡路大震災の被災現場を調査
――大学では土木のなにを学んだのですか?
北根さん 一番しっくりきたので、構造力学を学びました。今私がやっている研究室と同じ研究室でした。当時の教授の先生は渡邉英一先生でした。その下に現在も京都大学におられる杉浦邦征先生と現在は九州大学におられる宇都宮智昭先生がおられました。メタルの橋梁を中心に、浮体構造物なども研究する研究室でした。
私が4回生のときは、橋梁の鋼製橋脚の耐震性能について研究しました。修士1回生になったとき、阪神淡路大震災が発生しました。「大事な研究なんだな」と思いながら、現地調査などを行いました。
――現地調査では得るものが多かったのではないですか。
北根さん そうですね。地震前は先生に言われるがままに研究していたようなところがありましたが、被災現場を目の当たりにすると、興味が湧いて、目的意識を持ちながら研究することができました。
ゼネコンに面接で落とされ、博士課程に進み、そのままアメリカ留学
――就活はどんな感じでしたか?
北根さん 当時は研究者になろうとは思っていなかったので、修士2回生のときに、就活をしました。もともとモノをつくりたかったので、ゼネコンを受けました。大きな会社に入って、海外で仕事をしたいと思っていました。ところが、希望するゼネコンの面接で落ちました。それでどうしようかなと考えた挙句、博士課程に進むことにしました。博士課程に入った後、すぐにアメリカに留学しました。ニューヨーク州立大学に6年半ほどいて、博士号を取りました。
――6年半は長いですね。
北根さん はい、スゴく時間がかかりました。地震でモノがどう揺れるかもっと研究するために、地震工学研究センター所長のジョージ・リーという先生ところに留学しました。その先生に与えられたテーマが、モノが動的にどう揺れるのかについてこれまでの理論では説明できない新しい現象を追究するような内容で、非常におもしろいテーマでした。それで3年ほどその研究を続けたのですが、残念ながら実際にはこれまでの理論で説明ができてしまいました。
それで研究テーマを変えました。違う先生のもと、土木構造物へのFRPの活用に関することをテーマにして研究を始めました。具体的には、FRPとコンクリートとのハイブリッド構造物に関する研究で、FRPを橋梁の上部構造に使った場合の桁構造を提案するものでした。最終的にはFRPに関する研究で学位をとりました。
ワールドトレードセンターの倒壊原因調査に従事
アメリカ時代の職場の様子(北根先生提供)
――学位を取られた後、日本に戻られたのですか。
北根さん いえ、アメリカで就職しました。アメリカボストンにある「SGH」というコンサルタント会社で3年ほど働きました。日本に帰ることも考えましたが、選択肢があまりなく、また、せっかくアメリカに来たのだから、海外で働いてみようと考えたからです。SGHに決めた理由は、「フォレンジックエンジニアリング(Forensic engineering)」、日本語で言うと、「法工学」をスゴくやっている会社だったからです。たとえば、モノが壊れたときに、壊れた原因を探るということです。SGHでは主にこのフォレンジックエンジニアリングの仕事をやりました。
フォレンジックエンジニアリングの仕事は、訴訟に関係することが多かったです。なので、専門家として弁護士に雇われて、仕事をしました。モノが壊れたときに、なにが原因で壊れたかを巡って訴訟になる。そこでどちらかの弁護士に雇われて、原因を調査するという仕事です。
一番長くやったのは、2001年にテロで倒壊したワールドトレードセンターの倒壊原因の解析です。アメリカ政府として、倒壊の原因が火災だったのか、それとも爆破だったのか知りたかったからです。もし火災が原因なら、今の耐火基準で建設された世界中のビルが倒壊するリスクがあるという話になります。爆破に関しては、ビルのオーナーが爆薬を仕掛けて爆破したんじゃないかというウワサがあったからです。どっちにしても、政府として倒壊の理由が知りたいということでした。この仕事は非常におもしろかったです。
――倒壊の原因はなんだったのですか。
北根さん 複合的な要素が絡み合っていましたが、原因は火災と飛行機による損傷の両方でした。飛行機がビルに衝突すると、航空機燃料がビル内に飛散し、火災が起きます。ただ、火災が起きるのは飛行機が衝突した数フロアだけです。飛行機の衝突により、建物の柱などの重要部材が破壊されます。さらに、衝撃により鉄骨の耐火被覆材が吹き飛びます。耐火被覆がなくなると、熱で鉄骨の温度が上がりやすくなります。火災が起きたフロアの鋼材の温度が高温になった結果、床を支えている鋼トラスの強度が落ち床がズドンと落ちます。床が落ちると、柱の水平方向の支えがなくなることで、柱の長さが長くなり、座屈します。そうなると、火災がおきた部分より上の構造全体がズドンと落ちてしまいます。このズドンズドンが繰り返されて、最終的に倒壊したわけです。
――SGHを3年で辞めたのはなぜですか?
北根さん 仕事は非常におもしろく、まったく不満はなかったのですが、家庭の事情で、日本に帰ることにしました。日本の企業への転職も考えましたが、2005年ごろのことですが、当時の中途での就職は非常にハードルが高く、研究職に興味があったので、最終的に、名古屋大学に助手として拾っていただき、2006年に日本に戻ってきました。アメリカにはトータルで10年ほどいました。
――名古屋大学もメタルの研究室だったのですか?
北根さん そうです。それから14年ほど名古屋大学で研究を続けました。当時は伊藤義人先生のもとで研究していました。2010年に准教授にしていただきました。伊藤先生はメタルの腐食についてスゴく造詣の深いお方でしたので、腐食に関するたくさんの知識を得ることができました。
その後2019年に准教授として京都大学の私が学生時代に学んだ研究室に戻って来ました。杉浦邦征先生のもと、研究をしてきました。その後、杉浦先生が他の研究室に移られました。それからしばらくして2023年5月に教授になりました。
メタル、FRPの構造工学をメインに研究活動
北根先生と研究室メンバー
――こちらの研究室の主な研究内容について教えていただけますか?
北根さん 今は3本柱で研究しています。一つ目が「構造物を合理的につくる」です。新しい鋼構造を考えたり、新材料であるFRPを採用したりといった研究をしています。
二つ目が「鋼構造を維持管理する」です。鋼構造物を長持ちさせるためにどうやって補修するかということです。鋼構造物の主な損傷としては、腐食(サビ)があります。もう一つが疲労です。腐食や疲労を抑制する方法や補修方法について研究しています。
三つ目が「鋼構造物をモニタリングする」です。たとえば、現在橋梁は5年1回点検して健全性を評価していますが、センサーなどを橋梁に取り付けることにより、毎日橋梁の健全性をモニタリングすることはできないかという研究です。
――FRPに関する研究が興味深いのですが、土木構造物への採用事例について、最近の動向はどうなっていますか?
北根さん FRPの歩道橋はすでにいくつも事例があります。ほぼFRPだけでつくられた歩道橋は全国に10以上ありますが、歩道橋以外の構造物での採用としては、道路橋の合成床版に使われた事例があります。海外には道路橋の上部構造としての採用事例がありますが、日本では、FRPの耐久性についての確証が得られていないため、今のところ、道路橋の上部構造としての採用はまだありません。
耐久性とは、長期の材料特性や繰り返しの荷重を受けたときの疲労特性ということです。100年前につくられたFRPはないので、100年後にどうなるかわかっていません。
――歩道橋はOKだけど、道路橋はまだダメという感じなんですか?
北根さん そうですね。補修には使用されていますが、構造物の主部材としては使用されていません。あとは、腐食環境がキビしい場所の高速道路の検査路でも採用された事例があります。他には、水門扉にも使用されています。
――FRPのメーカーと共同で研究することもあるのですか?
北根さん それはあります。ただ、海外と比べると、メーカーの動きは弱いと感じています。海外では、FRPの複数メーカーが一緒になって、設計指針のようなものをつくっているのですが、日本にはそのような動きがまだ少ないです。
FRPは設計基準がなく、コストも高い
――FRPは非常に可能性を感じる部材だと思われるのですが、課題についてどうお考えですか。
北根さん ええ、可能性は十分にあると思います。課題としては、まず設計基準が整備されていないことです。国の基準の中に入っていないと、やはり採用されにくいです。高速道路会社が補修などで使っていますが、事業者が独自にマニュアルを作成して、その上で使っているのが現状です。補修に関しては、そのうち国の基準に入ると予想しているのですが。
――土木学会でFRPを扱う委員会はあるのですか。
北根さん あります。複合構造委員会の中にFRPを取り扱っている小委員会が複数あります。
――コストはどうですか?
北根さん まだ高いです。FRPの繊維になにを使うかでコストは変わってくるのですが、炭素繊維は高いです。炭素繊維は、材料特性としては優れているのですけどね。なので、FRPで土木構造物を作る場合は、ガラス繊維のみが使用されている場合が多く、炭素繊維を使用する場合は、ガラス繊維と組み合わせて、全体のコストを下げるということをやっています。トレジャーボートはガラス繊維で、アメリカズカップのヨットは炭素繊維でつくられていたりします。炭素繊維は高級部材なんです。
――環境面はどうですか?
北根さん 今のところは、あまり進んでいないと思います。とくに、リサイクルをどうするのかについて、あまり研究がなされていません。リサイクルの方法として、セメントの製造過程で燃料として利用される方法は実用化されていますが、その他、繊維と樹脂を分離し繊維を取り出してリサイクルする方法のほか、部材丸ごと粉砕してFRPの原料としてリサイクルする方法があるのですが、この辺の研究があまり進んでいないのが現状です。
レーザー照射による塗膜剥離についても共同研究中
――企業などとの共同研究はどうなっていますか。
北根さん 現在、炭素繊維メーカーとFRPとメタルの構造物の接合に関する共同研究をしています。FRPの中でも、ガラス繊維には導電性はありませんが、炭素繊維には導電性があるんです。炭素繊維を鉄に接着したときに、腐食しないのかという問題があるわけです。その辺の共同研究をしているところです。
あとは、腐食した鋼構造物の塗膜を剥がすためのレーザー開発についても、ある国内企業と共同研究しています。塗膜の除去はブラストが一般的ですが、ブラストでは施工できないこともあるし、レーザーでやると良いこともあるので、レーザーのメリットデメリットの整理みたいなことをやっています。
構造力学はモノが壊れないための学問
――「学生の土木離れ」が言われていますが、土木の教員として、どうお考えですか。
北根さん 土木業界が盛り上がるためには、まずはそこに人が入って来ることが大事です。そのためには、一人でも多くの学生に土木を学んでもらって、一人でも多くの人を土木業界に送り出したいと考えています。土木の教員としては、学生に土木のおもしろさを伝えることを心がけています。
研究については、一方的に「あれやって、これやって」と言うのではなく、学生がおもしろいと思って自発的に動くようにする、それを重視してやってきました。授業では、主に構造力学を教えているのですが、最初の授業ではいつも、壊れた構造物の話をすることにしています。構造力学は壊れない構造物をつくるための重要な学問だということを理解してもらいたいからです。
渡り廊下はなぜ、落下したのか?
渡り廊下事故に関する資料(北根先生提供)
北根さん あと、アメリカで起こった建築施工ミスによる事故についても、いつも話しています。ハイアットリージェンシーのロビーに渡り廊下が上下2つ架かっていたのですが、パーティーの最中に、上の渡り廊下が落下して、114名が亡くなるという事故がありました。この渡り廊下が落下した原因は、簡単な構造力学で説明することができます。
もともとの設計は、上から一本の吊材があって、上の渡り廊下の下にナットで固定し、下の渡り廊下も同じように下をナットで固定する構造になっています。ところが施工者は「こんなんできるか」ということで、図面と違う構造で施工したんです。一本の吊材に固定するのではなく、別々に固定したんです。
設計図面の構造と実際に施工された構造の両方の図を見せながら、学生に「どこがおかしい?」と訊くんです。答えは簡単で、施工時の構造だと、2つの渡り廊下の荷重、つまり設計の倍の荷重がかかるので、落下したわけです。
次に、「なぜこんな構造で施工したと思うか」と訊くわけです。多くの学生は、実際に施工したことがないので、答えられません。施工者の立場になって考えてみると、設計通りの構造にするためには、一番下から何mもナットをグルグル回して固定しなければなりません。実際の施工では、そんなことやってられへんから、施工しやすいよう構造を変えたわけです。ところが、図面と違う構造にしてしまった結果、落下して事故になってしまいました。
この事例からは、いろいろな教訓が汲み取れると思いますが、私は「構造力学の大事さ」を伝えるために、学生に紹介しています。