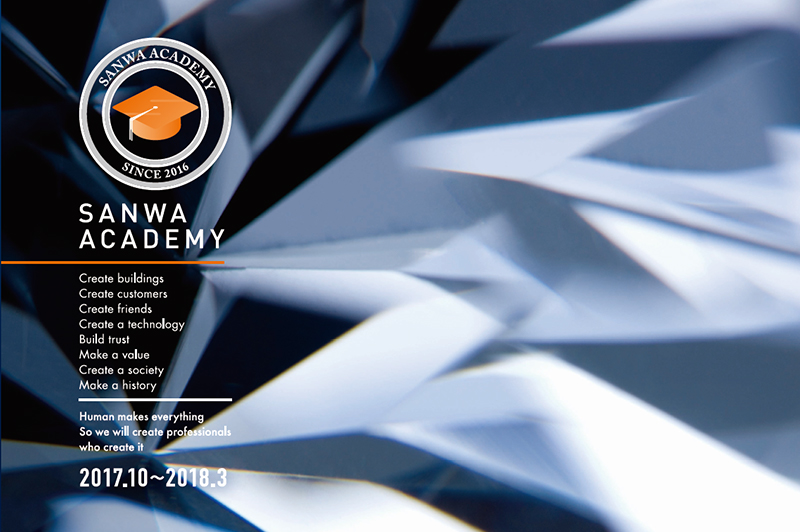「つくるひとをつくる®」が経営理念。三和建設株式会社が導入した「理念共感型」人財採用戦略とは?
「つくるひとをつくる®」を経営理念に掲げる三和建設株式会社(本社:大阪府大阪市淀川区)では数年前から、学生採用や社員育成など「ひとづくり」に力を入れている。
近年、新卒採用市場が「買手市場」から「売手市場」に転換する中、学生採用に関しては、「会社が学生を選ぶ」から「学生が会社を選ぶ」に方向転換し、「学生と会社との価値観のマッチング」に重点を置いた選考プロセスを導入。学生のエントリー数は年々増加し、内定辞退、入社後の離職者も大幅に減少した。
人財育成については、建築実務や会社の業務などを学ぶ社内大学校「SANWA アカデミー」を設立。講師に社員を登用することで、社員の能力、やる気の向上に取り組んでいる。
「人が大事」「人が欲しい」と言う経営者は多いが、実際にそのために行動し、成果を出した会社は少ない。三和建設は他の会社となにが違うのか?
三和建設株式会社 常務取締役・大阪本店長の辻中敏さんに話を聞いた。
三和建設株式会社 常務取締役・大阪本店長の辻中敏さん(会議室「YAMAZAKI」にて)
サントリー山崎蒸溜所など、民間建築工事で70年余の実績。目指すは「3大ソリューションのナンバーワンカンパニー」
三和建設株式会社は昭和22年に創業。大阪、東京に本店を構え、関西圏、首都圏を中心に、主に食品工場などの民間建築工事を手掛けてきた。同社のノウハウを凝縮した設計施工、保守を含めたトータルソリューションブランド「FACTAS®」は主力事業の一つだ。サントリー株式会社(サントリー山崎蒸溜所)は、ほぼ創業以来の顧客で、同社の会議室は「YAMAZAKI」「ROYAL」など縁の深いネーミングが用いられている。
食品工場と言っても、たんに画一化されたハコモノを建築すれば良わけではない。顧客のニーズ、工場の用途などを考慮し、緻密につくり上げる必要がある。とりわけ、空気や温度、湿度管理はシビアだ。「一般の建築物とは異なる高度な専門知識と経験が作り手には求められ、これらの経験を有している建設会社は決して多くはありません」と言う。
「一口に食品工場と言っても、その工場で生み出される製品の特性、製造方法、危害要因、販路などによってあるべき姿は多種多様です。その分、どうすれば、お客さまに新たな価値を届けられるか、使い勝手の良いものを提供できるかという点において、わが社のノウハウ、強みを発揮できる部分があるわけです」
三和建設の今後のビジョンはどういうものだろうか?
「わが社は、急激に会社の規模を大きくすることを考えていません。社員や協力会社、お客さまなど、関わるすべての人々のために永続することを重視しています。したがって、売上高よりも生産性の向上や未来への投資の原資となる利益を重視しています。現在の社員数は114名ですが、当面は150名体制に向けて緩やかな成長を志ざします。将来社員数が増えても、社員一人ひとりの顔が見える会社にしたいと考えています」
「われわれは、民間の仕事、食品工場(ファクタス®)や特殊倉庫(リソウコ)、長期にわたって価値を維持できるマンション(エスアイ)に特化し、その分野のトップカンパニーを目指していきます」
民間工事にこだわる理由はなんだろうか?
「お客さま様の声を直接感じたいからです。公共の仕事でも一定の感謝の言葉をいただけますが、民間のお客さまの方がよりダイレクトに『ありがとう!』と言っていただけます。時には厳しいお言葉もいただきますが、ツラいも嬉しいもダイレクトに感じられるのが、民間の仕事です。われわれのフィールドはあくまで民間です」
三和建設の「つくるひとをつくる®」取り組みについて、熱く語る辻中常務。辻中常務自身、1級建築施工管理技士の資格を持つ技術者でもある。
会社説明会に10数名の社員を投入し、数百名のエントリー学生を獲得
おおむね順調な経営を続けてきた三和建設だったが、平成12年以降、ベテラン社員の退職、職人不足などにより、人財不足問題が顕在化。新たに採用しようとしても、入社内定後の辞退者、入社後の離職者が少なくなく、思うように人材を確保できない状態に陥った。
危機感を抱いた三和建設は「つくるひとをつくる®」を経営理念として明確化。全社的に人財の採用、育成を強化する方針を打ち出した。「どういう戦略でいくか」「どういう人財が欲しいのか」などの骨格の部分を社内的に詰めていった。しかし、具体的にどうするかを決めるのは簡単ではなかった。
「最初はすべてが手探りで、なにをして良いのかわからなかった、というのが正直なところですね。例えば、会社ホームページなどの情報発信を充実させても、その辺の取り組みは他社と大差ないので、学生にそれほど訴求しませんから。そもそも情報が多すぎるんです。試行錯誤の後、『学生に共感してもらう』『考え抜いてもらう』ためにはどうすれば良いか、という方向性に沿って、物事を組み立てていくことになりました」
そこでまず、大阪、東京それぞれの合同会社説明会に積極的に社員を送り込むことにした。他社のブースには、人事担当者が1名程度しかいないところに、社員複数名を投入。人事担当だけではなく、現場の社員も送り込み、学生と積極的にコミュケーションをとるよう社員に徹底させた。
三和建設の合同会社説明会の様子。説明に立つのは、森本尚孝・三和建設株式会社代表取締役社長。(写真提供:三和建設株式会社)
「現場の社員を送り込んだのは、限られた人事の社員と話しても、会社の雰囲気全体は学生には伝わらないから。説明会の雰囲気が会社の雰囲気になるよう、三和建設の等身大の姿を学生に見せたいという思いからでした」
複数名からの社員が学生に声をかけると、数十人の人だかりができる。「あれ?人がいっぱい集まっている。なんだろう」と思って、さらに集まる。人が集まる好循環づくりに成功した。その結果、従来方式のエントリー者数が数十人だったのに対し、数百人のエントリー者数を獲得した。
学生に会社を選んでもらう「理念共感と成長」型の採用選考を導入
エントリー後の新卒採用の選考方法もガラリと変えた。「履歴書を見て、この子良いんじゃない?」という「会社が学生を選ぶ」従来方式から脱却。学生に会社を選んでもらう「理念、価値観共有方式」に転換した。書類選考、ペーパー試験もなし。学歴も重要視していない。
その一方、2週間に及ぶ職場体験などを実施。学生に自己アピールさせて、評価するのではなく、「学生に自分の人生を考えさせる」「三和建設の価値観を知ってもらう」「入社後10年後をイメージしてもらう」などのグループワークなど中心に、「学生の決断を支援し、信頼する選考」に徹した。
三和建設では、一人の採用内定に学生が会社と関わる時間は138時間に及ぶ。すべては会社と学生の「理念と価値観の共有と成長」のためと語る辻中常務。
「従来型の採用選考では、学生とはせいぜい1〜2時間程度の関わりしか持てません。そんなわずかな時間で、学生が会社のことを知るのは不可能です。入社しても、お互いに『こんなはずじゃなかった』と別れざるを得ないことになりかねません」
「その点、三和建設では、一人の学生が内定までに会社と関わる時間は、約138時間に及びます。社員の関与人数は延べ772人、社長の出動日数は延べ23日間、ひとの関わりが多い分、コストもかかりますが、営業活動と違って、採用は投入したエネルギーに見合う結果が必ず得られます」
「人を採用したいなら、時間とエネルギーをかけるべし」というわけだ。ド正論だと思う。ただ、不思議なのは、この当たり前のことをしないで、「人が来ない」と嘆く建設会社経営者が少なくないということだ。もしかしたら、「時間もエネルギーもかけないでも、良い人が来る」と夢想しているのかもしれない。だとしたら、良い人材こそ、そんな会社には寄り付かないだろう、と容易に想像できるわけだが。
三和建設が採用選考で最も重視しているポイントについて、聞いてみた。
「採用で一番大事なことは、内定ではなく、会社の理念や価値観を共有して、学生個人が三和建設に入社して成長、活躍できると確信してもらうことです」
「わが社としては、社員というより、家族の一員として迎え入れています。以前に比べ、会社に対する帰属意識が高い社員が増えていると感じています。少々仕事で辛いことがあっても、上司や仲間と一緒に働きたいという意識が強いですね。そのおかげもあって、入社後の離職者はほとんどいません」
投入したエネルギーに見合う結果が得られているようだ。
「過剰な熱意を持った人たち」に強い印象を受けた三和建設の新人社員
三和建設に入社した新人社員は、採用選考などについて、どう受け止めているのだろうか?新人社員の六嶋瞬さんに話を聞いてみた。
「三和建設の第一印象は、『過剰な熱意を持った人たち』でした。説明会の会場で、学生が反り返るほどの熱気で接する姿には、強い印象を受けたことを覚えています。正直なところ、就職活動が始まるまでは、どんな業界でもどの職種でも就職できればいいや、と考えていました。というのも、今後40年をかけて成し遂げたいことが明確になっていなかったからです」(三和建設株式会社 大阪本店工事グループ 六嶋瞬さん)
三和建設株式会社 大阪本店工事グループの六嶋瞬さん(写真は4次選考当時)
「そんな将来の軸がフラフラの中、就職活動にぶち当たり、自分が何をやりたいのか、人生で何を残していきたいのかを話すことができませんでした。就職活動とは、今後の40年を決めるものだと気づいたのもその時でした。悩みました。すごく自分の今までを否定された気がしました」
「それをきっかけに、考え方を変えようと思いました。これまでの自分を否定することになるかもしれませんが、そうでなければ真にマッチングした会社と出会うことができない、と選考会を通じてわかったからです」
「これは自分にとって、大きな選択でした。楽して生きていく道もありましたが、それではダメだと気づけました。その気づき、選択のおかげか、後悔したことはありません。選考会で得たものは、今自分の軸となり、あるべき方向を指し示すものとなっていると実感しています」
入社後、会社の雰囲気に対して、どう感じたか?
「ギャップは感じませんでした。説明会や選考会で感じた「熱意、熱気」という印象と、入社してからの印象に大きな差はなかったからです。相変わらずの熱量で仕事をこなし、プライベートを楽しむ姿には大変影響を受けています」
社員から選抜した講師による社内大学校「三和アカデミー」でひとづくり
三和建設が考える人材成長曲線
三和建設株式会社は平成29年4月、社員の育成を目的とした社内大学校「SANWA アカデミー」を開校した。SANWAアカデミーでは、役員、エキスパート社員が講師として登壇。若い社員に対して実践的な知識、ノウハウを伝授する。
SANWAアカデミーのねらいは、社員の「専門技術力(Ability)=一人でできる能力」と「統合力(Competence)=他者と一緒に、周りの力を借りて事を成す能力」の向上にある。
講座は、営業系、設計系、見積・調達系、工事系、アシスト(管理部門)系に分類し、それぞれが入門系講座、専門系講座、統合力系講座に分けられ、入社年数や部署に応じて必要な知識や技術を体系化している。その他、外部体験型講座、e-ラーニング・教材、内定者研修、資格支援講座などのコースがあり、講座数は130コマ。毎月第3土曜日に5コマ開講し、2年間かけて全コマを開講する。全ての講座は、TV中継で結ばれ、大阪、東京の会場で同時開講される。
SANWAアカデミーの講座受講中の様子
役員講師は、それぞれが担当する業務の概論解説などの講座を担当。社員講師は、個別業務のハウトゥーなどの講座を受け持つ。講師は係長クラス以上が担当。講座内容は基本的に社員が決める。受講後のレポート提出、1ヶ月後に現場実践の「成果」と「反省」を提出。今後はアカデミーと人事制度の連動を進めていく。
受講する講座は、各社員の担当業務により分かれるが、担当業務ごとに必修講座が決められている。各所属の上長が推奨する推奨講座のほか、担当業務以外であっても、社員が希望する講座を自由に受講できる。必要受講数は、社員等級によって各人で異なるが、入社3年未満の社員は、必要な全コマ受講が必須となっている。
「ひとづくり」にいくらお金と労力をかけても、かけ過ぎということはない
人財育成のため、研修制度が必要なことは理解できる。だが、アカデミーまで設立する必要があるのか、という疑問が湧く。
「三和建設株式会社の経営理念は『つくるひとをつくる®』です、つまり、社員の成長は、我が社の経営上の最重点事項なので、この部分にいくらお金や労力をかけても、やり過ぎということはありません」
アカデミー設立は、ただの企業PR、話題づくりではなく、会社の命運を賭けた試みのようだ。
SANWAアカデミーは、2016年10月のプレ開校から1年以上が経過した。どのような効果があるのかも気になる。
「現在は開講中の段階であり、すべてのデータが出揃っているわけではなく、その効果をすべて検証できているわけではありません。開講の頻度など見直すところもあります。ただ、すでに大きな手応えを感じている部分はあります」
それが知りたい。
「一つは、社員講師の地位確立に成功したことです。会社としては、講師にプレミア感を持たせるねらいのもと、エキスパート社員から選抜し、講師に登用したわけですが、受講した若手社員からは『いつか自分も講師になりたい』という声が出ています」
「もう一つは、講師自身のスキルアップです。エキスパートでも、人に教えるとなると、自分の知識やノウハウが正しいことなのか確認をします。講座内容は、役員が事前にレビューするので、知識やノウハウをちゃんと整理する必要があります。講師も自分の能力を高めよう、という意識が定着してきました」
講師、受講者ともに、業務として「やらされる」仕事ではなく、「自らやる」ムードが浸透しているようだ。この点、会社と社員の価値観共有の恩恵だろうか。
「さらに、社員の成長速度が明らかに増し、その水準も高まっています。以前は、社員が所属する部署や現場ごとに知識やノウハウに違いが見られました。それぞれの上司が個別に教えていたからです」
「また、他のセクションの業務も学べるので、『これは営業のせいだ』『これは設計のせいだ』といったタテ割りの弊害が薄れてきました。違うセクション同士がお互い手を取り合って仕事をする雰囲気が生まれています。全社員が知識、ノウハウを共有できるようになり、能力のボトムアップが進んでいると感じています」
「ひとづくり」は、数年間、腰を据えて取り組むもの。その成果について、性急な結果を求めるのはナンセンスだろうが、「すでに大きな手応えを感じている」という辻中常務の言葉からは、言葉以上の自信が感じ取れた。
実際に講座を受講している社員は、どう感じているのだろうか?
講座を受講している社員の弘瀬敏博さんににコメントしてもらった。
三和建設株式会社 大阪本店営業グループ主事の弘瀬敏博さん
「私は主に食品工場の営業を担当しています。これまで20コマほど受講しましたが、いろいろな知識を吸収できて、とても刺激になっています。一番タメになった講座は、営業ではなく、設計の講座でした。食品工場の設備に関する知識は、営業していく上で、非常に役に立っています」(弘瀬敏博・三和建設株式会社大阪本店営業グループ主事)
社員の評判も上々のようだ。
建築業界全体のために、いずれアカデミーを他社社員にも開放する
三和建設株式会社では、将来的に、SANWAアカデミーを同業他社の社員などにも開放していく構想を持っている。
利他的行為と言えば、聞こえは良いが、ライバルを育てることになるのではないか?という疑問が湧く。
「ライバル会社を利すると言われれば、それはそうですが、そんなことは小さなことです。関係ありません。大きく建築業界のためということを考えれば、われわれがそれをする価値は十分にあると確信しています。わが社の社員を講師として派遣することも可能です。何年後になるかは分かりませんが」
三和建設株式会社 常務取締役・大阪本店長の辻中敏さん
三和建設ではすでに、関西などの大学に社長や役員が訪問。建築を学ぶ学生を対象に出張講座を行っている。一義的には、三和建設の認知度向上など採用のブランディング活動の一環だが、建築業界のイメージアップのため、先進的な同業他社の取り組みなどもアピールするという。
自分の会社だけでなく、業界全体の利益を考えるハート、なによりも実際の行動が、学生の心を惹きつけているのかもしれない。