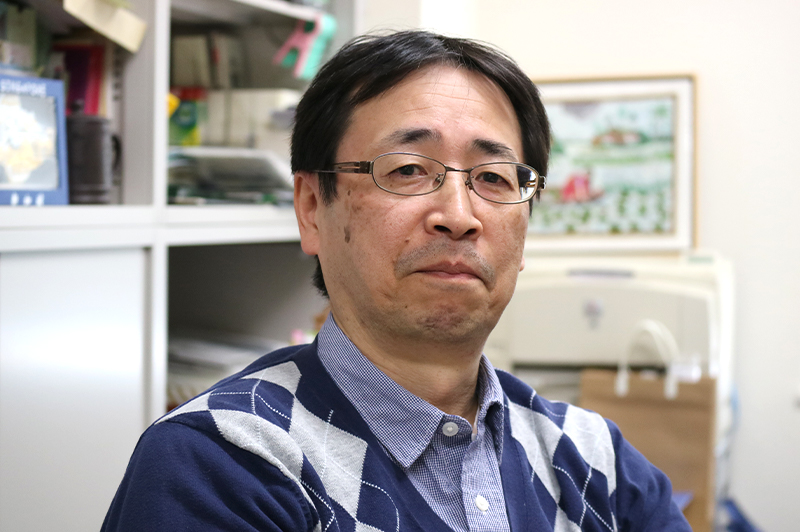平成最後の就活に奔走する土木系学生たち
2019年3月1日、「平成最後の就職活動」が解禁となった。
今、空前の売り手市場となっている土木系学生たちは、どのように就職先を選んでいるのか?また土木系学生と企業が抱える就活の課題とは何だろうか?
九州大学工学部は1911年に前身となる九州帝国大学工科大学が設立されて以降、多くの優秀な土木研究者・技術者を輩出してきた九州大学工学部。
同校の土木系学生の就職担当教授として、企業対応や学生の就職相談などを行っている久場隆広・九州大学大学院工学研究院教授に、最近の就職先データを基に土木系学生の就活動向について分析してもらった。
毎年60人の「土木のタマゴ」を輩出
――土木系の学生は何名ほどですか?
久場 九州大学工学部には、土木系の建設都市工学コースがあり、4年生は約80名います。大学院には、土木系の専攻が2コースあって、M1とM2合わせて60名程度います。4年生約80名のうち、60名程度は進学するので、残りの20名、大学院M2の60名、合計80名程度が今年4月に就職する予定です。学部3年生、大学院M1生の約60名がこれから就職活動を行うことになっています。
――土木系の志願者数、入学者数は?
久場 工学部地球環境工学科としてまとめて入試を行なっており、入試の段階で土木系の学生をわけているわけではありません。土木、船舶海洋、資源の3つのコースがあるのですが、1年生が終わったら、各コースを選ぶカタチになっています。
土木系コースには、各学年80名前後の学生がいます。土木系が他のコースに比べ、とくに少ない、人気がないということはありません。コースの学生数のバランスはとれていると思います。地球環境工学科として、土木系の良い学生を確保するのに苦労していないということはありませんが、志願者、入学者が減っているということはありません。
――女子の割合は?
久場 例年、全体の1割程度ですかね。
土木系学生は公務員志向が強すぎる
――最近の就職先の傾向は?
久場 就職先を大きく分けると、公務員系、コンサル系、ゼネコン系のほか、鉄道会社や電力会社などのインフラ系の4つに分かれますが、最近は公務員志向が強い傾向があります。ここ数年、国土交通省や環境省、福岡市役所や福岡県庁などに就職する学生が一番多いですね。ここのところ採用枠が増えているということもありますが。
個人的には「コンサルやゼネコンがもっと多いほうが良いんじゃないかな」「ちょっとバランスを欠いているかな」という印象を持っています。
地球環境工学科 建設都市工学コースの進路[平成28年3月修了] / 九州大学
――公務員志向が強すぎる?
久場 特定の自治体に九大生ばかり入るというのは、彼らにとって本当に「幸せ」なことなのか、大いに疑問が残るところです。上に行けば行くほど、技術職員のポストは限られてくるので、「将来のことをしっかり考えているのかな」という気がします。
――土木系の学生は安定志向?
久場 そうですね。昔からのことですが、その傾向が続いています。
――国土交通省などは?
久場 国土交通省を志望する学生はたくさんいますが、採用試験が難しいのでなかなか通りません。かなり実力のある学生でないと、通らないですね。国土交通省に入る学生は、院生を含め毎年5名前後ですかね。われわれとしても手厚く指導しているところであり、毎年コンスタントに学生を送り出しています。他の大学と比べても、頑張っているほうだと考えています。
公務員、とくに地方公務員の場合は、就職が決まるのが8月中旬ぐらいと遅いので、民間企業からすでに内定をもらっている学生は悩むケースが多いと思います。
「転勤したくない」土木系学生は地元志向も強い
――ゼネコン系は?
久場 ここ数年は景気が良いので、土木系の就職は「売り手市場」になっています。ゼネコンを含む多くの民間企業から「ぜひ九大生が欲しい」というお話をいただいています。実際、毎年1〜2名の学生がゼネコンに就職しています。毎年、大手ゼネコンから就職が決まっていく感じで、中堅ゼネコンまでですね。
――インフラ系で言うと、やはりJRですか?
久場 そうですね。地元ということもあって、学生にはJR九州が人気がありますね。JR関係は、土木系に限らず、九大生全体でも人気のある企業なので。
大学院工学府 建設システム工学専攻の進路[平成28年3月修了] / 九州大学
――地元志向が強い?
久場 もともと九州出身の学生が多いので、その傾向はありますね。自分の研究室の学生を見ていると、昔は「全国どこででも働く」という学生が多かったイメージがありましたが、最近の学生は「地元志向」が強い印象ですね。やはり、「転勤したくない」という学生は例年一定数います。
売り手市場だから「どこでも入れる」は勘違い
――最近の「学生気質」をどう見ていますか?
久場 私が就職担当になってまだ1年ですが、昔に比べて「ガツガツしていない」イメージがありますね。のんびりしているというか、「上昇志向に欠ける」というか。やはり「売り手市場」なので、「どこにでも入れる」という安易な考えをもっているイメージを持っています。
ただ、フタを開けてみると、ほぼ全員就職できましたので、はた目にはのんびり見えるけれども、実際は企業研究などをしっかりやっていたのかもしれません。昔に比べれば、授業数が減っているので、学生のチカラが落ちているのは確かです。会社にとって即戦力揃いとは言えませんが、OJTなどを通じて、実際の仕事をこなすための基本的なチカラを身につける程度には、教育し、送り出している自負はあります。
大学院工学府 都市環境システム工学専攻の進路[平成28年3月修了] / 九州大学
――ゼネコンなどの民間企業がかなり積極的に採用活動を展開していると聞きますが。
久場 「九大生が欲しい」という声は大きいですね。とくにゼネコンさんは。九州大学としては、民間企業からの具体的な求人内容を受け付けるのは、毎年3月1日以降と決まっていますが、3月1日より以前の段階で、求人票を携え私のところに訪れて、アピールするゼネコンの担当者の方はいらっしゃいます。
3月1日の就活解禁で混乱する学生
――学生にはどのようなアドバイスを?
久場 私のところに来る学生は、「大学推薦が欲しい」とかそういう相談で来るケースが多いので、そういう学生にアドバイスすることはあります。
まず、「志望は公務員なのか、民間企業なのか」を訊きます。公務員志望であれば、少しでも上の機関を目指すよう勧めます。民間志望でも同じようなことをアドバイスしています。とくにテクニックがあるわけではありません。院生の場合、研究室の先生がいるので、それぞれの先生が具体的なアドバイスなどをされているはずです。
ただ、問題は3年生です。3年生は、非常に中途半端な立場で3月1日の就職活動の解禁を迎えるからです。就職活動への準備が不十分なまま、戸惑ったり、混乱する学生も少なくないと思います。大学には、就職相談窓口がいくつかあるので、そういう窓口を利用する学生はいます。
3年生にはクラス担任の教員2名がついていますが、80名全員の面倒は見きれません。九州大学には「履修指導アドバイザー」という制度があって、1人の教員が8名程度の学生に対し、定期的に履修関係のアドバイスを行なっています。私もその一員で、私の場合、「進学するのか、就職するのか」などに関する相談にも乗っています。
3年生を対象に、昨年から研究室への暫定配属を行なっています。3年生の12月ぐらいから、お試し期間として研究室に在籍するものです。研究室の先生は、研究室の紹介のほか、就職に関する相談などに応じています。あくまでお試しなので、4年生になって違う研究室に在籍するケースもあります。
一部のゼネコンだけに学生が偏る危険性
――インターンシップは、学生と企業などがお互いを知る貴重な機会になっているようですね。
久場 インターンを受け入れた企業が学生を観察しているということは、実態としてはあるでしょうね。表向きは「インターンと採用とは関係がない」ことになっていますが(笑)。とくに冬のインターンでは、企業も学生もお互いを見極める大事な場になっているようです。
夏のインターンは逆で、志望していない就職先の仕事を体験する場としてとらえています。少なくとも、私はそのように指導しています。ゼネコン志望の学生の場合、公務員やコンサルのインターンに行くとか。「両方見といたほうがいいよ」ということでね。
――企業サイドもインターンには力を入れているようですね。
久場 企業サイドとしては、学生との「マッチング」ということを非常に気にされていますね。ムリに学生を入社させても、数年で辞めてしまったら、意味がない。そういう「ミスマッチ」が起こらないよう、企業サイドではかなり慎重に採用活動されているようです。ミスマッチは、お互いに不幸なことですからね。
――企業サイドに対する要望などは?
久場 企業サイドへの要望ではありませんが、特定のゼネコン1社に多くの学生が就職し、偏っているところがあります。そうではなく、複数のゼネコンにバランス良く、就職するほうが良いと思っています。大学にとっても、企業にとっても、将来の会社の持続性を考えると、あまり出身大学が偏るのは「いかがなものか」という気がしています。
就職先は最終的には学生が決めることではありますが、Aというゼネコンには毎年2〜3名就職するが、Bゼネコンにはここ10年間で一人も就職していないという状況は、大学としては好ましいものではないと考えています。