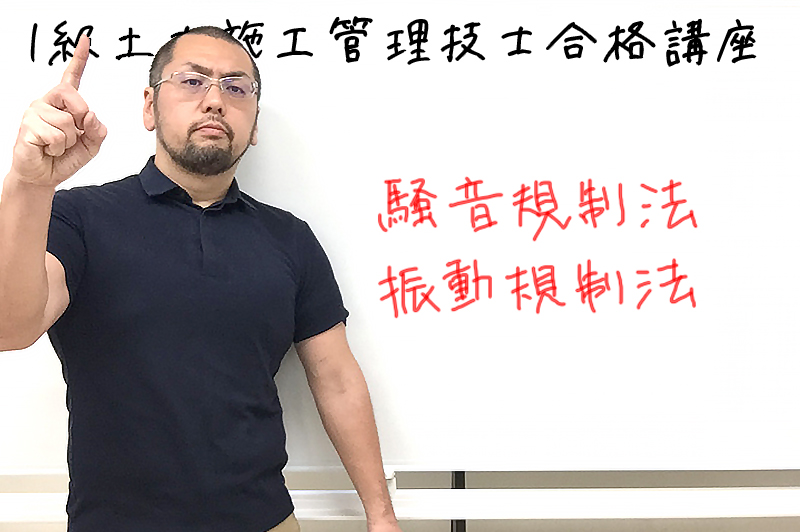1級土木施工管理技士 過去問分析に基づく試験合格対策 騒音規制法と振動規制法
騒音規制法と振動規制法は別の法律で、それぞれ1問ずつ1級土木施工管理技士の試験では出題されます。届出先、基準値等類似している点が多いので、比較しながら一緒に勉強していきましょう。
類似しているからこそ、そこが出題ポイントになります!混同しないよう注意が必要です。
騒音規制法と振動規制法「地域の指定」
-
- 騒音規制法と振動規制法は、生活環境を保全し、国民の健康を保護することが目的とされている。騒音や振動というのは、街中では問題となるが、人の住んでいない山の中や会場ではさほど問題にはならないので、人が住んでいる地域で工事する場合に、騒音や振動が発生する作業を規制する法律である。そこで、その規制対象となる地域を指定するのが都道府県知事である。
- 指定された中でも、学校や病院などがある箇所の周辺で、より厳しい規制の対象となる区域を第1号区域、指定区域の中で1号以外の区域を第2号区域という。
騒音規制法と振動規制法「特定建設作業」
特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、特に大きい振動または騒音を発生する作業として政令で定めるもので、2日以上に渡って実施される作業のこと。また、移動しながら行われる作業では、1日の作業の2点間の距離が最大50mを超えない作業に限る。作業開始した日に終わる作業は除かれる。
→騒音規制法と振動規制法における「特定建設作業」とは、2日以上同じ箇所で、大きな騒音・振動が発生作業と定義されています。そのため、道路の路盤を破砕するような作業箇所が移動する作業の場合、1日の作業位置が50m以上移動すると、同じ地点では2日以上騒音や振動は出続けることにはなりません。そのため、1日の作業距離が50mを超える場合は特定建設作業とはなりません。
騒音規制法と振動規制法「規制基準」
騒音規制法・振動規制法で定められている作業は次のとおりです。
- 騒音、振動の大きさの制限
(騒音規制法)85dB (振動規制法)75dB ※dB;デシベル - 騒音、振動の測定場所
工事個所の敷地境界線において
→ 1級土木施工管理技士の試験問題では「騒音、振動の発生源付近」「敷地の中心」「受音地」で測定と書いてあると×である。 - 夜間の作業禁止時間
1号区域 →午後7時から翌日の午前7時まで
2号区域 →午後10時から翌日の午前6時まで → 1号の方が規制が厳しい! - 1日の作業時間
1号区域 → 1日10時間を超えない
2号区域 → 1日14時間を超えない - 作業期間の制限
同一箇所において、連続6日間を超えて騒音・振動を発生させない - 作業の禁止日
日曜日、その他の休日は作業禁止
騒音規制法と振動規制法「市長村長への届出」
- 指定区域内で特定建設作業を含む建設工事を行う施工者は、特定建設作業開始日の7日前までに、市町村長に届け出なければならない。※災害など非常時は、施工者が届出できるようになった時点で、できるだけ速やかに市町村長に届ける。
→誰が、どこに届け出るか、災害時は、どのタイミングで届け出るのかがポイント!
騒音規制法と振動規制法「届出事項」
下記が1級土木施工管理技士の試験問題で出てくる届出項目です。
- 施工者氏名
- 連絡先
- 目的となる工作物
- 工事名
- 発注者名
- 作業期間
- 作業開始時間~終了時間
- 使用する機械の名称・形式
- 騒音または振動の防止方法
- 工事個所周辺の見取り図
- 工程表 等
届出の必要のない項目「工事費用(請負代金)」「推定の最大騒音値」「作業の実績」・・・これらの項目が出てくると、解答は×となります。
騒音規制法と振動規制法「市町村長による改善勧告等」
- 市町村長は、騒音・振動が規制基準をオーバーして、周辺住民の生活環境を損ねていると認める時は、改善するよう勧告をすることができる。
- 市町村長は勧告を受けた者が、勧告に従わず作業を継続している場合は、改善・作業時間の変更を命じることができる。(工事を中止させる権限までは含まれていない)
※法規に関する試験問題では、その法律を管理する「実施主体」が問われることが多いです。騒音規制法・振動規制法では、実施主体は市町村長です!最初に区域の指定で都道府県知事が出てきましたが。後は届出も勧告も命令も、違反していないか騒音を測定するのも、市町村長の権限で行われます。
【練習問題】次の記述は正しいでしょうか、誤っているでしょうか?
| 特定建設作業を行う場合は、いずれの地域で行う場合でも、市町村長への届出が必要である。 |
→解答×…この問題はひっかけ問題!届け出先は市町村長が正しい。騒音・振動の規制が必要な地域で作業を行う場合に届出をするのは「いずれの地域」ではなく「指定区域」なので×。
| 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要であると都道府県知事が指定した区域では、原則として午後10時から翌日の午前7時まで行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。 |
→解答×…第1号区域における深夜作業の制限は午後7時から翌日の午前7時まで。
| 騒音規制法における特定建設作業には、建設工事として行われる作業のうち、作業場所の敷地の境界線で85デシベルを超える騒音を発生する場合のすべての作業が該当する。 |
→解答×…騒音規制法における基準値は85dBで○。しかし、85㏈を超える騒音を発生するすべての作業が特定建設作業に該当するものではない。指定されていない作業は特定建設作業ではない。また、作業を開始した日に終わるものは除かれる。