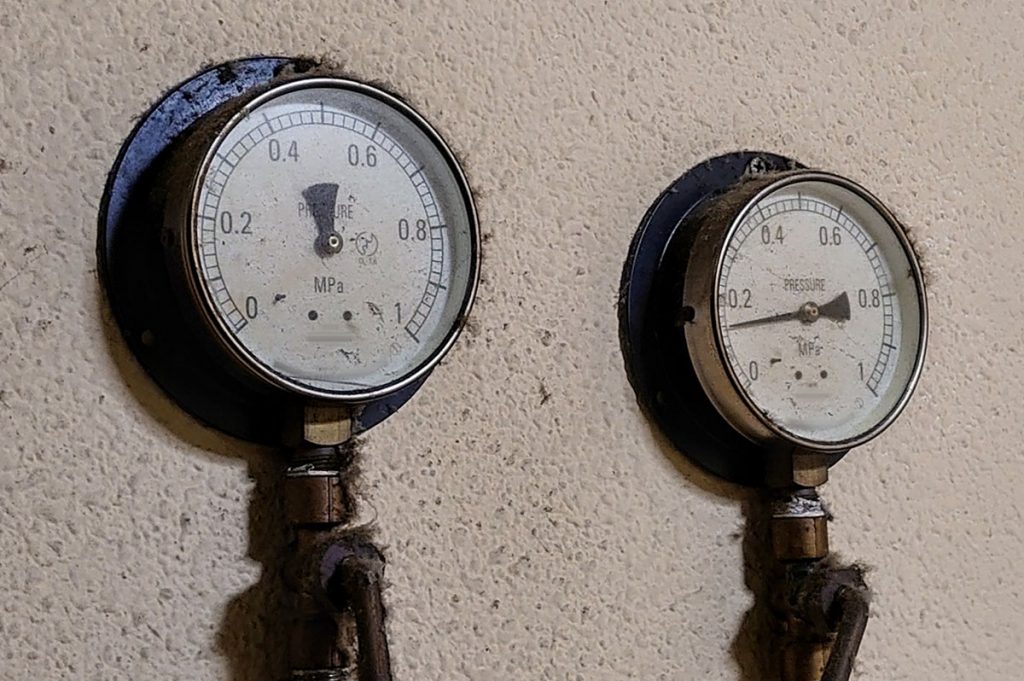皆さんは、「ボイラー技士」という資格をご存じですか?
ボイラー技士は国家資格なので、資格をもっていないと業務をおこなえません。そのため、比較的安定した収入が得られる職業だといえます。
そこで、ボイラー技士とはどんな職業なのか、資格試験の内容や難易度などについて紹介します。
ボイラー技士とは?
ボイラー技士とは、労働安全衛生法に基づく国家資格です。ボイラーは水からエネルギーを作り出す装置であり、多くのビルや工場などで使用されています。
小規模な簡易ボイラーの場合、資格は必要ありません。しかし、一定規模以上のボイラーの場合、管理には危険が伴いますので、資格をもっていると運用や管理、保守点検などに役立つでしょう。
ボイラー技士の仕事内容
ボイラー技士の仕事内容は、ボイラーの保守点検がメインとなります。日常点検に加え、不具合部分の確認や修繕、報告、故障が疑われる場合には業者の手配をします。また、簡単な不具合であれば、ボイラー技士が直すこともあります。
ボイラーは非常に高温であるため、体力が必要な仕事だといえるでしょう。
3種類あるボイラー技士
ボイラー技士の資格は、特級、1級、2級の3種類に分かれていますが、2級ボイラー技士免許をもっていれば、ボイラーの大きさにかかわらず、すべてのボイラーを運転することが可能です。
ただし、ボイラーの取り扱いや管理を的確に行い、安全性を確保するためには、後述するボイラー取扱作業主任者を選任しないといけません。ボイラーの大きさによってボイラー取扱作業主任者に必要な資格は異なります。
ボイラー取扱作業主任者
ボイラー取扱作業主任者に必要な資格、選任基準は以下のようになっています。
| 取り扱うボイラーの伝熱面積 | ボイラー取扱作業主任者の資格 | ||
| 貫流ボイラー以外のボイラー | 貫流ボイラー | ||
| 500平方メートル以上 | 特級ボイラー技士 | ||
| 25~500平方メートル | 250平方メートル以上 | 特級ボイラー技士
1級ボイラー技士 |
|
| 25平方メートル未満 | 250平方メートル未満 | 特級ボイラー技士
1級ボイラー技士 2級ボイラー技士 |
|
| 小規模ボイラーのみを扱う場合 | ・3平方メートル以下の蒸気ボイラー
・14平方メートル以下の温水ボイラー ・胴の内径740ミリメートル以下で胴の長さが1,300ミリメートル以下の蒸気ボイラー |
30平方メートル以下 | 特級ボイラー技士
1級ボイラー技士 2級ボイラー技士 ボイラー取扱技能講習修了者 |
500平方メートル以上のボイラーだと、特級ボイラー技士の資格をもったボイラー取扱作業主任者を選任することが義務付けられています。そのため、大規模な工場などで活躍できるケースが多いでしょう。
ボイラー技士資格を取得するメリット
ボイラー技士資格を取得するメリットとして、以下の3点が挙げられます。
資格手当がつく
ボイラーを使用する事業所にとって、ボイラー技士は必須の資格です。そのため、免許取得者に対して資格手当を貰えることがメリットのひとつです。
会社の考え方や資格の取得数に応じて資格手当は決まりますが、資格取得者が少ない場合には2級ボイラー技士に5,000円相当の資格手当が支給される会社もあります。とはいえ、資格手当には上限が定められているケースもありますので、注意しましょう。
転職に有利
ボイラー技士は、ビルの設備管理やサービスエンジニア、プラント操作などで役立ちます。また、病院やサービス業でもボイラー技士を必要としているため、資格を取得していれば、職の幅が広がるでしょう。さらに実務経験があると転職に有利です。
定年後の再就職に有利
ボイラー技士の仕事は危険が伴うものの、体に負担がかかるような仕事ではありません。高齢者の方が資格を取得し、ビルや施設などを管理する仕事に就くケースも多いです。そのため、定年後の再就職にも有利に働くといえます。
ボイラー技士の年収
厚生労働省の賃金構造基本統計調査によると、ボイラー技士の平均月収は29万円程度で、年収は年間賞与等を含め390~412万円程度です。ただし、年齢や実務経験、会社の規模によっても大きく変わるので、あくまでも参考までに覚えておくとよいでしょう。
ボイラー技士資格の試験について
ボイラー技士の資格試験は、安全衛生技術試験協会が実施しています。
ボイラー技士試験は、現在、公益財団法人 安全衛生技術試験協会が指定機関となって、全国7カ所の安全衛生技術センターで資格試験が実施(特級のみ東京都でも実施)されています。
2級試験は毎月1回、1級試験は2か月に1回程度、特級試験は年に1回実施されます。
試験の概要
特級、1級、2級のボイラー技士の試験は、以下のようになっています。
2級
| 試験科目 | 出題数(配点) | 試験時間 |
| ボイラーの構造に関する知識 | 10問(100点) | 13:30~16:30(3時間) |
| ボイラーの取扱に関する知識 | 10問(100点) | |
| 燃料および燃焼に関する知識 | 10問(100点) | |
| 関係法令 | 10問(100点) |
1級
| 試験科目 | 出題数(配点) | 試験時間 |
| ボイラーの構造に関する知識 | 10問(100点) | 12:30~16:30(4時間) |
| ボイラーの取扱に関する知識 | 10問(100点) | |
| 燃料および燃焼に関する知識 | 10問(100点) | |
| 関係法令 | 10問(100点) |
特級
| 試験科目 | 出題数(配点) | 試験時間 | |
| ボイラーの構造に関する知識 | 6問(100点) | 10:00~11:00 | 各科目1時間
合計4時間 |
| ボイラーの取扱に関する知識 | 6問(100点) | 11:30~12:30 | |
| 燃料および燃焼に関する知識 | 6問(100点) | 13:40~14:40 | |
| 関係法令 | 6問(100点) | 15:10~16:10 | |
受験資格
受験資格は以下のようになっています。
| 2級 | 1級 | 特級 | |
| 受験資格 | なし | 2級ボイラー技士免許を受けた者 | 1級ボイラー技士免許を受けた者 |
| 学校教育法による大学(短期大学を含む)や高等専門学校、高等学校等で、ボイラーに関する学科を修了し卒業した者で、その後1年以上の実地修習を経た者 | 学校教育法による大学(短期大学を含む)や高等専門学校等で、ボイラーに関する講座または学科を修了し卒業した者で、その後2年以上の実地修習を経た者 | ||
| エネルギー管理士(熱)免状(熱管理士免状も該当)を有し、1年以上の実地修習を経た者 | エネルギー管理士(熱)免状(熱管理士免状も該当)を有し、2年以上の実地修習を経た者 | ||
| 海技士(機関1、2、3級) | 海技士(機関1、2級) | ||
| ボイラー・タービン主任技術者(1、2種)の免状を有し、伝熱面積が25平方メートル以上のボイラーの取扱経験者 | ボイラー・タービン主任技術者(1、2種)の免状を有し、伝熱面積が500平方メートル以上のボイラーの取扱経験者 | ||
| 汽かん係員試験の合格者で伝熱面積が25平方メートル以上のボイラーの取扱経験者 |
(公益財団法人 安全衛生技術試験協会のHPより引用)
このように細かく受験資格が定められています。資格取得を検討中の方は、まず受験資格があるのか必ず確認が必要です。その他、受験資格の詳細や注意点などを確認したい方は、事前に公益財団法人 安全衛生技術試験協会のHPをご確認ください。
また、ここで注意したいのは、それぞれの試験に合格した=資格取得にはなりません。免許の交付を受ける際、実務経験の証明、階級によっては実技講習を受講したうえで、免許申請を行う必要がありますので注意しましょう。
ボイラー技士資格に合格するには
ボイラー技士資格に合格するには、どうすればよいのでしょうか。
勉強方法
ボイラー技士の問題は従来、過去問と似た問題が出題されるケースがあったため、過去問をこなせば合格ラインの60%まで到達できました。しかし、近年、新しい問題が出題されるようになり、難しくなっている傾向にあります。とはいえ、合格率が大幅に下落しているわけではないため、過去問を優先しつつ、テキストを精読することがおすすめです。
合格基準
ボイラー技士の合格基準は、特級、1級、2級いずれも、全科目の合計が60%以上の得点率です。ただし、各科目40%以上の得点が必要ですので、注意しましょう。
合格率
ボイラー技士の合格率は以下のようになっています。
| 特級 | 1級 | 2級 | |
| 令和2年度 | 29.1% | 50.9% | 58.4% |
| 令和元年度 | 30.3% | 52.5% | 50.8% |
| 平成30年度 | 25.7% | 58.2% | 55.8% |
| 平成29年度 | 34.5% | 59.4% | 57% |
| 平成28年度 | 19% | 60.7% | 58.5% |
合格後、免許申請を行う際には実務経験等の証明が必要
前述した通り、試験に合格し免許申請を行う際には、実務経験等の証明書類を添付する必要があります。
例えば、2級ボイラー技士免許を取得するためには、免許試験に合格するだけでなく、小規模ボイラーの取扱経験がないといけません。そのため、実務経験がない方は実技講習を受ける必要があります。実技講習は3日間連続での講習のため、1日でも休むと修了できません。そのため、実技講習を受講することが決まった段階で、スケジュールを押さえておきましょう。
(PR)年収700万以上/施工管理の求人を調べたい方はコチラ
定年後も安定して収入が得られるボイラー技士
ボイラー技士はボイラーの取り扱いができ、工場やビルなどで必要な職種です。
会社の規模によって年収に幅があるものの、専門性が求められる仕事のため、定年後の再就職にも有利に働くでしょう。
中でも2級は、受験資格がなく、実務経験がない方でも実技講習を受講すれば免許申請も可能なため、挑戦する価値はあるのではないでしょうか。