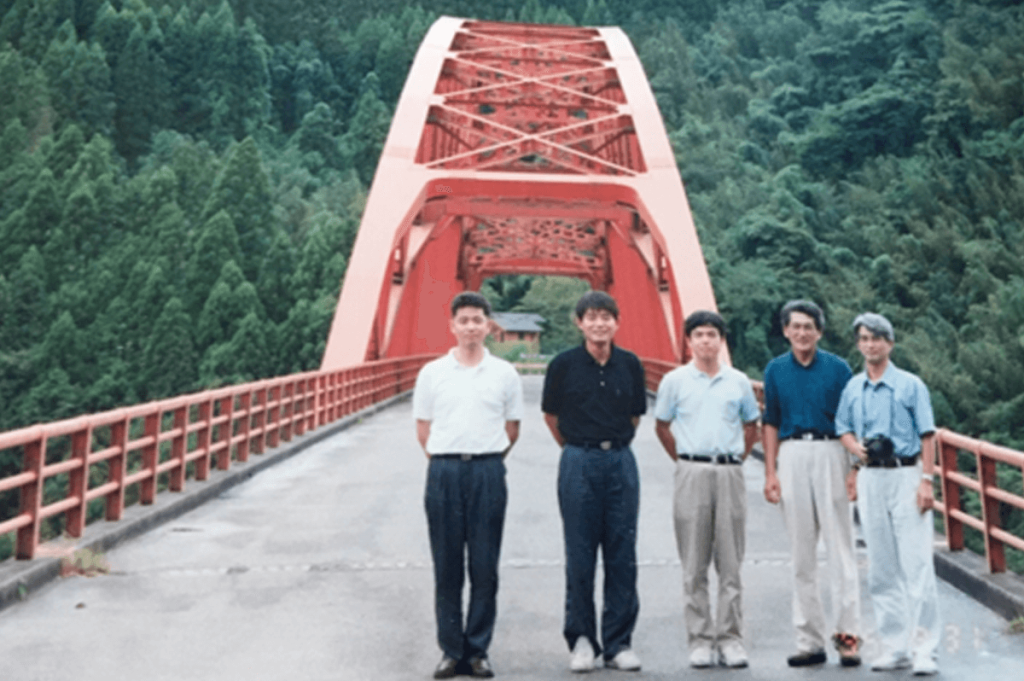本四公団や阪神高速をはじめ、出向先の自治体などで橋梁事業に従事してきた角和夫さんは、コンサルタント会社(日本インシーク=大阪市、小林祐太社長)に転職したのを機に、地方の小規模吊橋への愛情を「小規模吊橋健全度評価システム」として事業化した。
これまでの知見を余すところなく注ぎ、実際の現場に即した内容にまとめたことで、吊橋管理者の反応は早く、1年余りで事業は軌道に乗った。一般的に短期間で普及するものの特徴として利便性と効果ならびに費用、つまり実態に即した内容で取り入れることが容易であり、加えて効果が実感でき、納得できる費用であること、などが主な要素と言われるが、「小規模吊橋健全度評価システム」にはどんな工夫があったのか聞いてみた。
ケーブルの中が見える化できると安心する
作成:角さん
――角さんの地方の小規模吊橋に注ぐ愛情は耳にしていましたので、国内にはどんな小規模吊橋があるんだろう?と検索してみると、観光名所近くの吊橋などを紹介する自治体さんのサイトをいくつも見つけました。地元の生活橋であったり観光資源であったりと地方の小規模吊橋はとても大切にされていると感じました。吊橋は特殊橋梁なので、維持管理においては一般的な桁橋などに比べて考慮項目が多いとも聞きます。「小規模吊橋健全度評価システム」ではどんな工夫をされましたか?
角さん 橋にはそれぞれ、「その部材」が損傷すると橋全体が崩壊する危険性がある重要な部材、いわゆるFCM(Fracture Critical Member;崩壊危険部材)があります。吊橋のFCMは何か。ずばりケーブルです。なぜかというと、吊橋にしても斜張橋にしてもケーブルが生命線であるからなんですね。ですから、小規模吊橋においても、主索(以下「ケーブル」)や吊索(以下「ハンガー」)の点検・検査と評価ならびに適切な対応の選択が生命線となるんです。
ですので、「小規模吊橋健全度評価システム」ではケーブルの腐食状態(断面欠損率)を見える化することと、その結果、いつまでに何をするべきか明確化すること、を必須にしています。この点が管理者さんたちの支持を集めていると実感しています。なぜなら、国や地方自治体の従前の点検は定期点検要領に準拠していて、外観目視で判定していますので、ケーブル表面のさび・腐食により評価していますから、おそらくですが、ケーブルの中の様子を確認したい、という管理者さんの潜在需要が大きかったのかな、と。実際に中の様子が見える化できると、管理者さんは安心するんです。
――そうなんですね。では、需要に対して供給がない状況のなかで、「小規模吊橋健全度評価システム」ができたので、「あぁ、こういうの欲しかった!出たんだ~」と普及した感じですか?技術的な問題でこれまでなかったとかですか?ケーブルの断面欠損率を捉えることで中の状況が見える化できると、なにがどうよくなるんでしょう?
角さん 鋼線の集合体であるケーブルを非破壊検査で見える化する技術として全磁束法が結構前からありました。これによりケーブルの断面欠損率を求めることができます。断面欠損率とは、鋼線の集合体であるケーブル中に発生している腐食部分の率、すなわち、ケーブルに作用する引張力に抵抗しない部分を率として表現したものです。こうした大規模な吊橋のハンガーロープや斜張橋の斜材で使われてきた技術を、小規模吊橋の主索に的確に使うことが「小規模吊橋健全度評価システム」の一つのポイントです。
吊橋、斜張橋の点検にあたっては、道路会社(首都高、阪高、本四や都市高速など)さんでは独自に点検要領を定めています。同様に政令指定都市の大阪市さんでも独自の点検要領を定めています。繰り返しになりますが、吊橋にしても斜張橋にしてもケーブルは生命線であるからです。これらの管理者さんは必要に応じて、臨時点検、詳細(精密)点検を実施するように規定しているんです。腐食が気になればケーブルの非破壊検査(全磁束法や渦流探傷法)を実施しているんですね。
専門技術4ステップでケーブル余寿命を定量化
――それで、実際に「小規模吊橋健全度評価システム」ではどんな手順になりますか?活用技術については協力関係の会社さんとかはあるんでしょうか?
角さん 定量的な評価・診断と補修や架け替えを提案するための手順としては主に4ステップです。吊橋形状測量+ケーブル詳細調査(非破壊検査・張力測定)+詳細点検(特殊高所技術)+健全度評価です。また、必要に応じて(発注者さんの要望など)により補修・架け替え提案や補修設計を行います。
- 吊橋形状測量・・・過去の設計図面、管理図などが残っていないのが普通です
- ケーブル詳細調査・・・全磁束法による断面欠損率から残存耐力の推定をします
- 詳細点検・・・ケーブル張力算定と補修設計用に実施します
- 健全度評価・・・外力(死荷重+活荷重)と抵抗力(ケーブル残存耐力)の関係から保有安全率を算定します
必要に応じて、
- 補修・架け替え提案・・・ケーブルの残存耐力を元に今後の運用方法や補修・架け替え提案を実施します
- 補修設計・・・臨機応変に
詳細点検は安全で確実な技術を保有する特殊高所技術さん、全磁束法については本四の吊橋時代からの繋がりで東京製綱さんと技術協力しています。
そもそも吊橋は、橋が必要であるけれども橋脚が施工しにくいなどの架橋条件を背景として選択されている橋梁形式なので、同様に点検のための足場の仮設も困難かつ経済的合理性も低いことから、特殊高所技術で近接点検することとしています。
全磁束法は本四公団さんと東京製綱さんが共同開発した技術で、本四に代表される大規模吊橋のハンガーロープや斜張橋の斜材点検に利用されていますが、近年東京製綱さんは小規模吊橋の維持管理用途にコンパクト化したシステムを作って、これまでケーブルを納入された小規模吊橋のメンテナンスの要請に応えられていましたので、この技術を活用させてもらうことにしています。
――ケーブルの中を見える化することで、ケーブルの残存耐力、つまりケーブルの余寿命を定量的に示せるということですか?
角さん 管理者さんの潜在需要もそこなんですよね。安全とコスト、つまり管理者の仕事の根幹にかかわる部分ですからね。ですので、「小規模吊橋健全度評価システム」ではここで重要な、(1)あと何年ケーブルが耐えられるか、(2)ケーブル補修(例えば防食塗装)をしてどこら辺まで寿命を延ばせるか、(3)更新、修繕、架け替えのコストは、(4)撤去できないのか?というあたりを明確に捉えられるようにしています。
これらはまず、ケーブルの余寿命、つまりあとどれくらいでケーブルの安全率が基準の3を下回るか、ということが明確にできないと示すことができませんので、規模の大きい吊橋だけでなく、小規模吊橋でもケーブルの断面欠損率を見える化することは重要なんです。
小規模吊橋のハンガーはほとんどが細径でおおよそ外観目視で交換の判断が可能です。ケーブルは、太径であり、昭和30年代のものはダム工事などで使用されたワイヤーロープを転用しているケースが非常に多いです。多くが心材に麻ロープが、外周に鋼線が使用されています。見た目以上にロープ内部での腐食が多いです。昭和59年に日本道路協会が「小規模吊橋指針(案)」を発刊してからは鋼芯ロープが基本となっています。
つまり、小規模吊橋架け替えの原因は、そのほとんどがケーブルの劣化(外面腐食)です。その他の床版やハンガーは通常の舗装補修と同様に計画管理費的なお金を充当して修繕しています。ケーブルの安全率が3を下回ると、活荷重制限(車両や歩行者の通行制限)やケーブル架け替えが必要となり、コストも更新(=架け替え)に近い金額へと膨らんでしまいます。
小規模吊橋は、日本全国に1300橋以上あります。多くが1960年前後に作られたもので、すでに60年以上供用しています。長期修繕計画をもとに予算措置がなされ、予算がないのでⅢ判定をⅡ判定に落として報告したり、通行止め処置をしたりする例もあります。通行止めは安全対策上必要不可欠です。しかし、予算が足りないので通行止め期間を長引かせるほど橋の損傷は酷くなりますので、当初は補修工事で済んだものが、予算付けが回ってくる頃には架け替え工事になってしまって費用が膨張してしまうのも一面の真理です。
ですので、「小規模吊橋健全度評価システム」では、ケーブルの外観目視のみでⅢ判定やⅣ判定にするのではなく、しっかりとした非破壊検査とそれに基づく健全度評価を行い、本当に必要な補修方法等を提案しています。
予算や技術者が少ない管理者さんはどうすれば?
木の根元にアンカー
――本当に必要な補修を、適切なタイミングで、確実な品質で実施すると、吊橋が長寿命化のメンテナンスサイクルに入って、安全とコストが均衡してくるから、管理者さんの潜在需要に応えているということなんですね。それで、「小規模吊橋健全度評価システム」を利用したい場合、費用的にはどうなるんですか?また時間軸でみると、技術革新によって(今般でいえば大規模吊橋に使っていた技術を小規模吊橋に的確に導入するイノベーション)、点検や診断の精度が上がって、長寿命化修繕計画が見直されるのは自然のことのように感じますが、「小規模吊橋健全度評価システム」は長寿命化修繕計画の見直しにも対応する提案となっているということですか?
角さん 予算が潤沢にある管理者さんや補修優先度を考慮した計画を策定したい管理者さんは一歩踏み込んで詳細調査(非破壊検査など)を実施しています。道路会社さんは有料事業で安全をお金で買う理論ですから当たり前ですが。
なので、読者の皆さまも同じことを考えているとは思うのですが、「じゃあ、そうでない管理者、つまり予算や技術者が少ない管理者さんはどうすれば良いのか?これを『小規模吊橋健全度評価システム』で解決できるのか?」ということですよね。
「小規模吊橋健全度評価システム」は小規模な管理者さんの感覚からすると、決して安くはないです。数年前、小規模吊橋を数多く管理する自治体さんにシステムの提案をした際に、「お金が高いんですね、このお金があれば補修工事ができます」と言われたこともあります。その後、その管理者さんの吊橋の維持管理程度を確認すると、ケーブルを立ち木(枯れた杉)に引っ掛けたり、構造力学を完全に無視する対策に及んでいたりと…。自分たちで補修するという精神は素晴らしいとは思うのですが、その結果が安全の犠牲につながっては元も子もないのです。お金は補修に回したい気持ちはわかります。ですが、そもそものその補修の根拠が揺らぐような土台であれば、そこに依って立つ補修の効果は危うく、それこそ貴重なお金を無駄にしてしまうことになってしまいます。
このように管理者さんは多様でいろいろなことがあるにしても、根拠に基づく長期修繕計画の見直しについては、需要が高いのは事実で、それに応え得る提案としています。
【東証スタンダード上場】橋梁工事の土木施工管理(宿舎あり)の求人を見る[PR]
観光シーズン到来。心に残る吊橋景観は?
現在の角さんはこんな感じです=旅行先の三島スカイウォークで、手前のくろもこもこは愛犬クロちゃん
――余談なんですが、観光シーズンにも入りますので、教えてください。角さんは多くの吊橋をご覧になってきたと思うんですけれど、この景観はいいな~と思う吊橋はありますか?春夏秋冬いろいろあるとは思うんですけれど。例えば、心に残る景観10橋とか教えていただけますか?
角さん それぞれの吊橋の魅力は尽きないところですが、車が通行できる橋では大鳴門橋や関門橋、来島海峡大橋、小鳴門橋などでしょうか。大鳴門橋は鳴門海峡をまたぐ四季折々の表情を感じますし、本四公団に入社後最初に担当した吊橋であり、その20年後には維持管理を担当した吊橋で愛着があります。
関門橋は本州と九州をつなぐ近代長大吊橋の先駆者、本四公団に入社するきっかけとなった吊橋です。来島海峡大橋は来島海峡にスレンダーな3連吊橋であり、日本初の箱桁吊橋で計画を担当しました。小鳴門橋は日本で初の4径間吊橋です。主塔が3本以上の吊橋を多径間吊橋と言いますが、設計が難しい橋です。本四架橋完成後、私たちが検討した海峡横断道路超長大吊橋(豊予海峡や早崎瀬戸)でも必須の技術ですが次世代の夢の吊橋です。大鳴門橋への出勤途中に必ず通る吊橋で愛着があります。
大鳴門橋 撮影:角さん(課長時代に千畳敷で)
関門橋 撮影:角さん(福岡県課長時代に)
来島海峡大橋 撮影:角さん(副所長時代、糸山公園展望台から)
小鳴門橋 撮影:角さん(課長時代に通勤途中)
――そうなんですね。1橋、1橋、それぞれすごく思いの深さが伝わってきます。そういえば来島海峡大橋って、しまなみ海道の橋ですよね。しまなみ海道の橋って歩行者と自転車用のレーンが橋にあるので、歩いてみたいと思っていたんです。本四さんのホームページを見るとちょうど2026年3月31日までは歩行者・自転車は無料で通行できるみたいですし。車は通行しない吊橋はどうですか?
角さん そうですね、三島スカイウォークや、もみじ谷大吊橋、宮前橋(恋の吊橋)、美濃橋、苔の橋、久野脇橋なども周囲の景観と良い感じです。
三島スカイウォークは日本最大の歩道吊橋、もみじ谷大吊橋は紅葉に大吊橋がとても映えますし、宮前橋(恋の吊橋)はコンクリート主塔が苔で覆われているんですよ。美濃橋は日本最古の近代吊橋で国指定重要文化財、苔の橋も絶景です。久野脇橋は橋下の川や鉄道(SL)とマッチした写真などでも有名ですね。
――橋に苔がむすとは…、どの橋も趣がありますね。観光吊橋もあれば、生活橋として普通に地域で使われている橋もあります。近くに行く機会があれば立ち寄ってみたいと思います。ありがとうございました。
三島スカイウォーク 撮影:角さん
もみじ谷大吊橋 撮影:角さん
宮前橋(恋の吊橋) 撮影:角さん
美濃橋 撮影:角さん
苔の橋 撮影:角さん
久野脇橋(塩郷の吊橋) 撮影:角さん