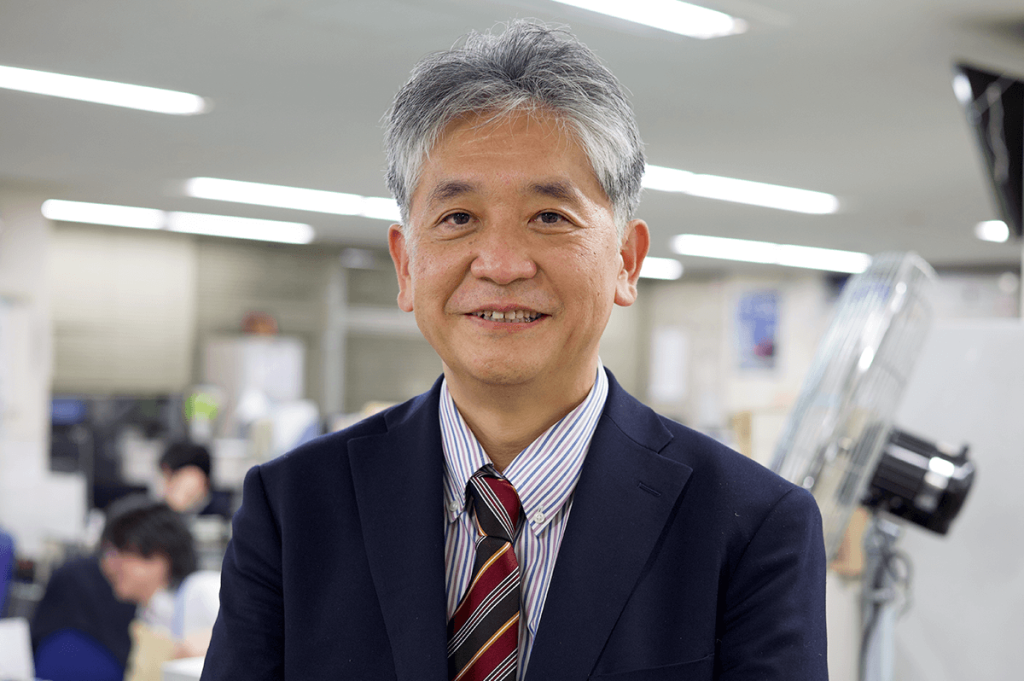以前、国土交通省の奥田晃久さんの記事を出したことがある。以来、なんか「気さくで熱い人」という印象がずっと残っていて、別件で本省を訪れた際には、奥田さんの職場に立ち寄ったりしてきた。
そんな奥田さんがいつの間にか技術調査課長に着任していた。技術調査課は、過去に何度も取材してきた馴染みのセクションであるが、あの奥田さんだったら、技術調査課の仕事について、どういう話をするんだろうということが、気になった。ということで、お話を聞いてきた。
直轄事業における担い手3法を軌道に乗せるのが、私の使命
――技術調査課の仕事は非常に幅広いそうですね。
奥田さん そうですね、入札契約、技術開発、採用、あとは、宇宙の関係とか、省内のいろいろな雑用みたいなこともやっていますし。
――技術調査課長のお仕事はどうですか?
奥田さん 2024年6月に担い手3法が国会を通ったので、不動産・建設経済局(以下、不建局)とともに、これをちゃんと軌道に乗せるのが、一番の仕事ですかね。私自身、建設業界はなくてはならないという強い思いがあるんです。
建設業界を若い人から選ばれる業界、仕事、職場にしていかなければならないというところなんですよ。もし選ばれないと、この業界の先はない、災害対応もままならなくなります。自衛隊が被災地を通れるようにしているのは、建設業界ですからね。
個人的には、被災地では、建設業界の方々が、体を、そして時には命を張りながらやってくれていると思っています。そういう方々の処遇はもっと改善されなければなりませんし、もっとカッコ良い存在にならなければなりません。今、週休2日とかいろいろやっていますが、全部ここにつながってくると思います。
今はそれなりに人がいるように見えますが、年配の方々ばかりで、若い人はめちゃくちゃ少ないです。5年10年経つと、一気に人が減って、ポキッと折れるんじゃないか、そんなことを心配しているんです。
ロボットを使うとか、オートメーションでやるとか、i-Construction関係の取り組みは、ウチの課の参事官(イノベーション担当)のほうでやっています。そういう道も含めて、やれることをやっていくという覚悟です。
【PR】転職に成功する施工管理と失敗する施工管理の「わずかな差」
建設業界は「週休2日でも働く」と思われている
――非常に根深い問題なので、これという特効薬はないという気がします。
奥田さん 地域によっても状況が全然違いますからね。技術調査課に来てから、全国各地のいろいろな業者さんの声を聞いていますが、「週休2日を強制するな」という業者さんもいれば、「週休2日ぐらいしないと、若い人が来ない」という業者さんもいたりで、本当にいろいろな意見があります。
たぶんですが、世の中からは、建設業界、とくに建築業界は、「週休2日でなくても働く」と思われているんです。たとえば、デベロッパーなんかは、資金を回収しなければならないので、工期は1日でも早いほうが良いわけですから、そのほうが都合が良いんです。
――土木業界も、直轄事業は週休2日がデフォルトになっていますが、市町村はそうではないそうです。
奥田さん そうなんです。「市町村レベルではまだまだ」という声はあります。ただ、建築と比べると、土木のほうがまだホワイトかなという感じがします。土木と建築は、採用という段階では、業界間で人を取り合っているような部分もあるので、土木がどんどんホワイトになれば、いずれ建築もホワイトにならざるを得なくなるかもしれません。
本省もそうだが、地整が職員採用に一番苦労している
――国土交通省も職員確保に苦労されていると聞いていますが。
奥田さん 今、理系の学生は引く手あまたなので、苦労しています。私自身、出身大学に何度も足を運んで、アピールしています。本省も昔に比べれば、ずいぶん働きやすくなりました。残業はかなり減っていますし、職員の配属先も柔軟に考えるようになっています。その結果、離職率も改善されています。
本省の採用も大変ですが、一番苦労しているのは、地方整備局です。たとえば、大卒の採用者数の枠より、合格者が少ないんです。
トップランナーである直轄事業が全国の建設事業を引っ張る
――課長として、とくにチカラを入れているお仕事はなんですか?
奥田さん 担い手3法をしっかり軌道に乗せることですね。直轄事業における働き方改革への対応、暑さ対策、入札における最低制限価格、技術基準、事業評価といったところです。
あとは、建設関係の中央や地方の業界団体との関係づくりです。2024年度は6つほど地方整備局を回って、各地方の業界団体の方々と意見交換しました。「なんでこうなってんねん」と怒られたりするんですけど、地方の生の声を聞くということは非常に重要ですので、可能な限り予定を合わせて回りました。
――担い手3法の関係では、技術調査課は直轄事業を担当するということですか?
奥田さん そうです。いわゆる業行政は基本的に不建局の所管ですが、技術調査課はそのうちの直轄事業の担当なんです。担い手3法のうち、入札契約に関する議員立法である品確法は、こういう発注をすべきという理念法なんです。
この理念を実現するには、まず直轄事業が先行して実施する、というカタチで進めています。残念なことですが、国が決めた入札契約制度を、必ずしも自治体は守る必要はないんです。直轄事業でまずやってみせて、良いことがある、得なことがあるというのを自治体に知らしめながら、新しい制度などを引っ張っていく、というのが、直轄事業の使命であり、われわれ技術調査課の仕事なんです。
われわれが引っ張っていくのは、主に都道府県や市町村の工事ですが、そのさきには民間の工事もあります。民間工事を引っ張っていくのは、極めて難しいんですけどね(笑)。それでも、「建設事業のトップランナーとして、直轄事業が頑張るんだ」ということでやっているところです。
「国の言うこと聞く義務ないのに、なんでせなあかんねん」
――市町村を引っ張るのも難しそうですが。
奥田さん ええ、大変ですね。市町村にもいろいろな考え方があるんです。中には「安くできれば、それで良いじゃないか」という市町村もあります。われわれからすれば、「安かろう悪かろう」はダメなことなのですが、その辺の考え方のミゾがなかなか埋まらないんですよね。
たとえば、100の工事を60で取ったとか、100の工事を取ったら150かかったけど、お金をみてもらえなかったという声もあります。こういうのは、業界全体で考えると、悪い影響がありますよね。
――以前、市町村を対象にキャラバンをやったとおっしゃっていましたね。
奥田さん そうですね。たとえば、事務所長が直轄事業を進める際、地元市町村の首長さんからいろいろお願いされるわけです。近畿地方整備局の企画部長のとき、管内の事務所長に「こっちからもお願いしろ」とハッパをかけていました(笑)。
でも、市町村には国の言うことを聞く義務がないんです。ここが難しいところなんです。「国の言うこと聞く義務ないのに、なんでせなあかんねん」という首長さんもいらっしゃいます。これで一番困っています。
技術調査課の仕事は、建設業界を良くし、業界の未来を担うこと
――以前、技術調査課長はめちゃくちゃ忙しいポストだと聞いたことがありますが、どうお感じですか?
奥田さん それは忙しいですよ(笑)。たとえば、さきほども言ったように、いろいろな会合に顔を出さないといけません。すると、私が職場にいない間、私が知らない間に、いろいろな大事なことがどんどん動いていたりするわけです。これは怖いし、なにより気色悪いですよ(笑)。「これ、大丈夫なのかな」と不安を感じます。ウチには優秀な職員がいるし、今はだいぶ慣れてはきましたけどね。
――技術調査課の魅力はなんですか?
奥田さん 技術調査課は、建設業界を良くする、業界の未来を担う、いろいろな大事な仕事を抱えています。そういうところが魅力ですね。われわれが頑張れば、業界も直轄事業も良くなるので、明るい仕事、職場です。決してネガティブな仕事ではありません。