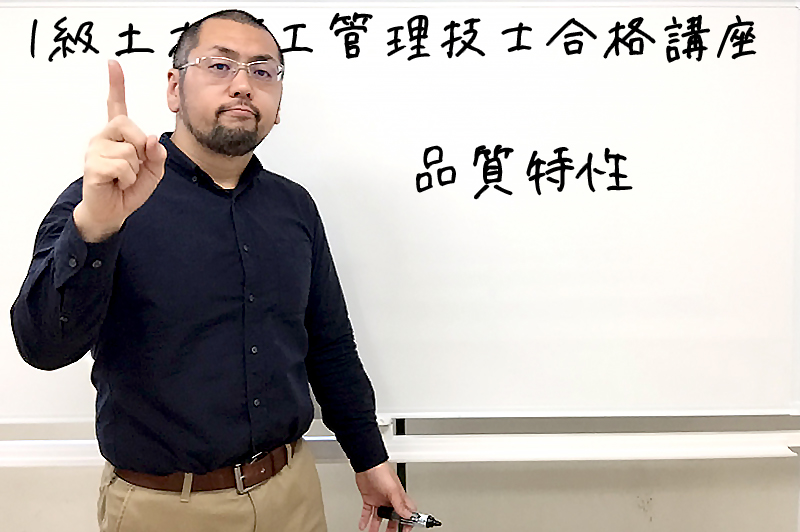1級土木施工管理技士 過去問分析に基づく試験合格対策 品質管理その2「品質特性」
1級土木施工管理技士 過去問分析に基づく試験合格対策の第34回目は、「品質特性」について学習ポイントをまとめます。
「品質管理の手順」「品質特性の選定時の注意点」「品質特性と試験方法の組み合わせ」についての出題傾向を抑えたら、練習問題にもチャレンジしてみてください。
品質管理の手順(品質特性)
品質管理の手順は、専門的な用語が多いので、現場に則したイメージしやすい言葉に変換しましょう。
手順1. 品質特性の選定 → 管理項目を設定
手順2. 品質標準の設定 → 規格値の設定
手順3. 作業標準の設定 → 作業方法を設定
手順4. データ採取
手順5. 分析
手順6. 作業方法の見直し
手順7. 作業の継続
1級土木施工管理技士の試験問題では、手順1~3の説明がよく出題されます。前回の記事で説明したPDCAサイクルにあてはめると、上記の手順1~3が「Plan(計画)」で、手順3~4の間に作業の「Do(実施)」があり、手順4と手順5が「Check(確認)」、手順6が「Act(是正)」、手順7はPDCAサイクルと継続していきます。
手順1~3の順番の並べ替えがよく出題されます。
品質特性→品質標準→作業標準の順番になります。
品質特性の選定時の注意点
品質管理の項目では、用語を説明する問題が多く出題されます。その中でも「品質特性の選定」が誤りの記述として多く出題されるため、しっかり覚えておきましょう!
品質特性の選定の注意点!( )内の記述は誤りの記述です。
- 品質特性は、品質管理における具体的な対象項目であり、工程を総合的に表すものである。(品質特性は、×工程に左右されない独自の特性を表すものである。)
- 品質特性は、できるだけ初期に測定でき、すぐに結果が得られるものがよい。(品質特性には、×完成後に結果が得られるものを選定する。)
- 品質特性は、品質に重要な影響を及ぼすものを選ぶ。(品質特性は、×品質に影響のないものである。)
- 品質特性は1つではなく、部位ごと工程ごとに複数あるのが一般的である。(品質特性が複数ある場合は、×その中から1つを選び品質特性とする。)
品質特性と試験方法の組み合わせ
1級土木施工管理技士の試験問題では、品質特性とその試験方法(試験機器)の組み合わせが出題されます。
よく出題されるものを一覧にまとめておきます。
| 工種 | 品質特性 | 試験方法(試験機器) | |
|---|---|---|---|
| 土工路盤工 | 材料 | 最大乾燥密度・最適含水比 | 締固め試験 |
| 施工 | 締固め度 | 単位体積重量試験・現場密度試験 (砂置換法・RI法) |
|
| たわみ量 | たわみ量測定(ベンゲルマンビーム) | ||
| 支持力 | 平板載荷試験・CBR試験 | ||
| コンクリート工 | スランプコンクリートのコンシステンシー | スランプ試験 | |
| アスファルト舗装工 | 材料 | 針入度 | 針入度試験 |
| 耐摩耗性 | ラベリング試験 | ||
| 耐流動性 | ホイールトラッキング試験 | ||
| 施工 | 安定度 | マーシャル安定度試験 | |
| 平坦性 | 平坦性試験(プロフィルメーター) | ||
| 完成後 | すべり抵抗(動摩擦係数) | 回転式すべり抵抗計測器 | |
品質特性の練習問題
【問題1】次の記述は正しいでしょうか、誤っているでしょうか?
◇品質管理の手順は、一般に管理しようとする「品質標準」を決めてから「品質特性」を決め、「作業標準」に従って作業を行う。
→解答×…品質管理の手順は、品質特性(管理項目)→品質標準(基準値)→作業標準(作業方法)の順に設定します。
◇品質特性は、工程に対して処置をとりやすい特性で、時間をかけても結果が得られるものを選ぶものとする。
→解答×…前半の工程に対して処置をとりやすい特性というのは正しいですが、そのためには結果が早く得られるものを選ぶことが望ましい。
【問題2】工事の品質管理における工種とその品質特性及び試験方法との組合せとして、次の(1)から(4)のうち適当なものはどれか。
| 工種・測定対象 | 品質特性 | 試験方法・試験機器 | |
|---|---|---|---|
| (1) | 土工 | たわみ量 | 平板載荷試験 |
| (2) | アスファルト舗装工 | 平たん性 | ベンケルマンビームによる測定 |
| (3) | アスファルト舗装工 | 針入度 | マーシャル安定度試験 |
| (4) | コンクリート工 | コンクリートのコンシステンシー | スランプ試験 |
→解答(4)…たわみ量の測定にはたわみ量試験により測定する。支持力の測定は平板載荷試験を用いる。平坦性の測定は平坦性試験により求める。たわみ量の測定には、ベンゲルマンビームを用いる。針入度の測定は針入度試験を行う。安定度はマーシャル安定度試験により求められるため、(1)~(3)は誤りとなる。