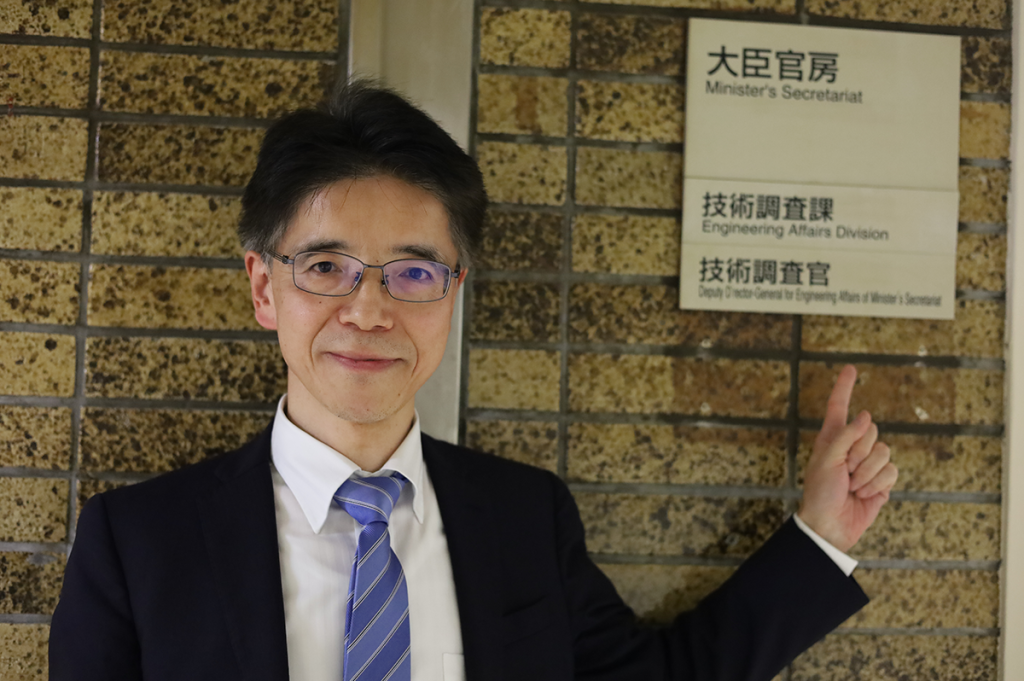技術調査課とはどういう課なのか?
これまで何度となく取材にご協力いただいてきた国土交通省の見坂茂範さんが今年6月、本省大臣官房の技術調査課長に異動された。
技術調査課とはどういう課なのか。課長として、見坂さんがどういう仕事をしているのか、気になった。本省は激務だというアタマがあったので、おそるおそる取材を申し込んだわけだが、幸いなことにご快諾いただいた。
この場を借りて、改めてお礼を言っておきたい。ということで、見坂さんにいろいろお話を聞いてきた。
メチャクチャ忙しいポスト
――本省勤務は何年振りですか?
見坂さん 前に本省にいたのが2018年夏まででしたから、4年振りです。
――技術調査課長とはどういうポストなんですか?
見坂さん メチャクチャ忙しいポストです(笑)。技術調査課は、大臣官房唯一の技術系の課で、所掌する業務が非常に幅広いです。
――なにをする課なのか、よくわかりません(笑)。
見坂さん まあ、そうですよね(笑)。
インフラDXから採用人事まで
――技術調査課ではどういった業務を担当しているのですか?
見坂さん 技術調査課が所掌する業務としては、大きく分けると、まず新技術の開発があります。インフラDX、I-Constructionなどといった技術政策全般です。あとは、建設産業に関わる仕事です。入札契約や積算に関する制度、工事成績評定といった発注行政に関する仕事です。さらに、職員の採用、人事もやっています。
最近の動きとしては、新技術に関しては、I-Constructionを中核として、インフラDXを推進しているところです。
発注行政に関しては、今、まさに、全国各都道府県の建設業協会との意見交換を行っています。現場の声をよく聞いて、それを政策に反映させるためです。
職員の採用に関しては、面接、選考に直接携わっています。先日は、来春入省が内定した方々の内定式を行いました。私も出席し、課長として訓示を行いました。
――見坂さんも面接するのですか?
見坂さん ええ、最終面接は私が行いました。以前にも企画官として採用を担当したことがあります。
――インフラDXから採用人事までとなると、非常に幅広いですね。どれも重い仕事でしょうし。
見坂さん そうなんです。なので、繰り返しになりますが、とにかく忙しいんですよ(笑)。
ホントはもっと採用したかった
――今年の採用活動はどうでしたか?
見坂さん 今年は非常に順調で、良い人が集まったと感じています。と言うのも、一昨年ぐらいから、全国の主な大学とタイアップしながら、各大学のOBOGの職員が学生さんに対し、国土交通省の魅力を伝えるといった取り組みを続けています。
これは、技術調査課だけでなく、国土交通省を挙げて、チームをつくって取り組んでいるところです。国土交通省として積極的にアプローチをかけたおかげで、今年は本当に良い学生に来ていただきました。
実際に面接をしてみて、ホントは「もっととりたい」と思いました。率直に言って、以前採用を担当していたときとは、かなり状況が違っています(笑)。来春入省する方々には非常に期待しています。
働き方改革のためのインフラDXに注力中
本省庁舎内に設置された「インフラDXルーム」
――課長として、とくにチカラを入れてやっている仕事はありますか?
見坂さん やはり、建設業界に関する仕事ですね。とくに働き方改革に絡むところにチカラを入れています。
建設業界は従来、キツイ、キタナイ、キケンの「3K」と言われてきました。今は、「新3K」として、「給料」がしっかりもらえる、「休暇」がしっかりとれる、「希望」が持てるの「新3K」を打ち出しています。
これを実現するために、I-ConやDXといった新しい取り組みをしていく。そういうスタンスで仕事をしているところです。
建設業界の給料はまだまだ低い
――具体的にはどういう取り組みになるのでしょうか?
見坂さん たとえば、給料で言えば、設計労務単価などを10年連続で引き上げています。この流れは今後も続けていくべきだと思っています。
私は、建設業界の給料水準は、ほかの業界に比べて、まだまだ低いと思っています。工場などの製造業と比べると、現場で働く方々の給料は引き上げられたとは言え、まだまだ低いと思います。
まずは、発注者が設定する単価については、今後もしっかり引き上げていく必要があると感じています。建設会社も、これを踏まえて、従業員の給料を引き上げていっていただきたいというのが、私の思いです。
週休2日の定着により、罰則付き時間外労働規制をクリアする
見坂さん 2024年4月から、建設業においても、罰則付きの時間外労働規制が適用されます。改正労働法の施行に伴う5年間の猶予期間が終わるからです。この規制が適用されると、月45時間、年360時間という時間外労働の上限規制がかかってきます。これを守らない建設会社は罰せられます。
いわゆる「2024問題」ですが、残り1年半を切りました。国交省としても、建設会社と一緒になって、働き方改革を進めていかなければならないと考えているところです。
その一つの手段として、建設現場の週休2日制があります。建設業界も「週休2日が当たり前」にならなければいけません。国交省直轄の土木工事で言えば、97%が週休2日になっています。都道府県、市町村の土木工事についても、週休2日を拡げていただきたいということで、お願いしているところです。
公共工事で週休2日が定着すれば、民間発注工事にもその波が及ぶことが期待されます。民間同士の契約なので、なかなか難しいところがありますが、われわれとしては、民間事業者に対して、週休2日の定着をお願いしていかなければならないと思っています。
週休2日が定着したとしても、平日の残業が増えてしまっては意味がありません。これを防ぐためには、工事書類や手続きなどの簡素化や削減といったことにも取り組んでいきたいと思っています。
インフラDXは現場だけでなく、国交省の働き方も変える
本省エレベータ内に掲示された本省での働き方改革に関するポスター(右)
見坂さん 期待を持ってもらうためのツールとしては、I-ConやインフラDXの推進があります。
I-Conについては現在、「2025年までに建設現場の生産性を2割向上させる」ことを目標にして、取り組んでいるところですが、すでにかなりの効果が確認できています。工種によっては、生産性の向上が見込めない工事もありますが、そういう工事も含め、目標達成に向け、引き続き取り組みを進めていく考えです。
インフラDXは、I-Conの取り組みをさらに広げた概念になります。I-Conが建設現場の生産性向上を目指した概念であるのに対し、インフラDXは、インフラの利用やサービスの向上を目的としたツールとしての活用といったことも含んでいます。たとえば、ハザードマップの3D表示、VRを用いたバーチャル現場、AIによる画像判別などがあります。
インフラDXを進めることは、建設現場で働く方々だけでなく、国交省職員の働き方改革につながる。そう考えています。
インフラのつくり方、使い方、伝え方を変える
――インフラDXの進捗はどうですか?
見坂さん これまでは、省内の各局ごとにインフラDXの取り組みを進めてきました。いわゆる「タテ割り」でやってきたわけですが、やはり、もっと組織横断的にやっていくべきじゃないかということになりました。そこで、国交省だけでなく、産官学が連携し、組織横断的に取り組むべく議論しているところです。
議論の中では、3つの視点で取り組むべきじゃないかという話になっています。
1つ目の視点が、「インフラのつくり方の変革」です。たとえば、現場にいなくても現場管理ができるといったことです。大手の建設会社では、建設機械が自動運転で作業するといったことが、すでに実施されています。将来的には、そういう現場をどんどん増やしていきたいと思います。
2つ目が、「インフラの使い方の変革」です。たとえば、ハイブリッドダムが挙げられます。平常時にはしっかり水を貯めて、その水で発電する一方、大雨時には貯水量を下げて、治水能力を最大化するダムということです。こういった取り組みを積極的に進めていこうと考えています。
3つ目が、「インフラまわりの情報の伝え方の変革」です。国交省は膨大な量のインフラに関する情報を持っています。この情報をもとに、「国土交通データプラットフォーム」を構築しています。
このプラットフォームには、気象庁が持っている気象データや国土地理院が持っている地形データなども入っています。データの統合ではなく、データの連携が目的で、可能なものはデータを公開しています。民間ビジネスへの活用も視野に入れています。
ただ、私としては、このプラットフォームはまだ使い勝手が悪いと思っています(笑)。実際に操作してみたのですが、動きが遅いところがあると感じました。その辺の改善も含め、議論を重ねているところです。
これらの視点を踏まえながら、インフラDXをしっかり進めていくのが、旗振り役である技術調査課の使命だと考えています。
3Dデータはちゃんと引き継げなければ意味がない
――来年度からのBIM/CIMの原則適用が迫ってきていますが、どのような状況ですか?
見坂さん 2023年度からのBIM/CIMの原則適用は、一般土木工事と鋼橋上部工事が対象です。ただ、「なにをもって原則適用とするのか」については、よく考える必要があると思います。
なんのためにBIM/CIMをやるのかと言えば、建設プロセスの最初の段階でつくられた3Dデータを最後まで引き継ぐことによって、受注者をはじめ、発注者の負担も減らしていくことにある。そう私は考えています。
理想はそうなんですが、実際は、各プロセス間のデータの引き継ぎがうまくいっていないんです。たんに3Dデータをつくるだけではダメで、いかにデータを引き継ぐかが、カギになると考えています。「データをうまく引き継げないなら、BIM/CIMをやる意味はない」とすら言えます。
そういうことで、データをうまく引き継ぐためにはどうすべきかということが、来年度の原則適用に向け、今われわれが果たすべきミッションだと捉えています。なので、設計段階において、高度で完璧な3Dデータをつくることは、必ずしも必要なことではありません。
それよりも、施工業者にとって「ちゃんと使える」データであることのほうが、はるかに大事なことだと考えています。これを実現するには、最低限のスペックとして、どのようなデータが必要なのか、この辺を明確にしなければならないと考えています。中小の施工業者にちゃんと使ってもらうことが、最も重要なことですから。
現在、現場の職員や業界の意見なども聞きながら、大詰めの検討を行っているところです。議論の中では、たとえば、堤防の設計は「断面×延長」があれば良いので、3Dを求めず、2Dで構わないといった話が出ています。議論の結果については、年明けごろにお示しさせていただく予定です。
建設業界のイメージも「カッコ良い」に変える
――建設業協会との意見交換の中で、BIM/CIMに関して、どのような声が出ましたか?
見坂さん 「ハードルが高い」、「なにをやれば良いかわからない」といった声もありました。われわれとしては、そういった意見にも耳を傾けながら、うまく制度設計していく必要があると考えています。
――建設業界の保守的な体質もネックになっていると思われますが。
見坂さん 建設業界も変わる必要があると思っています。I-ConやインフラDXを通じて、生産性が向上し、働きやすい業界に変える。業界のイメージも「カッコ良い」に変える。今それが求められていると思っています。
今建設業で働いている方々はもちろん、若い人や女性の入職という点からも、必要なことだと考えています。