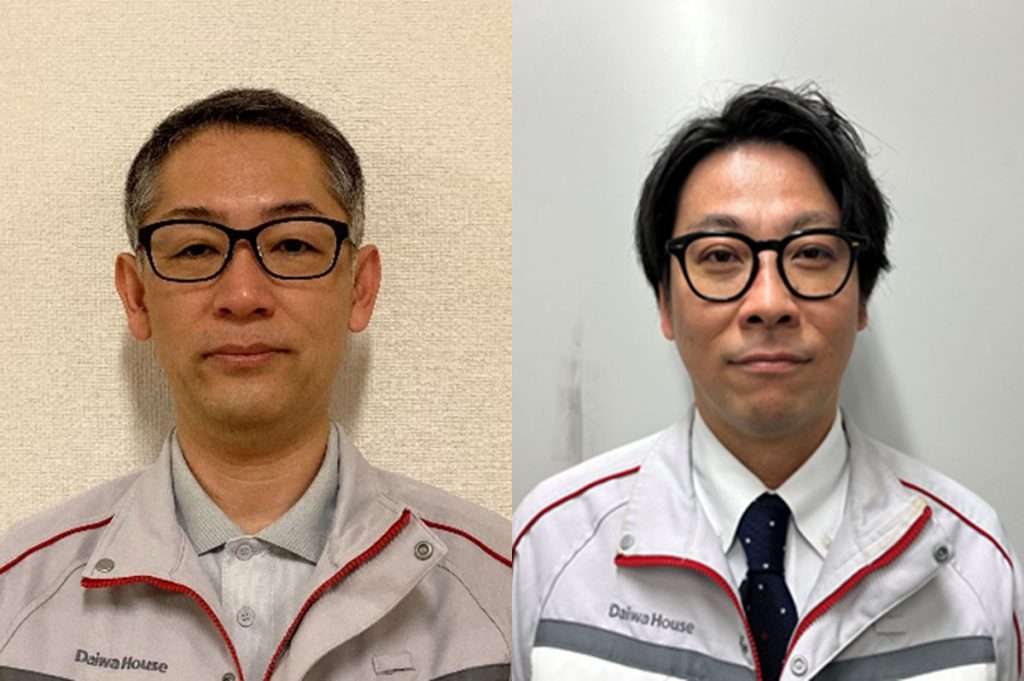大和ハウス工業(大阪府大阪市)は、事務所や工場などのZEB化を推進するため、初期設計段階で利用するZEB設計支援ツール「D-ZEB Program」と詳細設計段階で利用する「BIM連携ZEB設計ツール」を同時に開発し、運用を開始した。ZEB検討に必要な省エネ性能の計算時間を、従来の数週間から1時間以内に短縮。平面図しかない設計初期段階からのZEB提案や設計変更時のZEB化の検討にも迅速に対応可能となる。
同社は、設計段階の川上から川下までスピーディーで質の高いZEB提案を可能とすることで、2030年度に同社が建築する建物のZEB率100%を目指す。今回、同社総合技術研究所主任研究員の本間瑞基氏と建設DX推進部 DX企画室室長の吉川明良氏に開発の背景や狙いについて話を聞いた。
BEI計算の短縮で、早期のZEB提案が可能に
――まず、ZEB設計ツールそれぞれの開発概要からお願いします。
本間瑞基氏(以下、本間氏) 「D-ZEB Program」は設計初期段階で、「BIM連携ZEB設計ツール」は詳細設計段階で使用するものです。まず「D-ZEB Program」に関してですが、当社は建築する建物のZEB率100%を目指しており、計画の早い段階からZEB建築を受注していかなければなりません。ZEBの評価は設備設計が完成後に行いますから、設計初期の段階でZEB評価をするのは難しいのですが、早期にZEBの実現性について仕様と具体的な数値を示さないとZEBの仕事の受注は困難です。そこで設計の初期段階、私は“単線プラン”と呼んでいますが、ZEBを評価できる仕組みが必要でした。現場の設計者からもZEBについて設計初期段階から提案をしたいとの要望もあった点も開発の後押しになりました。
BEI算出全体像 / 大和ハウス工業
――従来、ZEB検討に必要な省エネ性能の計算時間に数週間かかっていたところ、「D-ZEB Program」の開発により1時間以内に短縮することが可能になったとのことですが、従来の作業フローはどのような流れなのでしょうか。
本間氏 意匠設計図の完成後に設備設計に入るわけですが、ZEB認証に必要な省エネ性能の計算指標であるBEI(Building Energy Index)の算出では、床面積や外壁面積、窓面積、設備機器の詳細情報を各室ごとに入力するなど、作業が煩雑で数週間の時間がかかっていました。そのため、顧客へのZEB提案が設計初期段階で行えないこと、設計変更時にZEB化の検討が迅速に実施できない点が問題としてありました。「D-ZEB Program」では、設備や断熱性能など建物の仕様が確定していない平面図の段階で、スピーディーなZEB提案が可能となります。
「D-ZEB Program」は、建物用途ごとの標準的な仕様や設備機器の台数を算出する計算式を取り込んで自動化するツールで、室名や床面積などの最低限の情報を入力し、ツールに整備された断熱や設備の性能を選択するだけで簡単にBEIを計算することができます。これにより、従来は数週間かかっていたBEI計算が、室数が少ないプランであれば10分以内、延床面積約2,000m2の事務所計画では1時間以内で実施できます。
初期設計段階では、「D-ZEB Program」で、詳細設計段階では「BIM連携ZEB設計ツール」でそれぞれ省エネ性能計算時間を短縮 / 大和ハウス工業
――同時開発された「BIM連携ZEB設計ツール」はどのように活用するものでしょうか。
吉川明良氏(以下、吉川氏) 「BIM連携ZEB設計ツール」は、BIMによる3Dモデルができた詳細設計段階(基本設計・実施設計)に利用することで、仕様変更時のZEB化の検討に迅速に対応できます。
当社は、事務所や工場など事業用建物の設計はすべてBIMで行っていますが、ZEB化の検討に必要なBEI計算では、図面にある必要な数字を手動で入力するため、多くの時間と労力がかかっていました。そこで当社は、BIMの属性情報(部材ごとの品番や寸法など)を活用することで、計算プログラムへの自動入力や自動チェックができる「BIM連携ZEB設計ツール」を開発し、BEI計算の大幅な時間短縮を可能としました。
ちなみに、私が所属する建設DX推進部では、BIMの展開や関連する施策の企画立案・開発・展開を担当しています。2017年からBIM構築を開始し、現在、商業施設や事業施設など建築系設計におけるBIM実施率は100%で、データをつくるレベルからデータを利活用するレベルにシフトしています。施工のBIM実施にもシフトしつつあり、設計がつくったBIMモデルの利活用が徐々にではありますが進みつつあります。
意匠と設備設計の両部門が協力して活用
――「D-ZEB Program」と「BIM連携ZEB設計ツール」は、どの部門で活用していくのでしょうか。
吉川氏 両ツールは意匠設計と設備設計が協力して使用していきます。当社はどの段階でも「Revit」を利用していますが、「Revit」で作成した単線図の属性情報を利用して、「D-ZEB Program」に落とし込んでいます。一連のフローでは「Revit」を軸にし、作業を行っている状態です。
意匠と設備設計担当が活用 / 大和ハウス工業
――それぞれのツールの開発は、別々に話が上がってきたのでしょうか。
本間氏 起案の段階では別々でしたが、一本の軸で進めていく方針で早い時期から話が決まり、総合技術研究所が「D-ZEB Program」、建設DX推進部が「BIM連携ZEB設計ツール」とそれぞれ開発を担当していましたが、両ツールをもとに短時間で最適な提案を可能にするツールへの方向性が固まっていきました。
――開発のポイントと苦労されたことを教えてください。
本間氏 「D-ZEB Program」では、いかに設計初期に導入するツールとするかがポイントでした。とくに、ファーストプレゼンテーション時にZEBを提案できることを念頭に置いておりました。この場合、建物の少ない情報からBEIを算出しなければなりません。一方で入力情報が多いと作業が大変になりますから、そのバランスを配慮した点が苦労しました。少ない情報からBEIの数値を出すと誤差が若干生じますが、その誤差を開発途上で抑制するようにつとめました。我々は誤差5%以内と考えておりましたが、検証しながら目標に到達しました。
いろんな設備や建物の情報を入力しなければ正確な評価はできませんが、項目によって数値に大きな影響を与える内容があります。その点も見定めていくことも肝要です。
吉川氏 しかるべき器にしかるべき情報を入れることがポイントで、実際に活用する設計者にとって作業の効率化が図れなければツールに誘導できません。そこでアドインツールを用意して、効率化を図り利活用できるBIMモデルとしています。
ツール連携の課題 / 大和ハウス工業
規模を問わずあらゆる用途に活用
――「D-ZEB Program」では、基本の情報を入力するだけで作業的には完了するのでしょうか。
本間氏 単線プラン情報は面積などに限られており、当社のZEB仕様もある程度は決まっていますので、情報の入力で作業は完了し、入力の部分も「Revit」から情報を持ってくることができますので、作業時間はかなり短縮化されています。
――各ゼネコンもZEB設計支援ツールを開発していますが、この潮流をどう見ていますか?
本間氏 各ゼネコンとも、当社と同じ課題認識を抱いているものだと捉えています。つまり、早期にZEB提案をし、BIMと連携し業務の効率化を図る方針だということです。
当社は小規模物件も含めて数をこなしていますし、建築系の意匠や設備関係者全員に影響を及ぼす話ですから、いかに設計当初の段階で少ない労力でこなすためのツールであることはとくに重要でした。
「D-ZEB Program」のイメージ / 大和ハウス工業
――ZEB率100%の目標について、進捗はいかがですか?
本間氏 2030年度までに当社が建築する建物のZEB率100%の目標達成については、順調に進捗しています。社内でもZEBに対する評価が高まってきているので、効率的に技術の手法を含め設計に織り込んでいけば、コストをかけずによりZEB率を向上させることができると考えています。
吉川氏 「BIM連携ZEB設計ツール」を扱う社員の理解度が必要なため、その点の教育を強化し、ツールをしっかりと使用してもらうことが重要です。今、説明があった技術的なノウハウの理解も当然必要になりますから、そのノウハウとツールを使う習得をしっかりと行っていきたいです。さらにツールを使った社員からフィードバックし、ツールの改善にも努めていきたいと考えています。
当社では、BIMを扱う人財育成については、中堅や責任者などそれぞれの階層に沿った教育スケジュールを立てています。また、BIMのスキルを定量評価し、スキルを見える化しつつ成長を促し、スキル向上に努めているところです。当社は事業所が多く、その事業所の中でコアの人財を養成するところから始めていますが、コア人財には若手も多いです。
――ZEBを開発する人材も世界的に求められていると思うのではないでしょうか。
本間氏 ZEBの評価システム(エネルギー消費性能計算プログラム)が運用されてから10年も経っていませんので歴史が浅い分野です。今、行っている研究開発を継続して積み上げて、その中で新技術を探っている状態です。
次は新たな手法を模索し、合理的でコストを抑えるための技術を探っていくことになるのではないでしょうか。また、ZEBには難しい用途もありますので、その点に対応できる技術者を養成する点も課題といえます。
「施工管理求人ナビ」では施工管理やBIMオペレーターなど求人を広く扱っています。転職活動もサポートしていますので、気になる方はぜひ一度ご相談ください。
⇒転職アドバイザーに相談してみる