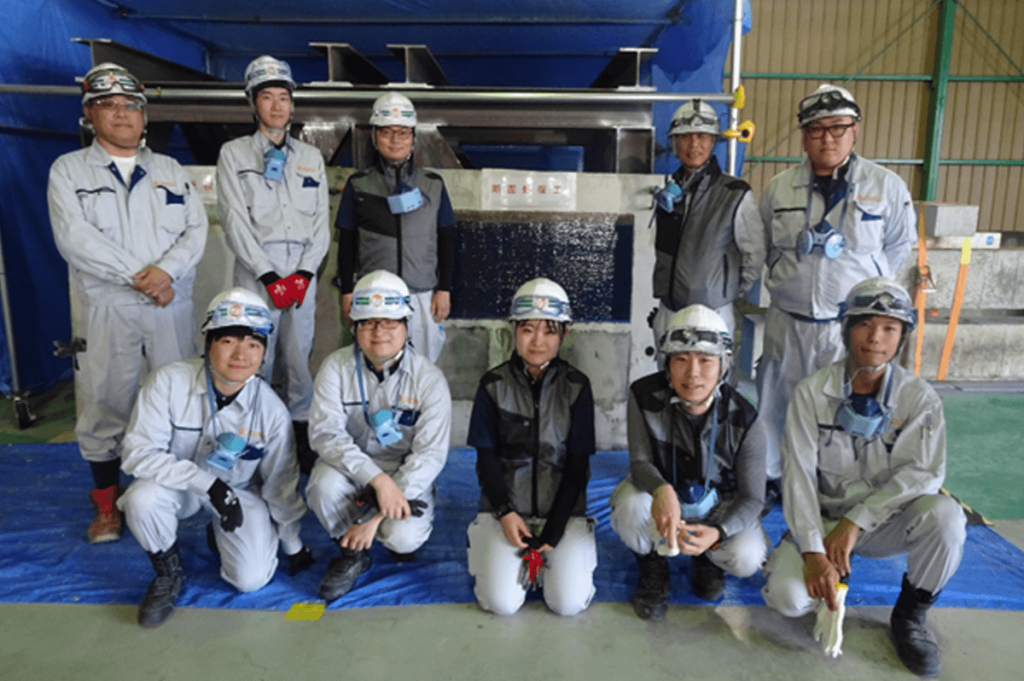※こちらの記事は、2024年8月掲載の記事を再掲載しております。
「どこの業界も人手不足。これまでみたいに、もう人は来ないのが普通。でもインフラの維持管理は、社会にとてもエッセンシャル。だからうちの会社は来てくれた人は責任をもって育てていくんです」と、前回取材時(2023年2月)に話してくれた横浜システック。
その2カ月後から社内にアカデミーを開講、最短3年で1級施工管理技士を取得するカリキュラムを作り、先輩社員が協力し合って、座学や実習そして現場での実務を通して必要なことをすべて教え、本当に未経験者を施工管理技士に育て始めた。
例えば、昨年4月の1期生は、「やってみたけれど、建設業に向いていなかった」と他業界へ旅立った仲間は数人にとどまり、ほぼ全員の11人が2級施工管理技士に合格、引き続き1級資格取得に向けてカリキュラムに取り組む。その後も「未経験者」が来てくれて、全社的な人育て→増収増益→業界平均水準以上の賃上げの好循環が軌道に乗ってきた。離職率は低いままという。
そもそも門戸を経験不問に広げたら、なぜ若者が来てくれる?
しかも辞めない。
建設業が不人気というのはまさか迷信だった?
どうなってる?
次々浮かんでくる疑問に重松会長は「来てくれる若い人たちに聞くと共通点が3つ。仕事を通して社会貢献ができる、キャリアアップができる、会社の雰囲気がいい、ということが横浜システックを選んでくれた決め手だそうです。施工管理という仕事を知っていたとか、施工管理をしたかったというんじゃないんですね。職種で選ぶっていうことではないようです」。新施設のお披露目を兼ねて、実習を見学させてもらったので、ついでにいろいろ聞いた。
最短3年で1級施工管理技士に合格するカリキュラム
6月にオープンした実習施設では、まず座学で仕組みを学んだあと、隣のヤードで実習する。この日はコンクリートの補修や補強技術を学ぶ5日間集中実習の4日目。
――1年半前(昨年2月)に取材させてもらった時、「横浜システックに来てくれた人たちは、経験や年齢を問わず、全員必ず育てます。そういうことを新年度からシステマティックに始めるんですよ」と仰っていましたけれど、この実習施設もその一環ですか?たしか、座学中心のアカデミーは昨年4月からやっていましたよね。
重松さん そうなんです。異業種から来た人たちも、同業から来た人たちも、資格をまだ持っていない人たちが、最短3年で1級施工管理技士を、最短2年で1級施工管理技士補を取得するカリキュラムを組んでいます。この新しい施設もその一環でもあるんです。
未経験の人には基本から教えないと、まずは現場で「自ら学びなさい」のやり方では本人も周囲も安全上危ないですし、成長ややりがいも生まれません。高校・高専・大学の土木工学で学ぶことをまず一気に集中して教えるのがお互いにいいんですね。そして同時に試験対策もやるんです。学び直しの人にも好評ですね、現場を知っている人は、より理解が深まるんです。
そして、6月に横浜と大阪でオープンしたこの技術や工法の実習施設では、座学で仕組みを学んだあと、隣の建物で実際にやってみるんですね。劣化したコンクリート供試体をさまざまな工法で補修や補強をする一連のことを、自身でやってみるんです。材料の準備から、施工、仕上げ、そして片付けまですべてです。施工管理は実際には自身が作業を担うことはないのですが、実際に自身で経験して一連の技術や工法を知っていないと、的確な管理、つまり施工品質を優良に保ちながら、無理・無駄・ムラを省いて効率的に進めていく、そして原価管理の側面から見ても合理的な管理ができないですからね。実際の作業を担ってくれる職人さんと本質的な話ができないんですよ、管理側も自身でやってみたうえで知ってないとね。
そういう意味では、この施設は新入社員に限らず、協力会社さんも含め、誰でも利用できるようにしています。今日の実習も下請けさんからの参加もあります。既存工法の研修に加え、新技術を使う前に試行してみるとかにも使います。こういう施設って結構重要なんですよ。何人かこうして集まって実際にやってみると、それぞれの人が経験知として蓄えてきたり、暗黙知として宿っていたりする知見も、共有できるんですね。こういう場合はこうしたらより良くなるんじゃないか、とかね。私も、なるほどそうか、と勉強になることもありますよ。いろんな現場がありますからね。
使用する工具の仕組みや扱い方も学ぶ。「安全についても必ず身に着けてほしい」。
実際に自身で必ずやってみる。
【PR】なぜ施工管理技士の資格は「転職=給与アップ」に有利なのか?
社員それぞれのキャリア形成をサポート
――試験に合格して資格を取得って、実際にどういう進め方なんですか?国家資格ですし、そんなに容易くはない感じがします。
重松さん 3年くらいスパンの時間軸で、いつまでに何をどのレベルまで習得するとか、それを着実に実行していくための1日の時間割とか、そういったものを作って、みんなで共有して進めている感じです。
まず、2カ月くらい初期教育をします。座学が中心ですね。私が技術系、青柳さんが社会人の基礎教育を担当します。先ほどお話ししたように技術分野は高校や大学の土木系科目で学習することを一気に教えます。社会人の基礎教育では、挨拶から始め目標設定まで、大手企業の新入社員研修でするような内容ですね。青柳さんはもともと小学校の先生だったんですね。大学で4年間教育を学んで、その後4年間実際に教育現場で実務をしていたので、カリキュラムを組むとか、社員の目標設定やキャリアアップの相談などは専門分野でもあるんです。
青柳さん 私も昨年4月に入社した新入社員で、アカデミーの1期生です。採用・教育の専任ではあるんですけれども、みんなと一緒に学んで、資格取得試験にもチャレンジしているんです。最短3年間で1級施工管理技士合格までのスケジューリングをして、私自身も昨年まず2級を受験して合格した体験を通して、理解しにくいところや勘所、ポイントなどをつかんでいますので、カリキュラムであるとかキャリア相談などにフィードバックしています。
横浜システックに入社してくる人たちはみんな私と同じで、就職活動をする前は施工管理という職種も、横浜システックという会社も知らないんです。ではなんで入社を決めたのか、という決め手もほぼみんな一緒で主に3つです。この会社では仕事を通じて社会貢献できるということ、会社の雰囲気がいいこと、キャリアアップできる仕組みがあることなんですね。キャリアアップできる仕組みがある、この部分は採用・教育担当でもあるので、現場の先輩方の協力をいただきながら、取り組んでいます。
昨年は1期生なのでみんな2級の受験でしたが、12人受験して、11人合格しました。未経験者を育成して資格を取得する取り組みも2年目に入っているので、サポートとかケアを工夫していきたいですね。
3年間のスケジュールを全体で立てているのと同時に、個々人のスケジュールと進捗もキャリア形成の一環として作っているんです。2級の第一次試験から合格していくと、どこで1級の施工管理技士になれるか、そのために何をいつまでに準備する必要があるのかスケジュールに出しています。毎週振り返りもやってもらって、こういうふうに勉強していきますっていうのがあったり、単元が終わるごとにプレテストをして、点数が足りないと補習をしたり。
まずはとにかく1級施工管理技士の取得を目指しますが、コンクリート診断士をはじめ、あると有利な資格の取得スケジュールも作っています。なので、社内で事業部の人たちが全員、何かしらの資格に挑戦しているというような状況にはなっています。
品質を大切にしてきたから、雰囲気がいい
――未経験から入社する側から見ると、タイパとコスパに優れた仕組みですね。しかもキャリアコンサルタントのような人材まで配置して、サポート体制も整えています。社員の人生、本気で面倒みるんですね。
重松さん 当然ですよ。採用しているんですから。会社側だって、自助努力に任せるような従前のやり方では、それこそタイパもコスパも悪いです。会社と社員、お互いの利益が一致しているから強いんですよ、組織として。
横浜システックという会社は何で食べている会社かといえば見た通り、インフラの補修・補強分野で施工管理と施工を担う一次下請けの会社です。何で利益を上げている会社かといえば、高い施工品質なんですね。トヨタは何の会社かといえば車の会社ですけれど、なんで稼いでいる会社かっていえばかんばん方式のジャスト・イン・タイムで稼いでいる会社、儲けの源泉は生産プロセスとか言うじゃないですか。
横浜システックは品質で稼いでいる会社なんですね。品質をコア・コンピタンスとして、だから材料の調達から施工まですべて一式で任せてもらえるようなケイパビリティが維持できるんです。これは品質にも、工程にも、原価管理にもとても重要ですね。「現場営業」といって、現場がその会社を物語るという考えから、品質や工期を大事にしていて、それで受注実績を増やしてきた歴史があります。
その品質を大事にしていることを評価されて、過去5年間で22件、記録をはじめた9年前からだと40件の表彰をいただいています。今年は、すでに3件の表彰をいただいていて、その中には25歳の若手もいます。施工管理として3年目で、初めての線路内工事でありながら、安全面への配慮を常に意識し、職人さんに的確に指示を出しているところが評価されました。
さらに、今年の7月に表彰された喜多川部長は、工事関係者との良好な関係を築いたことや対処内容を誠実に対応したことが評価され、お客様から推薦をいただき発注者である国交省に表彰されています。こういった表彰の背景には、現場代理人である施工管理の品質に対する意識の高さが関わってきます。それを個々人に任せっきりにせず、会社全体で意識を高める取り組みをしています。施工検討会や安全パトロールなど様々行っていますので、それをお客様にも評価されるのは何よりの成果ですね。
安全と品質への取り組みが認められ、毎年複数の表彰を受けている。
なんでこのように(1)品質が維持でき、(2)一式受注が維持でき、以下(1)(2)の繰り返しという好循環が持続できたのかといえば、ここが重要なんですが、会社側もきちんと社員のそうした働きを見ていて(3)評価してきたんですね。だから(1)(2)(3)(1)(2)(3)とサイクリックに回ってきたわけです。
一方で、(3)がきちんとしていないと、つまり人を大切にしていないとすぐに逆回転するじゃないですか。会社が社員のことを見ないで、オーナーだけが利益に浴するとか、内部留保を厚くするだけとか、そういうようになると逆回転して、スパイラルに陥るんですよね。疎かになって、品質が落ちたり、事故が起きたり、当然売り上げも落ちますし、利益どころでなくなる、会社の存続すら危うくなるわけです。
横山産業はインフラの補修・補強分野に参入するにあたって、横浜システックをМ&Aをさせてもらったのですが、この好循環はポイントなんですね。1つ懸念があるのが、建設業に入ってくる人が減っているなか、横浜システックも同様で、社員の年齢構成が高齢化していたんです。人がいなければ、好循環が回るより前に、事業が継続できなくなります。人手不足倒産って増えてますでしょ、すでに。そこで、システマティックに教育することで、有資格者を増やして、好循環を今後も継続して回そう、というビジネスモデルなんですよ、М&A後は。
そして、みんな、確実に忙しいんですよ。このシステマティックに人を増やす新しい取り組みを始める前より。だって、未経験者を増やしているわけですし、1人で現場を持てる1級施工管理技士になるまで育成期間が最短3年かかるわけです。加えて、1級施工管理技士補は最短で2年で取れますから、そうなると今まで1現場を担当していた1級施工管理技士は、2現場持つわけですよ、技士補がいると2現場まで持てますからね。すごく忙しいと思います。でも、このビジネスモデルをみんな共有していますし、加えて実際に成果が上がってきて売り上げや利益が増えたので、横山産業がМ&Aしてアカデミーを始めてから最初の決算期になりましたけれど、会社側も業界平均以上の賃上げを横浜システックに実施しましたから、そこで「体制が変わっても会社は引き続ききちんと見てくれている」という安心感と信頼関係が強まりますよね。
今日の実習にも来てくれていますが、下請けさんも一緒です。横浜システックは施工部隊も持っていますが、下請けの専門工事業者さんをお願いすることもあるんですね。品質でつながっている皆さんですので、よく理解してくれていて、横浜システックとしてもそこはよく見ています。
社員、スタッフと会社が目指す方向が一致していることや、ビジネスモデルをみんながよく理解しているから、互いの信頼感も増しますし、安心感にもつながっているんですよね。だから雰囲気もいい。そういう組織は強いんです。
けど、施工管理だしな・・・。逡巡の先の決め手は
――今日は実習で皆さま集まっていますので、お忙しいと思いますが、短時間で小座談会とか開いていただけますか?
重松さん 手短にでしたら大丈夫ですよ。隙間時間になりますけれど。では、入社3カ月経った多田さん、2週間経った大嶋さん、塩野さんにお願いしましょうか。あ、2年目の栃木さん(就業3年目)の姿も見えますね。先生役をしてもらっている池戸さんもお願いできますか?時間もないので、さっそく多田さんどうですか?
多田さん(入社3カ月) 横浜システックとは面接会で出会いました。すぐに紹介してくるエージェントさんも多いんですけれど、面接会でいろんな企業から話を聞けたので良かったです。
重松さん それで、対面で横浜システックとも面談をして、どうして入社しようと思ったの?
多田さん その時に説明してくれたのは、青柳さんと筒井さんだったと思うんですけど。まず施工管理っていう職種に関して話を聞いて、楽しそうだなって思って。それで1番の決め手は青柳さんかな。面接会してきたなかで、楽しそうに話してくれるし、こんな楽しそうに仕事のことを話せる人がいるんだったら、いい会社なのかなと思って。
大嶋さん(入社2週間) 僕はちょっと失礼ながら、エージェントさんで研修を受けるまで施工管理っていう仕事自体を知らなかったんです。エージェントさんの説明のなかで、最初からマネジメント系を学べるっていうことが、横浜システックが説明のなかでメインで挙げられていたんですけれど、そういった業種内容に興味を持ったっていうのもあります。面接会以前のアンケートの段階で、1番興味ある会社どこですか?みたいなので横浜システックを挙げていたんですけれど、面接会の時に青柳さんと初めて顔合わせをしたときに、1番楽しみにしてましたっていうふうに言ったら、こちらも把握しててちょっと楽しみにしてましたみたいなふうに言ってくださって。他の施工管理の会社の方とはちょっと雰囲気が違ったなっていう点で、横浜システックを1番に選んだというのがあります。
塩野さん(入社2週間) 自分は逆にいろんな業種があるなかで、施工管理がきついって聞いていたので、1番やりたくなかったんですけれど・・・。面接会でもちょっと嫌だなとは思いながら、バツをつけるのは失礼だと思って全部まるをつけて。で、マッチングしたなかに横浜システックがあって。自分も面接の時に青柳さんがすごく優しい感じで、なんかこの会社いいなとは思ったんです。けど、施工管理だしなと思い・・・。部長が自分の面接の時にちょっとだけ青柳さんの横に出てくれて、なんか上司もすごくいい人に感じて、いいな、けど施工管理だしな・・・みたいに思って。でも、実際、自分が1番大切なところは会社の雰囲気を重視していて、お話させていただくうちに、会社の雰囲気、青柳さんと筒井本部長のやり取りを見ていて、正直きつくても環境よけりゃなんとかなるかなっていう思いがあって。
重松さん もともとみんな大学では土木じゃないもんね。なのに来てくれたのは、職種じゃなくって、職場の雰囲気なんだね。今の若い人たちは、そういう順番なんですね。まぁ、そうかもしれませんよね。大事なことだからね。
それで、入って2週間とか3カ月とか経つと、現場にも行ってる人もいるでしょ。どうでした?ミスマッチ、やっぱりちょっと違うみたいなことはないですか?
多田さん ほとんど説明を受けた通りの施工管理の仕事なんですけれど、私は4カ月いるので現場の流れで穴を掘る作業とかちょっとしたんですけれど、でも、楽しくやれたら、なんともないです。1番最初に行った現場も、初日は本部長も池戸さんも来て、色々教えてもらえたりして、田村さんとも養生の時間中も一緒に勉強したりとか、楽しく現場に出ているので、ミスマッチってことはないです。楽しくできています。
重松さん みんなが楽しくっていうか、居心地のいい場所として、横浜システックに入ってくれて、目標に向かって取り組んでくれてるってことなんだね。少し先輩の栃木さんはどうですか?栃木さんはもともと文系で、まず建設業の派遣社員として入ったわけですね。
栃木さん(入社2年目で就業3年目) そうです。ちょうどコロナ禍真最中で、自分は博物館の学芸員っていう資格があって、そっち方向になりたかったんですけれど、元々募集が1人か2人しかないのに、コロナ禍でもう完全に募集がなくて、どうしようかなと思ってて色々探していくなかで、文系はやっぱり募集が少なくてダメだなと思って、視野を広げてみようってなった時に、エージェントの方に自分の性格とかそういうのに合うのが施工管理じゃないかって言われて。
重松さん 行動分析みたいなのをやったんだね。
栃木さん そうです。エージェント何人かにやってもらって、自分がしっくり来るようにしてみようと思って。で、派遣会社を紹介してもらって、でも雰囲気も良さげなら入ってみようと。元々この横浜システックに入る前に1年ゼネコンでやらせてもらってて、そこでは入った時はやっぱりギャップは結構あって、最初は雰囲気いいなって感じてたんですけれど、やっぱり昔ながらの風習が残ってて、1回で覚えるみたいな感じだったんです。業界自体が人手不足で余裕がないですから、現代的なやり方になかなか変えていけないっていうのもあるのかもしれないですけれど。それで、だんだん雰囲気が悪くなってきて。何回かもう本当に上司が前時代的に言ってくるので、辞めようかなって思った時もあったんですけれど、それでも学ぶことが現場をやっていくなかでやっぱり多かったので、とりあえず1年はその現場で色々経験を吸収して、そこできっちり辞めようと思って、1年は頑張ったんです。
重松さん なるほど。頑張ったね。大変だったね。現場に必要な学びがあるって吸収したんだね。ごめん、ごめん、話の途中で。続いてどうぞ。
栃木さん それでその後、辞めた後にまた探してもらった時に、横浜システックにマッチして。で、筒井さんに面接してもらって。雰囲気が良かったですし、もうこういう会社だからぜひ試しに入ってくれって言われて、試しに入ってみたんです。その後、森さんと出会って、初めて会った時はもうかなり話してくれる人で、すごくいい人だなと思ったんですけれど、改めて今、森さんって人見知りなところがあって、あんまり喋るタイプの人じゃないってことを知って、頑張って雰囲気出して面倒みてくれたんだなと思って、そこでまた会社の好感度が上がって、1年間やっていくなかで、森さんもきっちり細かく教えてくれる人なので、さらに学ぶことが多かったので、ここの会社なら入りたいな、と思って入社したんです。
重松さん なるほどね。地域のゼネコン1年と、横浜システックの派遣1年とで、この間に2級施工管理を取っているんですよね。
栃木さん 元々派遣会社がそういう資格を推奨していて、資格学校と提携していたんですよ。でも正直言っちゃうと忙しくて、全然授業は1回も見てない状態で、ほぼ自分で頑張った感じなんですけど。最初自分で授業料を払って、受かると全額後で振り込まれるんです。確かその派遣会社は資格を持ってるとプラスいくらか手当てがつくんです。
現場にポツンと独り立ち。でもみんな助けてくれる安心感
重松さん 派遣から社員にかわって、言われることもちょっと変わってきて、1人で現場を持つようになってきましたよね。この間は北陸道の現場に1人で行っていました。どうですか。1人でやれるようになって。
栃木さん 自由にやらせてもらえるので、肩の荷はちょっと下りたかなと思います。横浜とかだと森さんとかバックアップしてくれて、常にいる状態なので。自分の勝手な感覚ですけれど、いるなって思っちゃうんです。いつも気にしてくれていると。不安もあったんですけれど、現場をやってくなかでどんどん解消されていって、今までこう学んだこととかやってきたことをカスタマイズしてやったり、わからないことも電話すればすぐ答えてくれる人がいたりするので。場合によっては来てくれますし。
重松さん きちんとやり遂げて良かったね。みんな心配していたんですよ。1人だけどいいんですか、誰がきちんと見てあげているんですか、とね。畑山さんが見てるようですと。ようですではダメです、ちゃんとどれぐらいでどうなっているか聞いてあげてくださいと、言っていたんですね。俺も行こうかと思ったんです。京都まで出張していたから。でも、バタバタして行けなかったんだけれど。
――ちょっとよろしいですか?独り立ちみたいな時期が来ると、ポツンと1人で行かされるってことなんですか?
重松さん 最初の何日間かはやっぱり上司がついて見てくれていて、大丈夫だなと思ったら、離れて1人で現場です。だから栃木さんの場合、独り立ちが去年の春ですね。現場に自分しかいないと。
栃木さん 彦根はそうでした。自分と職人さんだけって感じで。
重松さん 何かあると誰かがすぐ来てくれる体制は作っているんですよ。どの現場も。彦根の場合は、名古屋のバックアップ体制が、しっかりしていたんです。多田さんは3カ月くらい経ちますけれど、研修期間どうでしたか。
多田さん 土木のことは本当に何も知らなかったので、ゼロからのスタートで、社会人経験もなくて、アカデミーで勉強してから現場に出て、こういうことだっていうのが理解できたので、良かったと感じています。先に情報を仕入れられたので、 現場に出て戸惑うことが少なかったです。
重松さん そうですか。前もって集中して教えているので、栃木さんみたいな苦労はなかったんですね。現場で教えていると、断片的に教えることになって、どうしても漏れがでるんですよね。2級土木施工管理技士の試験勉強をしているから、施工管理とは何が必要かっていうのを学びますからね。塩野さんたちは2週間経ってどうですか。
塩野さん そうですね。僕たち3人、もう1人がいるんですけど、まだ現場にも出てない状態で、今までは資格の勉強とか、今週はずっと実習なので、栃木さんとはまた逆で、勉強から入って実際に現場に行くっていう感じになるので、現場を見てない分、何を覚えなきゃいけなくて、何なら資料で確認できるとか、そういったその情報の取捨選択とかも結構難しいというのもあります。でもやっぱり先に学べるっていうのは、現場に出た時に理解がより早く深まると思うので、今の環境はすごくありがたいのかなというふうに思っています。
品質と安全に対して真摯に現場を運営。みんなでいい仕事をしよう
実習風景。先生役の先輩社員がこれまで経験してきた知見を丁寧に教え、実習生が自らやってみる。
重松さん 今日で4日目なんですけれど、実習はどんな感じですか。端的に言うと、研修カリキュラムを組んでいる立場としてちょっと聞いときたいんですけれど。
池戸さん そうですね。必要かと言われたら、自分はとても大事なことだなと思って見ています。作業のやり方とかを学んで知っていないと、現場に出ても職人さんに的確な指示を出すことができないですし。それと、注意を促したこと、注意されたことは覚えておいて、現場に出た時に職人さんたちに伝えられたらいいかなと。
初日に言ったんですけれど、まず新しい材料とか、とにかく1回触って。触ると粘性が高いなとか、粘性がないからハンドリングがいいなとか、いろんなことがわかる。それが触らなくてただ言うだけだと、多分ダメ。設計で、これでやってくれってなれば別だけれど、例えばチョイスはこちら側に任せてもらえる。ただ軽量モルタルと書いてある時だったら、じゃあ使いやすいやつ使おうかとか、そういうふうに自分たちで材料をチョイスしていくってとても重要なことで、職人さんたちも、作業性がよければやりやすいし、綺麗に仕上がるし。そこを何も考えないと、みんな品質とか進捗とか考慮して進めているんだから、クレームも出てくるし。
それと実際、今君たちがやってることで危ないところがわかる。やって、実際これやばいなとか、これ危ないなっていうのを見て感じてもらって、それを今度現場に出た時に職人さんたちに伝えて欲しい。今回の実習っていうのは、もちろんその材料的なもの、施工性のものだとか、安全に対するものも覚えてほしい。
それで、最初にも言ったんだけれど、君たちの仕事っていうのは一つの括りで言っちゃうと施工管理なんだけれど、じゃあそれを細分化したら、施工管理もそうだし、品質管理、工程管理、安全管理、あと社内的に言うとお金の管理、こういったものも全部トータルで施工管理だから、それをやっていくのに、この実習は、僕はとても意義のあるものだと思います。
君たちは今度ね、2年後、3年後経った時にどういうふうに成長しているか。この1週間の実習が、直近で言えば2カ月後ぐらいに、実際に現場に出る。そうなった時に本当に生きてくるから。そこで生かしてもらえれば幸せだし、2、3年後、君たちが1人で現場でバリバリやってね、職人さんたちといろんな話して、ゲラゲラ笑って、人間関係構築して、それで初めてこう、みんなでいい仕事できるから。職人さんに対して絶対高圧的な態度とかとっちゃダメだよ。同じものを作る仲間だからさ。
現場っていろんな会社が入っているじゃない、みんな助け合って、ひとつのいいものつくっているから。それに、信頼関係を築いて関係も構築ちゃんとできれば、限りなく事故が起きる要素は少なくなるし。現場ってみんなお互いよく見ているから、だから大変そうだなと思ったらちょっと手伝ったり、お互いそういう助け合いをしているからね。
あともう1個は、現場を一通りやってみて、始まりから完成まで全部見れて、だんだんそれが月日が経っていくと、物事を作り上げるっていう最初から終わりまで見えてくる。逆にそれも楽しくなるよね。
ただ、僕がパトロール行った時は多分楽しくないと思う。パトロール行った時は、やっぱりそこは言うこと言わなきゃいけないし、その時は知識や安全について足りなかったんだなっていうところで反省してもらって、是正してもらって、同じことは言われないようにしようと、 そういうふうに思ってもらえれば、本当に行った甲斐もあるし、 ということです。
――パトロールってなんですか?
重松さん 安全とか品質のことがちゃんとできているかっていうのを1カ月に1回なり、2週間に1回なりパトロールするんです。社内体制でやっています。元請けさんはもちろんやっていますし、それとは別に、うちみたいな一次下請けでやっている会社もあれば、やっていない会社もあります。
池戸さん もちろん1番大事なのは品質であり、安全です。それを確認するパトロールなので、できていなければ現場を止めます。そして是正するんです。どれだけ品質と安全に対して真摯に現場を運営していくのか、それをちょっと(研修の)最終日には僕がこれまで経験したことを話そうかなと思っています。現場って商品じゃないですか。汚い仕上がりだったり、品質ができてなかったり、安全がおろそかで事故を起こしたっていうのは、もう言語道断な話なのでね。