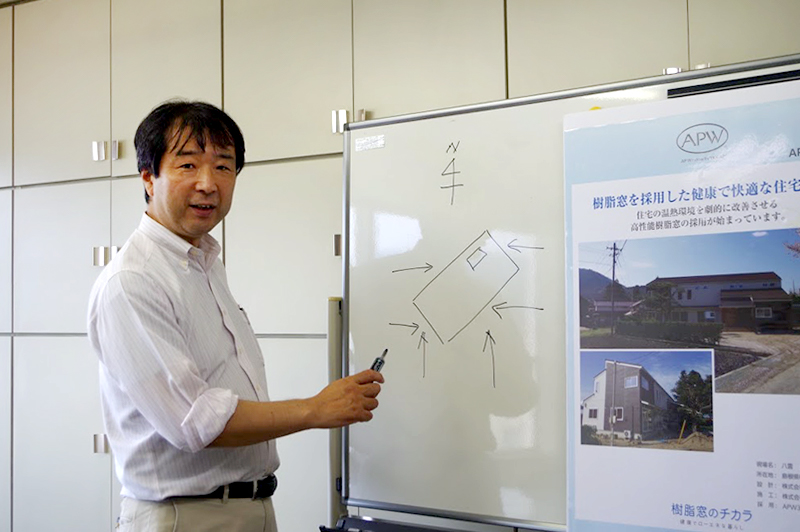「もったいない精神」と戦う島根県の上代工務店
島根県雲南市。人口4万人に満たない小さな街に工務店がある。社長を含めて総勢7名の上代工務店だ。
社長の上代悟史氏は、日本で美徳とされる「もったいない精神」と戦っている。
実はこの日本人らしい「もったいない精神」が仇となって、自宅で命を落とす事例が日本では多発しているという。
「いい家を建てたいと思う気持ちは人一倍強い」。そう話す上代社長が「もったいない精神」と戦う理由に迫った。
3代目になって初代の「家守の精神」に回帰
上代工務店は街の中心部ながら、すぐ横を川が流れる落ち着いた場所にある。車を走らせると、すぐに日本のふるさとの原風景とも言える棚田が広がり、初夏にはホタルが乱舞する。この環境に恵まれた地で上代工務店が誕生したのは昭和38年のこと。
上代悟史代表取締役。大学卒業後、中堅ゼネコンに入社、技術研究所と耐震研究室に在籍。Uターン後、家業を継いだ。
「初代は大工で家守(いえもり)の精神を説いていました。家は建てて終わりではなく、建てた家の暮らしを見守っていく役割があるという考え方です。
高度経済成長期を経て、学校や病院など公共工事がメインの会社となりましたが、3代目の私の代となってから、また、ほぼ100%住宅へと原点回帰してきたところです。会社は私を入れて7名、建築士は2名だけで運営しています」。
初代の家守の精神を改めて見直したとき、百年住み継がれる家づくりをめざす「百年の家プロジェクト」という全国ネットワークに興味が湧いたのは必然だった。
「暖房積極派宣言Let’sつけっぱ!」のススメ
上代社長は2009年から「いずも百年の家プロジェクト」に参加している。
「100年間住み継いでもらうために一番大切なのは、何よりもそこに住む人の生活があるということです。次に家本体、そして我々も家守として事業を続けていかなければなりません。」
家そのものより家に住む人の暮らしを大事にするからこそ、上代社長には繰り返し重要性を訴えていることがある。
上代工務店の外観。現在、社名を「ル・ラク・ホーム」に変更することを計画中。
それが、「暖房積極派宣言Let’sつけっぱ!」である。
「冬場のヒートショック対策として暖房を24時間つけっぱなしにすることを提唱しています。今、冬のお風呂まわりで亡くなってしまう方が年間2万人近くいると言われています。かつての“行ってらっしゃい、気を付けて”という家族の言葉が “おかえりなさい、気を付けて”と言うべき時代になってしまっています。
住む人の命を守るためにある家で命を落とすなんて本末転倒。ですから、私は“Let’sつけっぱ!”を言い続けるのです」。
ところが、ここで立ちはだかるのが「もったいない精神」なのだという。
ヒーローショーを開催して子どもにもわかりやすく
「これは意外と根深い問題だと思いますね」と上代社長は苦々しく話す。
「家を建てた後に施主さんとお話しをすると、“もったいないから暖房を入れていない”という言葉をよく耳にします。日本人が培ってきたもったいない精神は素晴らしいものです。
ですが、これからは“暖房をしたらもったいない”ではなく、“家族の健康が守れなかったらもったいない”にシフトしなければなりません」。
実は北海道では意外にもヒートショックが少なく、目指すべきは北海道の生活なのだという。「北海道はしっかり家全体を暖房していますからね。一方、部分的に温めるコタツをよく使っている地域はヒートショックが多い傾向にあります。山陰もコタツをよく使うので啓発が必要なんです」。
その啓発活動の一つがなんとヒーローショー。悪の総帥「ヒートショッカー」をやっつけるというストーリーで子ども達にもわかりやすく暖房の重要性を伝えている。
いずも百年の家プロジェクトが主催したヒーローショーのチラシより。
お風呂もあくまで家の中にある部屋の一つ
上代社長は空気の流れを取り入れた、高気密高断熱の設計を得意としている。
しっかりと換気をしながらも、暖房効率よく空気を綺麗にするシステムを採用。これにより、24時間暖房をつけっぱなしにしても省エネが実現できる。だが、最近は省エネを前面には出していないようだ。
「以前は省エネ性能を打ち出していましたが、究極の省エネは暖房をつけないことなので、もったいない精神に火が付いてしまいますからね。最近は“天井のないお風呂を建てています”と訴求することも多いです。
私達は今、お風呂場としての空間を仕切らず、他の部屋とつなげる仕様を標準にしています。お風呂も生活空間の一部で、閉ざされた個室である必要はないんだという視点を持ってもらうことが大事だと思っています」。
このような画期的な手法は、上代社長だけで思いつくわけではないそうだ。「百年の家プロジェクトに参加していることで、全国100数社のトライ&エラーの情報が入ってきます。自分一人だったら思いつかなかったこともたくさんあります。進化のスピードも劇的に早くなっていますね」。
月に1回、上代社長が欠かさず執筆・発行している「いずもありがとう新聞」。
工務店社長が考える、いい家の絶対条件とは?
地元の「いずも百年の家プロジェクト」のメンバーは仲間でもあり、ライバルでもある。「2カ月に1回はいずも百年の家プロジェクトの定例会に参加して情報共有しています。講演会の開催やイベント参加も積極的に行っています。年に数回は他県へ研修に出かけています。切磋琢磨できているのでとてもありがたいですね」。
「結局のところ…いい家を建てたいんですよね」と話す上代社長に「いい家」の条件を聞いてみると、
「やはり住む人が健康で、長生きできる家がいい家です。そのために必要なのが暖かいこと、日当たりがよくて明るいこと、そして地震に強いことだと思います。ここ数年、本当に進化のスピードが早いのですが、だからこそ家づくりが完成形になったとは思いません。まだまだもっともっといい家が建てられるのだろうなと感じています」。
この夏から「ル・ラク・ホーム」と名前を変える予定の上代工務店。「ル・ラク」は英語のリラックスに当たるフランス語から。これからも住む人が心からくつろげる家が生まれるに違いない。