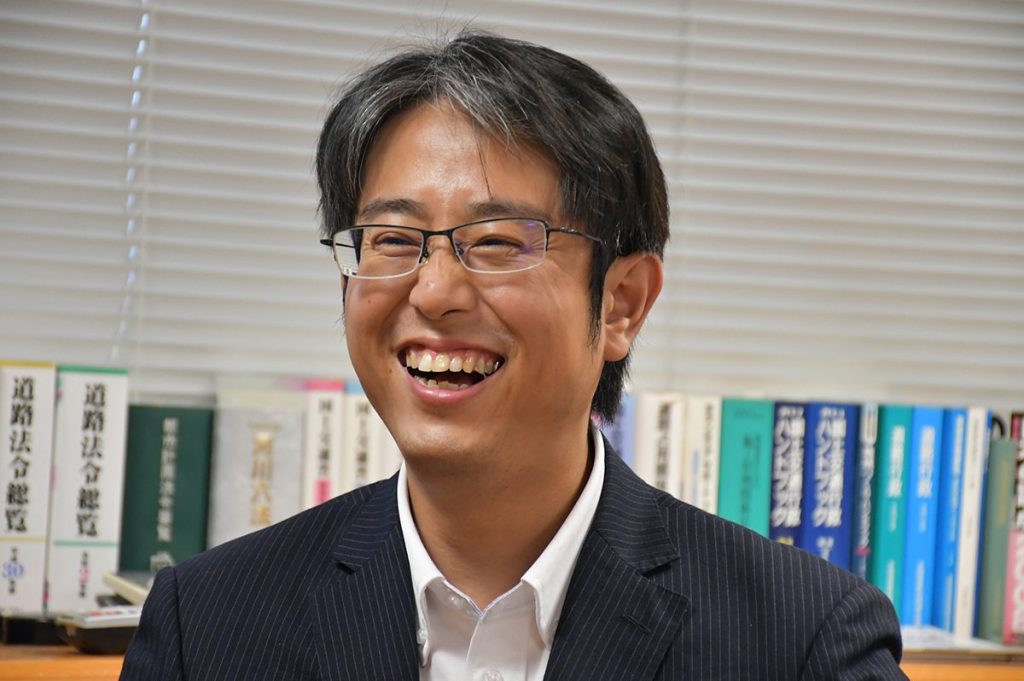【土佐国シリーズ#1】所長・岡本 雅之さん
国土交通省四国地方整備局に土佐国道事務所という出先がある。通称は「土佐国(とさこく)」。主に高知県東部の道路ネットワークを所管しており、現在、高規格道路の「8の字ネットワーク」の整備などを進めている。
いろいろあって、これまで取材を控えてきたが、自分が暮らすまちの道路を司る事務所であることだし、やっぱり一度取材させてもらおうと考えを改めることにした。ということで、土佐国の職員の方々にインタビューし、シリーズとして掲載していく。第1弾は、笑顔がステキな所長の岡本雅之さんだ。
なにもかも曖昧なまま、国交省に入省
――なぜ国交省を選んだのですか?
岡本さん 大学時代は、なんとなく土木を学んでいたのですが、どこに就職しようとかあまり考えたことがありませんでした。本当に漠然と「宇宙の仕事は面白そうだな」とか考えていましたので、地球工学科という学科を選んだら、宇宙に関する分野はほとんどなく、土木メインだったので少し戸惑いました。なので、初めから土木関係の仕事をしようとか、国交省に入ろうとか思っていたわけではなかったです。
国交省を選んだ理由としてなんとなくこれかなと思うのは、私自身、阪神淡路大震災で被災した経験があることです。私は芦屋市出身なのですが、自転車で国道2号を走って祖母の家がある宝塚市まで避難したことがあります。あとは、山手幹線という尼崎市と神戸市を結ぶ都市計画道路があって、私の実家もそのルートにかかっていたということがありました。そういったことから、大学では道路計画などを研究していました。
ですが、一番の後押しは、たまたま研究室の先生が国交省のOBだったからです。「行ってみないか?」とおっしゃられたので、「じゃあ、チャレンジしてみよう」と思って決めました。
現場がないと、「頭でっかちな政策」になりかねない
――これまでどのようなお仕事を?
岡本さん 2006年に入省して以来、ほぼほぼ道路の仕事ですね。最初の配属先で、中国地方整備局の広島港湾・空港整備事務所というところで、港湾の仕事を1年間だけやりました。2017年から陸前高田市に副市長として3年間出向したときを除けば、ずっと道路に関わってきました。
――副市長ですか。
岡本さん 副市長は私一人だったので、経済、農業、福祉など市政全般を担当しました。「道路から離れた」というよりは、「国交省から離れた」という感じでした(笑)。
――立場が変わって、気づいたこととかありますか?
岡本さん 市議会に出席したとき、土木関係の質問があまり出なかったことが印象に残っています。津波であれだけの被害を受け、復旧復興に向け様々なインフラ整備を進めているのにもかかわらず、「福祉をどうするのか?」といった質問ばかりだったのです。私は国交省の人間なので、「土木が世の中の中心」みたいに思っていましたが、国土交通省の外に出てみると、決してそんなことはないということを思い知らされました。
例えば、農林水産業の活性化について質問があった際には、最終的に「他の地域からいかに人を呼び込んでくるか」という議論になるのですが、私としては「これはまさに道路ネットワークが関わる問題だろう」と思うわけです。それで、ここぞとばかりに、三陸道の効果の話なんかをして道路のPRをしました(笑)。
――あとは道路ばかり?
岡本さん そうですね。現場における道路の設計をしたり、ITSを研究したり、交通安全施策や、東日本大震災の復興交付金の制度に携わったりもしてきました。道の駅の活性化とかフワッとしたこともやりました。山陰道の整備促進なんかもやりましたね。前職は、本省で高速道路のスマートICとかを担当していました。
――国土交通省のやりがい、魅力は?
岡本さん やはり「現場がある」ことですね。「政策」と「現場」の間を行き来できるのが魅力だと思っています。現場がある中央省庁はそうはありません。政策は考えるけども、現場では自分たちが直接携わらないものがほとんどです。自分たちの現場がないと、現場の声を吸い上げるのが難しく、「頭でっかちな政策」になりかねません。
ミッションは「ミッシングリンクの解消」と「御用聞き」
四国8の字ネットワークの事業概要(土佐国HP資料より)
――土佐国所長としてのミッションは?
岡本さん 高規格道路の整備ですね。四国には「8の字ネットワーク」という高規格道路の構想があるのですが、未だにミッシングリンクが残されています。これを1日でも早く解消することが私のミッションだと考えています。道路がつながっていないと、地域間競争に遅れをとってしまいますし、地域の活性化にも支障をきたしてしまいます。
あとは、「御用聞き」ですね。高知県内の市町村には、財政とか、地域の活性化とか、いろいろな悩みがあると思います。一所長としてできることは限られていますが、副市長の経験を活かし、市町村に寄り添りながら、いろいろ相談に乗っていきたいと考えています。
――市町村からどういう意見が出ていますか?
岡本さん やはり、「8の字ネットワークをつなげてくれ」という声が多いですね。
DXで「気合と根性」以外の魅力づくりを
――地域の建設会社について、どうお考えですか?
岡本さん 地域の建設業者さんは、われわれのパートナーだと考えています。コンプライアンスは守りつつ、県の建設業協会さんなどと連携しながら、コンスタントにしっかり仕事を出していきたいと思っています。こちらからも、働き方改革などいろいろお願いしているところです。週休2日の導入は、もはや当然のことではありますが、ちゃんと取り組んでいる業者さんについては、しっかり評価させていただくことにしています。
DXの導入もお願いしていることの一つです。「気合と根性」で現場仕事をするのもカッコ良いことだとは思いますが、デジタル化によって、「気合と根性」以外の魅力づくりも促していきたいと思っています。DXの導入は、地域の建設業、ひいては地域の産業を守ることにもつながっていくと考えているところです。
現在、高知県の建設業協会さんが主体となって、土木を広報するTV番組を制作することになっており、土佐国としても協力する話になっています。
息子と一緒に暮らせなくなるのは、ちょっと残念
――転勤は苦にならないですか?
岡本さん そうですね。旅行が好きなもので、半分旅行気分で楽しんでいます(笑)。転勤によって、いろいろな地域のいろいろな風土を知ることができるというのは、良いなと思っています。引っ越し作業はめんどくさいですけど(笑)。
土佐国勤務に際し、家族も高知に来ています。ただ、今4才の息子がいるのですが、これから息子が成長すると、いずれは単身赴任ということになりそうなので、そこはちょっと残念ですけど。