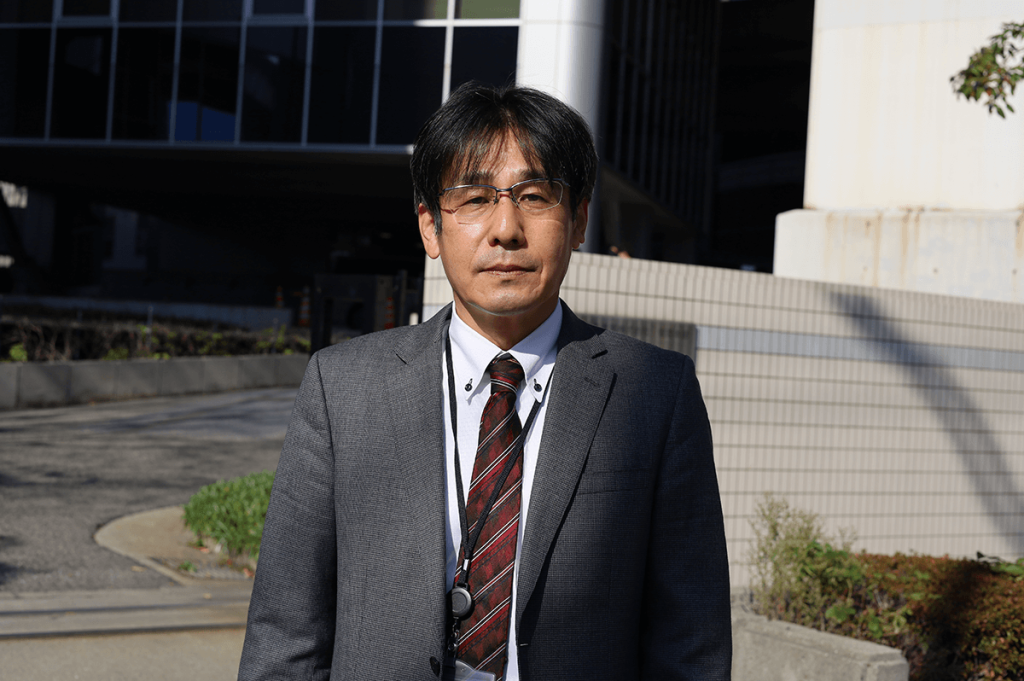大阪保全部長に聞く。仕事の魅力、人材育成で大切なこと
阪神高速では現在、「阪神高速リニューアルプロジェクト」と銘打ち、大規模更新事業(構造物の全体的な取り替えなどによる機能・性能の引き上げ)、大規模修繕(構造物を全体的に補修・補強することによる機能・性能の引き上げ)を実施している。以前記事にした喜連瓜破高架橋架替え工事は、大規模更新事業の一つだ。
このリニューアルプロジェクトの大阪管内の事業を司る大阪保全部長の三嶋大悟さんにお話を伺う機会を得た。これまでのお仕事を振り返りつつ、阪神高速という会社の魅力、やりがいなどについて、語ってもらった。
息の長いインフラに携わる仕事がええんちゃうか
――土木の道を志したきっかけはどのようなものでしたか?
三嶋さん もともとは、クルマ関係の仕事に就きたいと思っていました。子どものころ、スーパーカーブームというものがありました。裏六甲に住んでいたので、近くにあったゴルフ場の駐車場に停まっているフェラーリなどを見に行ったりしていました(笑)。
大学に進学するとき、将来自動車メーカーへの就職は念頭にありましたが、父親から「息の長いインフラに携わる仕事がええんとちゃうか」というアドバイスを受けました。それほど自動車メーカーにこだわりがあったわけではなかったので、「ほんなら土木に行こか」という軽い気持ちで、結果的に、土木系の学科に進みました。
――大学では、土木のなにを学んだのですか?
三嶋さん 研究室は土質でした。土質に興味があったと言うより、先生の人柄にひかれて選びました。
規模の大きな土木工事をやりたい
――就活はどんな感じでしたか?
三嶋さん 大学は関東だったのですが、小さいころから親族から「地元で働いてほしい」と言われていたので、地元関西での就職というアタマがありました。もともと地元の自治体に就職しようと思っていたのですが、研究室の先生から「阪神高速もあるぞ」と言われたので、採用試験を受けたという感じです。1993年入社なので、当時は公団でした。
――阪神高速でなにをやりたいというのはありましたか?
三嶋さん 自治体に比べて、大きい工事ができることが魅力でした。当時は実家の近くで阪神高速の北神戸線がまだ建設中だったので、「規模の大きな土木工事をやりたい」と思っていました。当時の阪神高速は、湾岸線はまだ全線開通していませんでしたし、淀川左岸線や神戸山手線もできていませんでした。大きな工事がたくさん控えていたんです。
希望が叶い、北神戸線の土木工事に携わる
――阪神高速ではどのような仕事をしてきましたか?
三嶋さん 最初に配属されたのは、北神戸線建設を担当する神戸建設部北神戸工事事務所でした。盛土や切土といった土工事や橋梁の基礎工事などの現場監督をやりました。たまたまでしょうが、希望が叶ったカタチです。深礎基礎の岩盤確認などもやりましたが、昇降梯子で地上から30~40m以深まで下りていくなど、今ではなかなかできない経験ができました。ここは2年間在職しました。
その次は大阪管理部保全第二課に異動となり、保全工事の積算業務を担当しました。当時は、阪神淡路大地震の起こった年だったので、橋脚や支承などの耐震補強工事の発注業務もやりました。
――震災復旧に携わりましたか?
三嶋さん 震災復旧には直接携わっていませんが、地震発生時は北神戸工事事務所にいましたので、神戸管理部の応援で、先輩に同行して構造物の点検などをやりました。地震で影響を受けた高速本線を黄パトで走ったりして、けっこう怖い思いをした記憶があります。
神戸線を通行止めにして、フレッシュアップ工事を敢行
三嶋さん 保全第二課の後は、部内異動で当時の大阪第二維持事務所という大阪管内の南側の路線を維持管理する事務所に行きました。ここで、フレッシュアップ工事(在職時は堺線で実施)の現場監督を初めて担当し、諸先輩方からフレッシュアップ工事のイロハを教えていただきました。フレッシュアップ工事(現在のリニューアル工事)とは、1路線を数日間全線通行止めにして、ジョイントや舗装の補修を大々的に行う工事です。
その後は、大阪建設局工事審査課に行き、淀川左岸線建設工事などの積算業務をやりました。あと、当時は阪神淡路大震災後の耐震補強工事を全路線で行っていたため、建設部門においても、耐震補強工事を受け持っており、その積算・審査もやっていました。ここは1年だけでした。
また大阪管理部に戻って、管制管理課というところで、交通管制システムの更新設計や通行止めによるフレッシュアップ工事の交通影響予測業務などを担当しました。ここも1年でした。次は本社勤務となり、保全施設部保全計画室というところで、保全工事の積算基準の改訂や保全工事の積算審査をやりました。ここも1年だけでした。
次に、新任係長として湾岸管理部の調査設計課というところに行って、大阪管内の湾岸線の構造物点検、補修・耐震補強の設計などを担当しました。当時、鋼製橋脚隅角部の亀裂が問題になっていて、そのための調査や検討に関する仕事なんかもやりました。このとき、設計に関する実務に初めて触れました。
またまた大阪管理部に戻って、保全第二課の係長として、ふたたび保全工事の積算業務を担当しました。1年半ほどいた後、ちょうど民営化した時期に、神戸管理部の保全管理課に異動しました。予算管理、工事の発注計画、各種調整ごとといったことをやりました。
当時、神戸線は、交通量が多く、ゴッツい渋滞するので、通行止めによるフレッシュアップ工事を行っていませんでした。ただ、私が配属されたときは、震災復旧から10年ほどが経過し、ジョイントや舗装がかなり劣化し始めていたこともあり、大阪で実施している通行止めによるフレッシュアップ工事の検討を前任から引き継ぎました。そこで、以前とはネットワークが充実していることもあり、関係機関と調整を重ね、通行止めによるフレッシュアップ工事を実施しました。神戸線の通行止めは27年ぶりのことでした。ここは4年いました。
【PR】転職に成功する施工管理と失敗する施工管理の「わずかな差」
保全畑が長いが、自分が向いているかはよく分からない(笑)
三嶋さん その後、久しぶりに大阪建設部に戻って、淀川左岸線建設事務所で現場監督を6年やりました。
――けっこう長くいたんですね。
三嶋さん それまで担当として供用開始というものを経験したことがなかったので、「供用開始までここにいたい」と毎年希望を出して、念願が叶い供用開始に携わることができました。長く在職していると欲が出て事業完了までもと思っていましたが、その1年前に次の職場に異動となり、事業完了を最後まで見届けることはできませんでした。
次の職場は、大阪管理局保全部の保全管理課で、このとき管理職になりました。ここでは、地元対応や関連事業として大阪市から受託した咲洲・夢咲トンネルを管理する仕事もやっていました。ここは2年間でした。
その次は、保全管理課長としてまた神戸管理部に戻りました。神戸線のリニューアル工事や通行料金が対距離制になったので、本線料金所を撤去して、新たにPAを設置するといった仕事も担当しました。また、大阪北部地震や台風21号など災害対応にも追われたときでした。
本社の保全交通部保全企画課長として異動しました。国土交通省との調整や保全事業のとりまとめなどを担当しました。ここも2年いました。
その次が、前職になりますが、大阪建設部の担当部長として、淀川左岸線延伸部を担当しました。延伸部区間の工事は、国土交通省との合併施行ですが、現場着手に向けた協議・調整などに取り組んでいました。ここは1年だけでした。
――保全畑が長いですね。
三嶋さん 今年で入社30年目ですが、結果的に保全部門が長いです。保全にかかる部署はほぼ経験させてもらいました。自分が保全に向いているかどうかはよく分かりませんが(笑)。
土木と設備両方押さえておかないとダメ
――部長という立場になると、保全という仕事の見方も変わりますか?
三嶋さん 部長の立場というか、保全の仕事は、365日24時間、お客様が安全・安心・快適にご利用いただけるよう構造物や設備の管理を行っていますので、日々緊張感をもって業務に携わっています。保全としては、土木と設備の両面があるのですが、どちらかと言うと、これまでは土木中心で物事を見てきたところがあります。設備においても、お客様のご利用に直接影響を与える不具合などが起こりますので、職種が全然違い、知識も少ない設備のことについても、これまで以上にしっかり押さえておかなければならないと考えるようになりました。
――仕事量的にはどうですか?
三嶋さん 多いですね。現在リニューアル事業を精力的に取り組んでいます。喜連瓜破、阿波座、湊町では、規模の大きな更新・修繕工事が動いていますし、老朽化したPC桁などの橋梁の修繕、また、耐震工事など、数多くの工事を行っています。昔と比べ、工事数、工事規模ともに膨れ上がっています。現場の体制をもっと拡充できればと思っているところです。
――メンテナンス工事は、新設工事とは違った難しさがあると聞きます。
三嶋さん そうですね。住宅が近接し、交通量が多い供用下で、現場が狭い場所で施工することが多いのですが、その条件下で地元の皆様にご理解をいただき、安全に留意し、品質の良いものに仕上げるよう工事を進めていくことは、関係機関との調整なども含め、都市高速ならではのシンドいところだと思っています。
失敗しても良いから、若手に自分の思いを持って仕事をさせる
――思い出に残っている仕事はなんですか?
三嶋さん さきほども触れましたが、民営化時に神戸管理部に在職していたときに、27年ぶりに神戸線で通行止めによるフレッシュアップ工事を行ったことです。交通量が多く、迂回路もないことから、「通行止めは絶対にダメ」と言われていた神戸線で通行止めによるフレッシュアップ工事を行うために、関係機関との度重なる調整においていろいろな苦労もありましたが、こちらが真剣に説明すると、相手も真摯に聞いてくれるもので、最終的にOKをいただきました。そのときは、やはり大きな喜びがありましたね。みんなでやったという達成感もありました。
――人材育成についてどうお考えですか?
三嶋さん 私は、阪神高速という会社で働いていく上では、専門性も当然必要ですが、いろいろな知識やスキルを広く浅く習得することが大事だと考えています。それらを早く身につけるためには、フィールドは豊富にありますので、経験豊富な社員が若手社員に対しOJT教育をしっかりと行うことが重要ではないかと考えているところです。
その際に大事なのが、できる限り、若手自身が自分で考えて仕事ができるように上司が後押ししてあげることかなと。大阪保全部では現在、「失敗しても良いから、若手に自分の思いを持って仕事させる」という環境を作ってあげて業務に取り組んでもらうようにしています。
メール「だけ」のやりとりはあまり好きじゃない
若手社員とコミュニケーションをとる三嶋さん(阪神高速写真提供)
三嶋さん 現在は、コロナ禍の影響もあり、社員同士のコミュニケーションがとりづらい状況があります。パソコンなどを介してコミュニケーションするのも、今の時代やむ得ないとは思いますが、可能な限り、「対面」でやりとりする機会を増やす必要があると考えています。
以前に比べ、社員間のメールでのやりとりが非常に増えています。とくに、メールだけで仕事を終わらせてしまっているようなところが見受けられますが、お互いに思いが伝わり、本当に理解した上で物事が進んでいるのか、疑問に思うこともあります。私自身、自分の思いを文章で表現することが苦手なこともあり、メール「だけ」のやりとりはあまり好きではありません。「機械的で、人間味がない」という感じがしてならないからです。
たとえば、メールで用件を一通り伝えた後に、電話でもいいのでこちらの思いを直接伝え、「頼むで」と一声掛けるとか、意思疎通ができる、思いやりのある仕事の進め方をしてほしいと思っています。仕事には、タテのつながりだけでなく、ヨコのつながりもあります。タテヨコのつながりをおろそかにしては、仕事をうまく進めることはできません。
私は、若い社員に「自分の職種以外の社員とコミュニケーションを大事に!」とよく言っています。同じ職種の社員同士は、自然にコミュニケーションがとれる機会が多いので、そこは別に良いんです。大切なのは、当たり前のことですが、土木系、施設系、事務系といった他職種の社員といかにコミュニケーションをとるか、人を知るかが、業務を円滑に進める上では重要だと考えています。
ただ、今のコロナ禍の状況では、「人を知る」大きな機会である「アフターファイブでのコミュニケーション」そのものが減っていますので、今の若い社員は「気の毒だな」と思うこともあります。
大きなプロジェクトに関われるのが、阪神高速の魅力
――阪神高速の仕事の魅力はなんですか?
三嶋さん さきほども触れましたが、大きなプロジェクトに関われることだと思います。大阪湾岸西伸部や淀川左岸線延伸部は大きな建設部門のプロジェクトですし、喜連瓜破の高架橋架け替えなど、リニューアル事業は大きな保全部門のプロジェクトです。
喜連瓜破の橋梁架け替え工事など、100年先も安全・安心・快適に高速道路をご利用いただくためのこのリニューアルプロジェクトは、建設工事に勝るとも劣らない重みのある工事だと思っています。自治体などでは普通経験できない、魅力のあるおっきな仕事ができるのが、やはり阪神高速の魅力だと思っています。