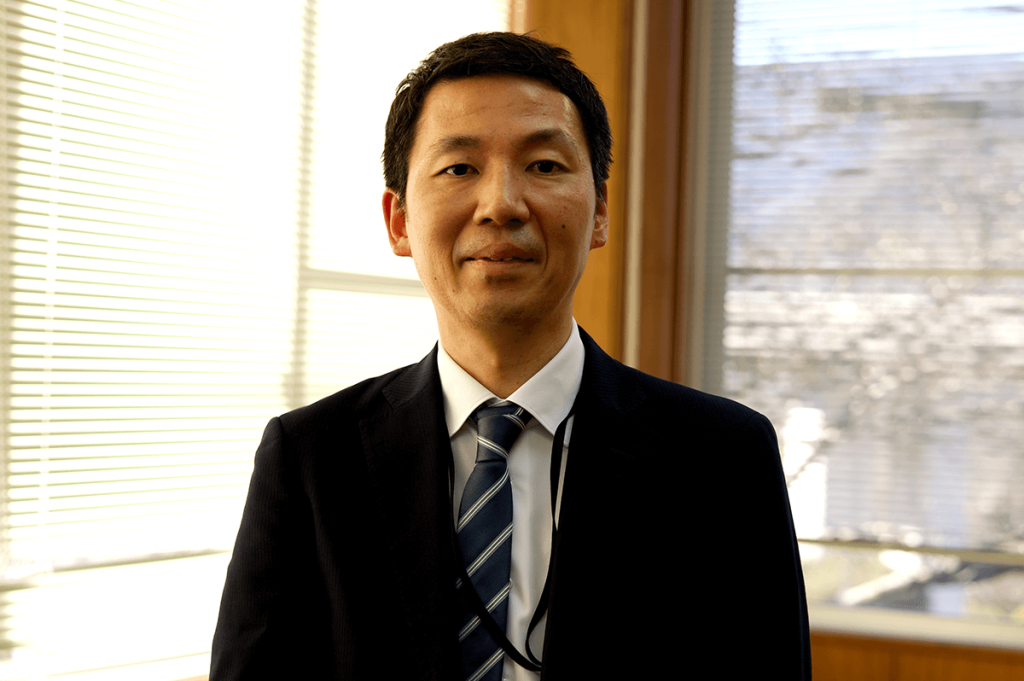「砂防職」の魅力、やりがいとは
徳島県西部の山奥、吉野川沿いの高台に四国山地砂防事務所という事務所がある。その名の通り、四国の山々を流れる吉野川流域や重信川流域などの砂防事業(砂防堰堤、地すべり対策など)を手がける事務所だ。その事務所長を務める野村康裕さんにお話を伺う機会を得た。
野村さんは、いわゆる砂防職として国交省に入省した。国交省砂防職職員の記事は、以前にも出したことがあるのだが、自治体に出向中だったこともあり、砂防職という仕事について、がっつり聞けなかったのがうらみとして残っていた。
野村さんにとって、砂防職の魅力、やりがいはなんなのか。これまでのお仕事ぶりなどを振り返ってもらいつつ、お話を聞いてきた。
※取材時期は2023年12月下旬
いつの間にか砂防の研究室に入ってしまった(笑)
――国土交通省に入省した理由はなんでしたか?
野村さん 私は兵庫県の宝塚出身なのですが、高校生のときに阪神・淡路大震災に遭いました。そこで防災に関心を抱いたということが言えると思います。大学は最初農学部に進んだのですが、その後いろいろ考えるところがあって、砂防の研究室に入り、防災関係の研究をしました。この研究室の先生が国土交通省の研究所のOBだったこともあって、結果的に、砂防職として国土交通省に入りました。
――砂防の仕事をやりたいという思いがあったのですか?
野村さん そうですね。砂防の仕事をやりたくて国交省の砂防職を選びました。ただ、もともと砂防の研究室に進んだのには明確な理由はありませんでした。
今振り返ってみると、阪神・淡路大震災のときに、実家の近くで大規模な地すべりが起きて、30数名の方々が亡くなって、かなりショックを受けたということがありました。もともと「環境や森林を学びたい」と思っていたので、防災は一旦置いておいて、大学は農学部に進んだのですが、農学を学んでいるうちに、いつの間にか砂防の研究室に入ってしまったという感じでした(笑)。
――研究室の先生にもススめられて国土交通省に入った感じですか?
野村さん そうですね。国土交通省に入った先輩も多かったですし。あとは、三宅島が火山噴火をしたとき、卒論の研究として、土石流の調査のために先生について現地に入ったのですが、災害現場などで活躍する先生の姿を見て、純粋に「カッコ良いな」と思ったというのもありました。人の生活や命を守るという仕事に対する憧れがあったということです。
新潟県中越沖地震の現地調査で3ヶ月滞在
――最初の配属先はどちらでしたか?
野村さん 高知河川国道事務所でした。調査課に所属し、仁淀川や物部川の河川整備計画の検討などの業務に携わりました。2年目は徳島河川国道事務所の交通対策課に行きました。砂防職であっても、最初に河川や道路に行くのは、よくあるパターンです。
3年目は土木研究所のほうで地すべりの研究をやりました。このとき、新潟県中越沖地震が発生したので、現地調査のため、現地に3ヶ月ほど滞在しました。新潟県中越沖地震の災害復旧は、当時話題になっていました。地震に伴い、山古志村という場所で大規模な地すべりが多数起きて、村が壊滅的な状況になりました。まだ3年目だったので、上司の随行員という感じでしたが、貴重な経験でした。
研究所には1年半ほどいて、そのあと本省の砂防部保全課に直轄砂防係長として戻りました。全国の直轄砂防事業を所管する係です。
――直轄砂防の予算関係ということですか?
野村さん そうです。予算のほか、前年に発生した新潟県中越沖地震の災害復旧なども担当していました。このときも被災現場に何回も行きました。
――本省の係長として現場に入ったのですか?
野村さん そうです。ふつうはなかなか現場に行く時間がないと思います。ただ、「現場を見なきゃいけない」という思いがあったので行きました。あと、週末の休みを利用して、関東、北陸などの直轄砂防の現場にも行っていました。
――ープライベートでも現場に足を運んでいたんですね。
野村さん ええ、山登りは好きなので、趣味を兼ねて行っていました。
⇒【施工管理求人ナビ】に相談してみる
ネパールで山岳道路建設を支援
ネパールのシンズリ道路の建設現場を確認する野村さん(先頭左、本人提供)
――その次の職場はどちらですか?
野村さん 外務省に出向して、在ネパール大使館に書記官として3年間ほど駐在しました。インフラ担当ということで、ネパールとインドを結ぶ全長160kmほどの山岳道路建設の支援がミッションでした。現地政府との調印の段取りや事業管理といった仕事をしていました。主なカウンターパートは、ネパールの財務省でした。
――ネパールはどうでしたか?
野村さん カルチャーショックが大きかったですね(笑)。首都のカトマンズに住んでいたのですが、電気や水道といったライフラインがほぼありませんでした。道路はボコボコですし、下水道はそもそもありません。電気は1日18時間停電していましたし、水道も2、3日間のうち出るのは30分だけという状態でした。
――水道に関しては、出たところで、飲めるのかという気がしますが。
野村さん 飲めないですね(笑)。ミネラルウォーターを買っていました。
夏休み返上で広島土砂災害の現場に入る
平成24年九州北部豪雨の現場調査をする野村さん(本人提供)
――そのあとはどちらに?
野村さん 国土技術政策総合研究所の砂防研究室に行き、研究官をしました。この間、けっこう土砂災害が多くて、平成24年の九州北部豪雨(熊本阿蘇)や決壊したインドネシア天然ダムなどの現場に緊急援助隊の一員として派遣され、1週間調査などに従事しました。
インドネシアのアンボン島天然ダムを災害調査する野村さん(たぶん左、本人提供)
野村さん そのあとは、また本省に戻って、砂防計画課課長補佐として、土砂災害防止法の改正などに携わりました。砂防部には保全課と砂防計画課の2課があるのですが、保全課は砂防関係事業、砂防計画課は施策や法律を所管しています。砂防職の人間は、2つの課を両方経験するのが一つのパターンになっています。
このとき、平成26年の広島土砂災害が起きました。発災したのが、ちょうど私が夏休みを取るタイミングでしたが、「出勤しろ」と言われて、職場に行ったら、「現地に行けるか」と言われて、夏休みを返上して、調査団の一員として、広島の被災現場に行くことになりました。発災したのが前日の夜中から早朝でしたが、翌日の昼には現地に向かうヘリに乗っていました。この災害を受けて、土砂災害防止法を改正することになりました。
住民の多くはそこが危険な場所だと知らなかった
――改正のポイントはなんでしたか?
野村さん 土砂災害防止法は、イエローゾーンやレッドゾーンとして区域指定し、土砂災害のリスクがある場所への住宅開発などを規制したり、ハザードマップをつくり警戒避難体制を整備するための法律で、それぞれの都道府県が調査して、指定することになっています。
広島土砂災害によって多くの被害が出た場所は、山際に新たに造成された住宅地で、住民の多くはそこが危ない場所だとの認識が十分ではありませんでした。広島県のハザードマップを見ると、おおむね危険なエリアに入っていましたが、住民からの反対などもあって、区域指定できていないエリアがありました。そういう経緯もあって、住民への周知が不十分なまま、被害が出てしまったわけです。
改正のポイントとしては、都道府県が調査結果をまとめて、ここが危ないというエリアの指定案が出来上がった段階で、その内容の公表を義務付けることにした点です。あとは、気象庁と都道府県が大雨のときに土砂災害警戒情報というものを出していますが、改正前は任意の情報であり、明確に法律で位置付けられたものではありませんでした。それを改正によって、避難指示につながる情報として、一般に周知しなければならないと位置付けました。
――自分が携わった法律改正をどう評価していますか?
野村さん 本来は、日本が高度成長する前の時点で、規制されればより良かったのかもしれませんが、全国津々浦々に適用される法律改正によって、土砂災害の防止という意味では、かなり前進したと思っています。
線状降水帯の研究がきっかけで、気象予報士の資格を取る
――次はどちらに?
野村さん 内閣府に出向して、参事官補佐として火山防災を担当しました。ところが、着任早々、熊本地震が発生しまして、災害対応のオペレーション室に入れられました。何週間もなかなか家に帰れない状態で、カンヅメになって、被災地に支援物資を送るなどの対応に追われました。
そのあとは、また国土技術政策総合研究所の土砂災害研究室に行きました。このときは、主任研究官として、西日本豪雨の被災地に行ったり、北海道胆振東部地震の被災地の調査を行いました。あとは、線状降水帯をどう検知するかという研究にも携わりました。
――線状降水帯の検知ですか?
野村さん 平成26年広島土砂災害のとき、線状降水帯の発生によって、局所的に豪雨に見舞われるという現象が起き世間に注目されました。線状降水帯の発生メカニズムについては、当時は、気象庁でもそれほど研究が進んでいなかったと記憶していますが、土砂災害につながる現象なので、土砂災害研究室でも研究しようということで、線状降水帯の発生を検知できるシステムをつくっていました。その研究を私が引き継いでやっていました。そのシステムは、現在気象庁が発表に使っているシステムのもとになっています。この研究がきっかけで、気象予報士の資格を取りました。
――気象予報士ですか?
野村さん ええ。
――なぜ気象予報士を取ろうと思ったのですか?
野村さん 研究を一緒にやっている委託業者の方々がみな、気象予報士を持っていたんです。私だけ持っていない状態で、いろいろ議論していたので、「ちょっとマズいな」と思ったからです。ただ、取るまでに3年ほどかかったので、そのときには次の職場である富山県庁の砂防課に異動していました(笑)。
――異動しても、あきらめなかったのがスゴいですね。
野村さん せっかく勉強したのに、まったくカタチに残らないのはもったいないと思ったので(笑)。
立山砂防の世界遺産登録に向けた活動も
立山砂防 白岩砂防堰堤(富山県庁提供)
――富山県庁はどうでしたか?
野村さん 印象に残っていることとしては、立山砂防の世界遺産登録の推進に携わったことです。立山砂防とは、国の重要文化財にもなっている現役の砂防施設群です。砂防課長として、ユネスコの本部に行ってアピールしたり、シンポジウムを開いたり、そういう仕事にも携わりました。
――それほどの価値がある施設なんですか?
野村さん そうですね。80年以上前に完成した施設ですが、今でも現役ですし。立山には、立山カルデラというおよそ5km四方の大きな窪地があって、この窪地に大量の不安定な土砂がたまっているんです。江戸時代に安政の大地震が起きた際、窪地の土砂が大崩壊して、常願寺川を堰き止めて決壊し大土石流となって富山平野を襲って大きな被害が出たということがありました。
その後もこの場所で洪水被害が頻発したことから、国が立山で砂防施設を建設してきたという歴史があります。そういうことから、富山の人には、立山砂防があるからこそ、現在の富山平野があるという思いが強いです。
ユネスコ本部でアピールする野村さん(本人提供)
――進捗的には今どんな感じですか?
野村さん まだ登録には至っていませんが、有力だとみなされているようです。
――同じ砂防事業でも、直轄と富山県では違うと感じたことはありましたか?
野村さん 富山県のほうがより地元密着で事業をしているという違いはありました。一番の大きな違いは、富山県では小さな沢の出口に砂防堰堤をつくりますが、直轄の場合は、河川流域全体の河床上昇による洪水氾濫のリスクを抑えるため、広域的な災害防止という観点から、砂防堰堤をつくる点にあります。やはり、事業規模の大きさが大きな違いだと思っています。
着任約9ヶ月で現場を一通り回る
栗ノ木川支川堰堤工事の状況(四国山地砂防事務所提供)
――そのあとは?
野村さん 今の四国山地砂防事務所です。出先勤務は入省1、2年目以来です。
――四国山地の印象はどうですか?
野村さん 四国山地の急峻な地形が印象的ですね。いわゆるV字谷が多いです。四国には東西方向に中央構造線が通っていて、地質が脆弱だし、雨も多いので、四国中央部は「地すべりの巣」と言えるほど、土砂災害が多いエリアです。
――所管する現場が点在しているイメージがあるわけですが。
野村さん 確かに、山地の中に点在しているカタチになっていますね。動いている現場が30箇所ほど、準備している現場も含めると50箇所ほどあります。2023年4月に着任して、9ヶ月ほど経ちましたが、一通り現場は見て回りました。けっこう大変でした(笑)。
――所長として心がけていることはありますか?
野村さん まずは現場に行くことです。四国の山の中に事務所があることの意味はそこにあるので、やはり「現場に出てナンボ」だと考えています。たとえば、砂防堰堤をつくるにしても、沢が一つ違えば、地形や地質などの条件も異なるので、常に最適なモノをオーダーメードでつくる必要があります。所長という立場であっても、現場を見た上で、状況をイメージできるようにしておくことが大事なんです。
有瀬排水トンネル工事の状況(四国山地砂防事務所提供)
――砂防事業のPRについて、どうお考えですか?
野村さん この事務所に来てから、PR力がちょっと弱いなと感じています。イベントや見学会などいろいろなことを一生懸命やってはいるのですが、立地的に不利なところもあるのか、あまりPRできていない印象があります。とりあえずは、SNSでの情報発信にチカラを入れているところです。現場の数だけは多いので(笑)、ちょっとしたことでもどんどん投稿するようにしています。たとえば、土石流が発生して、砂防堰堤でそれを止めたところの写真なんかをアップしています。
――いわゆるインフラDXに関する取り組みはどうですか?
野村さん 砂防事業は立体的に見たほうがわかりやすいことが多いんです。谷に堰堤を立ち上げるとか、地中にアンカーを打ったり井戸を掘ったりという工事は、2次元だとわかりにくいんです。点群データを取って、モデリングすることで、どこになにがどうなっているのかが、一目でわかるようになります。そういう意味では、砂防事業はICT施工に向いていると思っていますし、実際にやっています。
今チカラを入れているのが、衛星Wi-Fi、つまりスターリンクですが、これを活用した通信環境の構築です。現場にアンテナを立てるだけで、インターネット通信が可能になります。衛星Wi-Fiは今砂防業界で流行っていて、この事務所だけでなく、いくつかの事務所でも着手しています。現在は試行段階ですが、いずれ衛星Wi-Fiが山の工事のブレイクスルーになると期待しています。
スターリンクアンテナの設置状況(四国山地砂防事務所提供)
――野村さんにとって、砂防という仕事の魅力はなんですか?
野村さん やはり「命を守る仕事」ということです。いろいろな災害に関するニュースを見るたびに、「砂防でもっとできることがあったんじゃないか」という思いがあります。