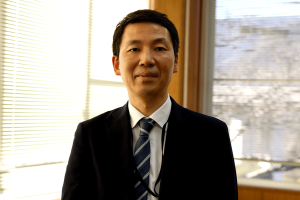「砂防職」の魅力、やりがいとは
徳島県西部の山奥、吉野川沿いの高台に四国山地砂防事務所という事務所がある。その名の通り、四国の山々を流れる吉野川流域や重信川流域などの砂防事業(砂防堰堤、地すべり対策など)を手がける事務所だ。その事務所長を務める野村康裕さんにお話を伺う機会を得た。
野村さんは、いわゆる砂防職として国交省に入省した。国交省砂防職職員の記事は、以前にも出したことがあるのだが、自治体に出向中だったこともあり、砂防職という仕事について、がっつり聞けなかったのがうらみとして残っていた。
野村さんにとって、砂防職の魅力、やりがいはなんなのか。これまでのお仕事ぶりなどを振り返ってもらいつつ、お話を聞いてきた。
※取材時期は2023年12月下旬
いつの間にか砂防の研究室に入ってしまった(笑)
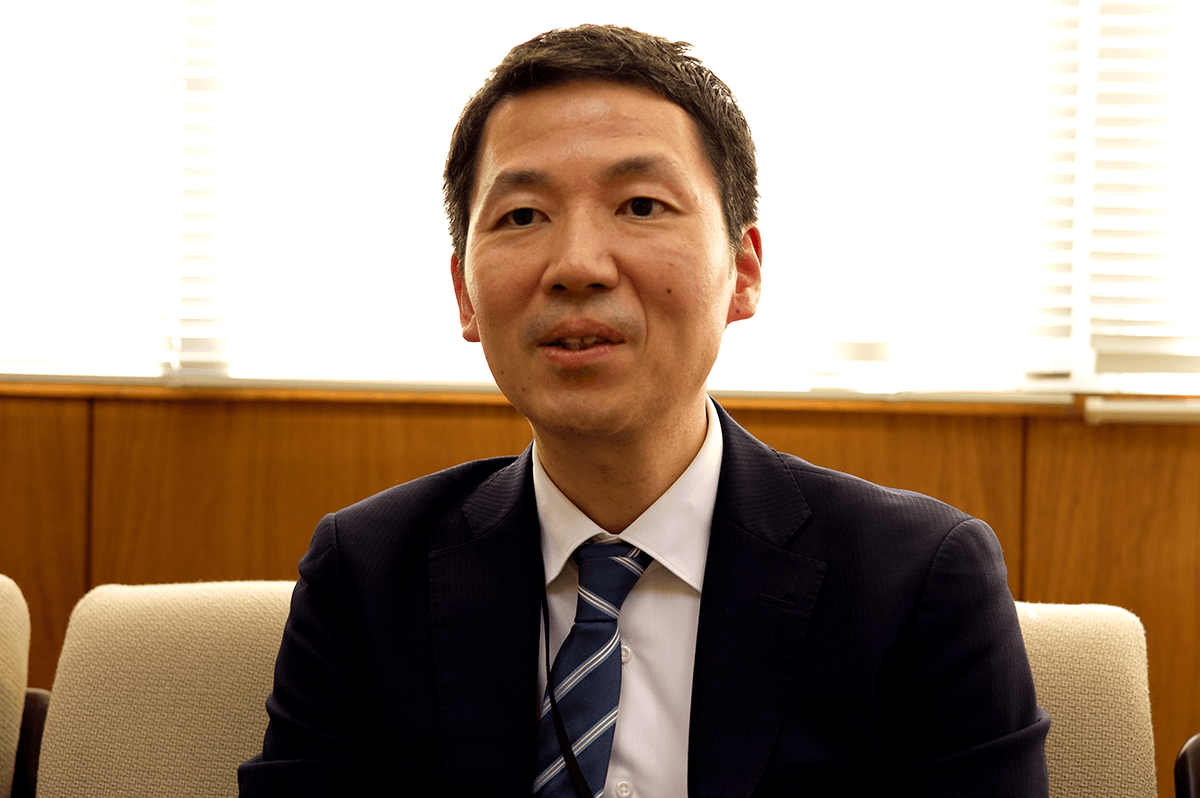
――国土交通省に入省した理由はなんでしたか?
野村さん 私は兵庫県の宝塚出身なのですが、高校生のときに阪神・淡路大震災に遭いました。そこで防災に関心を抱いたということが言えると思います。大学は最初農学部に進んだのですが、その後いろいろ考えるところがあって、砂防の研究室に入り、防災関係の研究をしました。この研究室の先生が国土交通省の研究所のOBだったこともあって、結果的に、砂防職として国土交通省に入りました。
――砂防の仕事をやりたいという思いがあったのですか?
野村さん そうですね。砂防の仕事をやりたくて国交省の砂防職を選びました。ただ、もともと砂防の研究室に進んだのには明確な理由はありませんでした。
今振り返ってみると、阪神・淡路大震災のときに、実家の近くで大規模な地すべりが起きて、30数名の方々が亡くなって、かなりショックを受けたということがありました。もともと「環境や森林を学びたい」と思っていたので、防災は一旦置いておいて、大学は農学部に進んだのですが、農学を学んでいるうちに、いつの間にか砂防の研究室に入ってしまったという感じでした(笑)。
――研究室の先生にもススめられて国土交通省に入った感じですか?
野村さん そうですね。国土交通省に入った先輩も多かったですし。あとは、三宅島が火山噴火をしたとき、卒論の研究として、土石流の調査のために先生について現地に入ったのですが、災害現場などで活躍する先生の姿を見て、純粋に「カッコ良いな」と思ったというのもありました。人の生活や命を守るという仕事に対する憧れがあったということです。
新潟県中越沖地震の現地調査で3ヶ月滞在
――最初の配属先はどちらでしたか?
野村さん 高知河川国道事務所でした。調査課に所属し、仁淀川や物部川の河川整備計画の検討などの業務に携わりました。2年目は徳島河川国道事務所の交通対策課に行きました。砂防職であっても、最初に河川や道路に行くのは、よくあるパターンです。
3年目は土木研究所のほうで地すべりの研究をやりました。このとき、新潟県中越沖地震が発生したので、現地調査のため、現地に3ヶ月ほど滞在しました。新潟県中越沖地震の災害復旧は、当時話題になっていました。地震に伴い、山古志村という場所で大規模な地すべりが多数起きて、村が壊滅的な状況になりました。まだ3年目だったので、上司の随行員という感じでしたが、貴重な経験でした。
研究所には1年半ほどいて、そのあと本省の砂防部保全課に直轄砂防係長として戻りました。全国の直轄砂防事業を所管する係です。
――直轄砂防の予算関係ということですか?
野村さん そうです。予算のほか、前年に発生した新潟県中越沖地震の災害復旧なども担当していました。このときも被災現場に何回も行きました。
――本省の係長として現場に入ったのですか?
野村さん そうです。ふつうはなかなか現場に行く時間がないと思います。ただ、「現場を見なきゃいけない」という思いがあったので行きました。あと、週末の休みを利用して、関東、北陸などの直轄砂防の現場にも行っていました。
――ープライベートでも現場に足を運んでいたんですね。
野村さん ええ、山登りは好きなので、趣味を兼ねて行っていました。
⇒【施工管理求人ナビ】に相談してみる
ネパールで山岳道路建設を支援

ネパールのシンズリ道路の建設現場を確認する野村さん(先頭左、本人提供)
――その次の職場はどちらですか?
野村さん 外務省に出向して、在ネパール大使館に書記官として3年間ほど駐在しました。インフラ担当ということで、ネパールとインドを結ぶ全長160kmほどの山岳道路建設の支援がミッションでした。現地政府との調印の段取りや事業管理といった仕事をしていました。主なカウンターパートは、ネパールの財務省でした。
――ネパールはどうでしたか?
野村さん カルチャーショックが大きかったですね(笑)。首都のカトマンズに住んでいたのですが、電気や水道といったライフラインがほぼありませんでした。道路はボコボコですし、下水道はそもそもありません。電気は1日18時間停電していましたし、水道も2、3日間のうち出るのは30分だけという状態でした。
――水道に関しては、出たところで、飲めるのかという気がしますが。
野村さん 飲めないですね(笑)。ミネラルウォーターを買っていました。
夏休み返上で広島土砂災害の現場に入る

平成24年九州北部豪雨の現場調査をする野村さん(本人提供)
――そのあとはどちらに?
野村さん 国土技術政策総合研究所の砂防研究室に行き、研究官をしました。この間、けっこう土砂災害が多くて、平成24年の九州北部豪雨(熊本阿蘇)や決壊したインドネシア天然ダムなどの現場に緊急援助隊の一員として派遣され、1週間調査などに従事しました。

インドネシアのアンボン島天然ダムを災害調査する野村さん(たぶん左、本人提供)
野村さん そのあとは、また本省に戻って、砂防計画課課長補佐として、土砂災害防止法の改正などに携わりました。砂防部には保全課と砂防計画課の2課があるのですが、保全課は砂防関係事業、砂防計画課は施策や法律を所管しています。砂防職の人間は、2つの課を両方経験するのが一つのパターンになっています。
このとき、平成26年の広島土砂災害が起きました。発災したのが、ちょうど私が夏休みを取るタイミングでしたが、「出勤しろ」と言われて、職場に行ったら、「現地に行けるか」と言われて、夏休みを返上して、調査団の一員として、広島の被災現場に行くことになりました。発災したのが前日の夜中から早朝でしたが、翌日の昼には現地に向かうヘリに乗っていました。この災害を受けて、土砂災害防止法を改正することになりました。