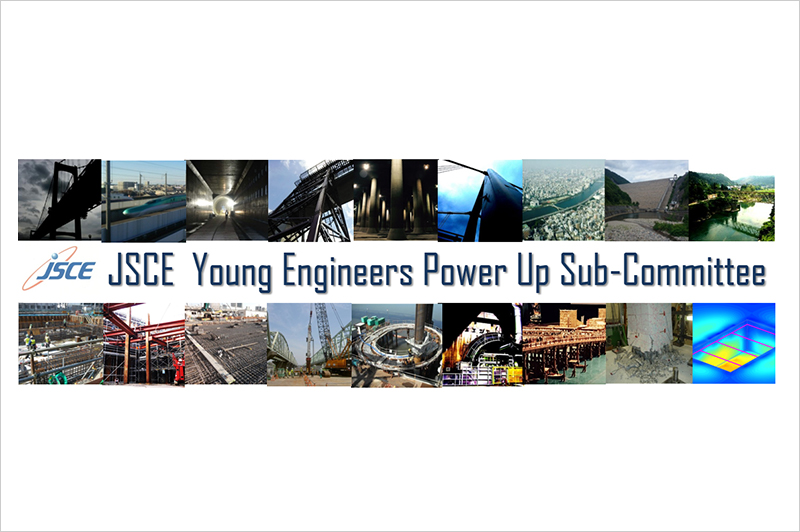土木業界の課題を洗い出す「土木辞めた人、戻ってきた人インタビュー」
土木学会の若手技術者たちが中心となって活動を開始した「土木学会若手パワーアップ小委員会」。
当委員会のひとりが、某ブログで「若手土木技術者の退職エントリ(記事)」を見つけたことがきっかけで、今回の企画「土木辞めた人、戻ってきた人インタビュー」がスタートしました。
私たち「土木学会若手パワーアップ小委員会」はそのブログを書いたご本人に、土木学会本部で直接インタビューを実施しましたが、その際、最も印象に残った言葉が「土木を辞めた人の意見は、実社会にもネットにも見つからない。今の土木業界には辞めた人の意見を聞く場がない」でした。
せっかく土木の世界に入ったのに辞めてしまう人達の退職理由から、今の土木業界の課題を洗い出せるのではないか?ーーそんな考えから「土木学会若手パワーアップ小委員会」は、土木を辞めた人へのインタビューをおこなっています。
大手ゼネコンを退職した女性土木技術者
今回ご紹介する「土木辞めた人、戻ってきた人インタビュー」は、30代女性の元土木技術者へのインタビューです。
彼女は都内の大学の土木系学科を卒業後、大手ゼネコン本社にて設計を担当。その後、関東地方の鉄道現場、本社での積算業務などを担当しましたが、入社5年目に退社。現在はプロのカメラマンとして、結婚式や座談会を撮影しています。
――まず最初に土木を職業として選んだ理由を教えてください。
中学高校の頃から、漠然と技術者とか職人、自分の技能を持って仕事をしている人に強い憧れがありました。そこから理系に進み、高校3年生の時、学科を決めるために色々と本を読んだ中に「メコン河流域開発」という本がありまして。カッコいいなと。
――就職先として大手ゼネコンさんを選択した理由は?
モノをつくりたいなと思いました。公務員の道も考えたのですが、公務員になってゼネコンに転職するのはかなり難しいだろうと、当時、先輩の話を聞いて感じました。そこでゼネコンに就職してみて嫌だったら公務員に転職しようと、ゼネコンを志望しました。
――当時、女子学生の大手ゼネコンさんへの就職は難しかったのではないですか?
私が就職活動をしている時には、女性を採用しようという流れがありましたね。女性採用のハードルは下がってきていて、私より年下の世代はもっと女性社員が増えていますね。
ゼネコンでの「お茶当番」「飲み会の強制参加」
――入社当時はどんな業務を担当されましたか?
1~2年目は解析が中心でした。数字の感覚を掴ませようとしてくれていたのだと思います。もちろん後々役に立つものではありますが、当時それ自体がやりがいになっていたかというと…。余裕があるときは自分でチェックして上司に説明していたのですが、余裕がなくなってくると、「チェックした?」「しました」だけになってしまって。
――思い描いていた技術者像との相違がありましたか?
想像していたような、突出した技能や技術を持って仕事をしている、という感じではないなと思いました。設計にしても指針ありきですし、技術的な理由ではなく、こういう結果に持っていきたいから…という仕事の進め方に違和感を覚えました。全てではないですが、本質的でないところを気にしているなと。
――実際の業務以外で、職場環境などで違和感はなかったですか?
他の業界と比べて、昔からの流れがずっと続いているところがあると思いました。飲み会の強制参加など、自分の時間を大切にしていない上司が多いので、若手にそれが降ってきますよね。自分の時間という概念が薄い人が多いイメージがあります。
――飲み会についてはどうですか?
いかにも「ゆとり世代」って言われそうですが、本当に必要なことであれば、交流会もお酒も業務時間中にすればいいと思っています。本当に必要なら業務時間にやって、それ以外は自由参加にしたらいいと。
私の場合、友達にIT系の子が多くて、本社にいた時はよくランチをしていました。どこもすごく自由な社風で。全員フレックスだし、どこでもオフィスって仕組みがあって、申請すると丸一日とか半日とかカフェで仕事をしてもよくて、成果を報告してOKっていう。
そういう子たちを身近に見ていて、うちの会社は個人の時間という概念が本当に薄いなと感じていました。業務外のイベント(飲み会やグループ旅行の計画など)に費やす時間が多く、そのことに反抗していました。
――「新入社員のお茶当番」の廃止を訴えたと伺いましたが?
私が入った時、お茶当番っていうのがありまして。新入社員が30分とか1時間とか早く来て、コーヒーメーカーや給湯器を数台セッティングするっていう。私が入社1年目の時にお茶当番の廃止を訴えましたが、却下されました。他にもコピー機の用紙がなくなったら、新入社員がダッシュして補充しに行かなくてはならないとか。
――新入社員のお茶当番の廃止は、どんな理由で却下されたのですか?
ひとつには新入社員は顔を覚えられていないから、コーヒーやコピーで顔を覚えてもらって、この子は新入社員だなと認識してもらえと。もうひとつは新入社員で仕事も出来ないのだからそれくらい感謝を持ってやれと。先輩方からも新入社員がかわいそうだって意見もありますけど、そう言う先輩には感謝の気持ちが伝わっていないからだ、と言われまして。
現場が一番面白かったが、体に無理が出てきた
――現場勤務はどうでしたか?
職場としては現場が一番面白かったですね。やっぱり職人さんに憧れがあったので。BH杭の施工管理を担当したのですが、最初は先輩の補助として入りまして、慣れてきたら次の杭打ちについて段取りをさせてもらって。業者の方から「がんばってるね」と言ってもらうのはとても嬉しかったです。
――女性だと、現場で信頼を得るまでにちょっと時間がかかるというのはなかったですか?
私が初めての現場だというのは皆さん知っていらしたので、わからないことばかりなのだと理解してくださっていて。敷居はなかったですね。良く言えば優しくしていただいていたし、悪く言えば舐められていたというか、甘やかされていたと。
――現場の勤務形態はどうでしたか?
超勤が月130時間くらいですね。土曜日は出勤がある時とない時がありました。私は「通し夜勤(夜勤の翌明けの日も連続しての勤務形態)」はありませんでした。それは配慮してくれていたのだと思います。夜勤は6日間連続でした。それで休みが入って、その次の週が昼に戻って。
――苛酷ですね。男女関係なく夜勤が出来ない人はいますよね。
私も昼間はよく眠れませんでした。本当は2年間現場にいるはずだったのですが、体調を崩して本社に戻してもらいました。現場が一番面白かったのですが、一番楽しいのに体の無理が出てきてしまって。「ああ、この道を極めるのは無理なのかな」と。
土木技術者を辞めたワケ
――現場から本社勤務に戻って、辞められるまでの経緯を教えてください。
その頃、ちょうど結婚しまして。夫がちょっと変わった人で、小学生からずっと虫が好きで。好きなことをやって、それを仕事にして生きている人です。好きなことを仕事にするとこんなに生き生きと楽しそうに生きられるのかと、凄く羨ましくて。
――土木技術者の仕事に魅力を感じられなかったと?
土木の魅力って言った時、好きだとかカッコいいとかより、人の役に立つって話が先行しがちですよね。もっと好きを全面に出した方がいいのでは?と思います。
――たしかに土木の人は「好き」だからと言わず、色々言い訳しながら働いている人が多いかもしれませんね。好きそうではあるけど、そんなに面白そうにやっていないっていう。また、組織の中で好きなことをするのはなかなか難しいところもありますね。
私は普通に面談で言っていましたね。海が好きなので、海に関わる仕事がしたいと希望を出して、設計の2年目は海洋関係のグループに移してもらいました。
会社に海洋研究所がありまして、そこに行きたいって何度も希望を出しました。でも、お前は学科が土木だろって。専門も全く違うのに何を馬鹿なことを、って一蹴されました。以降、そこに行くって話は一切なくなって。
――そこに行っていたら、今でも働いていたかもしれないですか?
そうかもしれません。同じ海好きの友人がいまして、友人も専門外ですけど10年言い続けて研究所に。10年待てば?とも言われましたが。10年か…と。
――会社を辞めるきっかけはありましたか?
現場で体調を崩していた時に、友人の結婚式を撮影していた方の写真を見て、すごく感動してしまいまして。結婚式の写真といえば会場専属のカメラマンがきまりきった写真を撮るというイメージを持っていたのですが、その人の写真は思い出の瞬間を切り取った、非常に心動かされる写真で。こういう仕事があるのかと。
当時は現場が忙しくて何もできなかったのですが、本社に戻って土日休みでそれほど超勤もなくしていただいて。とにかく写真がうまくなりたいと思って、週末はそのカメラマンさんのアシスタントをしていました。
――すごい行動力ですね。ご家族の理解はありましたか?
最初は全然応援してくれてなかったですね。その急激な変化に戸惑っていたようです。でも平日に仕事して、土日の疲れている中で写真に行くのを毎日見ていて、そんなに好きならしょうがないな、となったようです。
――写真に出会ってから、退職までどれくらいでしたか?
退職を言い出すまで半年、実際辞めるまで1年ですね。
――各方面から慰留されませんでしたか?
若手の教育担当の方と直属の上司には、かなり真剣に止められましたね。本当に優しい方達で、本当に私の人生を心配してくれました。でも私には写真を撮っていきたいという具体的な夢があったので、それだけ言うならがんばれってことになりまして。上の方ともその後お話したのですが、その方達にはむしろ止められなくて。なんか変な面白いやつだな、がんばれよって。女性の幹部も心配はしてくださいましたが、見つかったなら良かったねと。
――後ろ髪ひかれるようなことは言われなかったですか?
なかったですね。そこまでに散々悩みましたので。同期にも、先輩にも上司にも言わずに考えた期間が結構ありました。
土木業は「ありがとう」が見えにくい
――組織を離れることに対する怖さはなかったですか?
それはありますね。今もあります。少しでもミスをしたら次の仕事はこないっていうのもあります。
――土木は対象領域が広いですし、この中で違う選択肢を選ぶことは考えませんでしたか?
今は、私に撮ってほしいという依頼をもらって写真を撮る仕事をしています。お客さまは、私にしか出来ないことを求めてくれます。それに応えることでお客さまから「ありがとう」と言っていただける。それに凄く価値を感じます。
土木はちょっと結果が遠すぎたというか。本当になくてはならないものだけれど、それを使っている人からの「ありがとう」が見えにくい部分がありますね。
土木を好きってエネルギーが不足しているなと。もちろん仕事なので、やりたくないこともありますし、やらなきゃならないことも。それでも、組織の中で「好き」を表明した人の想いをもっとくみ取ってほしい。
――自分を選んでもらえることは大きなやりがいですね。土木の仕事はそうではなかったですか?
そうですね、単純にもっと仕事が出来て、年数を重ねていれば自分も「これは是非あなたに…」というところまで行けたのかもしれないですが。自分がやっている範囲ではそういったものを感じられなかったですね。
でも、ずっと土木には関わっていきたいと思っていまして、土木学会の座談会の写真なども撮影させてもらっています。それ以外にも道路とか、施工中の写真なんかも撮っていきたいなと思っています。
――土木の経験や知識が勿体ない感じもしますが?
もう覚えていないですよ、お役に立てないかと。でも土木の写真であれば、他の人とは違う写真が撮れると思います。
――土木は好きですか?
今でも、大きなものを造る人達への憧れはあります。でも、自分が進む道ではなかったですね。
「土木辞めた人、戻ってきた人インタビュー」後記
土木の世界では、若い頃から自分が会社の代表となって仕事をする、ということが最近どんどんなくなってきています。そして、お金の余裕も時間の余裕もない中、新入社員は作業ばかりになってしまい、やりがいが見つけ辛くなってきています。
従来の土木技術者は、やりたいことが出来るまで10年待ったのだと思います。でも、10年となると今の若手は次に動く力を持っています。合理的な判断の出来る若者が増えることは素晴らしい。一方で、それは土木業界にとっては危機でもあります。
今の業務体制、特に大きな組織では、仕事に人が付くのではなく、人に仕事が付く仕組みになっています。その点をうまく活用していく必要があるのではないでしょうか。