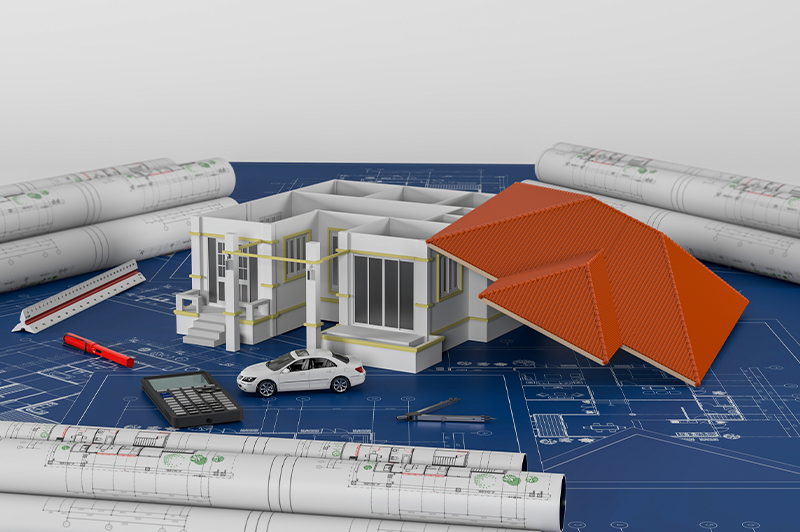生産性効率のための2D CAD部品
土木技術者にとっての2D CADは、手書きの図面作成からの画期的な生産性向上ツールだった。
最初は「技術者たるもの、図面は手書きができて一人前」という経験主義が蔓延し、2D CADが手書きに置き換わるまでに時間がかかった。
しかしながら、いまでは逆に手書き図面を書く人が少ない。土木技術者の集まりとして新しいツールを導入するには、そうした悲しい変遷を経ることが常になっているような気がする。
さて、そんな変遷を経て2D CADが一般的になってくると、CAD図作成の生産性を向上させるために、部品が欲しくなってくる。
2D図面を作成する時、資材等、形状が決まっているものを作図する場合、製品のブロックをメーカーのサイトや個人が作成しているジェネリック2D部品を集めているサイトなどからダウンロードをして使用する。
しかし、そのサイトを探すにも多量にサイトがありすぎて、欲しい部品を見つけるまでに時間がかかったり、使用したいメーカーは2D部品のダウンロードサービスがなかったりと不自由を感じたことが随分あった。
そして、探しまわった挙句、欲しいものが見つからず各自で作成してしまうことも。効率的に部品・ブロック・パーツを使用しているつもりであるのに、これでは本末転倒である。
もっと効率化できないものか? すべての部品を1か所に集めることで、無駄な時間や不用な作業がなくなれば、利便性を上げ効率的に使用できるのでは? との思いに至った。生産性の改善は、データの取得方法と共にその利用方法に大きく依存することを我々土木技術者は経験値から理解している。
2D CADでの利用経験は、数年前から国土交通省をはじめとする行政が積極的に展開をはじめた3D CADの世界でも同じことが起ころうとしている。
これから3Dモデルが積極的に利用される状況になろうとしている中、益々3D部品を使いやすくすることが必要ではないかと、現在、Civil User Groupの有志で3D部品について、ワーキンググループを発足し、調査やガイドラインの作成など行っている。
ちなみに、2007年土木分野への3Dモデルの導入推進を目的に、Civil 3D User Groupを発足し、その後、2012年に、設計者・施工者をはじめとした土木技術者の集まりとしてCivil User Group(略称:CUG)へと発展し現在に至る。
Civil User GroupのWebサイト(https://cim-cug.jp/policy.php)
その間登録ユーザー数は、うなぎ上りに増え2019年8月末時点で約3,000名程度の利用者登録となっており、国内で最大級の土木分野における技術者集団といえるだろう。
最近のBIM/CIMの推進状況
国土交通省では、これまで3次元モデルを活用し、社会資本の整備や管理を行うCIMを導入することで、受発注者双方の業務効率化・高度化を推進してきた。
一方で、国際的なBIMの土木分野での国際標準化の流れを踏まえ、社会資本整備を見据えた3次元データを基軸とする建設生産・管理システムを実現するため、産官学一体となって再構築し、BIM/CIMとして推進している。
『CIM導入ガイドライン』の中には、「2次元図面から3次元モデルへの移行による業務変革やフロントローディングによって、合意形成の迅速化、業務効率化、品質の向上、ひいては生産性の向上等の効果が期待される」とあり、2Dから3Dへの移行は必然となった。
満を持してスタートしたCIMはまず、3Dモデルの作成とそれに合わせた属性の管理をどうするかという議論からスタートした。
CIMは、 3Dデータで設計者・施工業者・発注者で一元管理されたモデルとそれに付随した属性情報を共有する。モデルを作成する際に、すべてのモデルを一から作成するのはとても時間がかかる。ある程度のモデルを作り始めてくると、同じようなモデルを部品として再利用したくなる。
まだまだ、3D部品・モデルを作成できる人材が不足していることもあり、部品が積極的に活用できる環境を整えようと、官民合わせての検討は始まっている。
アメリカ、イギリス、韓国…世界の3D部品の整備状況
では、世界の3D部品の整備状況はどうなのだろうか。米国、欧州、アジアの様子を以下にまとめた。
- ウィスコンシン州では、発注機関からソフト、部品、テンプレート、マニュアル等すべて提供されている。
- イギリス王立建築協会が運営しているサイトで、主にメーカーが作成したBIM用の部品が登録されている。
- シンガポールはBIMが進んではいる。しかし、確認申請時に3Dモデルが必要ではあるが、部品サイトは存在していない。
- 韓国は、建築分野のライブラリーは民間団体が配布している状態である。土木分野のライブラリーは国土交通部と政府の研究機関、韓国建設技術研究院が100%運営している。
設計・積算に主眼を置いているため、3D部品に限らず、アセンブリ(組立図)の登録もされているが、政府機関が必要なものに限られている感がある。 - スウェーデンのベンチャー企業のBIMobject社は、世界最大のBIMデータライブラリーサイトを運営している。2017年にはBIMobject Japanが設立されている。
国内外の3D部品の作成状況を調査したところ、部品サイト運営として韓国は理想的ではないかと感じたが、効率化という点では共通しているものの、日本の設計者・施工者の誰もが汎用的なものを共有化しようと考えての3D部品の活用とは異なっていると感じた。
本来発注者が一番活用すべき部品なのかもしれないが、現状では利用者である、設計者や施工者が部品の最大利用者となっている。
世界最大のBIMデータライブラリーサイト「BIMobject」とは?
世界最大のBIMデータライブラリーサイト、BIMobjectというサイトがあることを知ったのは2017年の時であった。
メーカー側から対価を徴収する一方、ユーザーは使用料無料でコンテンツをダウンロードできるというビジネスモデルで、メーカー側は訪問履歴やダウンロードなどのマーケティング情報が宣伝・営業になり、マーケティング情報を提供する対価としてメーカーから使用料を徴収するビジネスモデルである。
「BIMobject Japan」のページ
使用者は無料で効率的に3D部品を活用できるという、互いに必要な情報を活用できるため、ユーザー・メーカー双方に便利なサイトであった。現段階では、建築系メーカーがほとんどで、土木系のメーカーの参入が無いようだ。
このように、BIM(建築系)では、建築保全センターという公的な団体が中心となり、適切な属性情報が付いたBIMパーツを標準化し、BIMユーザーに供給しようという取り組みを行っている。
CIMについては、国土交通省は2018年3月、効率的に3D設計を進める1つの手法として、3Dモデルを構成するパーツを作成・提供する「CIMライブラリー」の構築に乗り出す。2020年度の運用を目指し、CIMライブラリー構築の検討が始まっている。
3次元オブジェクトの供給に関する検討 / 国交省
3次元オブジェクトの供給に関するイノベーション促進 / 国交省
今後の予定 / 国交省
『CIM導入ガイドライン』の中にCIMモデルとは、「3Dモデル」と「属性情報」を組み合わせたものを指す、とあり、BIMobjectの3D部品は属性も多く付与されており、ガイドラインに合致している。このサイトでの土木系3D部品があれば、誰もが使用しやすく効率という観点からも利便性が高いのではないかと思われる。
この際、Civil User Group有志のワーキンググループですでに運営しているBIMobjectを、ユーザグループとしての利用から拡大し、公的機関が引き継いで運用することができれば、今後の部品作成・運用・展開にも効率的だと思われる。
土木ユーザーにも広がるBIMobject
建築系だけではなく、土木系でも有益ではないかと、Civil User Groupで作成した3D部品を実験的にBIMobjectのプライベート空間で1年間限定の運営をしている。運営から半年が過ぎ、訪問、ダウンロード履歴等を見てみると、土木のユーザーも3D部品を必要とし相当数の訪問、ダウンロードをしているという結果が出ている。
日本では、メーカーがこのビジネスモデルを有益だとは感じられていないようだが、ユーザー側としてはこの先、3D部品、CIMモデルを推進していくために、非常に有効なサイトであると確信している。
現在、実験的にCivil User GroupでBIMobjectを活用し、部品展開を半年間運営しているところである。利用者の反応や利用LOGを分析したところ、どの部品がよくつかわれていて、どの分野の部品をさらに増加させなければならないかという利用者の傾向がわかり、本サイト運営に良い手ごたえを感じている。
これらの運用を継続して実施していきたいところだが、BIMobjectの運用には年間150万円程度のコストがかかり、現在無料、無償で活動している土木技術者の集まりであるCivil User Groupの継続した運用は難しい状況である。
他国の事例でもわかる通り、これら部品サイトの運営は発注者が行うものが多いため、日本でも発注機関がCivil User Groupの立ち上げたBIMobject運営の支援を行うか、発注機関が自らBIMobjectと同様の部品サイトを構築し、運営していく必要があると思う。