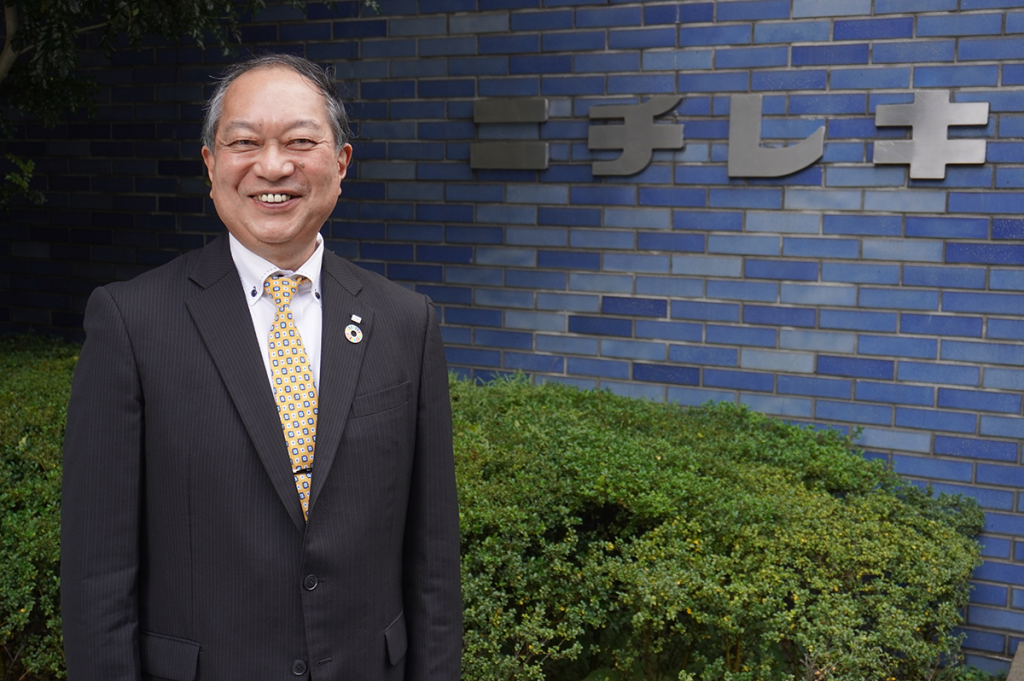【ニチレキシリーズ最終回】羽入 昭吉さん
ニチレキシリーズ最終回では、羽入昭吉さんの「シビルケミスト」としての半生を振り返る。羽入さんはニチレキに入社して40年超のキャリアを持つ大ベテランだ。彼を良く知る人は、尊敬の念を込めて「舗装の神様」と呼ぶ。
羽入さんは過去に「2回の運命的なチャレンジ」に遭遇したと言うが、それらのチャレンジがあってこそ、神と呼ばれる領域に羽入さんを引き上げたようだ。ともあれ、神様の語るところを聞いてみよう。
「お前はゼネコン向きじゃない」
若いころの羽入さん
――土木に興味を持ったきっかけは?
羽入さん 小学校のときに、テレビで「黒部の太陽」を観たことです。その後、原作の小説も読みました。黒部ダムを建設する話ですが、「むちゃくちゃカッコ良い。これぞ男の仕事だ」と憧れました。
――それで土木を学んだと?
羽入さん そうです。北海道の工業大学で土木を学びました。
――舗装の勉強をしたのですか?
羽入さん ええ、研究室は舗装でした。素材を触るのが好きだったのと、舗装の材料研究で有名な先生がいたからです。
――舗装をやりたいということで、ニチレキに入社したのですか?
羽入さん いえ、最初はゼネコンに行こうと思っていたんです。ところが、研究室の先生から「お前はゼネコン向きじゃない」と言われ、ニチレキを紹介されたんです。
当時は日瀝化学工業という名称だったので、「化学の会社みたいでイヤです」と反論しましたが、「そんなことはない。とにかく会社見学してこい」と言われました。そこで見学に行ったのですが、実際に見てみると、「おもしろそうだ」と気が変わりました。それでニチレキに入社することにしました。
――なにが「おもしろそう」だったのですか?
羽入さん オリジナルな材料を製造して、それを仕上げるところですね。ゼネコンや他の道路会社がやらないような材料を使って、特殊な機械で施工する。オンリーワンの会社だと思いました。当時すでに、道路や橋梁をレーザー光線で診断する非破壊検査の研究開発もやっていました。先見の明のある経営者がいたことにも、魅力を感じましたね。
良いアスファルトをつくるため、工場改造を提案
本州四国連絡橋の現場に携わっていたころの羽入さん
――印象に残る仕事はありますか?
羽入さん 本州四国連絡橋の舗装工事です。この国家プロジェクトとも言える事業では、「メンテナンスフリー」がキーワードにあり、舗装にも新しい技術開発が求められました。
舗装の長寿命化に貢献する新たな改質アスファルトを当社が開発しました。海上に架かる長大橋なので、しょっちゅうメンテナンスするわけにはいかないからです。私が入社した年に工事が始まりました。当時研究員だった私は、大鳴門橋の舗装工事のため、1ヶ月ほど現場近くの姫路工場に出張しました。
ですが、なかなか良いモノが開発できませんでした。当時の工場の設備では、ゴム濃度が低い汎用品程度の品質のものしか製造できなかったからです。そこで私は、会社に対し工場の改造を提案しました。すると、「やってみよう」と受け入れてもらったのです。当時の私は23才の一研究員に過ぎませんでしたが、これは嬉しかったですね。
その甲斐あって、通常の100〜200倍の耐久性を持つ改質アスファルトができました。大鳴門橋にはこのアスファルトが採用されています。
このときの経験は、その後の私の舗装屋としての人生にとって、大きな財産になっています。「原理原則に則っとれば、良いモノができる」ことを知りましたし、「材料づくりと製造設備の開発は表裏一体だ」ということを学びました。
発想の転換で、ポーラスアスファルトを開発
――この経験が舗装屋としての原点になったわけですね。
羽入さん そうですね。ただ、私が本格的に研究開発をやり始めたのは、その10年後、33才のときからなんです。
それまでにも研究所に4年ほどいて、その期間に誰にも負けないぐらいアスファルトの研究をした自負はあるのですが、それを仕事に活かす機会には恵まれませんでした。その後、東京支店のほうでセールスエンジニアのようなことを6年ほどやりました。そして、再び研究所に戻ってからです。
お客様から「こういうアスファルトをつくれないか」と言われたとき、「絶対につくってやるぞ」という強い気持ちに変わりました。しかし、新しいアスファルトをつくると決意したのは良いものの、どこにも答えがありません。当時の専門書を開いても、海外の論文を読んでも、載っていません。だから、答えは自分で見つけるしかありませんでした。答えを見つける上では、20代に研究所で得た基礎知識が役に立ちました。
そこで、仮説を立てて、お客様にわかりやすいように絵に書いて、どうやったらちゃんとつくれるか、100回やったら100回ともつくれるかということを研究しました。
――それはどのような研究開発だったのでしょうか?
羽入さん 高速道路の排水性舗装です。私の40年の舗装屋人生の中でも、2回目となる運命的なチャレンジでした。
1980年代に「第二次交通戦争」ということが言われました。高速道路で多くの死亡事故が発生し、日清戦争の戦死者数を上回るほどの死亡者が出たからです。1960年代の第一次があったので、第二次と言われたわけです。
当時の高速道路の舗装は、密粒度アスファルト混合物という一般的な舗装でした。この舗装だと、短期間でワダチぼれができて、そこに水が溜まって、交通事故が多発していました。あちこちでハイドロプレーニング現象が起きたわけです。
そのころ、ヨーロッパのほうでは排水性舗装というものをちょっとずつやっていたので、日本でもこれをやってみようという話になりました。そこで、そういうアスファルトをつくることが、当時の33才だった私のミッションでした。「ポーラスアスファルト」という新たなアスファルトの開発でした。
ポーラスアスファルトは、通常の舗装に比べ、空隙率が約5倍とスカスカで、雨がよく浸透するので、水が溜らないのが特長です。
当時の日本には、ポーラスアスファルトを支える丈夫なアスファルトがありませんでした。一般的なアスファルトは、アスファルトネットワーク型で、アスファルト中にSBS(スチレン・ブタジエン・スチレントリブロック共重合体)というポリマーを分散させて強度を出すという構造でしたが、この構造のまま雨を浸透させようとすると、強度的にムリでした。何度か試験しましたが、すべて失敗しました。
そこで、それまでの常識を無視し、発想を逆転して、SBSネットワーク型に変えようということで、SBS中にアスファルトを分散させる構造を試してみました。一番安いアスファルトを増量材として使ったわけです。試験した結果、これなら使えるということになりました。
ポーラスアスファルトが採用された結果、当時の日本道路公団の調べでは、交通事故の発生率が84%も減少しました。こういう1ミクロンとか10ミクロンの世界で起きていることをコントロールすることで、巨大な土木構造物の性能を大きく変えることができるわけです。
私がこれまでやってきた仕事は、こういう国家プロジェクト的な大事な現場で使えるアスファルトの開発が多いです。最近では、コンクリート橋床のための高性能防水、30年持つ防水材料を開発しています。
世の中にないアスファルトをつくるのが喜び
――仕事で一番嬉しかったことはなんですか?
羽入さん それはやはり、今までに世の中になかったアスファルトを自分でつくったときです。自分で考えた新しい発想をカタチにして、疲労試験をやって、他の研究員たちと一緒になって、「これはスゴい、これを使って本格的にやろうぜ」と盛り上がったときです。ポーラスアスファルトを開発したときがまさにそうでした。ポーラスアスファルトが実際の高速道路に採用され、交通事故が大幅に減ったことも嬉しかったですが。
あと、親戚から「最近の高速道路は走りやすくなったよね」と言われたときも、非常に嬉しかったです。
――ツラかったことはありますか?
羽入さん 製品のクレーム対策で国内外の現場を飛び回ったことです。やっているときは大変でしたが、クレーム処理の仕事を通じて、結果として多くの新製品・新工法を開発することができました。加えて、いろいろな人脈ができましたし、技術を現場に根付かせることもできましたし、非常に密度の濃い時間でもありました。
現場で「開きを埋める」のも舗装屋の大切な仕事
――やはり現場仕事は大事ですか?
羽入さん 研究所でどんなに良い材料をつくっても、現場の施工力、技術力が追いつかないと、実際の現場では良いモノはできないということがあります。机上の要求性能に合わせてつくったモノが、現場の要求性能と合致するように施工できるかと言えば、それは非常に難しいことだからです。
例えば、ある高速道路の橋梁床版防水の研究開発をしたことがあるのですが、床版のすべてのコンクリートが同じ状態で仕上がっているかと言えば、そういうことはありません。橋梁屋さんの世界ではちゃんと基準を満たしているのですが、われわれがつくった床版防水がそこにうまくはまるかどうかという基準と比べると、その緻密さにおいて2オーダーぐらいの大きな開きがありました。
われわれには、その開きを埋めながら、仕事をする必要があるんです。舗装屋にとって、そういう仕事も大事な仕事なんです。
私が大切だと思っていることは、たくさんありますが、特に目に見える要求性能や仕様などを単に満足するだけでなく、そのウラ側に潜む本当の問題・課題に気づいて、丁寧に観察し、メカニズムを考え、仮説を立てて課題解決するという真摯な姿勢、丁寧な仕事を実践することです。地味ですが、コツコツとひとつひとつ良い仕事を続けることです。
今回の連載シリーズを読んで、ニチレキに興味を持ったクレイジー技術者をお待ちしております。