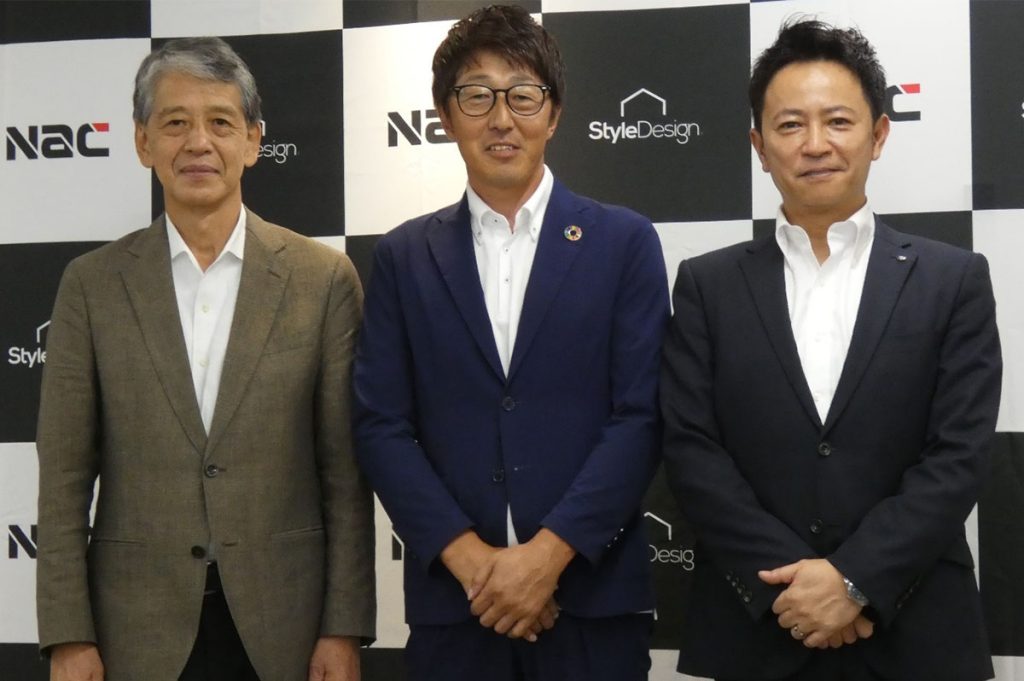株式会社ナック(東京都・新宿区、吉村寛社長)は、同社の工務店支援を展開する建築コンサルティングカンパニー(大場 直樹代表)において北関東で住宅事業を展開する株式会社Style Designと業務提携契約を締結した。今回の業務提携契約に伴い、中小工務店では内製化が難しいとされる「デザイン性が優れた規格住宅の図面データ」や「モデルハウスを建てずに受注に繋げるDX活用接客スキル」などのノウハウを盛り込んだ商品「i-Style(アイスタイル)」の提供を開始。
新商品の紹介をはじめ、建築や住宅でのデザイン性の重要性やニーズ、中小工務店が抱える課題、街づくりにおける建物のデザインの重要性について、建築家である株式会社JWA 建築・都市設計の渡辺純代表取締役、株式会社Style Designの稲葉龍也代表取締役会長、株式会社ナック 建築コンサルティングカンパニーの大場直樹代表が語った。
北関東に強いStyle Designと業務提携
ナックは、全国のビルダー・工務店に向け、経営支援ノウハウ商品や建築部資材の販売と施工、住宅フランチャイズ事業を展開。経営戦略をはじめコスト削減や商品開発、営業手法などの経営支援ノウハウを通じて地場工務店を支援、全国7000社以上の企業がナックのソリューションを導入している。
近年のオンライン化の需要拡大や原材料費高騰など工務店業界を取り巻く外務環境は依然として厳しい。そこでナックが持つ工務店ネットワークとStyle Designが持つ高い商品力、集客・接客やノウハウを融合することでより多くの中小工務店の経営課題の解決に寄与することで提携に至った。現在の工務店にはどのような経営課題があるのか、まずはナックで開催した発表会の内容を見てみよう。
新商品の発表に先立って最近の工務店業界の「倒産件数と給付金」「資材高騰の影響による売上の減少」「大手メーカー、ビルダーの受注状況」の3点のトピックスの解説があった。
工務店業界の倒産件数は、2019年から2021年の3年間はほぼ横ばい傾向であったが、2022年には3年ぶりに増加。理由はコロナ禍での売り上げ減少、物価高や人手不足が挙げられる。この厳しい情勢を乗り越えるために持続化給付金や補助金などを活用した工務店も多く、持続化給付金の業種別給付実績では建設業が全業種で見ても突出して高い数字であった。
こうした政府の支援や金融機関の無担保・無利子融資(ゼロ・ゼロ融資)による下支えにより、倒産件数は見かけ上は一時的には抑制した。しかし、このゼロ・ゼロ融資の返済も2023年7月から開始。その影響により負債に圧迫されての廃業が増加傾向にあり、この先受注減、利益減、返済増となると2023年は2022年に引き続き倒産増が予想される。
デザイン力は工務店にとって差別化の源泉
特にコロナ禍が拡大するにつれて建設業は大幅に減収した。これはコロナ禍を直撃した飲食店やサービス店の新規出店の手控え、新築住宅・リフォームなどの小規模工事の中止や延期が響いたという。中小企業での経営課題でのアンケートでは、「資材高騰」がトップで、「人手不足」「電気料金の高騰」が続く。
こうした中小工務店の苦境が続く中で目指すべきところはどこにあるのか。
「現実的には独自性が低い部分を高くしていくべき。具体的には差別化を図る試みが重要だ。実務では、商品・集客・セールスの面で独自性を発揮していくべきで、デザイン面でも言うまでもない。しかし独自性を自社HPにアップすると必ず同業他社は模倣する。そこで模倣困難性が高く、持続的な差別化を続けていかなければならない」(大場代表)。
また稲葉会長は、「真っ先にいいデザインを目指すべき。理由は、デザインが受注活動の優先順位に挙げられるからだ。優れたデザインの施工に乏しい中小工務店としては、対応力ではなかなか難しい。進行管理が効果的でない場合、予算超過、工期遅延が発生する可能性がある」とデザイン力の重要性を指摘。続けて、「デザイン力は中小工務店の競争力を圧倒的に向上させることができる。過去のデザインの成功事例から見ても、顧客の評価を高め、そして安定的な顧客獲得につながる」と語った。
しかし、デザイン性の高い住宅を施工することは、この人材不足時代では容易ではない。稲葉会長は「中小工務店は施工経験が少ないと対応が難しい。しかし当社はデザイン住宅を営んでいくなかで、何があったら施工しやすくなるのか、逆にしづらくなるのかを日々研究した。その中である種の規則性があることに気が付いた。その規則性に則り、デザインをして施工するよう社内が動き出した。そこで規則性を重視したマニュアルを用意して、皆がそれに沿って活動している」と語った。
さらに建築家の渡辺純氏は、建築・住宅において「デザイン性が高いことは非常に重要なことだ。デザインこそが顧客の最初の提案で注意をひく部分になる。そして顧客にとって新築住宅の建築は一生に一度の大きな買い物であるからこそ、良いデザインは背中を押す効果をもたらす」と力強くデザインの重要性を述べた。
工務店業界の受注は二極化
現状、大手ハウスメーカーや工務店でも、確実に受注を獲得しているところとそうでないところに二極化している。例えばある大手ハウスメーカーでは、住宅展示場での受注は減少したが、その代わりにウェブ経由の受注を大幅に伸ばした。コロナ禍での受注戦略をウェブと紹介の2点にシフトしたところ好結果を残せた事例があった。また最先端ツールを駆使したオンライン集客、商談も展開している。そこで工務店としても「受注力の強化」「メディアミックスによる集客力の強化」「付加価値による販売単価のアップ」の3点の経営戦略が必須と指摘した。つまり、工務店業界としては少人数かつ高生産の経営戦略が重要になるわけだ。そして、今後の工務店業界として重要な施策として「受注力付ける(一人当たりの売上の伸ばす)」「モデルハウスを持たない営業手法の実践」「高単価のデザイン住宅を販売」「少数精鋭の部隊を設置している」の4点を挙げている。
Style Designの稲葉龍也会長は下請けの大工からスタート。限界を感じたときに、ナックにと出会った。そこで経営の「イロハ」を学び、当時社長であった稲葉氏、現場監督そしてパートの3名という少人数体制にもかかわらず12棟の受注に成功した。その後、「少人数と多店舗展開」を軸とし、今では高単価のデザイン住宅を年間50棟の受注に成功する工務店として成長した。
なぜ茨城県を中心にモデルハウスなしで受注を確保しているのだろうか。同社の創業当時をさかのぼってみると、2006年の同社の前身(イナバ総合建物)の時代では、社長のマンパワーでの経営、低単価(1300万円台)、1店舗のみでの活動であった。現在のStyle Designは、社長がいなくても回る仕組みを構築、ローコスト受注をやめ、今は高単価での受注にシフトし、4店舗で展開するなど創業と現在ではずいぶんと改革した点が多い。時代や顧客の変化に応じてスピーディーに会社が変化をし、トライアンドエラーを試み改善した結果、茨城県を中心としたエリアから選ばれる工務店づくりに成功した。
Style Designの成功ノウハウを中小工務店に提供
そこで今回、ナックは、Style Designのノウハウをより拡大することを決定。同社と業務提携を結び、メタバース展示場にも展開できるデザイン性の高い規格住宅と集客・接客ノウハウを詰め込んだ中小工務店向けのノウハウ商品「i-Style(アイスタイル)」の提供を開始した。
Style Designの規模は4店舗、スタッフ15名で売上高は15億円。ナックとしてはいきなりここまで目指すのではなく、まず1店舗をスタッフ3名で確実に運営し、年間10棟規模を受注できるような高生産経営を目指すべきと提起した。
Style Designが成功した要因
一方、大場代表は経営には、①社会性(社会的課題を解決し、社会に受け入れられるビジネス)、②革新性(新たな価値・差別化ビジネス)、③事業性(健全な収益性のあるビジネス)の3つの要素があるとした。「i-Style」はこの3つの要素をどうカバーしているのだろうか。まず社会性は、モデルハウスをもたないことがStyle Designの大きな特徴だ。それは過剰供給をしない会社につながり、カーボンニュートラルに対しての意識づくりを全体で行っている。
次の事業性では、デザイン性の高い住宅を供給することで、正社員とパートも含めた強い組織を構成していく。3番目の革新性だが、これはDX(メタバース展示場、バーチャル展示場)による接客を展開し、新人でもできるデザイン住宅のプラン提案を仕組化した。
社長のマンパワー経営への依存から脱却を
それでは、「i-Style」の商品内容を具体的に見てみよう。まず強化項目の一つ目としては、一つの目標に向けての組織づくり「チームビルディングの強化」がある。これは工務店でよくありがちなことだが、社長依存型のマンパワー経営も決して少なくない。このマンパワー経営の脱却を図り、チーム戦での受注戦略を自社に落とし込み、一人ひとりが機能する組織づくりをする稲葉会長方式のチームビルディングを研修で学べる。稲葉会長はワンパワーのみの経営から脱却できた理由を「仕組みの上に人を乗せた」と語る。この形式であれば100点は取れなくても70~80点の経営で進められるという。もちろんそれは容易にできるのではなく、「トライアンドエラーを繰り返した」と稲葉会長は当時の試行錯誤を振り返る。
次に「i-Style」の特徴として注目住宅、規格住宅のいずれも対応できるデザイン住宅を実現。規格住宅では、クラシック(カフェのようなくつろぎを自宅でも感じられる)、カントリー(ラフに使える土間空間をそのまま室内に取り込む)、エタージュ(ワンフロアで家族がつながり、動脈を短く過ごせる平屋)、リトリート(南面の中庭とつながるようにLDKを配置)をラインナップとして取りそろえた。「i-Style」には、テキサス大学終身教授資格のある渡辺純氏監修の高いデザイン性を実現した規格住宅が入る。今後追加していく注文住宅のラインナップにおいても監修を予定し、より一層「i-Style」をアップグレートしていく予定だ。
「デザイン性が優れた規格住宅の図面データ」などのノウハウを盛り込んだ商品「i-Style(アイスタイル)」を提供開始
また規格住宅以上にこだわりの住宅を希望する工務店に対しては4カテゴリー(ヴィンテージ・ナチュラル・リゾート・ホテル・シンプル)の10種類の注文住宅も実際の図面や参考実行予算と合わせて用意した。
今、デザインに対して顧客からどのような声が上がっているのか。稲葉会長は、「特に多いのはオリジナリティがほしいという声だ。数千万円の買い物であるため、それに見合う高級感と居心地の良さを求めている。最近の顧客はデザイントレンドにすごく敏感で、細心のライフスタイルやテクノロジーが盛り込まれたデザインを魅力的に感じている。だからこそ中小工務店も顧客のニーズに応じたアップデートされたデザイン提案が求められている」と解説する。
注文住宅の実際の図面や参考実行予算も用意
デザイン力の重要性が今後のトレンドとなっていく中で、今回の新商品である「i-Style」は中小工務店にとってどのような効果をもたらすか。大場代表は「まず一つ目は即効性、次はブランディングがポイントになる」と大きな期待を寄せる。
このほかDX接客としては、全規格住宅のVRを使用することで実際のモデルハウスを建設しなくとも顧客に疑似体験を提供。また全規格住宅と一部の注文住宅がバーチャルハウスとして設置している「メタバース展示場」を使用することも可能で顧客に説明しやすい仕様になる。
今回のノウハウ商品「i-Style」の特長は主に5点ある。① 経営の基本である「ヒト・モノ・カネ」の強化②チーム、組織づくりの構築③ Style Designの商品・集客・営業を自社へ④エリアでお客様から選ばれやすい工務店経営⑤稲葉会⾧による経営指南を受けることが可能になる。
今、中小工務店業界は様々な外部的要因で苦境に立たされている。そこで成功事例をどん欲に吸収し、自社の成長を促すことは有力な戦略で、「i-Style」は有力なツールと言っても良いだろう。