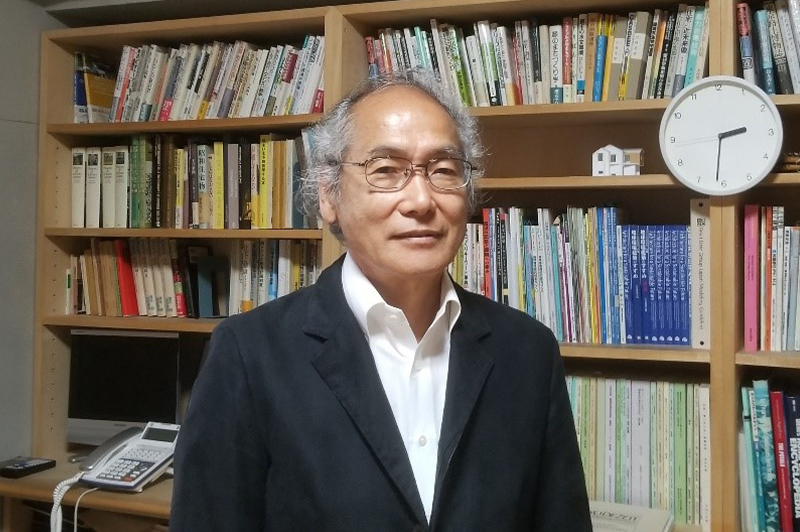日本の商業施設を支え続ける、元鹿島の技術者
鹿島建設で、30年以上にわたり商業施設の設計に携わった奥平与人氏。「ニチイ」(現イオングループ)や「ダイエー」など、有名な商業施設の企画、設計を数多く手がけてきた。
また、長年の商業施設で培った経験・知見から、施設の耐用年数をあらかじめ想定し、その期間に見合った合理的な材料・工法で建設する「有期限建築」という考え方を日本で初めて提唱したことでも知られている。
定年後は大学教授などで活躍したのち、現在は(公社)商業施設技術団体連合会で副会長をつとめ、後進の育成に励んでいる。
73歳という高齢ながら、今なお現役で活躍できる秘訣や、鹿島建設での商業施設に携わってきた経験談などについて語っていただいた。
パルコやニチイ、ダイエーなど、様々な商業施設を手掛ける
――鹿島建設にはどういう経緯で入社されましたか?
奥平与人氏(以下、奥平) 私が大学院生だったとき、まだ学生運動が華やかだった時代のことです。建築家の先生のゼミに入っていたこともあり、当初はゼネコンに入る考えはなく、あるアトリエ設計事務所で修業する予定でした。
ただ、当時お付き合いしていた女性と結婚することになり、周囲からも大手で月給が出るところに就職して欲しいと言われまして。
そんな折、鹿島建設の設計部長自らが大学にスカウトに来て、ゼミの先生からも「奥平くん、会ってみなさい」と勧められたので面談してみたら、その場で鹿島建設への内定が決まりました。
――商業施設を手掛けられるようになったのはいつから?
奥平 設計要員として建築設計本部に配属され、入社から1年ほど経った頃、パルコの商業施設の社内コンペがあったんです。
当時はまだ、鹿島建設では商業施設グループが確立していなかったので、人材集めのためにコンペを実施していた背景があるんですが、応募してみたところ上司から「お前、パルコのチームに入れ」と言われて、それからはずっと商業施設一筋ですね。客先が決まっている実施設計ではなく、提案型の営業設計を約10年間手掛けていました。
――大変だった思い出はありますか?
奥平 お客様は保有されている土地に対してハードな条件を求められます。最初にイメージ図を示した上で、「この土地には、こういう商業施設を建設すればメリットがありますよ」「お客様の持っている土地であればこういう商業施設が望ましいです」ということを、A2の厚いミューズボード10枚に提案内容をテーマ別にわかりやすくプレゼンすることを心がけていました。
このような形で、毎週テーマを決めてプレゼンを実施していたのですが、徹夜による疲労から肺に穴が開いてしまって、2か月間休みを取ったこともありましたね。
そうこうしているうちにションピングセンターやスーパーなど、本格的な商業施設の設計も手掛けるようになりました。当時のダイエーをはじめとする多くのスーパーなどとお付き合いを深めていきました。
――その後は、どのような商業施設を手掛けられてきたのでしょうか?
奥平 かつて存在していたニチイというスーパーから「軽装備店舗を建設したいからサポートしてほしい」との話がありました。その際、「ハード面は任せるけれど、毎回同じ坪単価で計算できるようにしてくれ」との要望もあったんです。
そんなことを言われても、建設する土地によって坪単価は変わりますから、作業としては大変でしたね。それでも正式提案することになり、その後はしばらくニチイの軽装備店舗の仕事が続きました。
ニチイはその後、旧マイカルグループ を経て、現在はイオングループになっています。マイカルグループは「マイカルタウン」という街づくりも行っていたので、私の仕事も商業施設から街づくりへと展開していきました。
愛知県新文化会館郡設計コンペ(名古屋)。1987年 一般公開コンペ優秀賞受賞。歴史的都市軸の上に劇場・シンフォニーホール・図書館等公共施設を立体的に配置し、人の流れと溜りをハイテク技術で表現した大規模複合文化施設。
同時期に、自由が丘の小さな店舗で、(一社)日本商環境設計家協会(JCD、現・(一社)日本商環境デザイン協会)のデザイン賞で入賞したことがあるのですが、それ以降は建築家やインテリアデザイナーの仲間との交流も増えていきましたね。
シェルガーデン(東京)。1983年 商空間デザイン賞受賞。
――施工側との調整で苦労したことは?
奥平 昔、現場所長の権限が特に強かった時代がありました。その時は、色々な現場の現場所長とやりあいましたね。
ただ、丁寧な説明をすれば、意見が通ることが多かったですね。東京メトロ・銀座線の稲荷町駅近くのペンシルビルを設計した時、オーナーには気にいっていただいたのですが、所長からはなかなか理解が得られなかった。
そこで所長に分かりやすいよう精巧な模型をつくって説明すると、「分かった。つくってやるよ」と言ってくれたこともありましたね。
上野三生ビル(東京)。1992年。
「有期限建築」を社会ではじめて提唱
――商業施設の魅力は?
奥平 「人間生活の中で最も楽しく他人と出会うことができ、新たな知恵を得る空間であること」だと私は思っています。
アニヴェルセル表参道(東京)。1998年KAJIMA DESIGN賞受賞。華やかな道化師の居るような都心部のブライダル施設。裏路地につなぐパッサージュを作りそこをカフェ・ブライダルイベントに使う。
ただ、そんな商業施設も永久に残るものではありません。鹿島建設には「100年をつくる会社」というスローガンがありますが、100年の建築をつくり、持続するためには変革も必要です。
そこで、施設の耐用年数をあらかじめ想定し、その期間に見合った合理的な材料・工法で建設し、機能が終わったら解体する「有期限建築」という概念を社会ではじめて提唱しました。
――「有期限建築」とは、具体的にどのようなものですか?
奥平 従来の建築が固定の建築形態を作れば終了するのに対して、有期限建築は常に変化する状況に適応していこうとする発想です。
従来建築との建設過程を比較すると、例えば従来建築では「土を掘る→大地にアンカーする→基礎をつくる→躯体を立てる→仕上げをする→設備を作りこむ→家具を入れる→サインをつける→備品を入れる」が一般的な建設過程です。
これに対して「有期限建築」のプロセスは、
- PROGRAMING 何をすべきかを知る(何をいつまでどんな方法で)
- PLANNING(PROCESS DESIGNING) 最適な状況を作る
- SELECTING 予算の中で部材、建材を選ぶ
- METHODING 部材の組み合わせ方を作る
- ORDERING 発注する
- ARRANGING 整地する
- DELIVERING/TRONSPORTATION 部材を運ぶ
- ERECTION/CONSTRUCTION 組み立てる
- MAINTAINING メンテナンス方法(取り替えるシステムを提示する)
となります。
――実際に手掛けられた「有期限建築」の事例は?
奥平 劇団四季から「地方の劇場だと出しものが入りきらない。だから、移動できる劇場を建築したい」との提案がありました。そこで、私は三週間で建設し、一週間で撤去できる劇場を提案しました。これは私にとってエポックでしたね。
また、東京デザイナーズウイークではコンテナを4段積み上げ、仮設会場のパビリオンを作りました。会期中に台風が来てさすがに入場中止にしましたが、パビリオンは全く問題ありませんでした。
2004年 デザイナーズウウィークのオフィシャルマガジンのトップを飾る(左)。 ツイストロックのみにより12m離れた4段目の40フィートコンテナを繋いでいる(右)。
千日デパート火災を機に創設された「商業施設士」
――これまでのご経験を活かし、現在は(公社)商業施設技術団体連合会の副会長をつとめていますが、この団体の役割とは。
奥平 1972年5月、大変な悲劇をもたらした千日デパート火災が発生し、行政から商業施設の安全・安心を高めていかなければならないという指示が強まっていきました。
そこで、社団法人日本店舗設計家協会や社団法人日本ディスプレイ業団体連合会、日本マネキン商工組合など、関係する9団体が集まり、商業施設の総合的技術の確立とその普及、商業施設の企画、設計、監理に係る技術者の認定とその育成などを目的に、1973年に設立しました。火災の2年後の1974年には、「商業施設士」の資格制度を創設しています。
現在は14団体が参加しています。2019年4月からは(一社)日本ショッピングセンター協会も加わりました。今までは商業施設の作り手側の団体が中心でしたがいよいよ、運営側も加わることで、より団体としての厚みも増してきたと感じています
――商業施設士とはどのような資格ですか?
奥平 商業施設士は、商業施設の企画、設計、デザイン、監理などの知識及び技能に関して認定する制度です。主に、店舗設計を行うデザイナー、設計、コンサル事務所、ゼネコン、大手のディスプレイ業やコンサルタントに勤務している人が取得しています。
――商業施設士に求められるものは?
奥平 商業施設士に求められる商業施設に関わる知識と技術は次の5点です。
- 人の暮らしや社会と直結する商業施設の役割と原理、歴史などの知識
- 社会の姿と密接な関係を持つさまざまな商業の形態とそれを具現化する商業施設の業態計画技術
- 商品・顧客の流れ、規模など、商業施設の目的を具現化する施設計画・設計の技術
- 商業施設が立地する地域、まち、他用途との複合施設などを計画する施設計画の技術
- 商業施設を適切な時間と費用で実現させる施工、監理の技術
各業務分野によって、求められる能力は異なります。
技術者は好奇心を失ってはいけない
――鹿島を辞められてからは、どのような仕事をされてきましたか?
奥平 もともと65歳まで鹿島で働く予定だったのですが、ある女子大学の非常勤講師も兼任していて、その大学から教授としてのオファーがあったので受けることにしました。住居デザイン研究室の室長も兼ねながら、若い人たちの教育を実務の経験を生かして指導していました。
大学を退任してからは、(株)岩村アトリエで「SDGsの商業版の事例作成」などに携わっています。
――奥平さんは現在73歳ですが、今でも精力的に働ける秘訣は?
奥平 若い時と比べると衰えは隠せませんよ。昔は街中を歩くときは小走りで客先に向かっていましたが、今はゆっくりと歩いています。
やはり、定年後は足腰を丈夫にするために歩くべきですね。私は今、朝と夕に犬の散歩で毎日2回歩いていますが、これが健康の秘訣です。
それに、早朝に起きて思いつくことをなんでも調べているのですが、高齢者になっても好奇心を失わないほうがいいですね。
――最後に、若き技術者たちに何かアドバイスを。
奥平 今の話の繰り返しになりますが、好奇心を抱き続けることが大切です。自分の人生を振り返っても、自分の業務以外のことについても興味を持っていました。
施工管理技士や現場監督も、現場を管理することはもちろん重要ですが、それだけでなく人やモノ、エネルギーなどをあらゆることを網羅して管理することも大事なつとめです。
ある評判の現場所長のもとにインタビューに行ったことがあるのですが、その方の現場を観察すると、毎朝、所長自らが朝礼を行い、資機材の整理整頓も徹底していました。誰が見ても分かりやすいよう書類も統一化され、ローコスト化にも成功していました。
他の現場から学ぶことは多いので、事務所にこもるのではなく、できるだけ多くの人と会うべきだと思います。