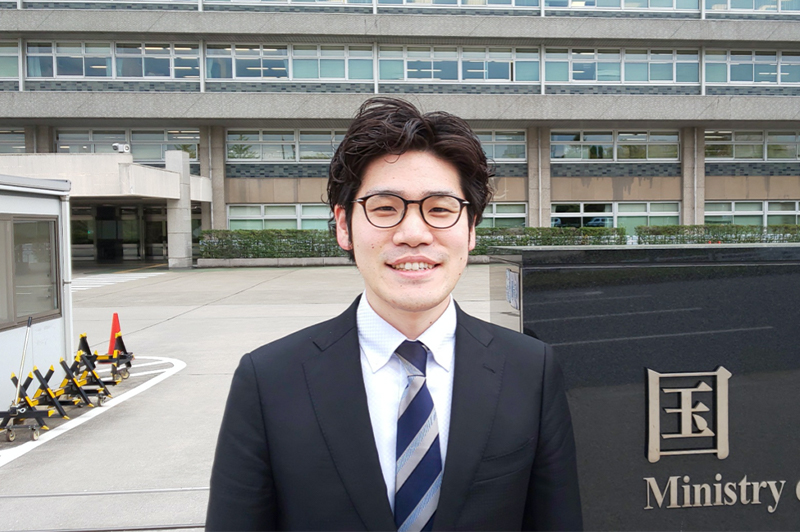ウェビナーでキャリア官僚を採用できるか?
国土交通省は、今年3月から総合職新卒向けのWEBイベント(セミナー・説明会、個別面談など、以下ウェビナー)を実施している。言うまでもなく、新型コロナウイルス対策のためだ。
当初は、霞が関に出向いて、イベントの様子を取材することにしていたが、こちらも地元県知事からの「首都圏への渡航自粛要請」を受け、あえなく断念。
じゃあと言うことで、オブザーバーとしてウェビナーそのものに参加し、取材することにした。国のキャリア新卒採用にウェビナーはありなのか。求める人物像などを含め、担当者の酒匂一樹さん(国土交通省大臣官房技術調査課技術調査係長)に話を聞いてみた。
「防災・減災」ウェビナーを傍聴
今回、傍聴したイベントは、4月17日に実施された中堅職員によるセミナーのうち、防災・減災をテーマにしたコマ。講師に立ったのは、入省20年目の中須賀淳・水管理・国土保全局治水課流域減災推進室企画専門官。荒川の治水対策、避難対策など、これまでの仕事を振り返りつつ、「防災減災に絶対的なゴールはありません」と述べるなど、事前防災の必要性、難しさなどを説明。チャットを通じ、参加者との質疑応答を行う時間もあり、少々突っ込んだ質問にもざっくばらんに回答していた。
ウェビナーといっても、イベントの内容は相対イベントとほぼ同じ。まず国土交通省から説明した後、質疑応答に入るスタイルだ。ただ、プライバシーに配慮して参加者の顔出しはなく、質問のやりとりはチャットで行うことになる。なお、個別面談にでは、顔出し、声ありでやりとりする。
首都圏、関西などから毎回約30名が参加
ウェビナー第一弾は、3月中旬に実施した業務分野(土木・建築・機械など)のもの。最も参加者の多い回では、定員である約30名が参加した。酒匂さんによれば、「これまで10回ほど実施してきましたが、軒並み定員いっぱいの参加者がありました。参加希望が定員をオーバーし、参加をお断りするケースもありました」と言う。定員を30名に設定したのは、使用するシステムの通信状況などを考慮した暫定的な措置だと言う。今回、ウェビナーには「Skype for Buisiness」を使用している。
新卒採用絡みでウェビナーを開くこと自体は珍しくもないが、国土交通省がやるとなると話は別だ。「よく決断したな」と感心する。ウェビナー実施の経緯について、「新型コロナウイルスのため、当初予定していたイベントが軒並み中止になりました。でも、学生のみなさんは情報が欲しい。どうにかできないかということで、急きょWEBイベントを実施することになりました。国土交通省では、本省と各地方整備局を結ぶTV会議を実施していたので、このシステムを流用することにしたわけです」と説明する。
参加者の所在地は、首都圏と地方がだいたい半々。国立大学、私立大学の割合は、ざっくり7対3ぐらいになる。「WEBだと、地方大学の学生も参加しやすいので、学生さんにとってもメリットがあると思っています。対面式のイベントになると、霞が関に足を運ぶ必要があり、交通費がかなりかかってしまいますので」と指摘する。
自分だけがしゃべると、お経を唱えているようになる
現在のスタイルでのウェビナーの難点は、参加者の反応が見えないことだ。ウェビナーでしゃべっているのは、基本的に国土交通省の人間だけだ。参加者が本当に聞いているのかどうかさえわからない状況の中で、カメラに向かって熱心に話しかけなければならない。それなりのメンタルと経験が必要そうだ。
一般的なWEBライブでは、主催者がチャットで視聴者のリアクションを確認しながら、話題を変えたりする状況が見られるが、それはあくまでプライベートな領域での話。国土交通省の採用ウェビナーともなると、参加者は、通常のセミナーと同様、かしこまってしまう状況があるようだ。
この点、「参加者の顔が見えない中で、自分だけがしゃべっていると、お経を唱えているような感覚に陥ることがあります。イベントの臨場感を出すために、あたかも参加者と実際に会話をしているようなスタイルの司会進行をすることもあります」と明かす。
個別面談形式であれば、お互いの顔が見えるので、この難点は解決できる。ただ、「われわれとしては、参加者になるべく多くの情報を提供することを主眼に置いています。その意味では、セミナー形式ではなく、個別面談の方が、より参加者が求める情報をお届けできます。ただ、物理的・時間的な限界がありますので、ある程度はセミナー形式に頼らざるを得ないのかなと思っています」というのが現状だ。
「君たちは良い時代に生まれたんだよ」
参加者から必ずある質問の一つが、転勤に関する質問だそうだ。ただ、「転勤がイヤだという学生が、国土交通省に入ることはまずありません。官公庁とは言え、土木の仕事である以上、現場での業務も経験しますから、どうしても転勤を伴います」と言う。「全国転勤OK」はキャリアになるための必要条件のようだ。
「あと多いのが、休日とか残業に関する質問です。霞が関はかつて『不夜城』と言われましたが、今はそんなことはありません。馬車馬のように働く文化はもうなくなっています。職場での残業の多寡は、管理職のマネジメント能力を評価する基準の一つにもなっていますので」。
「私は入省7年目で、不夜城の時代を知りませんが、その頃を知る上司の話を聞くと、『今の時代に入省してよかったな』とつくづく思います。学生にも『君たちは良い時代に生まれたんだよ』と言っています」と笑う。この点、霞が関も時代の流れに乗っているようだ。ただ、災害対応などの急を要する業務を担当している場合は、残業、休日出勤があることは覚悟しておく必要があるだろう。
ウェビナーには本省上層部も好意的
気になるのは、国土交通省のウェビナーが今回限りなのかということだ。
「今回は、新型コロナウイルス対策のため、代替手段としてWEBイベントを実施したわけですが、われわれ担当者の間では、WEBイベントというものを前向きに捉えています。実際にやってみると、『意外に簡単にできた』というのが率直な感想です。セッティングなど難しいものだと思い込んでいたので、やってこなかっただけだったと。これからも継続できるのであれば、やっていきたいと考えています。本省の上層部も好意的に見ています」と前向きだ。
「個人的には、国土交通省の働き方もこれから変わってくると思っています。デスクワークを中心とした仕事は、必ずしも一つの場所にいないとできないわけではないからです。ただ、土木、建設の魅力は、現場でものをつくることなので、その部分は大きく変わることはないと思っています」と付け加える。
連携、チームプレイできる人材を求む
最後に、求める人物像を聞いてみた。
「今の時代、複雑な課題を様々な機関と協力して解決するという、連携、チームプレイが求められるようになっています。とくに国土交通省の所掌する業務は関係者が多く、一つの政策を進めていくうえでも、他省庁、自治体、民間事業者など多様な主体に協力してもらうことになります。
また、国土交通省内で考えても、いくつもの部局が存在し、その中に法律、経済、土木、機械、建築など、バックグラウンドの違う人間がたくさんいて、それぞれが機能し合いながら日々課題解決に取り組んでいます。国土交通省の強みはその『多様性から生み出される力』だと思っています。
学生のみなさんには、連携、チームプレイの重要性を理解した上で、国土交通省に来ていただきたいと思っています。もちろん、個々の能力は重要ですが、いくら能力があったとしても、自分の力だけで仕事を進められることはありませんから。自分の考え・色は持ちつつも、他者を慮ったり、他の意見を尊重できる学生をこそ、われわれは求めているんです」。
「国土交通省で働きたい」という人は、この言葉を噛み締めた上で、試験に臨んでほしいところだ。