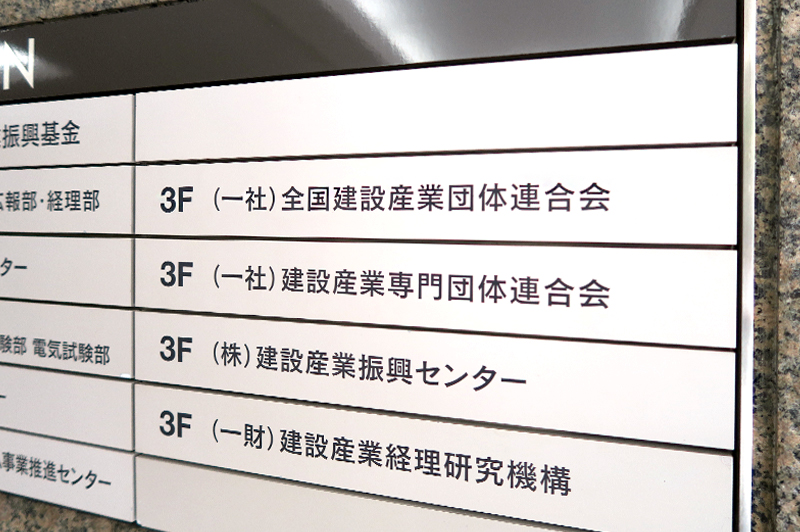「建産連政治連盟」を立ち上げた全国建産連
ゼネコン、サブコン、測量、地質など、建設業界の「職域」を超えた唯一の全国団体が、全国建設産業団体連合会(以下、全国建産連、渡邉勇雄会長)である。
全国建産連は、ICT技術やドローンを利用した建設業の生産性向上、そして建設技術者の人材育成に力を入れているが、その一方で最近、政治団体「建産連政治連盟」を立ち上げた。政治家に対して建設業の施策を訴えていこうというのだ。
政治とICTによって激変の時代を迎えている建設業界だが、その大海原の中、地域建設業はどのように舵を切っていくのか。全国建産連専務理事の竹澤正氏に話を聞いた。
職種を超えた唯一の全国組織「全国建設産業団体連合会」
——全国建産連はどのような団体ですか?
全国建産連 建設業の業界団体はたくさんありますが、そのほとんどは職種別の団体で構成されています。その点、全国建産連は違っていて、地方のゼネコン、サブコン、その他の建設関連業、上流部のコンサル、地質業者も加入する「職種」を超えた唯一の全国組織です。
建設産業版の「商工会議所」と言えばわかりやすいかもしれません。その分、会員内でも意見の統一などは難しい面もありますが、俯瞰的には同じベクトルに向かって共通項での課題解決を目指しています。
——存在意義は?
全国建産連 国土交通省の生産性向上、社会保険未加入対策や働き方改革など大きな施策は、個々の職種ごとでは解決できないことばかりです。そこで全国建産連という職種を超えた団体の存在意義が高まってきていると実感しています。
ただ、建設業界だけでは始末におえない課題も山積しています。そのため、政治との連携が必要になってくるわけです。
——政治団体「建産連政治連盟」を立ち上げた狙いは?
全国建産連 建設産業を支援する国会議員たちとコミュニケーションを深め、建設業は今後どうあるべきか、課題共有することが一番の狙いです。昨年の総会で建産連政治連盟の設立について承認を得ました。
——いわゆる「族議員」をつくると?
全国建産連 「族議員」と言うとイメージは良くないですが、本来は利権などと関係なく、悪い存在ではありません。むしろ、建設産業に理解が深い、専門性の高い国会議員の集団が、今こそ必要だと考えています。
専門的な知識があるからこそ、政治的施策の妥当性も判断できます。誰とは言いませんが建設業に無知な政治的な施策を打ち出されると、建設業界も国民も困ります。有意義な施策のためには、行政や業界内だけでは限界があるので、これから全国建産連として、国会議員も交えた勉強会に取り組んでいこうと思っている次第です。
建設業に精通した国会議員を増やしていく
——建産連政治連盟で何を目指す?
全国建産連 全国建産連の全国会議でも必ず言及されるのは、住宅、都市、道路、その他交通基盤の社会資本の整備の「あり方」です。端的に言うと、人口減少社会である国づくりのための長期的なプランとして「全国総合開発計画」的なビジョンが求められています。
地域建設企業は、国の将来的な方向性が不明瞭であるため、常に不安を抱きながらの経営を強いられています。国が示した計画に基づいて、新設が必要なインフラや劣化した橋やトンネルの問題などについて自治体で討議し、地域建設企業がその整備計画を誠実に実行していく、そうした道筋の見える体制を整えることが、政治連盟としての願いの根幹です。
——自民党の「公共工事品質確保に関する議員連盟」(品確議連)の国会議員との連携もある?
全国建産連 品確議連はありがたい存在で、改正品確法の制定後、建設業界には次々と新しい動きが出てきました。われわれ全国建産連も今後、本格的に法律が必要になってくれば、当然、品確議連の先生たちにお願いすることも考えています。「建設業界が専門領域です」と断言していただけるような国会議員を増やしていくことが大切です。
ただ、一口に建設業界と言っても、スーパーゼネコンとローカルに根ざした地域建設企業では、お願いしたい施策も変わってきます。両者とも建設業法では同じ立ち位置ですが、全国建産連としては基本的に、地方の視点を強化していきたいと考えています。
たとえば、現行法令では、会社同士での現場監督や技能労働者の貸し借りはできないことになっています。しかし、俯瞰的に見ると、ある地域で仕事が捌ききれないほど多忙で、別の地域は仕事がなく閑散としている状況があれば、本籍を維持したままダイナミックに技能労働者を移動するなど、地域建設企業の連携によって乗り切ることが可能です。
こうした合理的かつ持続可能な地域の建設業界のあり方について、法改正も視野に、いろいろな視点から模索していくことが、建産連政治連盟に科せられた課題です。
国会議員と連携して、建設業のあるべき姿を模索
全国建産連 老朽化した社会資本整備の維持も危機的な状況です。戦後営々として築き上げてきた社会資本の老朽化・劣化について、建設業界や関係行政の関係者は深刻にとらえていますが、日本国民の多くの方々が危機感を感じているとは思えません。このままだと大変なことになるでしょう。
現在、社会資本整備費用は年間およそ6兆円ですが、膨大な公共ストックは一気に解決できません。今後10年以上かけて維持修繕や更新を行うインフラと、それを諦めなければいけないインフラに「仕分け」していく必要に迫られるでしょうが、その際、経済合理性をもとに地域住民や国民に選択してもらうのは、政治家の仕事です。そういう意見交換の場としても、建産連政治連盟と国会議員との勉強会は期待が大きいです。
——公共事業の増加も訴える?
全国建産連 地方の公共事業が削減され、地方自治体によっては、力のある地域建設企業が存在しないところも出てきました。そうなると、地域の防災力や応災力、除雪という観点からすれば、建設業の衰退はその地域の弱体化も意味します。
建設会社は民間企業である一方、地域のセーフティーネットの役割も果たしています。しかし、仕事がなければ存続することは出来ません。建設会社に対してどのような供給力を求めているか、建設会社はどういう形で地域社会に貢献が可能なのか、従来の建設関係者だけの会議や全国建産連だけで考えるのはもう限界です。
これからは他の地場産業との交流や行政や国会議員と連携する中で、建設業はかくあるべきという意見をまとめていきたいと考えています。今後、定期的な勉強会を開催していきますが、一般社団法人の顔とは別に、政治団体のスタイルで政治へアプローチしていきます。
——「公共工事は税金のムダ」という批判については?
全国建産連 特に3月の工事、年度末工事については誤解が多いです。よく予算を使い切るためだと文句を言われる方がいらっしゃいますが、それは間違いです。
地方自治体の公共工事は新設が優先され、年度後半になると古くなった道路の維持保全費の確保にメドが立ってきて、そこで年度末に道路の維持保全工事をしているだけに過ぎません。意味のない公共工事など存在しません。本来、年度をまたいで4、5、6月の間に工事ができれば望ましいですが、最近は国や地方自治体が工事の平準化を進めたことで、年度末の工事はだいぶ減ってきました。
ビルやマンションの民間工事は、建築構造物の計画が決まると、共同溝があれば別ですが、ガスや水道、電力を供給するために道路を掘り返す必要があります。それは大きな道路に面していることが多く、たまたま年度末に重なって誤解されることもあるでしょう。いずれにせよ、こうした建設業に関する偏見も工事側の説明不足と関係者の勉強不足が原因ではないでしょうか。
全国建産連でドローン操縦者も育成
ドローン講習の様子(写真提供:全国建設産業連合会)
——i-Constructionについて、全国建産連での取り組みは?
全国建産連 国土交通省が掲げているi-Constructionを進めていけば、少人数で多くの業務を担う「多能工」の道へ必然的に向かっていくでしょう。建設業は29業種に区分されていますが、従来10人分だった業務を7人で実施しなければ、これからの人口減少社会を乗り切ることはできません。品質を担保しつつ、マネジメントもできるような、技術的なイノベーションと多能工を組み合わせた時代が到来すると思います。
企業単体としても、100あった仕事が将来70に減っていくとなれば、受注量を拡大するには、多能工的に対応できる仕事の幅を拡げる必要があります。受注量を確保できなければ、建設会社で働く現場監督や技能労働者に対して給与を払えず、会社を持続できません。そういう点でも、建設業の区分は29業種のままでいいのかなど建設業法の改正も視野に、立法府の国会議員に理解していただかなくてはなりません。
——個々の建設会社も変化しなければならないということですね。
全国建産連 そうです。小規模な地域建設企業でも、たとえば、ICT(情報通信技術)に無関心のままではいけません。地域や企業の規模に適した形でICTを展開する必要があります。ICTと言っても種類はたくさんありますが、コスト削減、生産性向上、働き方改革、応災力の観点から、全国建産連ではドローンが最も有用なツールの一つだろうと考え、昨年3月からドローン操縦者の養成を開始しました。
ドローンを使えば、機能として簡単に工事状況を俯瞰的に見られるので、熟練すればインフラの維持管理にも応用できますし、災害現場では消防、警察、自衛隊より先に建設会社が道を切り開く必要があり、危険防止のためにもドローン操縦者の養成は企業と地域に貢献できると思います。
カリキュラムは現在、DJI JAPAN株式会社が主催するドローン操縦者の民間資格を使わせていただいています。今後、持続的に100名を超える資格者を輩出できるようになれば、国土交通省から管理団体として認定を受けることも可能になるので、最終的には全国建産連の資格を創設したいと考えています。
今年は栃木県で操作体験、10時間のドローン講習、資格試験をパッケージで実施しました。茨城県、埼玉県での実施も控えており、 全国建産連の会員から「ドローンを実際に触ってみたい」「操作方法を知りたい」という声に応えていきます。今後は、関東ブロックをモデルケースとして、ドローン操縦者の育成について順次全国展開を図っていきます。