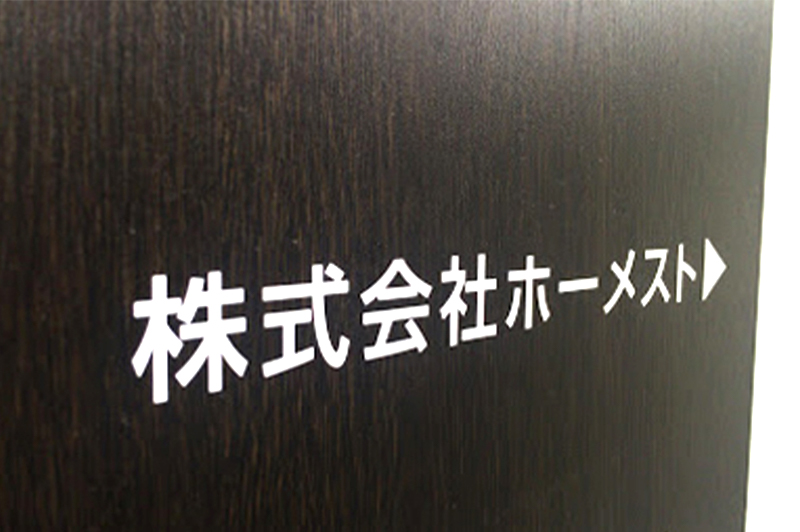シェアハウス「かぼちゃの馬車」の建築請負業者、ホーメストが破産
女性専用シェアハウスの「かぼちゃの馬車」の建築請負業者であったホーメストは11月27日、東京地裁に破産を申請した。申請代理人は井田大輔弁護士(赤坂総合法律事務所)ほか2名。負債総額は2018年3月期決算時点で9億1,175万円。
新築木造住宅ブランドとして有名なホーメストが破綻した理由は、事実上「かぼちゃの馬車」の運営会社であるスマートデイズの専属下請と化していたからだった。
ホーメストが入居するビル
同社の2016年3月期決算は売上高13億8,928万円と、一時は好評だった。しかし、2018年に入るとスマートデイズの経営難が表面化。施工契約を結んでいたシェアハウスオーナーからの建築代金の支払いがストップし、資金繰りが困難を極め、破産を申請することとなった。
シェアハウスにのめり込んだ結果、スマートデイズへの依存度が高まり、一時的には売上や利益が向上したものの、スマートデイズとともにホーメストも破綻した形だ。建設業界は重層下請構造であるが、ある専門工事会社は「1社依存度は25%以内に抑えなければ危険水域になる」と断言する。
ホーメストの破綻劇について、エム・テック破産に引き続き、東京商工リサーチ情報本部情報部の増田和史氏が解説する。
竹下景子さんのCM、2度の破綻でも残ったホーメストブランド
バブル世代にとっては、ホーメストは懐かしいブランドに思えたのではないだろうか。木造住宅の大手・殖産住宅相互の新築住宅ブランド「ホーメスト」が前身。同社は、竹下景子さんが演じるテレビCM「ホーム、ホーマー、ホーメスト」のキャッチコピーで知られていた。
https://www.youtube.com/watch?v=dUjzdh18St8
その後、殖産住宅相互は民事再生を申請、ホーメスト部門は建築リフォームのペイントハウス(現・ティーエムシー)に譲渡。ペイントハウスも破産した際、2006年9月に都内の不動産関連業者がペイントハウスなどから事業譲渡を受け、ホーメストが設立されたという複雑な経緯がある。
つまりホーメストは運営会社が2回破綻しつつも、ブランド力が高く評価されて生き残った形だ。
スマートデイズ社長とホーメスト社長の関係
「ホーメスト」にはブランド力があった。では新築住宅、木造住宅が中心であったホーメストがなぜ、シェアハウスを展開するようになったのか。
シェアハウスの業界筋は、スマートデイズの大地則幸前社長とホーメストの八島睦社長の人間関係によるものだろうと推察する。大地氏は、1983年千葉県出身、国際理工専門学校建築設計課を卒業後、大手ゼネコンの清水建設、レオパレス21などを経て、株式会社スマートライフ(現・スマートデイズ)を設立したという経歴の持ち主。
一方、八島社長は、北海道札幌市出身。大工を目指して高卒で東日本ハウス(現・日本ハウスホールディングス)に就職したが、配属は営業職。24歳で営業課長まで出世したため、相当貪欲に飛び込み営業をこなしたと言われている。ホーメストの前身会社に就職し、その後、神奈川県相模原市のサカエ建設東京支社長をつとめているが、どこかで大地氏との接点が生まれたのだろうと観測が生まれた。「実はシェアハウスのノウハウは、サカエ建設で学んだのではないか」(業界筋)
実際、八島氏がホーメストの社長に就任したのが2016年、その後、シェアハウス案件にのめり込む。しかし2016年以降の2017年3月期には売上高10億3054万円、経常利益4,476万円と落ち込み、2018年3月期の売上高は24億6,242万円急拡大するものの、経常利益が1億8,159万円の赤字と経営は急激に悪化してきた。この時期からはシェアハウスの回収不能の多発で資金繰りの行き詰まりがほぼ表面化していた。
シェアハウスの建築はホーメストを指名
あるシェアハウスオーナーはこう指摘する。
「シェアハウスの工事会社はいくつかありましたが、事実上ホーメストを指名してくるのと同然でした。ですから、我々オーナーはホーメストと建築工事請負契約を結んだのです。しかし、私たちシェアハウスオーナーからすれば明らかに高く、それはおかしいと思っていました。」
完成したシェアハウスのサブリース契約は、シェアハウスオーナーとスマートデイズで結ばれる。仕組みは至ってシンプル。スマートデイズは投資家向けにシェアハウスが建設可能な土地を探し出し、これにホーメストなどを使ってシェアハウスを建築させ、投資用不動産として投資家に販売する。スマートデイズは賃料を保証し、投資資金をスルガ銀行との提携ローンにより、普通のサラリーマンでも気軽に不動産投資を行えるようなビジネスモデルを構築した。8%という高利回り、しかも30年保証であるがゆえに飛びついたワケだ。しかし、今や都内でも8%の高利回りの不動産物件などはほぼ存在しない。
年収600万円~1000万円クラスの一般のサラリーマン、公務員、医者がなぜ、このシステムの罠にひっかかったか大きな疑問だ。
「シェアハウスオーナーはシミュレーション結果の説明を受け、向こう30年毎年8%の利回りを受け取ることの話はあったと思います。稼働率が高ければビジネスモデルは成立していましたが、下手すると50%の稼働率でした。シミュレーション通りに行かなかったところに問題がありますが、これが意図的に行った詐欺にあたるかどうかの判断は難しいところです。」(増田氏)
シェアハウス「かぼちゃの馬車」のビジネスモデル
「かぼちゃの馬車」のスキームそのものは、“不動産知識がなくても不動産投資が出来る”ことが謳い文句だった。大地氏は、著書『「家賃0円・空室有」でも儲かる不動産投資———脱・不動産事業の発想から生まれた新ビジネスモデル』により、シェアハウスのビジネスモデルを紹介しているが、その後、「この本は私が執筆していない。ライターが執筆した」と吐露している。スルガ銀行は投資家の資産が仮に100万円というところを1,000万円に改ざんし、1億円や2億円を貸し付けた。明らかに過剰融資であった。問題の多いスキームであったことは明確であった。その点について増田氏は次のように解説する。
「年収500万円~600万円の人に対して一生返せない金額をスルガ銀行が貸し付けたことにも問題がありますし、シェアハウスのスキーム自体がずさんでもありました。
キーポイントはセミナーです。スマートデイズがセミナーを活発に行い、サラリーマン投資家を勧誘していったのです。“みなさん、こんないい土地にシェアハウスができました。ここは入居率100%になるに決まっています”と煽ったのです。」(増田氏)
しかし、「かぼちゃの馬車」の魔法は解けた。スマートデイズは2018年1月、契約していたサブリース賃料を支払えないことをシェアハウスオーナーに通告。その後、スマートデイズは破産した。そこでシェアハウスオーナーもホーメストへの工事代金支払いを一部止めていた。
ホーメストはこれに対して、工事代金入金を要請、一部オーナーに対しては工事代金支払いを求める提訴も行なった。
シェアハウス建築にあたっては、契約時に1/3、上棟時に1/3、完成時に1/3の代金をそれぞれ支払うこととなり、ほかの建設工事代金支払い慣習と同様な形式。「最終の残金を支払う前にスマートデイズのずさんな実態が明らかになり破綻して、シェアハウスオーナーは支払う必要が無いと考えたようです。」(増田氏)
「外国人の入居を促進すべき」というシェアハウス会社
10月26日、東京地裁の口頭弁論でシェアハウスオーナー側は、適正価格を逸脱した工事請負契約であり、「詐欺取消」と主張、スマートデイズの「詐欺的スキーム」にホーメストも荷担したため、同社への損害賠償も辞さない構えだった。次の弁論は2019年1月を予定していたがホーメストの破産申請により、裁判は中断。ホーメスト側の破産管財人が業務を引き継ぐ。オーナー側の代理人の谷合周三弁護士は、「今後の破産管財人の調査でホーメストとスマートデイズのキックバックにかかわる内部調査が明らかになることが期待される」と話す。
「今後は破産開始決定が下りる見込みですが、破産管財人が売掛金の回収をすすめていくでしょう。訴訟中のシェアハウスオーナーに対しても回収を求める可能性があります。」(増田氏)
しかし、ホーメストとスマートデイズの間でキックバックがあったとしても、シェアハウスオーナーがまったく支払わなくて良いかと言えば疑問視する声もある。この裁判はまだまだ長引きそうである。
また、あるシェアハウス会社からは、「かぼちゃの馬車を引き受けても良い。そして家賃も保証する」との話もある。そのシェアハウスの社長は匿名を条件にこう説明する。
「これから日本には外国人がどんどん入ってくる。オーナーが外国人の入居をOKすれば、弊社にはノウハウがあるから引き受ける。家賃も問題なくシェアハウスオーナーに支払う。しかし、今はシェアハウスの批判もあるので弊社自らは動けない。周囲、弁護士、オーナー一同から何とかして欲しいという声が高くなったときに動く。」
シェアハウス会社は、解決策として外国人入居をあげた。
下請のビルダー・工務店にも影響
ところでシェアハウスの実際の建設にあたって、ホーメストは直用というスタイルを採用していなかったようだ。エム・テックと異なる点は技術者がいなかった点だ。
ホーメストは、ホーメストグローバルネットを設立、全国のビルダー・工務店と技術・情報・ノウハウを共有するグループを形成していた。これが事実上の工事担当会社である。「本社には営業マン、総務関係者くらいで社員も23名ほどです。」(増田氏)
ホーメストが使っていた下請に対しては、「支払いはシェアハウスのオーナーから回収するからそれまで待ってくれ」と伝えていたという。しかし、裁判も長引き、下請に工事代金を払えなくなっている。
「下請は3月以降、どれだけ返してもらっているか分かりませんが、取りっぱぐれになったケースもあります。」(増田氏)
一定数、全国のビルダーや工務店に影響がありそうだ。実はシェアハウス問題では、ホーメスト以外でもシェアハウスオーナーに工事代金の支払いを求めた提訴や仲裁を申し立てている建築業者が複数ある。そのため、今後、シェアハウス問題はさらに拡大する可能性がある。つまり、第二、第三のホーメストが今後、破綻する可能性はあるのが現状。
一気にシェアハウスを大量に供給したため、不良債権化してしまった。たとえば、東京・足立区が区内のシェアハウスの実態を調査したところ、建設中を含めて313棟が建てられている。そこで足立区は、違法ビジネス転用防止のため独自規制を実施することを決定したばかり。しかも、スルガ銀行はシェアハウスオーナーに対して、1億円~3億円を貸しているが、こちらも不良債権化する可能性が高く、事実上棚上げになっている。
不動産業者には、投資用マンションとともにシェアハウスを保有しているところもある。規模的に売上100億円の不動産会社でシェアハウスに大きくのめり込んでいるところや取引している建設会社も今後、要注意だと増田氏は指摘する。
1社専属下請の恐ろしさ
今回のホーメストの破綻の教訓について増田氏はこう説明する。
「ホーメストの運営会社は2回倒産しても、ブランドとして残ったわけですから、その価値を大事にすべきでした。安易にシェアハウスの拡大に乗ったところに問題がありました。1社専属下請になると営業をしないから楽です。
ところで破産したエム・テックの1社専属下請は今大変なことになっているのではないでしょうか。今回も、スマートデイズの依存度を高めたホーメストは事実上、下請みたいなものです。“仕事が来るから会社としては安泰だ”と考える下請もおりますが、これは怖いことです。ですから、元請が潰れた時のリスクヘッジをするため、取引先は分散することが定石です。ところが売上を追求すると、安易な方に流れがちです。」
建設業界は実は1社専属下請が他の業界と比べて多い。割りがいい仕事に比重を置くことにより、売上を高める手法はあるが、1社専属下請の危険性はもっと周知されてもいいだろう。