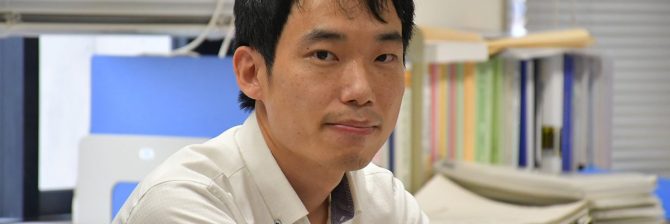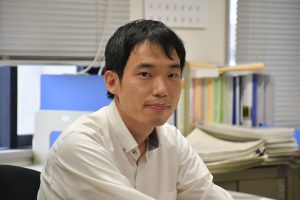シンガポール政府で半年ほど情報収集
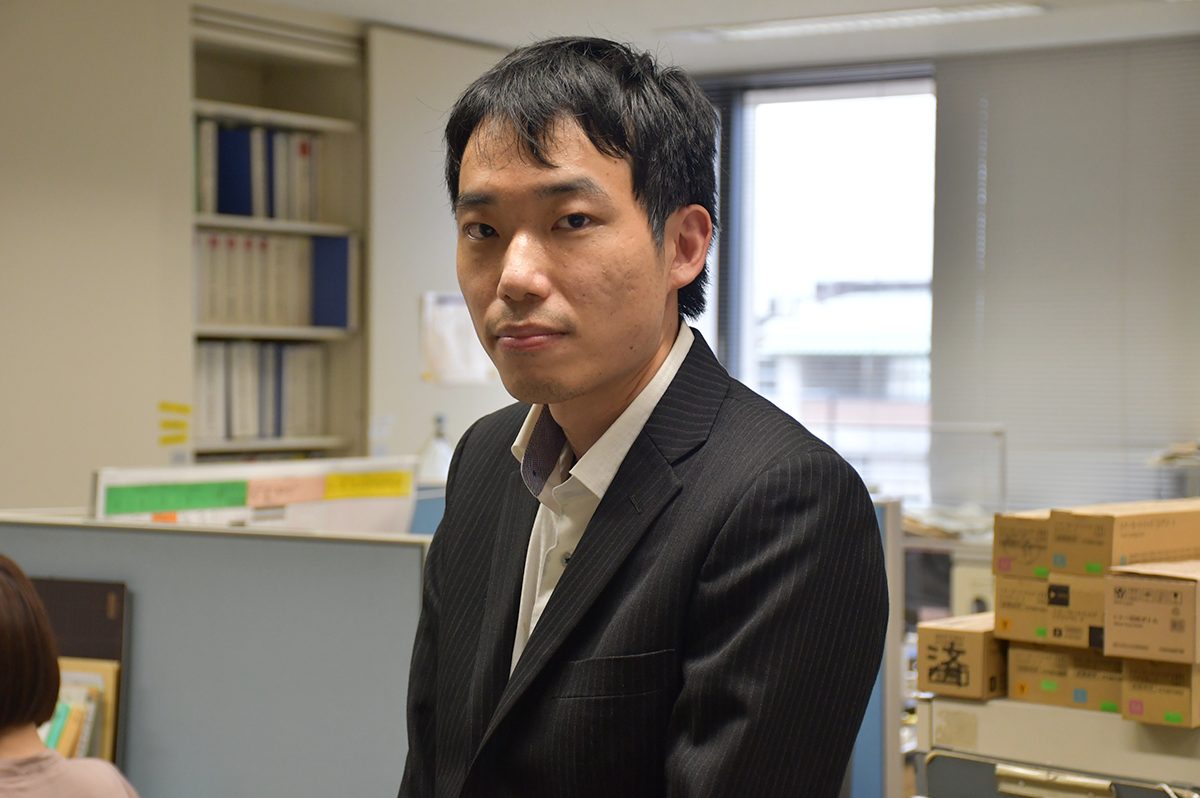
――オリパラの次は?
龍馬さん 本省に戻って、総合政策局の海外プロジェクト推進課に所属して、半年間ほどシンガポールに行きました。技官としては、初のシンガポール派遣だったようです。シンガポール政府のURA(都市再開発庁)とかJTCコーポレーションに入って、情報収集、発信とかをしていました。URAは都市計画とかを行う政府機関です。JTCコーポレーションは、あえて日本で言うと、UR(UR都市機構)みたいなもので、政府機関なんだけども、国土の10%ほどの土地を持っていて、デベロッパーみたいなことをするところです。
――東京駅周辺の再開発をやったときの三菱地所みたいなイメージ?
龍馬さん まあ、そんな感じですね。
――英語は大丈夫でした?
龍馬さん 得意ではないですが、まあ伝わるぐらいの感じでやってました(笑)。
――半年間という期間は微妙ですが。
龍馬さん 長期インターンという感じで、短いと言えば短いですが、シンガポールのある程度の知識や雰囲気は習得できたと思っております。シンガポール政府はどういう組織で、どういうふうに物事を動かしているのかについて、勉強してきたということです。日本企業の現地駐在員さんとも情報交換したりしていました。
国土交通省は「経済官庁」だと考えている
――日本とシンガポールの違いはありますか?
龍馬さん シンガポールの公共事業は、かなり大きいロッドの工事を一つの企業にバーンと発注するんです。ところが、日本では、国土交通省工事を一つひとつ小分けにします。そういう違いがあるんです。例えば、大きな橋梁をつくる場合、地元の業者も受注できるように工事のロッドを橋脚一つ一ひとつに分割して発注することもあります。杭が長くて費用がかかるものは、さらに一つの橋脚を複数の工事に分けることもありますね、○○下部工事「その1」「その2」みたいな感じで。
シンガポール政府の人間にそういう話をしたら、「意味がわからない。なんでそんな面倒で、非効率なことをするの」と言われました。最初は、私がジョークを言っていると思ったようです。非効率と言われればその通りですが、「日本では、災害が多いため地元の業者が重要で、しっかり仕事をとってもらい、根付いてもらうことが必要なんだ」と説明しました。そうしたら、彼らも理解してくれました。そういう意味でも、私は国土交通省は「経済官庁」だと考えています。
――合理性、効率性を追求すれば、土佐国の仕事もずいぶん変わるでしょうね。
龍馬さん 極論ですが、シンガポールのように本省が高知西バイパス工事という1本の工事をバーンと出して、それをスーパーゼネコンのどこかの会社が取るというカタチにすれば、土佐国の職員もいらなくなるので、かなり効率的になるでしょう。ただ、それをやってしまうと、高知に常駐する建設会社が少なくなり、南海トラフ地震の発生などの有事の際、災害復旧の担い手がいなくなってしまいます。
同じ仕事を続けていると、なまけちゃいそう
――国土交通省の魅力は?
龍馬さん 幅広い仕事ができるところです。もちろん同じ仕事を続けることもできますし、次から次へと新しい仕事にチャレンジすることもできます。私の場合は、新しい仕事を与えられるたびに、自分がドンドン成長していることが実感できるので、いろいろな仕事にチャレンジできるのが楽しいです。まあ、大変ではありますが(笑)。
逆に、自分の性格を考えると、同じ仕事を続けていると、なまけちゃうような気がするので、いろいろな仕事をやらしてもらえる環境のほうがありがたいです。
それと、先ほど申し上げた「経済官庁」であることも、国土交通省の魅力だと思っています。経済の礎となる社会基盤をつくるとともに、日本の経済を回しているというところですね。
人材採用・企業PR・販促等を強力サポート!
「施工の神様」に取材してほしい企業・個人の方は、
こちらからお気軽にお問い合わせください。