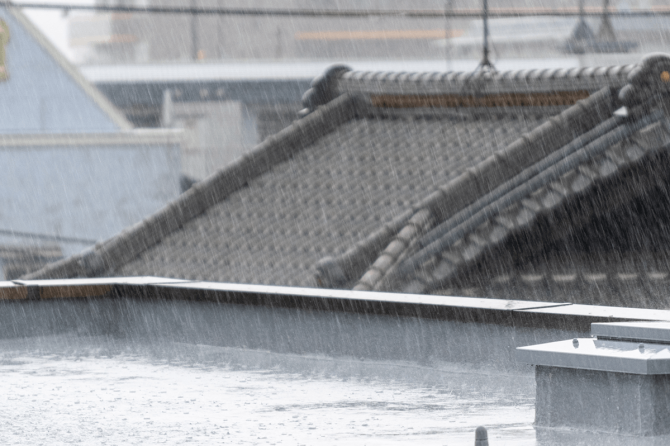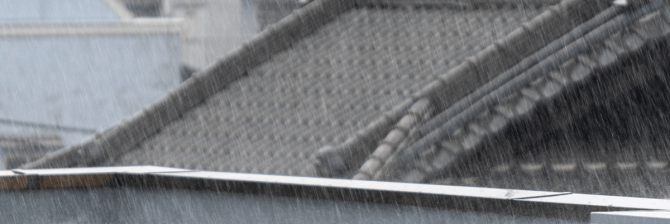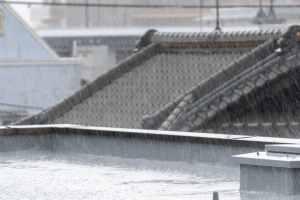パラペットとは
パラペットとは、屋上や平らな屋根、バルコニーなどの外周部に設けられた、低い立ち上がり部分(手すりのような部分)のことを言います。
パラペットの他に、「胸壁(きょうへき)」や「扶壁(ふへき)」、「手すり壁」とも呼ばれます。
高さは10cm~150cmと場所や用途によって幅があり、基本的には、水平な屋根の陸屋根(ろくやね)、マンションやキューブ型住宅、バルコニーなどに用いられます。木造住宅ではあまり見られません。
パラペットの役割
パラペットの役割は、主に以下の3つが挙げられます。
- 雨水を排水し、外壁の劣化を防ぐ
- 接合部の補強
- 転落防止
傾斜がある屋根の場合、雨が降っても雨水は自然に地面へと流れますが、パラペットがない陸屋根の場合は、雨が降ると屋根から外壁をつたって雨水が流れ、雨漏りが起こったり、外壁の劣化にもつながります。
しかし、パラペットがある陸屋根の場合は、雨水を受け止め、外壁をつたって雨水が流れることを防いでくれます。さらに、パラペットと屋根の接触部分は、内樋と呼ばれる排水できる仕組みになっているため、雨水を適切に排水してくれます。
また、屋根やバルコニーにパラペットがあることで、屋根と壁面との接合部を補強する役割や、人や動物・モノなどの転落防止にもつながります。
パラペットのメリット
1.雨水を排水し、外壁の劣化を防ぐ
パラペットの上部には、笠木(かさぎ)やパラキャップと呼ばれる仕上げ材が使われており、雨水が内部に入り込まないよう補強されています。
そのパラペットがあることで、雨水を受け止め、外壁をつたって雨水が流れるのを防いでくれます。また、内樋を用いて、雨水を適切に排水してくれます。外壁が酸性の雨水に晒されることがないため、外壁の劣化を防いでくれます。
2.外観のデザイン性向上に役立つ
パラペットを設置することで、キューブ型住宅など、外観デザインにもこだわることができます。キューブ型住宅は、傾斜のある屋根の住宅に比べ、シャープでスッキリとした印象になるでしょう。
また、店舗などの場合、パラペットに看板を設置することもできます。
3.転落防止につながる
屋根やバルコニーにパラペットがあることで、人や動物・モノなどの転落防止にもつながります。
パラペットのデメリット
1.笠木は雨漏りしやすい
パラペットの上部には、雨漏りを防止する役割で笠木(かさぎ)が仕上げ材として使用されますが、実は、雨漏りの原因となりやすい箇所でもあるのです。
笠木同士をつなぎ合わせているつなぎ目の部分や、笠木を取り付けている釘やビスの穴、または笠木の中にある防水シートの長さが足りないなどの理由から、雨漏りすることがあります。雨水の浸入で腐食し、シロアリが発生する可能性もあります。
2.外壁の通気がとりにくく、結露リスクが高まる
雨水が内部に入り込まないようパラペットは笠木に覆われていますが、それ故に外壁との間を塞いでしまうと、内部に入り込んだ雨や湿気は逃げ場を失い、通気ができなくなります。よって、結露リスクも高まります。
結露により、木材の腐朽やカビなどが発生することもありますので、パラペットには、入り込んだ雨や湿気を外へ排出させるための通気口が不可欠です。
3.こまめな清掃やメンテナンスが必要
内樋は屋上の雨水だけでなく、落ち葉などのゴミも集まり、劣化しやすくなります。そのため、定期的に清掃やメンテナンスが必要です。
清掃やメンテナンスを怠った場合、ゴミが詰まって雨水があふれる原因になったり、内樋が金属製の場合はサビが発生したりするため、注意が必要です。
パラペットのメンテナンス
ゴミを溜めないために内樋の清掃、つなぎ目に亀裂がないかの定期的なチェックなど、パラペットのメンテナンスはこまめに行いたいものです。
紫外線もパラペットの劣化原因になるため、日常的にチェックを行いたいところですが、屋上や屋根での作業には危険が伴います。無理して自分で対処しようとはせず、専門業者に相談することをオススメします。
パラペットの防水工事と費用
パラペットが劣化していたら防水工事が必要です。劣化箇所によって工事費用は様々ですが、内樋の劣化であれば15万円前後、笠木・つなぎ目などの亀裂は10~30万円、パラペット内部への浸水などで全体の工事が必要な場合は100万円を越えるなど、かなり高額になることも予想されます。
パラペットの耐用年数は約10年と言われているので、パラペットの劣化に気づいた場合は、なるべく早めに専門業者へ相談し、対処するようにしましょう。
パラペットの役割を理解しよう
屋上や陸屋根、バルコニーなどの外周部に設けられたパラペットは、転落防止の役割だけでなく、屋根の防水においても非常に重要な役割を担っています。
外壁の劣化防止やデザイン性向上にも一役買っているパラペットですが、外壁の通気がとりにくい点や清掃・メンテナンスが必要というデメリットもあります。
長く安全に快適な暮らしを実現するためにも、こまめな清掃や定期的なチェックを行いながら、正しくメンテナンスを行いましょう。劣化箇所を見つけた場合は、自分で対処せず、まずは専門業者に相談することも大切です。
「施工管理求人ナビ」では建築施工管理の求人を広く扱っています。転職活動もサポートしていますので、気になる方はぜひ一度ご相談ください。
⇒転職アドバイザーに相談してみる