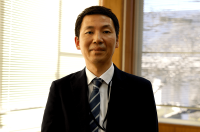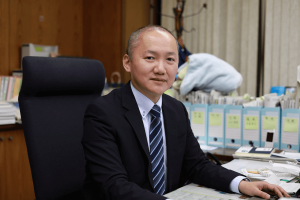国土交通省荒川下流河川事務所の所長を務める菊田友弥さんにお話を伺う機会を得た。岩手県盛岡市出身の菊田さんは、幼少期の経験や阪神・淡路大震災をきっかけに土木の道を志し、東京工業大学で学びを深めた後、2004年に国土交通省へ入省。河川防災を中心に、国内の災害対応から国際協力まで幅広いキャリアを築いてきた。
本記事では、菊田さんの原点から現在の取り組み、そして未来への展望まで、その情熱と知見に迫る。
※取材は2025年1月下旬
土木への第一歩 父親の影響と震災の衝撃
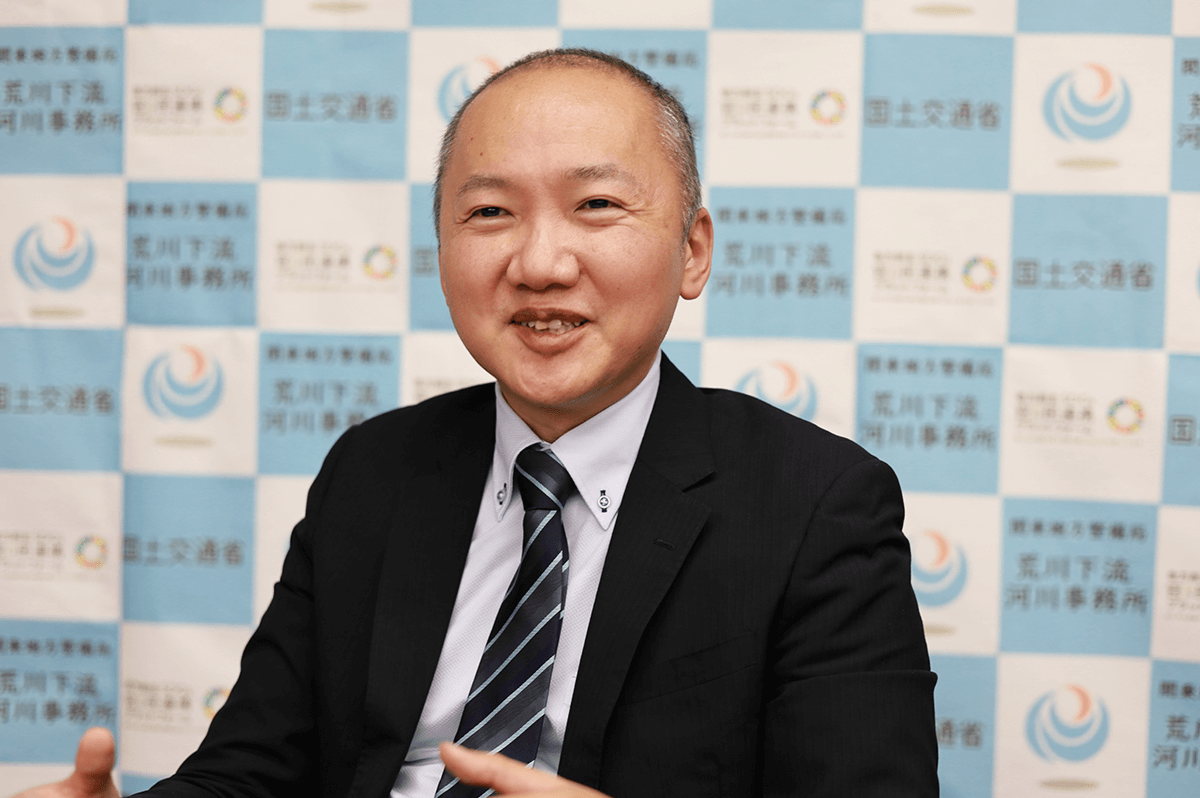
菊田 友弥氏
――菊田さんが土木の道に進むきっかけは何だったのでしょうか。
菊田さん 私は岩手県盛岡市出身なんです。父親が建設コンサルタントとして働いていて、それが大きな影響を与えています。父親は岩手大学で農業土木を学び、地元でコンサルタント会社を立ち上げたメンバーの一人でした。代表ではなかったものの、会社設立から関わり、県や国の仕事を手がけていたんです。
小さいころから、父親に現場に連れて行ってもらった記憶があります。たとえば、岩手県の遠野市の山間部で、父親が設計したワサビ田を見せてもらったり、「ここをつくったんだよ」と教えられたりしました。そうやって幼少期を過ごしたことが、土木への興味の原点ですね。
――具体的な出来事が進路を決めた瞬間はありますか。
菊田さん 中学3年生の時、阪神・淡路大震災が起きました。1995年のことです。当時、私はテレビでその映像を見て、幼いながらに大きな衝撃を受けました。神戸は岩手から遠く離れていますが、「何とかならないのか」と強く思ったんです。
その後、地元の理数科のある高校に進学し、大学でインフラや防災を学ぶなら土木だろうと考えました。それで、東京工業大学に進学したんです。土木の中でも構造やコンクリートなど色々な分野がありますが、私は水系の研究グループで、衛生工学の研究室に所属しました。
環境ホルモンとの出会い
――大学ではどのような研究に取り組まれたのですか。
菊田さん 4年生の時、研究室で環境ホルモンの分解の研究に取り組みました。当時、社会問題として注目されていて、人の尿や医薬品に含まれる微量物質が生態系に悪影響を及ぼすのではないかと言われていました。それが下水処理場でどれだけ除去できるのかを調べる研究です。
土木の授業で学ぶ構造力学などとは少し違っていて、微量物質を検出するために分析化学を一から勉強する必要がありました。実験室で白衣を着て、下水処理場からサンプルを取ってきて、実験室内の活性汚泥で処理し、どれだけ除去されるかを測定するような研究でした。化学実験に近い研究ということもあり、ちょっと一風変わった経験でしたね。
――その研究が後のキャリアにどうつながったのでしょうか。
菊田さん 大学院の修士課程まで進み、指導教官から博士課程への誘いもありました。でも、私は研究者として働くイメージが持てなかったんです。もともと「現場に出たい」という気持ちが強かったので、博士課程には進まず、2004年に国土交通省に入省しました。
入省の決断 就職氷河期と父親の助言
――なぜ国土交通省を選ばれたのですか。
菊田さん 入省した2004年は就職氷河期の真っ只中でした。ゼネコンが潰れてしまうかもしれないと言われ、公共事業も削減傾向にあった時代です。当時の総理大臣は小泉純一郎さんで、大学の同級生の中には、土木を学んでも、銀行や保険業界に進む人もいました。公共事業が悪者扱いされる時代背景もあったのかもしれません。それくらい就職がキビしかったんです。
私も民間の情報通信系の会社やシンクタンクを受けましたが、一番やりたかったのは土木系の仕事でした。「絶対に潰れない就職先はどこか」と考えたとき、国土交通省が浮かんだんです(笑)。少しネガティブな理由に聞こえるかもしれませんが、社会的に公共事業が批判される中でも、インフラの仕事に携わりたいという思いが強かったんです。
――ご家族の反応はどうでしたか。
菊田さん 父親からは「この分野で働くなら発注者になるべきだ」と言われました。大きな仕事ができ、コンサルタントやゼネコンとも連携できる立場だと。それも入省の後押しになりましたね。
初任地での試練 災害対応の洗礼
――入省後の初任地はどこだったのでしょうか。
菊田さん 初任地は新潟県の長岡市でした。2004年のことです。その年は災害が多くて、入省して3ヶ月ほど東京や他の地方で研修を受けた後、7月から本格的に仕事を始めたら、新潟・福島豪雨が発生しました。7.13水害と呼ばれるものです。
さらにその年は台風が連続で日本を襲い、日本全国に被害をもたらした10月の台風23号では、信濃川中流部でも戦後5番目の洪水が起きました。その対応が終わった2日後に、新潟県中越地震が発生したんです。もう年中、災害対応に追われていましたね。
――初めての現場で大変だったでしょうね。
菊田さん 普通の河川の工事や管理の仕事ではなく、災害対応から始まったので、初年度から濃い経験をさせてもらいました。1年3ヶ月ほど長岡にいて、その後は富山県の事務所に道路の担当として異動しました。そこでまた、平成18年豪雪という大雪に見舞われ、交通規制や通行止めの対応をしました。
初めの2年ちょっとで災害を多く経験したことが、その後のキャリアに活きたと思います。当時の上司にも「これまでの経験を活かしなさい」と言われ、次のステップに進むきっかけになりましたね。
内閣府での学び 防災の総合行政を体感
――その後はどちらに?
菊田さん 3年目に内閣府の防災担当に出向しました。旧国土庁の防災局が省庁再編により内閣府に移った部署です。そこで初めて、防災が国交省だけでなく、全省庁が役割分担を持って取り組む総合行政だと学びました。
たとえば、災害救助法は当時は厚生労働省が担当しましたし、大規模な災害では金融庁が支援に関わったりします。出向者が多い部署で、インフラ省庁だけでなく全省庁と仕事を調整する役割を担っています。
――具体的にどんな業務を経験されましたか。
菊田さん 全国で災害が起きたら対応しなければならず、広報や報道対応、企業の防災対策、風水害への備えなど、幅広い業務を経験しました。当時は小さな組織でしたが、意思決定が早く、大臣にすぐ話が上がるような環境でした。霞が関の仕事の仕方を学び、各省庁の考え方や行政全体での防災の重要性を体感できた貴重な時間でしたね。