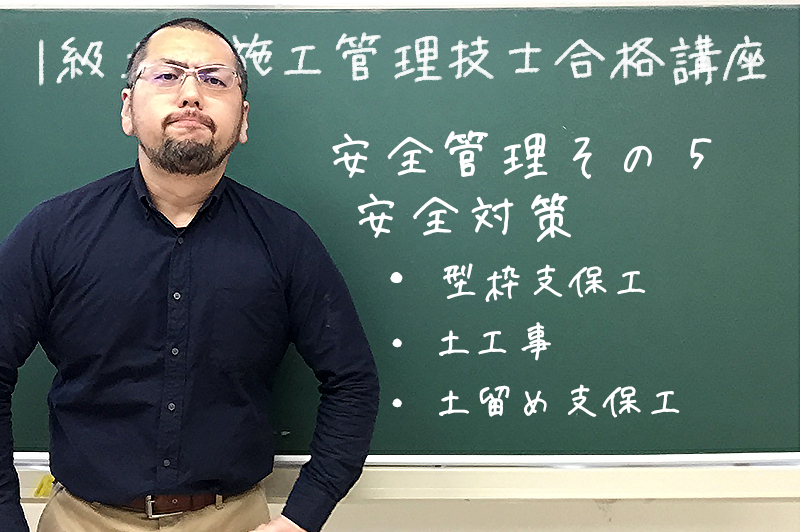【1級土木施工管理技士の試験対策41】安全管理その5「安全対策(型枠支保工・土工事・土留め支保工)」
【1級土木施工管理技士 過去問分析に基づく試験合格対策】の第41回目は、安全管理その5「安全対策(型枠支保工・土工事・土留め支保工)」のポイントについてまとめていきます。
型枠の設置や土工事、土留め支保工では、前回の足場の安全対策と同様に、各種作業時の安全対策(労働災害の防止)に関する問題が出題されます。
型枠支保工の安全対策
型枠支保工の安全対策に関しては、足場の安全対策の項目と同様に、届出・作業主任者および安全基準について出題されます。
1級土木施工管理技士試験では、下線部がよく出題される箇所ですので注意しましょう。
- 高さ3.5m以上の型枠支保工を設置する場合は、その計画を作業開始の30日前までに労働基準監督署長に届け出なければならない。
- 強風、大雨等の悪天候によって型枠組み立て作業に危険が予想される場合は、作業を中止する。
※「各部材の接合部等を十分に点検した後、組み立て作業を行う」のように、慎重に注意して作業を行えばOKといった記述があると誤りになります。
- 組立図には、各部材の寸法、配置、接合方法、組立寸法を明示する。
※「完了後に明示する」との記載があると誤り。組み立てるための図面なのに、完了後に明示するのはおかしいですよね。
- 脚部の固定、根がらみ等を用いて支柱の脚部の滑動防止措置を講ずる。
- 型枠支保工設計について、鉛直荷重について安全なものとするのは当然だが、水平方向の荷重に対しても対応できる構造とする。
※「横荷重の検討は行わなかった」との記述があると誤りとなります。
- 支柱の継手は、突合せ継手または差込み継手とする。(重ね継手は誤りです)
- パイプサポートは3本以上ついて用いないこと。
- パイプサポートを継いで用いる場合には、4個以上のボルトまたは専用の金具を用いること。
型枠支保工の安全対策の練習問題
【例題】次の記述は正しいでしょうか、誤っているでしょうか?
◇ 強風,大雨,大雪等の悪天候によって組立作業に危険が予想されるときは、各部材の接合等を十分に点検したのちに当該組立作業を行わせなければならない。
解答×…悪天候によって組立作業に危険が予想されるときは作業を中止する。
土工事の安全対策
次に土工事の安全対策に関して、よく出題される箇所をポイントごとに見ていきます。
- 事業者は、作業開始前に大雨の後、中震以上の自信の後には、浮き石・亀裂の有無・湧水の状態の変化を点検しなければならない。
※現場の点検は事業者の責務です。これが「作業主任者を選任し点検させた」との記述になると誤りとなります。
- 掘削機械や運搬機械を使用することにより、ガス管や地中電線路等が損壊し、労働者に危険を及ぼすおそれがある場合は、これらの機械を使用してはならない。
※「監視員を配置すれば、これらの機械を使用してもよい」との記述があると誤りとなります。
- バックホウで土砂をダンプに積込み時、バケットがダンプの運転席の上を通過しないよう逆旋回させる。
人力掘削を行う場合の掘削勾配および高さの基準
| 岩盤または堅い粘土からなる地山 | 90°以下(5m未満) |
| 75°以下(5m以上) | |
| 砂からなる地山 | 35°以下または5m未満 |
| 発破等により崩壊しやすい状態になっている地山 | 45°以下または2m未満 |
※試験問題では、とくに下線部を違う数値に代えて出題されることが多いです。
土工事の安全対策の練習問題
【例題】次の記述は正しいでしょうか、誤っているでしょうか?
◇ 発破等により崩壊しやすい状態になっている地山を手掘りにより掘削の作業を行うときは、掘削面のこう配を60°以下とし、又は掘削面の高さを3m未満としなければならない。
解答×…発破等により崩壊しやすい状態になっている地山の場合、掘削面のこう配は45度以下、高さは2m未満としなければならない。
土留め支保工の安全対策
最後に、土留め支保工の安全対策について見ていきます。
土留め支保工の杭および鋼矢板の根入れ長については、次のように定められています。
- 鋼矢板…3.0mを下回ってはならない
- 杭…1.5mを下回ってはならない
慣用法という簡易的な杭(鋼矢板)の根入れ長を計算する方法もありますが、この方法は第三者へ危害を及ぼす影響のある重要な仮設では使用せず、上記の最低根入れ長を採用します。
1級土木施工管理技士試験では、下線部を違う数値や言葉に代えて出題されます。
- 土留めに使用する木製の土留め板は最小厚30mmとする。
- 圧縮材(押し合うように力の加わる箇所)は突合せ継手とする。(重ね継手は誤りです)
- 事業者は土留め支保工設置後、7日を超えない期間ごと、中震以上の地震の後、大雨の後等は点検を実施しなければならない。
土留め支保工の安全対策の練習問題
【例題】次の記述は正しいでしょうか、誤っているでしょうか?
◇ 土止め支保工を設けたときは、異常の発見の有無に係わらず10日をこえない期間ごとに、点検を行わなければならない。
解答×…事業者は土留め支保工を設置後、7日を超えない期間ごとに点検を実施しなければならないと定められている。