解体現場で問われる「状況判断力」と「発想力」
大型体育館の解体工事の現場で直面した「課題」と、それを克服した「アイディア」について報告します。
解体する建物は、地上階が体育館、地下階には両脇に隣接するホテルのインフラ設備が入っているという、特殊な構造物です。
解体工事で直面した課題とは?
解体工事は、構造体以外のPC版や、内装、天井、扉、サッシの類を先行して解体する手順で進めます。
まず鉄骨屋根の仕上げ部分(軽量モルタル、デッキプレート、表層のトタン)の撤去と並行して、2階席のバックヤードの外側に位置する外壁PC版と、その間にあるサッシの撤去を開始しました。
下図は体育館の平面です。
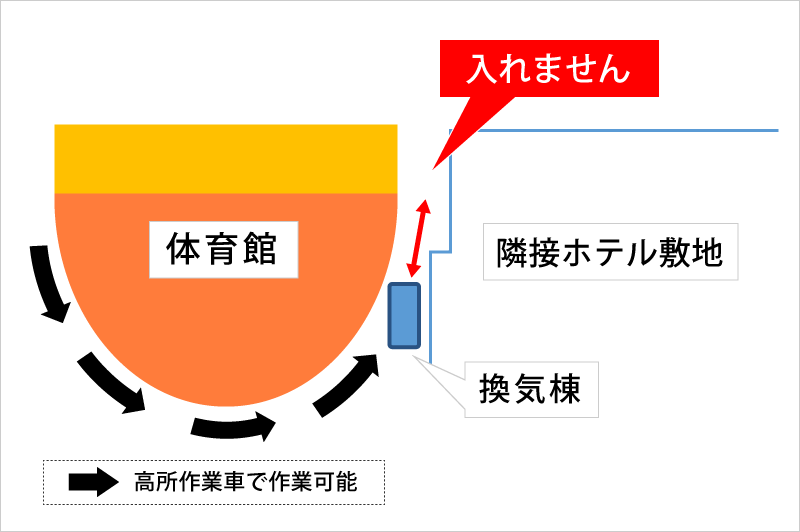
解体現場の平面図
R部分はW=2m、H=7mのPC版と、W=900、H=6mのサッシが交互に取り付けてあり、サッシを外して、次にPC版を外す計画。サッシとPC版の間はシール(コーキング)で埋めてあり、シール部分を除去しないとサッシが外せないため、高所作業車で反時計回りでシールをはがしていきました。
ところが、途中まで来ると、地下からの換気棟が邪魔で、高所作業車が入っていけなくなりました。図の赤矢印部分(約20m)が高所作業車を使用できない部分です。
高所作業車も足場も組めない解体工事
高所作業車が入れないのであれば、その部分に足場を組まなければなりませんが、シール除去のためだけに、この部分全体に足場を組むのはムダが多すぎます。最小限の足場で、移動しながら作業が可能なものをつくる必要があります。
しかし、次の2つの悪条件が立ちはだかりました。
- 地上レベルでは、内部解体で出たトン袋やガラ袋があり、足場を組むスペースが確保できない。
- 高所作業部分の高さが、地上4.5~11.5mで、しかもその上部には1.2m程の跳ねだした壁がある。
この現状を見て私が考えついたのは、足場を躯体にぶら下げる方法です。
足場を躯体にぶら下げる!

壁面にぶら下げる足場を地組みする
壁面にぶら下げることのできる足場は、W=1200m、H=7m弱、3スパンで地組みしました。
足場のサイズは、サッシ2枚分のシールが撤去可能な幅に設定。
足場上部には、足場の荷重を支えるためのパイプ2段を4カ所設け、離れを設定したパイプも取り付けました。
昇降はタラップ付きアンチを使用。乗り込みは最上段からとしました。外周部には垂直ネットを貼り、最下段には層間ネットも取り付けました。
山留H鋼で「吊り天秤」をつくる!

山留H鋼を利用して作った吊り天秤(バランサー)を使い、取り付け位置までクレーンで移動
次に、ムダなお金と時間をかけずに作業がスムースにできる方法として、現場にある山留H鋼を利用して、吊り天秤(バランサー)をつくりました。
セットバック位置(上部の障害物からどのぐらいの位置に足場がぶら下がるのか)と、足場の総重量を計算して、山留H鋼のどの部分を吊れば良いかをモーメント計算。地切りは計算どうり成功しました。
そして足場を取り付け位置までクレーンで移動し、レバーブロックで引き込み固定。玉掛けを外し、バランサーを開放後、シール除去作業に入りました。

レバーブロックで引き込み、足場を固定する

玉掛けを外し、バランサーを開放

実際にぶら下げた足場
……建設現場では、その時の状況判断と問題解決のための発想が、良い仕事をするポイントです。
ぜひ「アイディアの種」としてご参考いただければ幸いです。









