東京の地下鉄は全滅
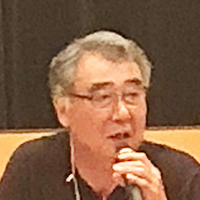
建設通信新聞・服部さん
さあ、松田さん、どうしましょう?
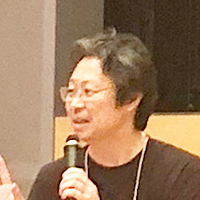
建設技術研究所・松田さん
さらに地震が起きます。今は震度7が一番大きいとされていますが、さらに経験したことのないような地震が広範囲に渡って起きるはずです。災害対策をする前に、こういう災害だと何が起こるかを予測しておくことが大事だと思います。
例えば、堤防などの土木施設は、振動で多くが壊れると思います。隅田川より東側には、海水面より低い土地の「海抜ゼロメートル地帯」があって、堤防が壊れると江東区・江戸川区・墨田区・葛飾区・足立区の大部分が海になります。
そういう事が起き得るということを考えて毎日生活しないといけないと思いますね。対策をどうするかというのは、何が起きるかを考えたあとです。
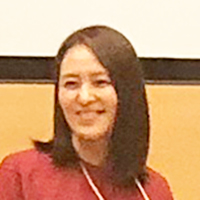
応用地質・津野さん
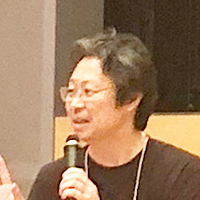
建設技術研究所・松田さん
千代田線、丸の内線、 都営新宿線だけじゃなくて、山をすぐ降りた所に銀座線や日比谷線があります。そこに穴が開いちゃうわけですから、当然、海の水が地下街に入り込みます。
そうすると、地下鉄はみんな繋がってますから、地下の商店街も含めて、多くの地下空間が水没することになります。
日本の地質と地名
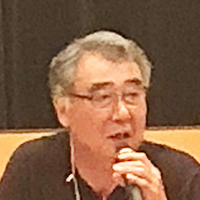
建設通信新聞・服部さん
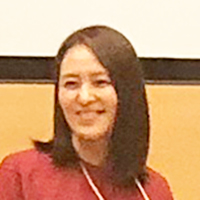
応用地質・津野さん
しかし、最善策を見つけるのが建設コンサルタント、地質調査会社の責任です。例えば、斜面と地質の重なり方が平行だと崩れやすいですが、斜面と地質の重なり方が逆だったら崩れにくいんですね。地すべりが起きるきっかけは水が多いので、水が流れやすい所を調べて、そこから水が入ってきた時に逃す道を作ると地すべりは起こらない。ちゃんと調べれば分かるし、考えれば対策ができるんです。
西日本の土砂災害があった所の土の多くは、花崗岩が風化した「真砂土」というサラサラの土でできています。真砂土は水が入るとすぐ崩れるので、危険な場所だと分かってはいた。けれども、それを認めたくない住民の方もおられて、なかなか災害の被災者が減らないという現実があります。

日特建設・藤代さん
役所の方や建設業界の人たちも、ここは危ないから対策をしようと少しずつ対策を進めていますが、これからは「ここは元々こういう場所だったから対策する必要があるんだ」と、住民の方々から上がってくる声を私たちが拾って社会を作っていくというのも、今後の一つの方向性として出てきてもいいところではないかなと感じます。
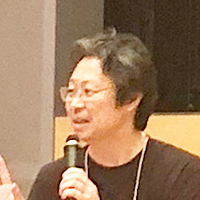
建設技術研究所・松田さん
そうするとみんな、「うんうん」と頷くんですよ。私は驚いて「ちょっと待った、私、土木屋です」と言って「あの辺は、綾瀬川の氾濫原であり、荒川、中川もあり、遠くまで行くと江戸川、利根川もあって洪水の被害を受ける可能性がある地域なんです」と発言しました。
そしてハザードマップの荒川版・江戸川版・利根川版全部持って、「ここは数メートル水没しますからね」ということをマンションの皆さんに説明したら、そんなこと知らないで住んでるよという人がほとんどでした。下水道や河川が整備されたから、もう洪水が来ないとみんな思っていた。しかし、そうではないと分かったら、土嚢を積むための材料を備蓄しようかとか、トイレを買おうというような議論をするようになりました。
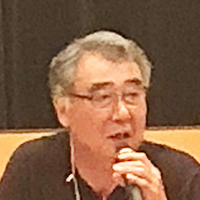
建設通信新聞・服部さん

日特建設・藤代さん
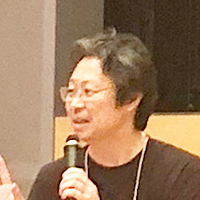
建設技術研究所・松田さん

日特建設・藤代さん
それから大阪の「梅田」は、昔は、埋めるという字を当てて「埋田」という時期もありました。土地の地名の漢字にも注目して住む場所を選んでいただけたらなと思います。







