頭で理解できても、心の奥は変われない
これまでに建設業界で、大きなパラダイムチェンジはあったでしょうか?
私が大林組に入社したころに比べると、大きく変わったことは確かです。しかし、かなり鈍足のように思えます。
かつてドイツの方々と仕事をした時のことです。彼らは「世代交代の後に、ようやくパラダイムチェンジができた」と言っていました。私がドイツを訪れた時は10年くらい前ですが、すでに完全週休二日、金曜日は半ドンになっており、GDPはその当時も、今も、ドイツと日本はほとんど同レベルのはずです。
そもそも産業革命をはじめ、日本は欧米の後ろに付いていっているわけですが、それでも、今の日本の状況を見ていると、改革を進めるというよりも、「そこそこ、このあたりで、落としどころかな」といった風潮を感じます。
大手企業トップの「血」
今では、共働きの方が専業主婦より増えましたが、それでも亭主の稼ぎが良ければ専業主婦をしていたいという方はかなり多いように思います。「やりがい」とか「自己実現」を求めて社会に出ている女性は、もしかするとあまり多くはないのではないでしょうか。
その理由をなぜかと考えますと、どうしてもその時代の「あたりまえ」は生まれてからずっと染みついているわけです。実は私自身の中にも「これだけ頑張ったんだから、女性としてはいいんじゃないかな」と思っているところがありました。
「女性としては、いいんじゃない」って何なのだろう?そしてふとあたりを見回すと、根本的に今の社会のトップに居る方々の根底には(古き良き時代かどうかわかりませんが)、男性中心の右肩上がりの高度成長期の血が残っていることに気づきました。
頭の中での理解はできていても根本、心の奥までは変わっていない、こういう人種が大手企業のトップにまだたくさんおられるような気がしております。
政治の世界でも、女性の活動や多様なジェンダーの問題について「ほっといてよ」という自由の獲得を許しはしましたが、やっと多様性について認めるべきであると頭では理解するに至った、だけです。
障害者雇用の問題についても、率先すべき肝心の役所はほとんど守れていないという現状も明るみに出ました。頭の中での理解と、身についているパラダイムの不一致の賜物でしょう。
リーダーは常に「改革者」であるべき
また、最近では、医大入試で女性の合格率を下げていたという事件も発覚しました。女性の医者が増えると夜勤ができないとか、長時間に耐えられないということが、理由のひとつとのこと。
なぜシステムのほうを工夫できないのか?こういったことを踏まえて考えるに、日本がパラダイムチェンジしきれない原因は、新しい頭と心、心も実は脳の働きなので、本来の言い方をするならば新しく生まれ育ってきた真に新しい、若い脳がその発想、創造力を発揮しきれていないからではないかと思っております。
もちろん、革新的な新しい脳を持って、心身のみ熟成された方々の存在も否定はしませんが、多くの古き良き時代を無意識に引きずる世代(残念ながら私も含まれます)が、幅をきかせ過ぎていないでしょうか?
どうか男女を問わず、ジェンダーを問わず、障害の有無を問わず、次世代を担う方々に、10年先、20年先を見据え、年寄りをひょいとよけながら、新しい社会を築くリーダーとしてトップに立っていただきたい。
そして、どんなに穏やかな世の中であろうとも、リーダーは常に改革者であるべきです。なぜなら、今の最適はすでに最適ではなくなろうとしつつあるのであり、すなわち、3年、5年先の最適であろうはずがないからです。
少し肩に力が入りましたが、次の世代のリーダーにとっては、こうした私の言葉も受難?の一つかもしれません。しかし、私は若い世代の台頭を応援し続けてまいります。




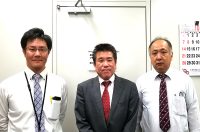





いい記事だと思った。
素晴らしい。
大手ゼネコンから変えないと建設業の働き方は変わらないと思っているが、こういう考えの人が増えていくことを望む。
こういう上司あればこその成長
たまにひどい上司もいる
でもそれこそ大手ゼネコンの裏表