危険なトンネル工事現場で働くということ
そもそも、トンネル工事の仕事は、業界外にはあまり知られていない。
「まず、発注者から受注したゼネコンが、トンネル専門工事業者に工事を依頼し、その業者が施工を担当します。地元以外から職人が来られるように、仮の宿舎を建て、賄いを作る料理人を雇い、そこで数十人が共同生活をしながら工事を進めます。
職人は工事ごとに契約していて、終わったら別の現場に行くようなスタイルです。専門的で特殊な技術を必要とし、危険を伴う仕事なので、そのぶん報酬も高いです。
トンネルは短くても、準備から完成まで1年はかかります。長いと5~6年かかることも。その間はずっと宿舎暮らしなので、単身赴任で何年も家族と離れて、ということも当たり前の世界です」

作業中の職人たち / 山崎エリナ 『トンネル誕生』より
トンネル工事の手順は、大きくは準備、掘削、コンクリート打設の三段階に分けられる。
「まず準備として、周辺に工事するための場所や仮設備設置用の土地を作り、工事用道路の整備などを行います。その後は、専用の重機などを使って掘り進めます。掘るときは1班5~6人が機械を操作して掘り、出た土をダンプやベルトコンベアなどで運びます。中には手作業もあります。
掘った後ろから、専用の移動式型枠を使って仕上げのコンクリートを打っていきます。一つのサイクルが決まっているので、基本そのサイクルを回しながら、約1mずつ掘り進めていきます」
現在は以前よりかなり減ったものの、トンネル工事は事故が起きると死亡災害などに至ることもある、危険な仕事だ。
「掘った山がそのまま目の前にあるわけですから、リスクは高いです。狭く、暗く、騒音や粉塵がすごいなか、大きな重機が動いているので、接触する危険性も高い。経験を積まないとできない仕事です。作業時は、落盤に備えて作業着の上からプロテクターを背負い、ファン付きの粉塵マスクをしています」
トンネル屋ならではの「貫通の儀式」
そんな森崎さんがトンネル工事をしていて一番嬉しいのは、やはり貫通した時だという。
「道路が開通するときはトンネル屋はすでにいないので、一番象徴的なシーンになります。トンネル工事は規模やリスクが大きく、苦労も多いため、貫通したときは言葉にならないほどの感動があります。
貫通の儀式には、発注した役所の人、元請け会社、現場関係者など、大勢が立ち会います。関係者にとっては念願の瞬間なので、たくさん来るんですね。山の神様を掘るので、貫通したところを塩・米・お酒でお清めします。これはどこのトンネルでもやっている、トンネル屋の儀式です」
来月には、トンネル現場を撮影した写真集『トンネル誕生』(グッドブックス)が出版されるという。「山崎エリナさんという、ルーブル美術館でも展示するようなすごい写真家に、とてもいい写真を撮ってもらいました。それを見ると、もっとトンネル工事の魅力を感じてもらえると思います」

工事開始前の神主による安全祈願 / 山崎エリナ 『トンネル誕生』より
山が多い日本では、トンネルは非常に重要な交通インフラだ。トンネルが開通することで道路ができ、山に阻まれていた遠い場所にも行けるようになった。日本では年間およそ100本もの道路トンネルが掘られている。
コロナ禍で、感染リスクを負って外で働くトラックドライバーや配達員に、感謝の声が集まっている。しかし、平時から命を懸けてインフラを作ってくれている人々がいることも、心にとめておきたい。
人材採用・企業PR・販促等を強力サポート!
「施工の神様」に取材してほしい企業・個人の方は、
こちらからお気軽にお問い合わせください。

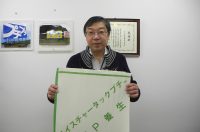



天照大神がお隠れになった天の岩戸。貫通時の感動は、やはり祈り。トンネル工事のOBより。