「10年後の地域建設企業は、一体どういう方向性で進むのか」――この議論を行うため、国土交通省は有識者会議「建設産業政策会議」の中に、3つのワーキンググループ(WG)を設置した。そのうちの1つである「地域建設業WG」の初会合が3月13日に開かれ、地域建設企業の将来のあり方について、活発な議論が交わされた。
今回、この地域建設業WGで座長を務める大橋弘氏(東京大学大学院経済学研究科教授)にインタビューを行い、“10年後の地域建設企業”に関してお話を伺った。
地域建設企業の経営基盤の底上げが必要
施工の神様(以下、施工):地域建設業WGの初会合の感想はいかがでしたか?
大橋弘教授(以下、大橋):初会合では、各委員(※)の意見を拝聴することから始めました。初会合の論点は、地域建設企業の経営基盤をいかに底上げするかということでした。
地域建設企業は、除雪作業のほか、いざ災害が発生するとなれば「地域の守り手」の役割を期待されます。その一方で、地域建設企業が各都道府県の建設業協会から脱退する動きもあり、いかに「地域の守り手」を確保するかが課題になっています。具体的にどんな施策を打ち出すのかは国土交通省次第にはなりますが、地域建設企業は規模も大小さまざまありますので、各社が共有できる認識をいかに探っていくかは、大変困難さを伴う作業になるだろうと思っています。
委員の総合的な意見としては、地域建設企業の全体的な需要の引き上げによって、経営基盤を底上げすることが必要だということだろうと思います。
※地域建設業WGの委員
犬飼あゆみ氏(中小企業診断士)、大串葉子氏(新潟大学経済学部経済学科准教授)、梶田真氏(東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻准教授)、蟹澤宏剛氏(芝浦工業大学工学部教授)、木下誠也氏(日本大学危機管理学部教授)、髙橋一朗氏(宮城県土木部技術参事兼事業管理課長)、寺田治氏(幕別町建設部土木課長)、畑田操氏(一般財団法人建設業振興基金企画広報部長)、松島昭雄氏 (奥出雲町建設課長)
民間工事にも踏み込んだ提言が必要か?
施工:地域建設企業が「地域の守り手」としての役割を果たすためには、一定程度の工事量が必要です。地域の仕事はなるべく地域建設企業が行なうべき、という意見も強いですが、この点についてはどのようにお考えですか?
大橋:地域には公共工事だけではなく、民間工事もあります。公共工事の調達制度はしっかりしてきているものの、民間工事は公共工事レベルの調達制度には至っていません。どこまで国が民間工事に提言できるのか分かりませんが、国が民間工事に対するガイドラインを示すことができるのであれば意味があるように思います。
また、以前のように国や地方公共団体が予算も含めた5カ年計画を立案することも検討する価値があろうとは思います。今は複数年に亘る計画を示すことができないため、建設会社が事業量を一定量見通すことは難しくなっています。今後、都市のコンパクト化により、事業量が増える地域もあるでしょうが、それはごく一部の地域です。国全体を見通すと、事業量が膨大に増加することはありません。
そこで建設需要に合わせて、「建設業」「経営事項審査」「建設業法」という建設業の3輪のタイヤは変化を余儀なくされるだろう、と考えています。この3輪については、「建設産業政策会議」全体で議論されることになるのだろうと思います。
広域発注によって限界工事量を維持する?
施工:群馬県建設業協会の青柳剛会長が2016年7月に発表したデータによると、群馬県建設業協会の会員企業のうち、2015年度公共工事受注実績が限界工事量(道路除雪などの災害対応に必要な工事量)を下回った企業が約6割にも達したそうです。除雪体制や「地域の守り手」としての役割を維持していく上で、「工事量受注減による建設業本業の体力低下」が問題視されていますが、これについてはどうお考えですか?
大橋:あってはならないことですが、このままでは除雪を実施することが出来なくなる地域もでてくる可能性があります。地域建設業WGの委員も発注者側の意見として発言しておられましたが、地域では除雪を受けてくれる方が不足しています。除雪作業が不調に終わってしまうことも多く、大変悩ましい事態になってきていると思います。
地域建設企業の事業環境の悪化に伴い、災害対応、除雪、インフラ維持管理などの能力を有する地域建設企業が減少することは、地域建設業WGの各委員もたいへん危惧していました。このままでは地域社会の必要最低限のインフラ維持管理も困難となる地域が生じかねない、という共通認識もあります。
施工:現在、何らかの対策はなされているのでしょうか?
大橋:国土交通省は、インフラ維持管理を適切に行う担い手の確保が困難となるおそれがある場合には、地域の実情を踏まえつつ、契約方式を工夫する入札方式「地域維持型契約方式」を実施しているようです。これは、施工の効率化と、施工体制の安定的な確保の観点から、透明性を持ちつつも共同企業体(JV)によって落札する契約形態をとります。一部の地方公共団体でも「地域維持型契約方式」を取り入れています。
しかし、発注者も実は技術者が不足しています。そのため発注者側も問題を抱えており、単体の地方公共団体で発注を行うのではなく、いくつかの地方公共団体が集まって発注する、という案も出てきます。その場合、発注するいくつかの地方公共団体と、受注する地域建設企業が協力してそれぞれ設計、工事計画案、図面作成、積算を行い、地域建設企業がその工事を受注することにより、地域建設企業は地域の中で存続が可能になります。このような案により、大きく儲けることは難しいにせよ、限界工事量を下回ることはなくなると思います。
施工:自治体単位ではなく、広域で考えるということでしょうか?
大橋:そうですね。地域を「広域」で考えると色々なことが考えられます。下水道もすでに広域で管理され始めていますが、それと同じように、橋梁やトンネルも広域で維持管理を含めて発注すれば良いというアイディアもあります。地方公共団体の広域発注も1つの案です。地方を切り捨てることだけは、避けなくてはなりません。
ただ、地域の広域性を検討すれば、「地域の守り手」を担保できますが、地方公共団体の単位では地域建設企業を維持できなくなるのではないか、という議論と必ず衝突します。ここの議論は今後も進めていかなければなりませんが、広域性を検討しつつ、限界工事量を下回ることにないように、事業量の検討を深めていきたいです。
ただ広域で発注する場合、地方公共団体のマインドとして、各地方公共団体に温度差が生じるという問題もあります。自分の業務は外注したくない、というマインドも働くはずです。しかし、国が方向性を示すことで、地方公共団体に危機意識を持たせることは出来ると考えています。
地域建設業WGの役割としては、一般市民への情報発信という側面もあると思っています。今、一般市民の目線で建設業を見ると、建設業は儲かっているという誤解をされていますが、地域建設企業の視点では全くそんなことはない、というメッセージを世間一般に公表するという意味もあると考えています。
存続してほしい地域建設企業をどう選択するか?
施工:東京商工リサーチのデータによると、2016年に多くの中小地域建設企業が廃業・休業しました。後継者不足、建設業の先行きの不透明さなど様々な要因によりますが、これについてどうお考えですか?
大橋:倒産件数が減っていることを考えると、自民党政権になってから建設業界も上向いてきて、負債も返済でき、ようやく廃業・休業できる体制が整ったのだと解釈しています。建設産業政策会議はこれまで、2016年10月から2017年1月まで、3回開催していますが、発注者側として地域建設企業を含めた供給構造のあるべき姿に関わる議論は、直接には避けてきたのではないかと思います。地域建設企業のあり方については、公共工事の需要増減と、市場の自由競争の原理に任せようという考え方だったのではないかと思います。
しかし、地域建設企業の体力が本格的に衰退すると、究極的には「残したい企業は一体どこなのか?」という選択の議論に踏み込むことになります。地域にとって存続して欲しい企業が退場すると、「地域の守り手」が不在になります。地域建設業WGの委員には、地域のためになる企業にどうやって存続してもらうのか、という議論まで意識している方も多いです。残念ながら、すべての地域建設企業が存続するというストーリーは難しいかも知れません。後継者に継がせたくない、継がないという企業で出てくれば、地域にとって残したい企業なのか、という視点から考える必要があります。総合評価方式などの工夫により、残したい企業が残るような制度設計も必要です。
ただもう一方で、会社単位ではなく、技術者単位で考え、少なくとも人材を残せるように手当てするという視点もあります。建設技術者・技能者の人材流動化とマッチングも旧来のやり方を超えて、人材確保の平準化を行っていけば、色々な可能性が考えられます。
施工:公共工事の繁忙期と繁閑期をなくす「平準化」の動きも検討されていますが、それとの関係性もありますか?
大橋:工事の平準化によって、年度に亘ってまんべんなく地域の工事量を確保できれば、地域建設企業にとって人員計画を立てやすくなります。それは週休2日制の確保にもつながると思います。
また、工事量が少ない地域建設企業が、地方公共団体の枠を越えて需要が多い地域に応援に行き、JVを組むといった広域地域における建設企業共同体も1つの案として浮上してくるはずです。
地域建設企業の合併・統合問題
施工:地域建設企業の合併・統合という話題も浮上しています。地域建設企業の中には、もしメリットがあれば、合併・統合しても良いという声もありますが、合併・統合問題に対する意見についてお教えてください。
大橋:合併・統合については、各建設業協会にとっては避けたい話だと伺うことがあります。残ってもらいたい地域建設企業には、合併・統合というストーリーもあるかも知れませんが、国や地方公共団体が強制的に合併させる手法は望ましくありません。
かつて造船業でも合併・統合が議論されましたが、2014年頃以前は口では合併しないと明言していた企業が多かったにもかかわらず、2014年頃以降は合併・統合を断行しました。ですから、地域建設企業の合併・統合問題は、経済情勢や、オーナーの想いによって行われるものだと思います。
建設業は今、経済状況が良いので、企業にとっては合併・統合は飲み込みやすい話と思います。ただ、経営事項審査を上げるための「名ばかり合併」では困りますので、政策的な後押しをどのようにすべきかについては検討課題が残ります。
現状のままでは担い手確保・育成のハードルは高い
施工:担い手確保・育成の問題は、危機的な状況です。建設業の55歳以上就労者の比率は35%を占める一方、29歳以下の比率はわずか約10%に過ぎません。建設業振興基金の内田俊一理事長は、この状況をワニの口にたとえ、建設産業専門団体連合会の才賀清二郎会長は建設技能労働者の処遇改善を求めています。建設技術者・技能者における担い手確保についてどうお考えですか?
大橋:問題意識はみなさん同じです。他方で、担い手確保・育成はわが国においてあらゆる産業に共通しています。どの業界も人手不足になっていますが、縮小するパイを各産業間で取り合うことになっています。担い手確保で重要なことの1つは教育です。現在、工業高校が統廃合され、普通高校に進学する生徒が増えており、工業高校でも土木を志す生徒は少ないです。問題は一般市民にとって、建設業、特に土木という仕事が可視化されていない点です。これは国、地方公共団体、地元の経済界が一致協力し、若者に魅力がある建設業を目指すべきです。
もう1つは、外国人を増やすことも視野に入れるべきです。移民とまでは言いませんが、実際、外国人技能実習生の受け入れも進み、留学生が卒業すれば、日本企業で働くケースも増えています。制度上での受け入れはすでに行っていますが、問題はそれを拡大する方向を示すかどうかです。ただ、日本が移民を受け入れるようになったからと言って、外国人が大勢来るかと言えばそれは幻想かも知れません。そうなると、いかに少ない人数の中で質の維持を図りながら、どう技術開発を行っていくか、という取り組みが必要になってきます。
施工:それは国土交通省が進めている生産性向上や「i-Construction」の推進のことを指すのでしょうか?
大橋:「i-Construction」についてですが、地域建設企業の方々にも受け入れられやすい形にしていくことが肝要です。ただし、それがすべてを解決するわけではないですが、このままでは建設業も建設技術者・技能者の人材も、続かなくなる可能性があります。
建設業の人材は一定数必要ですが、そのためには建設業の慣行を変えないと厳しいです。工程管理で待ち時間が長いなど無駄も多く、週休2日もままならないなど、担い手確保に不利な要素が多いようです。今、ちょうど公共工事で週休2日制モデル工事を実施していますが、これが全ての民間工事に広がる兆しはみえにくいのではないでしょうか。
先ほど、国土交通省が民間工事にどこまで関与できるのかという話題でも触れましたが、官邸も働き方改革で様々な提案をしています。今の状態が続けば、建設業が担い手を確保・育成するハードルは非常に高いです。どれを取っても一朝一夕に解決できるものではありませんが、地域建設企業の未来像を描くためにも、地域建設業WGで引き続き多角的に議論していきたいと思っています。
施工:ありがとうございました!よろしくお願いします!
人材採用・企業PR・販促等を強力サポート!
「施工の神様」に取材してほしい企業・個人の方は、
こちらからお気軽にお問い合わせください。


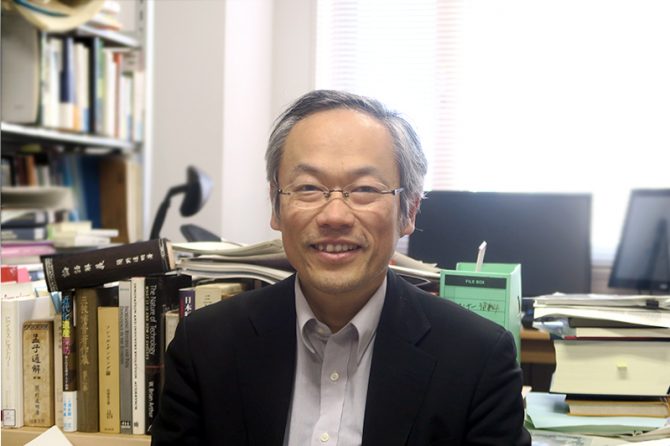






中小企業での総合評価方式は、会社の技術力以外(資金力等)での
要素が落札に大きく影響を与えていると思う。それなので、
一概にこの方法でふるいにかけるやり方が、真の残したい企業とは言えないと思う。
というよりも、今まで頑張ってきた企業を簡単に切り捨てるような発言に
憤りを感じる。