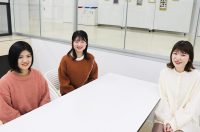住民のつながり意識と防災の関連性を研究
――それぞれの研究内容を詳しく教えてもらえますか。
東さん 地域における住民間のつながりは、目に見えないので、それぞれ感じているところも異なり、住民のつながりは「これ」と一概には言えません。たとえば、あいさつをしたらつながっていると考える人もいれば、そう考えない人もいます。
私の研究では、このつながりについて、なるべくたくさんの住民の人々にアンケート調査をして、それを分析しています。つながりがあると感じている人ほど、地域に対して安心感を持っているのではないかということで、つながり意識と防犯意識の関連性に主眼を置いて研究しているところです。
――松永先生、東さんの研究内容について補足をお願いします。
松永先生 地域の安心安全には、防災とか交通安全とか、いろいろな切り口がありますが、東さんの場合は、主に防犯を対象とした調査を行っています。防犯には、直接犯罪に巻き込まれるということのほか、不審者に遭遇するとか、犯罪ではない状態も含まれます。
これまでの研究で、実際に犯罪が起きた場所と住民が不安を感じている場所は、あまり一致しないことが明らかになっています。なので、安心安全なまちづくりを進めていく上で、どういうアプローチをするかは、非常に難しい問題です。私としては、エリアマネジメントの手法を住宅地に当てはめてみるという研究をやっています。
物理的な環境要因をしっかり設計するとか、パトロールするとかすれば、一定の効果はあると思います。しかし、それらによって安心感を得られたかと言えば、必ずしもそうではないからです。安心感というものは、それぞれの住民が直感的、経験的に感じているものだと思いますが、なにが貢献しているのかについて、学術的に明らかにするというのが、東さんの研究です。
東さんは、私の子どもが通っている小学校校区でもアンケート調査を実施予定です。
GISを活用し、居住実態とコミュバス利用実態のギャップを研究
――守田さんはどういった研究をしているのですか?
守田さん コミュニティバスはお年寄りなどの日常的な移動を助けるためのサービスだと思っています。糸島市では、少子高齢化が進んでいますが、一方で、他の地域や海外からの移住者が多く、市の人口そのものは増加傾向にあります。つまり、糸島市には、他都市にはあまり見られない人口動態があるわけです。
そうなると、居住分布などにも変化が生じているはずなので、コミュニティバスの路線やバス停にも変更を加えるべき点があるはずです。需要と供給のギャップなど解明するため、GISを使いながら、調査分析しています。
松永先生 この研究は、守田さん自身が興味を持って始めたことです。ウチの研究室では、2021年に別の研究で糸島市役所にご協力いただいたという経緯があります。
守田さん 研究を始めたのはたまたまです。私が住んでいる場所と糸島市がたまたま近くだったからです(笑)。
松永先生 GISを使った調査分析がちゃんとうまくできるかどうかは、守田さんの頑張りにかかっているので、期待しています(笑)。
守田さん 難しいので、ヤバそうです(笑)。
松永先生 チュートリアルがあるので、一緒に頑張りましょう(笑)。
団地における住民の防災意識を調査
――政次さんはどうですか?
政次さん 研究対象となる団地は3ヶ所あるんですけど、そのうちの1ヶ所の団地の近くの広場に防災設備を設置する計画があります。防災設備の設置によって、住民の防災意識がどう変化するかを調査しています。設置完了は私が卒業した後になるので、最後まで調査に携わることはできないのですが、前段階の調査をしています。
ほかの2つのうち1つは、数年前に防災公園が整備されている団地なので、ちゃんと避難訓練が行われているかなどを調べたいです。最後の団地は、自治会の防災意識の高い団地だそうで、なぜ防災意識が高いのか、どういう活動をしているかなどについてヒアリング調査を行った上で、団地整備に必要な要素を把握したいと思っています。
――松永先生、お願いします。
松永先生 高度経済成長期に一気にたくさんの団地が整備され、現在それらの建物の老朽化、住民の高齢化が社会問題になっています。そういった問題を背景に、団地の環境整備が進められています。
政次さんの前の学生が3つの団地内の花壇や農園を比較して、運営組織や管理内容、住民の交流状況などについて調べながら、どうすればうまくいくのかについて分析しました。物理的な環境整備主体でやるのか、自治会などの人的な活動主体でやるのかなどを比較調査するものでした。政次さんの研究は、その延長線上にあると言えます。
防災施設は必要な施設ですが、ただ設置すれば良いというわけでありません。施設がほったらかしになるケースもあるからです。防災施設がちゃんと機能するためには、住民の防災意識が重要であって、住民参加型で環境整備する必要があります。防災にまちづくりには、ファシリテーター以外にも、なにか必要なものがあると考えています。
地元大野城市と隣接市のより良いコミュバス乗り継ぎ運用について調査
――佐藤さん、研究内容の詳細について教えてください。
佐藤さん 大野城市をはじめ、隣接する春日市や太宰府市にもそれぞれコミュニティバスがあります。それぞれのコミュニティバスがうまく乗り継ぎできるようになれば、より簡単に相互の行き来ができるようになります。パーソントリップ調査を使いながら、コミュニティバスのより良い運用に関する調査をしています。
先日、大野城市内を通る西鉄大牟田線の高架化が完了したので、高架化に伴うコミュニティバスの運行時間の変化などについても調べることにしています。調査結果がまとまったら、大野城市さんに提出することも視野に入れています。
――先生、お願いします。
松永先生 大野城市さんは前々からコミュニティバスの相互乗り入れを検討されているようです。ただ、実際にやるとなると、法的、財政的な面でいろいろと問題が出てくるのですが、今のところは、移動の需要がどうなっているのか、どこで乗り継げば効果的なのかといったところを、とりあえず把握するための調査になります。
大野城市のコミュニティバスについては、以前に学生が路線バスとのアクセシビリティの比較研究をしています。大野城市の南部は、路線バスがあるので、コミュニティバスが走っていないんです。コミュニティバスと路線バスとは、運賃や運航ルートなどのサービスレベルが違っていて、市民から不公平だという声が上がっていたりします。