「ありがたい現場」
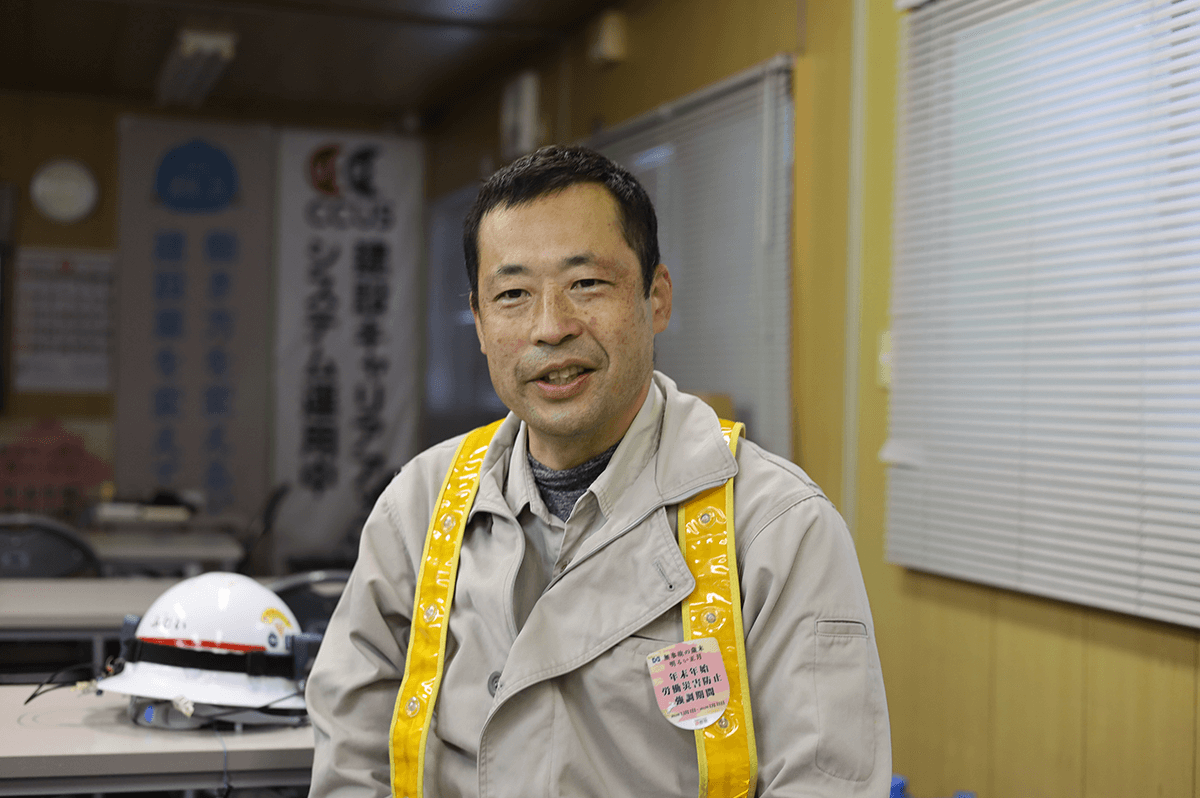
――この放水路に対する地元自治体などの期待は大きそうですが。
藤井さん 私は、土木工事というものは、人に喜ばれてナンボであって、それが土木工事の原点だと考えています。この現場はまさに、地元に貢献できる仕事だと思っています。
見学会も非常に多く、たくさんの方々から直接励ましのお言葉をいただく機会も多いので、非常にやりがいを感じます。道路トンネルの現場だと、そういう機会はあまりないのですが、この現場は、とくにお声かけいただく機会が多い印象です。そういう意味で「ありがたい現場」だと感じているところです。
――完成に向けた意気込みをお願いします。
藤井さん まずは、最後まで無事故でいきたいと思っています。あとは、品質不具合がないようにということです。とにかく安全にキレイなモノを工期内に納めたいです。最後まで気を緩めずやっていきたいです。
最初に配属されたトンネル現場で「トンネルはおもしろいな」
――鹿島建設でこれをやりたいというのはあったのですか?
藤井さん 入社したときは、とくにコレというものはなかったですね。ただ、最初配属された現場が、高知と愛媛の県境を結ぶ寒風山トンネルでした。そこで「トンネルはおもしろいな」と感じました。
入社以来、ほぼほぼトンネル工事に携わってきています。いわゆるトンネル屋ですね。道路トンネル以外も、地下駐車場、地下鉄、地下発電所など、地下構造物ばかりです。
――印象に残っている現場はどこですか?
藤井さん それぞれ特徴のある現場を経験してきたので、すべてが印象に残っています。強いて言うなら、愛媛と高知の県境をまたぐ地芳トンネルの現場です。四国カルストの直下を貫くトンネルで、大量の湧水にさいなまれた工事でした。
私は10年の工期中、8年近くいて、貫通の瞬間にも立ち会いました。苦労した分、貫通の喜びはひとしおでしたね。
完成時の式典では、地元の方々が「命の道をありがとう」という横断幕をあちこちで掲げてくれました。仕込みなしで(笑)。こんなことは後にも先にもありません。非常に嬉しいことです。
――湧水はどんな感じだったのですか?
藤井さん 四国カルストは石灰岩でできた台地なんですが、地下は空洞だらけで、そこに大量の水が溜まっているんです。そのようなカルスト下部に穴を開けたわけですから、湧水量20t/分、湧水圧20kg/cm2級の水が噴出してきました。
当初は排水工法で掘っていましたが、抜いても抜いても一向に湧水が減りませんでした。そのうち、四国カルストの生態系の維持という観点から止水工法で掘削することが決まりました。とにかく水量、水圧がスゴいので、止水域が破られることもあり、非常に苦労しました。自然の偉大さ、恐怖を感じた現場でしたね。
とにかく、想像を絶するようなことが起こる現場だったので、記憶に残っています。
地質がどうなっているか想像するチカラが必要
――トンネル工事では「危険を察知する能力が重要」という話を聞いたことがありますが。
藤井さん その通りだと思います。トンネル工事はまさに「一寸先は闇」ですから。前方の地質を察知するには、いろいろな方法があります。この現場では、削孔検層をやっていて、ある程度の予測を立てながら、掘削を進めてきました。ただ、削孔検層はあくまで「点」の情報でしかないので、この情報をもとに、地質がどうなっているか想像するチカラが必要になってきます。そこが技術者としての技量が問われる部分だと思っています。
あと、私が大事にしているのは、作業員さんの感覚からくる意見を聞き逃さない、ということです。作業員さんは、常に切羽と対峙しているので、地質のちょっとした変化などを敏感に察知しています。そういう感覚的なことをポロッと言うことがあるので、そういった声も聞き逃さないよう心がけています。
キレイじゃない現場はあり得ない
――「他の現場に負けたくない」という気持ちがあったりしますか?
藤井さん それはありますね。非常に強くあります。他の現場と比べて、当現場が劣っていると少しでも感じたら、すぐにでも挽回したいと考えます。私がとくに気をつけているのは美観です。構造物のキレイさ、現場のキレイさには、非常にこだわってきたし、今もこだわっているところです。
たとえば、この現場ではトンネル覆工の清掃を何回もやりました。その分時間もお金も余計にかかりますが、汚れたままで納品するわけにはいきません。なので、今の現場では、至るところでしょっちゅう掃除しています(笑)。あとは、坑内の照度とか、路盤の整備などにもこだわっています。
なぜそこまで現場のキレイさにこだわるのかと言えば、生産性や安全性に影響すると考えているからです。キレイじゃない現場は、私にとっては、あり得ない現場です。







