新たなエコロジカルネットワークの誕生

杜の田んぼ
2010年3月、中央環状新宿線と大橋ジャンクションが開通。翌2011年、杜づくりが完了した。首都高は、杜を周辺の緑地とつなぐ「エコロジカルネットワーク」の拠点と位置づけ、生き物の生活圏を支える役割を担わせた。杜は都市のヒートアイランド現象の緩和や空気浄化にも貢献。コンクリートの構造物が、自然と共生するインフラに変わった瞬間だった。
エコロジカルネットワークの象徴的な事例が、オオタカの飛来だ。ハトを捕食した痕跡があったことから、首都高が監視カメラを設置したところ、カメラはオオタカの姿を捉えた。首都高職員がiPadでその映像を見せてくれたが、空の捕食者でありながらも、愛らしく振る舞う様子に思わず目元が緩んだ。
共生のまちづくり 地域を分断しないジャンクション
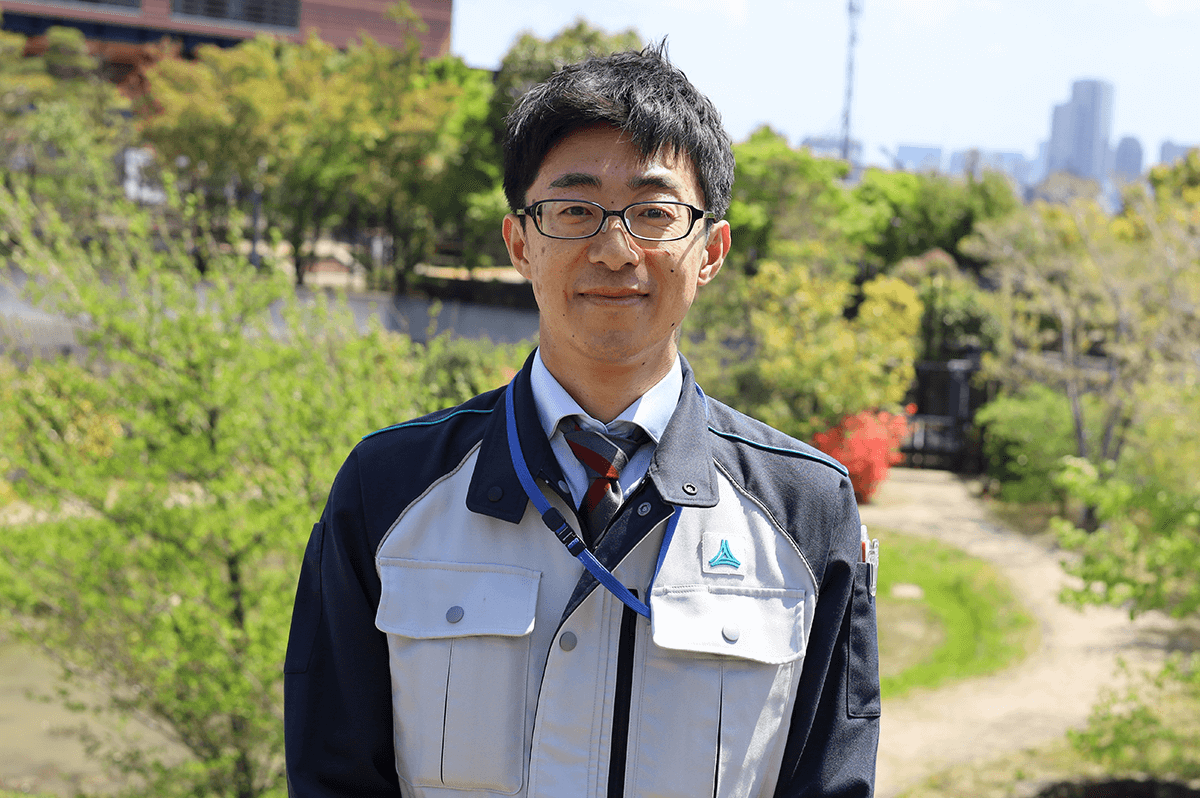
伏屋 和晃氏
繰り返し強調するが、大橋ジャンクションの成功は、建設技術だけによるものではなく、地域住民との対話が、それを支えた。計画当初から、首都高は東京都、目黒区、住民と協働し、数多くの話し合いの場を設けた。反対意見を抑えるのではなく、共通の目標――「地域を分断しないジャンクション」を掲げ、合意形成を図った。
杜づくり完了後、首都高は地域との交流イベントを毎年開催。地元の小学生が参加する稲作体験や自然観察会では、子どもたちが稲作を体験し、都市の中の生態系を学ぶ。年に数回開催する一般公開イベントでは、杜に飛来するキジバトやシジュウカラ、トンボやバッタを観察し、生物多様性の重要性を共有する。
これらのイベントには、年間1000~2000人が参加。ある住民はこう語る。「高速道路に反対だったけど、杜を見て、街が生き返った気がした」。コンクリートの構造物が、地域の誇りに変わる瞬間だった。
首都高の伏屋和晃氏(東京西局調査・環境課)は、地域との関係をこう強調する。「建設当初から、住民との対話を続け、関係者で協力して作り上げた大橋ジャンクションは、まちづくりの結晶です」。この共生の精神は、3つの緑化の設計にも反映された。壁面緑化は、周辺の街並みと調和し、コンクリートの圧迫感を軽減。天空庭園は、住民が気軽に訪れられる憩いの場として機能している。
受賞理由は、長年の地域共生の取り組み、外部認証、そして巡り合わせ

加藤 千裕氏
グリーンインフラとは、自然の機能を活用して都市の課題を解決する考え方だ。さきでも触れたが、杜は、国土交通省のグリーンインフラ大賞を受賞した。この受賞の背景には、首都高の長年にわたる地域共生の取り組みと、外部認証(例:自然共生サイト認定)の積み重ねがあった。あとは、ちょっとした巡り合わせも働いたようだ。
首都高の加藤千裕氏(サスティナビリティ推進室)は、今回の受賞を「この評価は、首都高の長年の取り組みがカタチになった証。地域や利用者との持続的な関係を築きながら、今後も積極的に発信を続けたい」と総括する。今回の受賞には、杜が単なる緑化プロジェクトを超え、都市の未来を切り開くロールモデルとしての外部からの期待が存分に込められていることは想像に難くない。
なお、注意すべきは、「積極的に発信していきたい」という言葉は、「誰でも杜に入れる」ということを意味しないということだ。みだりな人の出入りは、生態系の毀損、破壊につながるからだ。杜という試みなどの情報は積極的に発信していくが、園内の様子は、目黒区が管理する目黒天空庭園から見えるが、園内への立ち入りはできないので、一般公開の際にお立ち寄りいただきたい、というのが首都高の真意だ。
杜は、グリーンインフラのグローバルトレンドを映し出す鏡という見方もできる。2009年の委員会当時、生物多様性は今ほど注目されていなかった。しかし、涌井氏ら有識者の先見性により、杜は時代の先を行く存在となった。欧米を中心とする世界では近年、気候変動やヒートアイランド現象への対策として、グリーンインフラに対する関心が高まっているが、杜の先進性は今でもまったく色褪せていない。
東京都は、2024年から「Tokyo Green Biz(グリーンビス)」と称して、あらゆる機会を通じてみどりを増やす取り組みを進めている。奇しくも、杜は、都のこうした動きの先駆けとして、みどりの可能性を支える存在となっている。
杜は、地域と自然をつなぐ架け橋
首都高にとって、杜は単なるプロジェクトではない。企業のミッション――「地域の皆様とともに、よりよい環境の実現と地域社会の発展を目指す」――を体現する挑戦だ。高速道路会社が本業を超えて生物多様性に取り組む姿は、インフラ事業の新たな可能性に光を灯す。
加藤氏はこう語る。「杜は、地域と自然をつなぐ架け橋。首都高のサスティナビリティの代表事例として位置づけ、都市部の緑化に貢献していきたい」。
唯一無二の挑戦 次のみどりはどこに?
杜は、土木構造物の上に緑を重ねたグリーンインフラの稀有な事例だが、唯一無二であるがゆえに、その独自性が課題を投げかける。
他の事業者や地域で、同様のアプローチを再現するのは容易ではないからだ。首都高も同様で、加藤氏は「現時点で次なる具体案を持ち合わせていない」と話す。首都高にしてみれば、グリーンインフラが本業ではない以上、「ケースバイケースで考える」ということになる。新たなみどりのプロジェクトの機会があれば、首都高は地域に根ざした挑戦を続けるだろうが、杜に匹敵する事例に育つかどうかは、まだ誰も知らない。
とあるグリーンインフラの専門家はこう指摘する。「杜は確かに素晴らしい。しかし、すべてのインフラが杜になるわけではない。重要なのは、各地で小さなみどりをつなぐこと」だと。その通りだとすれば、杜が示したのは、単一の成功モデルではなく、都市ごとに異なるみどりのカタチを模索する姿勢ということになるのかもしれない。
実際に杜を訪れ、杜が教えてくれると感じたことは、自然と技術、地域と事業者が手を取り合うことで、都市はもっと生き生きとした場所になるということだ。首都高は今後も、杜を育て続ける。だが、杜は同時に、さらなる問いを投げかけているように思える。
「都市のみどりは、どこまで広がるのか? 新たな土木構造物は、どんな物語を紡ぐのか? そして、あなたのまちは、どんなみどりを育むだろうか?」と。この問いをどう受け止めるか、そしてどう動くかは、杜を訪れた人々、一人ひとりに委ねられている。
人材採用・企業PR・販促等を強力サポート!
「施工の神様」に取材してほしい企業・個人の方は、
こちらからお気軽にお問い合わせください。






