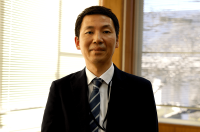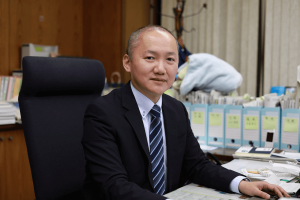東日本大震災 被災地の復興に奔走
――東日本大震災の際はどちらに?
菊田さん 2010年4月から秋田の湯沢河川国道事務所で勤務していたんですが、2011年3月に東日本大震災が発生しました。秋田でも相当揺れて、揺れ始めには、東北出身の多くの所員は「ついに、(想定されていた)宮城県沖地震が来たか」と言っていました。4~5分も揺れが続いたので、「これはただ事じゃない」と感じました。
翌朝から太平洋沿岸への支援が始まりました。私は調査課長として派遣者の人選を補佐し、夜のうちから準備をして翌朝には現地に向かう段取りをしました。8月には、仙台の本局に異動になり、被災した海岸堤防の復旧を担当しました。
――復旧事業で難しかった点はありますか。
菊田さん 岩手、宮城、福島の被災3県で、海岸堤防をどの高さで復旧するかが大きな議論でした。堤防の高さが決まらないと復興まちづくりが進まないと言われかねない状況で、早急に方針を決める必要がありました。当時、中央防災会議において、「最大クラスの津波に対しては命を守り、頻度の高い津波に対しては資産も守る」という概念整理がされました。
専門的には「L1津波」「L2津波」と呼びますが、住民に伝えるには分かりやすい表現が必要でした。各県と調整し、「頻度の高い津波は施設で守り、最大クラスの津波には多重防御と避難で命を守る」と説明に回りました。被災自治体の首長さんたちに直接お会いして説明するなど、時間がない中で大変でしたが、やりがいのある仕事でしたね。
国際協力への挑戦 日本の技術を世界へ
――その後、どちらに?
菊田さん 東日本大震災の日本の経験を、海外で活かすように、ということだったのかもしれませんが、2012年からJICA本部に出向しました。また、2019年から2023年まで、インドネシアのジャカルタで長期専門家として働きました。現地の公共事業省で、水資源・防災分野の政策支援や技術支援、新規プロジェクトの案件形成の支援を担当しました。
たとえば、フィリピンのミンダナオ島で台風被害を受けた河川の治水計画や、ジャカルタの洪水対策マスタープランの見直しに携わりました。日本の技術を現地に伝えつつ、一緒に計画を作るスタイルが特徴です。インドネシアでは、ジャカルタの抜本的な洪水対策として地下放水路を提案し、日本からの技術支援を決定してもらったこともあります。ダム再生事業も日本の得意分野で、堆砂したダムを改良するプロジェクトを進めました。
インドネシアでは経済発展が優先され、防災インフラが後回しになりがちでした。ジャカルタは見た目は都会なのに洪水が頻発する状況で、日本が60年以上支援してきた歴史を活かし、現地のニーズに合わせた提案を心がけました。
また、2015年には仙台で開催された国連防災世界会議に関与しました。そこで「事前防災投資」の重要性を日本が主張し、「1ドルの投資で15ドルの復興費用を削減できる」と訴えました。途上国が自然災害で発展を阻まれるのを防ぐため、日本の経験を伝えたいと思ったんです。
――印象に残っていることはありますか。
菊田さん コロナ禍で2020年3月に日本に一時帰国した時、テレワークでインドネシアの仕事を続けました。2020年12月に現地に戻った後、コロナに感染してジャカルタの病院で入院したんです。39度の高熱が1週間続き、CTスキャンで肺が真っ白だと診断されました。現地の隔離病棟で治療を受け、PCR検査で陰性になるまで退院できず、インドネシア語でのやり取りも大変でした。心細い思いをしましたが、命が助かったのは幸いでしたね。
もう一つは、天皇陛下のジャカルタ訪問です。2023年に陛下が即位後の最初の公式訪問先としてインドネシアを選ばれ、かつての日本の協力で復旧した排水機場を、現地でご案内しました。陛下は水問題をライフワークにされており、日本の支援で復旧した施設を熱心にご覧になっておられました。現地に駐在する専門家として貴重な機会をいただいたことは、忘れられない思い出です。
荒川下流での挑戦 京成本線橋梁架替とDX
――現在、菊田さんが所長を務める荒川下流河川事務所の主な取り組みは何でしょうか。
菊田さん 一番大きな事業は、京成本線の荒川橋梁架替プロジェクトです。荒川下流域には戦前からの地下水くみ上げによる広域地盤沈下で、ゼロメートル地帯が拡がっており、堤防も部分的に低くなっているところがあります。特に、この橋梁付近は堤防が部分的に低くなっている治水上の弱点で、2019年(令和元年)の東日本台風では、河川の水位が桁下1.2メートルまで迫りました。
対策として、上流側に新しい橋を架け、線路を移設して堤防をかさ上げします。730億円の事業で、2023年から工事を開始しました。営業線に影響を与えないよう夜間の工事も多く、2037年に完成する計画です。荒川を挟む2駅をコントロールポイントとして、その間で架け替えする制約もあり、既設橋から15メートル上流に新たに架橋するという限られた範囲で工事を進めています。京成電鉄さんに工事監理を委託し、安全第一で取り組んでいますね。
――DXにも取り組まれているそうですね。
菊田さん はい、河川管理のDXを進めています。たとえば、ウェアラブルカメラで巡視を効率化し、報告などの対応に要する時間を3分の1に減らしました。デジタル管内図を公開して、外部からの問い合わせにかかる時間を減らしたり、オンラインで工事工程会議を行ったりしています。年間1,200万人以上が訪れる荒川の河川空間を管理する中で、職員が「もっと楽に効率化できないか」と工夫しているんです。
また、RFI(技術情報提供依頼)という取り組みも始めました。民間企業に新しい技術情報を募集し、実証フィールドとして荒川下流管内の現場を提供しています。河川巡視や点検、除草の自動化・効率化の技術を求めていて、既に複数の情報が寄せられています。これから現地での実証実験も進める予定です。
現場で汗を流す人々と政策をつなぐ役割
――国交省の仕事の魅力は何だと思いますか。
菊田さん 現場と政策が組織としてつながっている点が最大の魅力です。私は21年間で13のポストを経験しましたが、転職せずに、バラエティに富んだ新しい仕事に挑戦できる環境は、ほかにないと思います。河川防災を中心に、国内から海外まで成長の機会を与えてもらっています。
たとえば、海外での経験を通じて、日本の技術力の高さを再認識しました。インドネシアで「防災といえば日本」と言われた時、それはゼネコンやコンサル、地域の皆様のこれまでの積み上げがあってこそだと感じました。現場で汗を流す人々と政策をつなぐ役割にやりがいを感じますね。
――今後の展望をお聞かせください。
菊田さん 荒川放水路は昨年10月に通水から100周年を迎えました。気候変動の影響で大雨が増える中、地域の安全を守る使命は変わりません。新しい技術を取り入れつつ、建設業界や地域の皆様と協力して進めていきたいです。荒川下流には、青山士さんが基幹施設となる岩淵水門の設計と建設に携わったりと、新たな技術や施策を導入してきた伝統があります。その精神を引き継ぎ、DXやRFIで未来を見据えています。
日本の土木や防災の技術力は世界から信頼されており、それを支える皆様に感謝しながら、次の100年を考えたいですね。とくに、荒川水系の河川整備基本方針を今年1月に気候変動対応に改定したように、前例のない課題に立ち向かうため、流域に関係するあらゆる皆様との連携を深めていきます。地域の安全・安心を確保しつつ、日本の技術力を内外に発信していきたいです。
人材採用・企業PR・販促等を強力サポート!
「施工の神様」に取材してほしい企業・個人の方は、
こちらからお気軽にお問い合わせください。