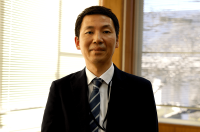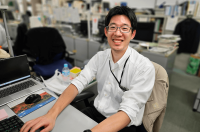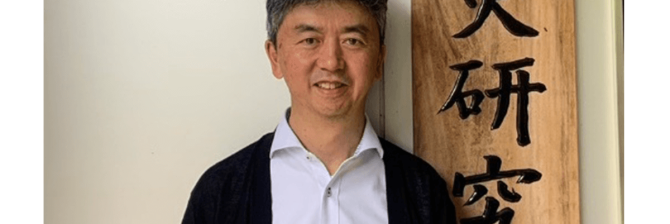筑波大学教授として砂防学を研究している内田太郎さんに取材する機会を得た。
内田さんは、京都大学で砂防の学位を取った後、研究員生活を経て、30才手前という遅咲きで、砂防職として国土交通省に入省。国総研などで16年ほど勤務したのち、5年ほど前に筑波大学教授に転身した経歴を持つ。
そんな内田さんの目に、砂防という世界はどう映っているのか。これまでの歩みを振り返っていただきつつ、砂防研究の魅力などについて聞いてみた。
一番興味を持てたのが砂防だった
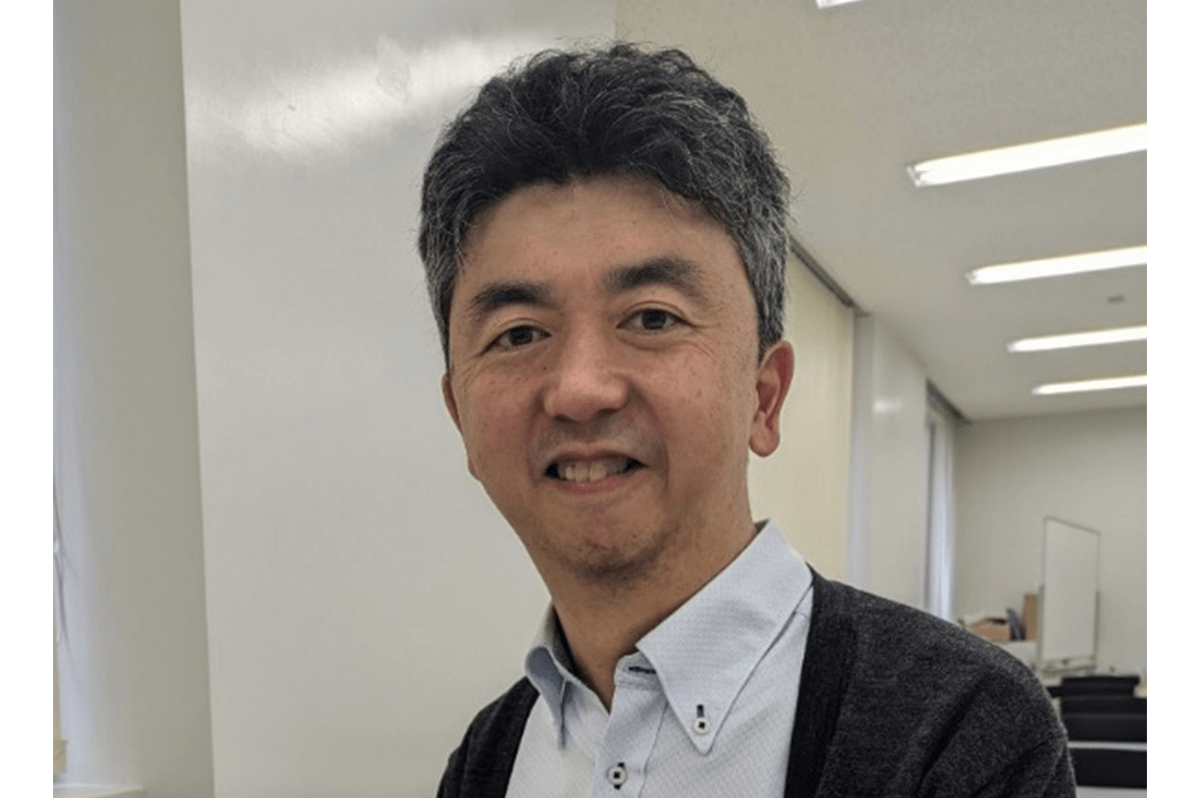
内田さん(本人写真提供)
――砂防との出会いはどのようなものでしたか?
内田さん 私は京都大学農学部の林学科というところで、森林について学んでいたのですが、研究室を選ぶ際に、一番興味が持てたのが砂防研究室でした。それが砂防との出会いでした。どちらかと言えば、なりゆきでした。
博士号を取った後、なりゆきで国交省に入省
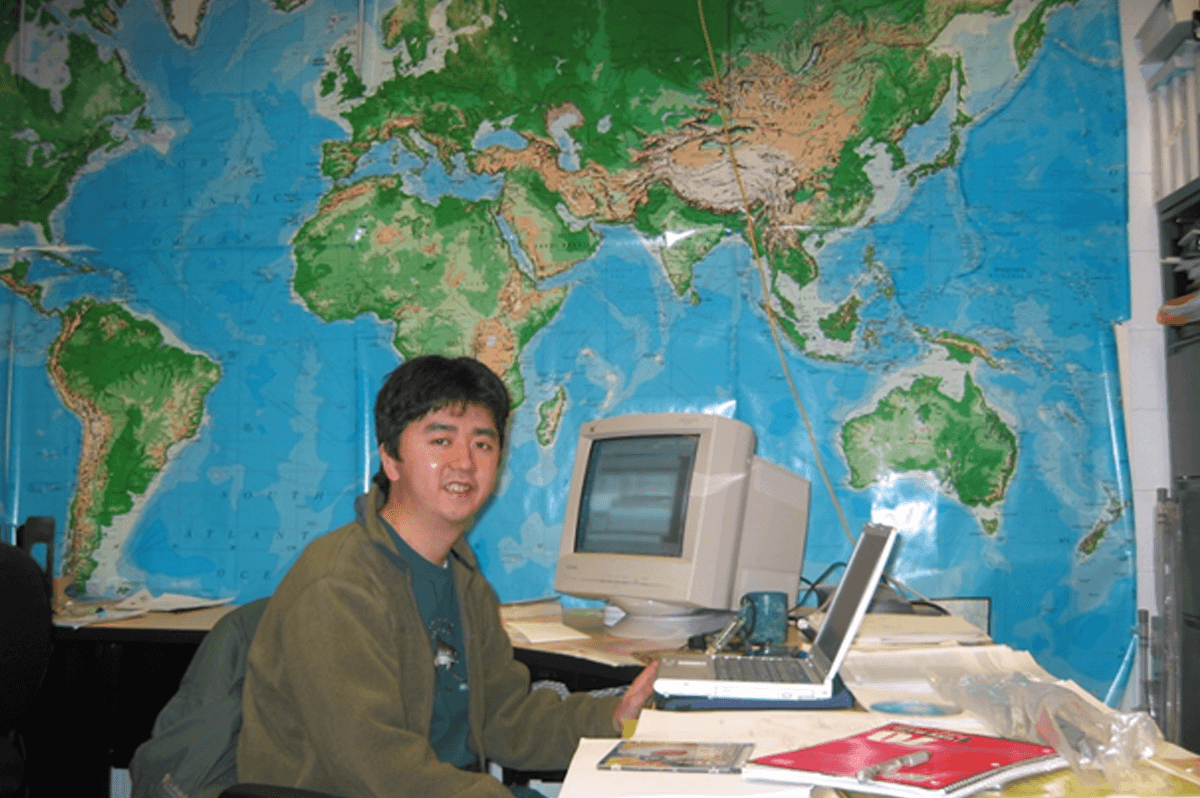
ポスドクのときに留学していたオレゴン州立大にて(本人写真提供)
――その後、国土交通省に入省されたそうですが、どういう経緯だったのですか?
内田さん 砂防研究室に入ってから、修士と博士の学位を取りました。その後、日本学術振興会の特別研究員などとして3年間勤務しました。いわゆるポスドクみたいな感じで、こういう研究をしたいということを振興会に申請して、生活費と研究費をもらいながら、研究をしていました。
そんなとき、今後の選択肢の一つとして、国総研や土研などの国の研究所で働くのもあるのかなと考えるようになりました。周りからもそのようなアドバイスを受けたこともあって、国家公務員の試験を受けることにしました。この選択も、流れに身を任せたみたいなところがありましたね(笑)。筆記試験はうまいこと受かりました。
当時の指導教授に相談すると、「だったら、砂防職で国交省に入るのがいいのでは」ということを言われました。ずっと砂防の研究をしてきたので、砂防の仕事に就くこと自体はなんの違和感もありませんでしたが、それまではあくまで選択肢の一つということで、積極的に公務員になりたいとも思っていませんでした。最終的には国交省に入ることにしました。
――入省したときはおいくつでしたか?
内田さん 30才手前ぐらいでした。あとで聞いたところでは、私のような入り方をした職員は、当時例がなかったそうです。
国交省在籍中の大半を研究活動で過ごす

国土技術政策総合研究所時代のスリランカでの現地調査の様子(本人写真提供)
――国土交通省ではどのようなお仕事をしましたか?
内田さん 国交省には16年ほど在籍しましたが、その期間の大半は、つくばにある国総研や土研といった研究所で働いていました。1年間だけ、本省砂防部の砂防計画課で係長をしました。研究所では、主に砂防に関する技術開発、災害対応、技術支援に携わりました。
――ほぼ研究畑一筋というのは、珍しいことではないですか?
内田さん そうですね。あまりいませんでした。
――技術開発にはどのようなものがありましたか?
内田さん 一例を挙げると、深層崩壊という大規模な斜面崩壊について、過去の発生データをもとに、全国のどの場所にその発生リスクがあるのかを示す、推定頻度マップというものを策定しました。
――災害対応として、たとえばどの災害ですか?
内田さん たとえば、平成30年の西日本豪雨です。発災直後に被災地に入って、被災状況を調べたり、復旧や二次災害への対応などに関する助言などを行いました。
【東証プライム上場】未経験者歓迎!土木施工管理の求人[PR]
砂防の人材育成のため、大学教員に転身
――筑波大学の教員になられた経緯について、教えてください。
内田さん 国総研で砂防研究室長をしていたときに、大学などの教育機関での砂防の人材育成がかなり大きな問題になっていました。私が人材育成に少しでも貢献できるのであれば、そういう道もあるのかなということで、筑波大学の教員になりました。
――大学教員にならないかというオファーがあったということですか?
内田さん 筑波大学の方で、砂防に関する公募があるので、「応募しないか?」という話がありました。
――業界的に、砂防の研究者自体が減っているという危機感が背景にあってのオファーということでしょうか?
内田さん 背景までは分かりませんが、周りの先輩方からも「砂防の人材育成にぜひ貢献してほしい」というようなことは言われました。砂防の技術者、最終的には研究者の育成のほか、砂防に関わる人材の裾野を広げるため、という業界的な要請をハダで感じていました。