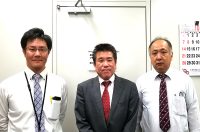担い手確保を含めた多面的なフォーラム
――九州建設技術フォーラムとはどういうものですか?
日野 建設技術は日進月歩です。建設技術に関する情報を共有することによって、開発、実用化を促進し、品質や環境の改善、コスト縮減など、さまざまな建設環境の改善に貢献することを目的としています。ブースやパネル展示、プレゼンなどを通して、技術交流する場を提供するものです。
昔はフェアというカタチで開催していましたが、今のフォーラムになったのは2004年からで、今年で16回目の開催になります。他の地域でも類似のイベントがありますが、技術プレゼンを行っているのは、このフォーラムだけですはないでしょうか。
われわれのフォーラム独自の取り組みとしては、数年前から、高校生や大学生などを対象に「建設分野の仕事」に関する情報提供を行うリクルーティングプレゼンテーションを行っています。
毎年多くの学生が参加しており、今年も400名が参加予定です。担い手確保を含めた多面的なフォーラムとなっています。
――リクルーティングプレゼンテーションではどのようなお話を?
日野 特定の民間企業としてではなく、業種ごとの業界団体として行っています。業務内容をはじめ、ふだんの生活などにも踏み込んだ部分についても説明しています。
プレゼンを行うのは学生に近い年齢の若い方々なので、学生との距離が近く、積極的に参加してもらっていると感じています。100名ぐらいの会場で、立ち見も出ています。
――今回のフォーラムの見どころは?
日野 今回のフォーラムのテーマは「技術の力で、防災・減災、そして国土強靭化へ」です。昨年のテーマは「インフラメンテナンス」でした。基調講演には、河田惠昭・関西大学特別任命教授をお招きします。
河田先生は、日本の防災分野研究の第一人者で、ハード、ソフト両面の全体システムの重要性を訴えてこられた方です。今回の講演でも、そういった観点からお話しいただくことになっています。
私としては、自治体など発注者の方々にこそ、会場に足を運んでほしいという思いがあります。民間会社がいくら技術を開発しても、それを使うのは発注者です。今どういう技術があるのか、自治体の職員の方々に知ってもらいたいです。
自治体職員の中には、技術系出身ではないため現場を知らず、民間に仕事を丸投げする人もいます。また、技術・材料・工法など、常に建設技術開発の動向を把握していなければ、適切な発注者業務を遂行することも難しいと思います。来場すれば、いろいろな技術情報を一度に収集することができます。
ハード対策あってのソフト対策
――ここ数年、九州では毎年のように災害が起きていますね。
日野 地震は、九州に限らず、全国のどこで起こっても不思議ではありません。加えて、九州は台風の通り道ですし、火山噴火もあります。九州には、多くの自然災害のリスクがあります。防災減災の備えをする上で、これで終わりということはありません。
災害の備えについて、世間的には「ハード対策だけではなくソフト対策も」と言われますが、私個人としては、最近つくづく「ハード対策あってのソフト対策」だと感じています。
ここ数年、風水害の規模が昔に比べ大きくなっています。既存の構造物は、過去のデータをもとに設計されていますが、それが参考にならないぐらい最近の災害外力の規模が巨大化しているわけです。
われわれ土木技術者は、この巨大災害に対して最大限努力していかなければなりません。フォーラムでは、災害の備えに関する意識の共有を図りたいと思っています。
――展示の方はいかがですか?
日野 今回は全115ブースのうち、防災関係の展示が35を占めます。例年に比べ、防災関係の展示が多くなっています。九州各県、政令市のパネル展示もあります。展示会場には、NETISなどに関する国の技術支援窓口も設置されます。