大東建託が現場監督の働き方改革に成功した秘訣
2024年4月から、建設業に時間外労働の上限規制が適用される。特別な事情があって具体的に取り決めをしない限り、時間外労働は月45時間、年360時間以内に制限される。建設業界の働き方改革は待ったなしの状態にある。
こうした背景のもと、大東建託株式会社は6月1日から、現場監督などの工事職員などを対象にコアタイムのないフレックスタイム制度の導入を開始。生産性も向上するなど現場からの意見は上々で、速報値ではほぼ100%の工事職員が利用しているとのことだ。
大東建託がなぜ、建設現場の働き方改革で成功したか。その秘訣について、同社人事部の菅野敦志次長、安全品質管理部環境指導課の目黒航課長、広報部の新宮聖徳課長にそれぞれ現場の目線で話を聞いた。
工事職を対象にコアタイムのないフレックスタイム制度を導入
――大東建託での働き方改革の現況について教えてください。
菅野 6月1日から、建設現場の現場管理を行う工事職の社員を対象に、コアタイムのないフレックスタイム制度「フリーフレックスタイム制度」を導入しました。
フレックスタイムは、出社や退社の時間を本人の裁量で自由に決めることができる制度です。ここに「フリー」という文言が入っているのは、フレックスタイム制度では一般的な「何時から何時までは、必ず勤務していなければいけない」というコアタイムを定めていないためです。つまり、働く時間帯自体を指定しておらず、社員はフレキシブルタイム(7:00~20:00)の間で働く時間帯を自由に決めることができます。
当社は1日の労働時間は7.5時間と定めているため、仮に1か月の労働日数を20日とすれば、7.5時間×20=150時間となります。ある日は8時間、別の日は6時間であっても、1か月全体で150時間以上の所定労働時間さえ確保されていれば問題ありません。
――実際の稼働日数はどのくらいでしょうか? 建設業では4週8休を確保する動きもありますが。
菅野 大東建託では、「年間休日125日」と定めているので、年間の稼働日数は約240日となります。月によっては夏季休暇等により、営業日数のずれが生じますが、ならして考えると1か月当たり20日が稼働日数になります。








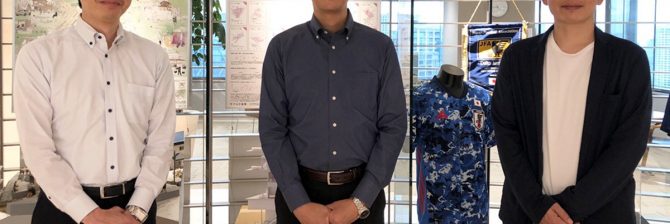

ゼネコンがフレックス導入しても職人はどうするの??